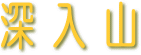
〜深入山(秋の七草コンプリート?(後編))〜
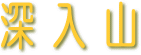 |
(後編) |
【広島県 安芸太田町 令和6年9月28日(土)】
yamanekoにとって22年ぶりの深入山。その後編です。(前編はこちら)
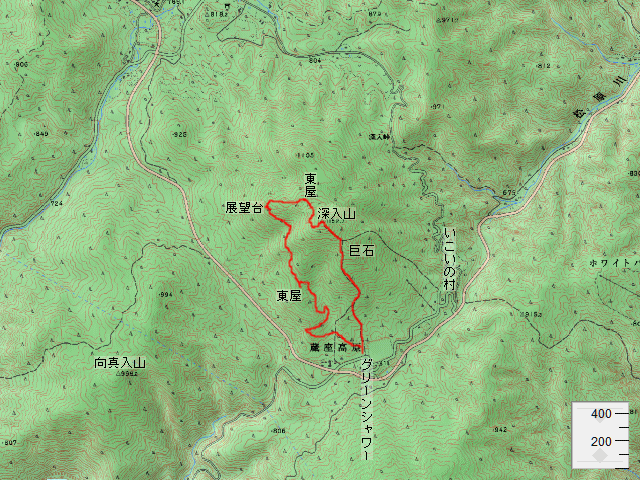 |
Kashmir3D |
今回の登山の起点は深入山グリーンシャワー。その駐車場にレンタカーを停めて、準備を整えスタートしたのは10時30分でした。そこから草原状の深入山南面を登ること2時間15分。12時45分に山頂に到着しました。
| 深入山山頂 |
深入山の山頂は芝生広場みたいな感じでした。広さはテニスコート1面くらい。眺望は360度です。
| 西−北 |
空腹で騒ぎ出す腹の虫を抑えながら、まずは景色を楽しむことに。
上の写真は西から北にかけてのものです。臥龍山や掛頭山(かけづやま)は深入山の北に位置し、その向こう側は八幡高原。更にその先は島根県になります。西の方に湖面が見えていますね。三段峡の上流部にある聖湖です。
| 北−北東 |
こちらは左にパンして北から北東にかけての風景。天狗石山や阿佐山は島根県との県境の山。つまり中央分水界上にある山です。
| オミナエシ |
ふと足元を見るとここにもオミナエシが。山頂の厳しい環境でもちゃんと花を付けているんですね。丈が低いのはその環境のせいか。
| イヌタデ |
イヌタデは低地のものと思っていましたが、標高1000mを超えるところでも普通に生えていました。西中国山地の標高1000mの環境は関東ではもう少し低い標高の環境に相当するのかもしれません。
| 昼食 |
眺望や植物をひとしきり楽しんだら、ようやく昼食です。ホテル近くのコンビニで調達したおにぎり弁当ですが、外で食べると何でも美味いです。ところでこのカラフルなビニールシート。どんな山奥であっても敷いたとたんに行楽感を出してきます。恐るべし。
| 下山開始 |
山頂での滞在時間は30分。午後1時に下山を開始しました。下山は登ってきたルートではなく、西側斜面を下りながら一旦北に向かった後、回り込んで南に向けて高度を下げていきます。
遠くに恐羅漢山を望みながらのんびりと下っていきます。yamanekoが若い頃、恐羅漢山には林野庁が運営するスキー場がありました。いわば国営スキー場です。ただそこに至る道が細く急峻だったので、雪道の運転に慣れてはいても勇気が必要でした。今でもスキー場はありますが(国営ではなくなっている)、別ルートからの広い道が開通していて、アクセスが劇的に改善されています。
| サワヒヨドリ |
下山ルートも花いっぱいのようです。まずはサワヒヨドリから。
| ヤマハギ |
これはヤマハギ。山上憶良が詠んだ秋の七草の萩はこのヤマハギやマルバハギなどをひっくるめて指したものとのこと。当時は細かな分類などなかったでしょうから当たり前ですね。万葉集には植物が出てくる歌が1千5百くらいあり、その中で最も多く読まれている植物が萩なのだそうです。その数141首だそう。
そういえば今年の秋分はこのまえの日曜日(9月22日)でしたが、おはぎ食べなかったな。
| ノアザミ |
上りではモリアザミを見かけましたが、下りで出会ったのはノアザミ。本来は初夏に咲くアザミですが。
| マツムシソウ |
マツムシソウは開花し始めの段階では花冠の中心にある筒状花だけです。そのうち外周部分にある花だけが外側の花弁を伸ばし始めます。そして写真のような姿に。
| 掛頭山遠望 |
道は途中から北に向かって下っていきます。正面に見えるピークは掛頭山。この山にも昔からスキー場がありました。広島県北西部は芸北地方と呼ばれていて、冬には雪も多く、スキー場がたくさんあります。バブルの頃には一大スキーブームがあって、当時は20か所くらいあったと記憶しています。
| ツクシコゴメグサ |
これはツクシコゴメグサ。よく枝分かれする茎に小さな葉が密生していて、その先に可憐な花を付けます。花の大きさは1cm足らずですが、案外目立ちます。
| 東屋 |
山頂の北側斜面にある東屋が見えてきました。
| 森の中へ |
東屋をすぎると道は森の中に入り、ぐるっと回り込むように方向転換して南西に向かって山肌を下っていきます。
| アキチョウジ |
このスマートな花はアキチョウジ。シソの仲間です。半日陰のような環境を好む花です。なので登ってきた道では見かけませんでした。
| イナカギク |
秋の野山歩きではいろいろなキクに出会います。これはイナカギク。別名ヤマシロギクとも呼ばれます。関東地方ではあまり見かけない野菊です。ところでイナカギクという名前。きっと都会の人が付けた名前でしょうね。田舎の人はわざわざ田舎とは名付けないでしょうから。
| 展望台 |
下り始めて20分、木立が切れた場所がありました。そのすぐ先にせり出すようにして大きな岩があり、その上に立つと眺めが良いようです。
| 南西方向 |
その眺めがこちら。眼下に向真入山(むこうしんにゅうざん)が見えています。「向」は向正面とかの向と同じで「対面する」という意味でしょうね。ただ、「深入」が「真入」になっていますが。その遥か奥には芸北の名山、恐羅漢山と十方山です。
| ズミ |
テラス状になっている大岩の脇にズミがありました。色づき始めています。転げ落ちないよう気をつけながら写真を撮りました。
再び山道に戻って、森の中を下っていきます。
| アケボノソウ |
アケボノソウ。深山のやや湿った環境を好みます。名前は、花弁にある斑点を曙の空に残る星々に例えたものだそう。涼やかな印象を受ける花です。
| ヒヨドリバナ |
秋の野山を代表する花、ヒヨドリバナ。花冠から長く飛び出す雄しべが特徴的です。
結構な斜度の坂道。膝を痛めないよう歩幅を狭めて歩きます。
| ヤマジノホトトギス |
むむ…これは? ヤマジノホトトギスの果実が開裂したところですね。中の種子はもうなくなっているかもしれません。
| キバナアキギリ |
キバナアキギリも咲いていました。開花後、花冠はすぐに落ちてしまいます。写真下の方に写っているのは花冠が落ちた後に残った萼です。
山肌を伝うように湧き水が流れ落ちていました。程よく湿気がある環境は、植物だけでなく動物や鳥、昆虫たちにとってもありがたいものだと思います。
| ツルニンジン |
ベルのような花冠をもつツルニンジン。多摩丘陵でもときどき見かけます。
1時45分、森が途切れました。登山道は左手に向けて下っていますが、分岐を右に進むと丘の上の東屋に続いている模様。ちょっと行ってみることにしました。
| 東屋 |
雨宿りや日陰を求めるときにはちょうどよい感じの東屋です。
東屋の前から振り返る深入山。ススキが揺れて秋の風情満点です。午前中はこの稜線に沿って登ってきたことになります。こう見ると結構な斜度ですね。どおりで息が切れたはずです。
| カワラナデシコ |
元の道に戻って下山を続けます。このカワラナデシコは生き生きとしています。繊細な花弁が切り絵細工のよう。平安時代に中国から移入された唐撫子に対して、もとからあった和製のものを大和撫子と呼んだそうで、これがすなわちカワラナデシコなのだそうです。
| キキョウ |
秋の七草が続きますね。このキキョウを含め、今日は七草のうち撫子、萩、尾花(ススキ)、女郎花(オミナエシ)の5種に出会いました。見てないのは葛と藤袴です。フジバカマは野生のものはめったにお目にかかることはなくなり、代わりに今日は近縁のサワヒヨドリに出会ったので、6種に出会ったと言ってもよいのかも。
| オオナンバンギセル |
誰かが造花をこんなところに突き刺して…、いやこれは本物の植物で、オオナンバンギセルです。花冠が普通のナンバンギセルの5倍くらいあり、頭が重そうです。ススキに寄生していて、その根元に生える植物です。
| ウド |
ウド。丈は1.5mくらいになります。でも、決して大木にはなりません。花序は茎の下の方まで付きますが、実ができるのはもっぱら先端のみ。山菜として食用にするのは早春に芽吹く若芽です。
道は再び森の中に入りました。ここからグリーンシャワーまではそう遠くはないはずです。
| ミヤマガマズミ |
赤い美味しそうな実を付けているのはミヤマガマズミ。薄暗い森の中でもよく目立ちます。主に里山に生えるガマズミに対し、より深山に生えるのでミヤマガマズミの名があります。それ以外の形態的な相違ももちろんありますが。
小さな流れを渡ります。この先で森が途切れているようです。
| シコクママコナ |
これはシコクママコナですね。花冠の上唇と下唇の境目の左右に黄色の斑があり、これが午前中に見たママコナとの大きな違いです。花の模様もこちらの方がスッキリした印象です。
森を抜けました。正面の看板は「ここから先登山道」だったか、「熊に注意」だったか。確かそういう看板だったと思います。西中国山地はツキノワグマの生息域なので、出会わないよう注意が必要です。お互いのために。
道の先に駐車場が見えてきました。ゴールはもうすぐそこです。
| 下山完了 |
2時20分、グリーンシャワーに戻ってきました。のんびり下りてきたつもりでしたが、下山に要した時間は1時間20分でした。それにしてもたくさんの花々に出会え、わざわざ広島市内から遠征してきた甲斐があったというものです。懐かしさもあって楽しい野山歩きになりました。
駐車場で軽くストレッチをして、MAZDA2に乗り込み一路広島へ。なにしろこれから広島に戻ってレンタカーを返して、お土産を買って、夕方の新幹線で帰京する予定です。
広島は夕方の凪の時間で、じっとりと蒸し暑かったです。深入山は爽やかな秋でしたが、下界はまだまだ残暑の中でした。汗をかきかきビールや弁当も買い込んで、慌ただしく東京に向かいました。
広島はいつ行っても懐かしく魅力的なところです。また訪れたいと思います。