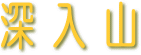
〜深入山(秋の七草コンプリート?(前編))〜
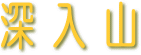 |
(前編) |
【広島県 安芸太田町 令和6年9月28日(土)】
異常な暑さを記録した今年の夏。その暑さは9月になっても衰えることはなく、秋分を過ぎても猛威を振るっていました。ただ、乱れながらもやはり季節は巡っているようで、東京(多摩地域)では9月24日を境に急に秋がやって来ました。その変わりよう、「ウソだろ」ってくらいキッパリと。そしてこの秋の訪れを待って野山歩きに出かけました。行き先は深入山(1153m)。広島県北西部、西中国山地に位置するなだらかな山で、yamanekoにとって22年ぶりのご対面となる懐かしい山です。
今回の広島行きにはマツダスタジアムでのプロ野球観戦という別の目的があり、観戦後一泊して、翌日の夕方に広島を発つまでに一山登ろうと思い立ったわけです。野球のチケットを取った時点では優勝候補の筆頭にいたカープでしたが、観戦当日はCS進出も望み薄の4位という悪夢のような状況。それでもカープ応援グッズと山装備をリュックに詰め込んで、第二の故郷広島に向かったのでした。そして、到着した広島の街はまだ日差しギラギラの夏でした。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
翌朝8時半、駅前のレンタカー屋さんで車を借りて、一路深入山へ。国道54号線を北上し、広島ICから山陽道、広島道、中国道と乗り継いで、戸河内ICで下道に下り、そこから中国山地の奥深くに分け入ります。そして国道191号線を走ること30分、深入山の麓にある「深入山グリーンシャワー」の駐車場に着いたのは10時15分でした。
| MAZDA2 |
今回レンタルした車はMAZDA2。妻と二人、あとそれぞれのリュックだけなので、このサイズで十分です。コンパクトで運転しやすかったです。このクラスだと保険の特約をフルに付けても1万円ほどでした。
yamanekoは広島に行くときは現地でレンタカーを借りてあちこち行くことが多いのですが、いつも利用するレンタカー屋さんの場合、保険特約をどのランクにするかは当日店頭で決めることになっていて、その際は決まって最上ランクの特約を付けることにしています。というのは、5年前、レンタカーを運転中にもらい事故に遭い車が走行不能になったことがあり、その時たまたま特約をフルに付けていたおかげで、レッカーや替わりのレンタカーの手配など一切の手間と費用負担なしで処理され助かったことがあったのです。その時は目的地から広島に戻る途上での事故で、事故処理を終えてレッカー車を見送った後山の中の片田舎に取り残される形に(レッカー車は事故車を積んで広島に向かいましたが、地元の業者さんで同乗は不可でした。)。最寄りの営業所は逆方向約70kmのところにあり、やむを得ずそこまで事故の相手方の親族に送ってもらい、そこで替わりのレンタカーをゲットして別ルートで広島に戻るという(行程270km!)、どっと疲れる状況でした。しかも夜の雨の中を。でも、営業所には話が通っていてスムースに乗り継ぎができ、しかも広島でも到着まで店を開けて待っていてくれて、どこまでが特約内容に含まれていたのかは分かりませんが、ありがたかった思い出があります。
| 深入山 |
さて、車を停めた深入山グリーンシャワーとは、地元安芸太田町が設置している観光保養施設で、オートキャンプ場やスポーツグラウンド、サイクリングロードなどがあります。山の中にもかかわらず多くの利用者があるようで、駐車場も広々としていました。
その駐車場の正面に深入山が。登山道はここからまっすぐに延びています。深入山の標高は1152m。駐車場は810mちょっとなので、標高差は340mくらいになります。
| 管理棟 |
駐車場の脇には管理棟があり、中には観光案内所や売店などがありました。もちろんトイレも借りられます。
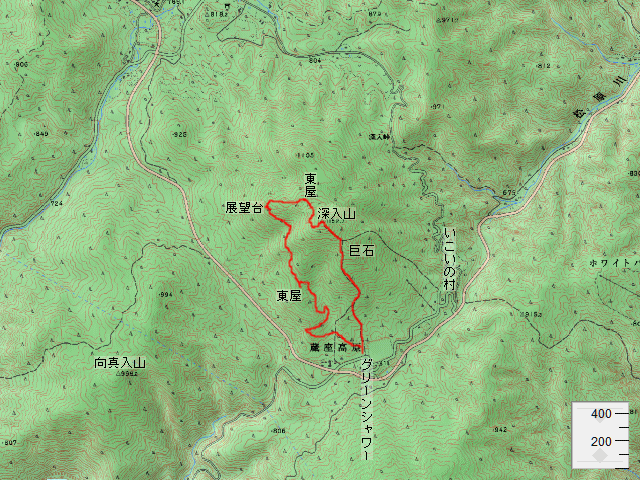 |
Kashmir3D |
今日のルートは、グリーンシャワーの駐車場から深入山南面を直登し、山頂へ。分かりやすいです。下山は一旦北側に回り込み西側山腹を下りてきます。深入山の南面は毎年早春に山焼きが行われるので、高木はなく見晴らしは最高です。一方下山に用いる道はもっぱら林間を通っています。
ところで、この地図を見ると、北東−南西の方向に2本の谷筋が並行しているのが分かります。深入山が位置する広島県西部一帯にはこの方向に走る断層が平行して何本もあり、山々はこれに沿った谷に削られ、航空写真で見るとまるでレンガを斜めにきれいに並べたように見えます(こちらのgoogleマップの航空写真参照)。レンガ一つ一つが大きな山塊で、その隙間が谷です。これは、この地域を覆っている花崗岩の節理の方向に断層が発達したからということです。ちなみに、海に浮かぶ宮島もそのレンガの一つで、谷の部分まで海水が進入して島になったことがよく分かります。
| スタート |
さて、準備を整えてスタートです。時刻は10時30分になっていました。yamanekoたちの前にも数組の登山者が出発していきました。
見てのとおり、ここから山頂までは草原の花々にたくさん出会えると思います。
| シラヤマギク |
最初に出迎えてくれたのはシラヤマギク。一番の特徴は葉の形。葉柄は長く翼があり、その先は長めのハート型です。あと、茎が赤みを帯びているところも。
| ママコナ |
ママコナです。久しぶりに見ました。ママコとはご飯粒のことで、花冠にある白い斑紋をご飯粒に見立てた名前だそうです。以前はゴマノハグサ科でしたが、現在はハマウツボ科だそうです(ハマウツボってどんなのだったっけ?)。
| サイヨウシャジン |
これも久しぶりに見ました。サイヨウシャジンです。多摩丘陵でよく見かけるツリガネニンジンにそっくりですが、花冠や萼片の様子など細部で微妙に異なっています。(花冠の広がりが大きい→ツリガネニンジン、小さく筒型に近い→サイヨウシャジン。萼片が反り返る→ツリガネニンジン、水平に広がる→サイヨウシャジン)
| ノギラン |
ノギラン。一見枯れているように見えますが、これが開花の状態です。そういえばこのノギランも多摩丘陵ではあまり見かけないような…。
草原状の山肌をジグザグに登っていきます。上空は晴れたり薄雲が広がったり。
| サワヒヨドリ |
これはサワヒヨドリだと思います。図鑑には湿ったところに生えると記されていますが、葉の形や付き方がどうもそれらしいのです。ネットで文献を探してみたところ、深入山のまさにこの火入れをする草地でサワヒヨドリが確認されているオフィシャルな調査結果があったので、これがサワヒヨドリであっても矛盾はないと考えた次第。
| ホクチアザミ |
ホクチアザミ。ずいぶんとスマートなアザミです。左の写真が開花前、右は開花後です。ホクチアザミのホクチとは漢字で「火口」と書き、これは火打ち石から火を移すための綿状にした繊維のこと。その繊維が一部のアザミの葉の裏から採れるのです。
| 風化流紋岩の土 |
深入山は主に流紋岩類の岩石でできているとのこと。それが風化した赤土の上を登山道が延びています。流紋岩は、その成分は花崗岩と同じで、マグマが地下深いところで固まったものが花崗岩、地表近くや地表に噴出して固まったものが流紋岩なのだそうです(中学校の理科の教科書情報)。
| ナガコガネグモ |
キョロキョロしながら歩いていると立派なクモを見かけました。大きさは10cm弱。ジョロウグモかと思いましたが、なんか違うような。調べてみるとナガコガネグモのようでした。確かに腹部の模様にジョロウグモの方は薄灰青色の帯があります。なにより決定的に違うのは網の大きさ。このナガコガネグモの巣はササの下に張られた小さなものですが、ジョロウグモは直径1mくらいのものも普通です。
登り始めて20分が経過。振り返ると駐車場がずいぶんと下にあります。左側のグラウンドではちびっこのソフトボール大会が開催されていて、ここまで歓声が届いていました。広島市内からも多くのチームがやってきているようでした。
| キキョウ |
秋の七草の一つ、キキョウです。「秋の」といいつつ場所によっては夏のうちから咲いていますが。秋の七草は万葉集に収められている山上憶良の詠んだ歌が基となっていて、萩、薄(すすき)、葛、撫子、女郎花(おみなえし)、藤袴、桔梗とされています。千数百年前に歌人を楽しませた花が絶滅することなく今も野にあることに軽く感動。
| ウメバチソウ |
これはウメバチソウですね。明るい草地や湿地で見られる花です。家紋の意匠に梅の花を模した「梅鉢」というものがあって、それに花冠が似ているからこの名になったのだそうです。確かに梅の花は(この花も)お鉢のような湾曲した形になっていますね。
| ワレモコウ |
草原といえばワレモコウ。小さな花がギュウギュウに寄り集まって、楕円形の穂のようになっています。これでもバラの仲間なんですよね。
| カワラナデシコ |
ちょっと傷んでいますが、これはカワラナデシコ。秋の七草の撫子はこの花のことです。
| オケラ |
キクの仲間、オケラ。漢字では「朮」と書くようです。他での使われ方を知らない漢字ですが、音読みはジュツで、確かに「述」や「術」にも似たパーツが使われていますね(あれは「ホ」に点じゃなかったんだ。)。ちなみに昆虫のオケラは正しくは「ケラ」で、漢字では「螻蛄」と書くのだそうです。
| ハバヤマボクチ |
草波から高く伸び出すハバヤマボクチ。頭花の様子が禍々しいですね。名前は葉場山に生える火口(ほくち)という意味。葉場山とは茅刈り場がある山、すなわち草原状の山のこと。火口はさっき見たホクチアザミのホクチと同じ意味で、ここではその原料となるアザミのことを指しています。
南西に向かってまっすぐに谷が延びています。その谷の奥右側の山が恐羅漢山(1346m)、左側の山が十方山(1328m)で、鞍部が水越峠。その峠を超えると細見谷と呼ばれる奥深い渓畔林が続いていて、以前その谷で何回か自然観察会をしたことがありました。本当に自然の深部に入り込んだという気がしました。
| アキノキリンソウ |
山野の秋を飾るアキノキリンソウ。別名をアワダチソウとも。セイタカアワダチソウはアキノキリンソウの背の高いバージョンということでしょう。確かに両種とも同じアキノキリンソウ属で、頭花はよく似ています。この属の植物は北アメリカに特に多いそうで、アメリカを代表する野草の一つなのだそうです。それを知ると見方も変わってきますね。
| ムラサキセンブリ? |
ああ、これは開花前のセンブリですね。高さは15cmほど。他の草に紛れていましたが、たまたま目に止まりました。この深入山はムラサキセンブリも有名なので、もしかしたらそっちかもしれません。
キキョウの花冠の中央に注目。キキョウは先に雄しべが成熟します。左の写真は成熟した5個の雄しべが雌しべにに寄り添うようにまとまっている状態。右の写真は、役目を終えた雄しべが雌しべから離れてバラけ、今度は雌しべが成熟し始めるところです(成熟した雌しべは先端が星型に5裂します。)。
| 南西方向 |
更に登ってスタートから1時間が経過。さっき振り返った恐羅漢山の方向です。手前の濃い山影と奥の山々との間には国の特別名勝の三段峡があります。花崗岩の摂理に沿うように柴木川が削り込んだ深山幽谷です。ここから恐羅漢山方向にまっすぐに延びる谷筋とちょうど直行するように延びています。ちなみに、特別名勝とは文化財保護法が定める名勝のうち特に重要とされたものだそうで、天然記念物のうち特に重要なものを特別天然記念物とするのと同じ法的根拠をもつものなのだそうです。
| オミナエシ |
ここにも秋の七草のメンバーがいました。オミナエシです。普通、ひと叢、ふた叢と、ある程度まとまって生えるのですが、ここではぽつんと一株だけ。ちょっと寂しそうでした。
秋の深入山。長閑な山容です。奥のピークが頂上か。だいぶん近づいてきました。
ん?手前の稜線上に何かありますね。ずいぶん大きな岩みたいです。
| コウゾリナ |
コウゾリナ。花冠はタンポポに似ていますが、茎はタンポポよりも細く長く、全体にスマートな容姿です。でも、触るとザラザラしていています。
| リンドウ |
ササ群落の中に咲いていたリンドウ。ずっと以前、ここ深入山で「二つの竜を探そう」というテーマで観察会をしたことがありました。スタッフが考えていた二つの竜とは、このリンドウ(竜胆)とリュウノウギク(竜脳菊)のことでしたが、参加者の中にはギンリョウソウモドキ(銀竜草擬)も見つけた人がいて、結局竜は三ついたというオチになりました。
| モリアザミ |
草原のアザミですが名前はモリアザミ。モリアザミの総苞片は棘状ではなく、細長い葉のように横に広がっているのが特徴。根は味噌漬けにして「やまごぼう」の名で売られていたりするそうです。
| サルトリイバラ |
サルトリイバラの実が色づき始めていました。食べて美味いという話は聞いたことがありません。この時期には酸っぱいながらもまだ実が詰まっているようですが、真っ赤に熟す頃には中はスカスカになってしまいます。
| ヤマハッカ |
ヤマハッカ。似たような花はいくつかありますが、唇形花の形に特徴があります。下唇は左右が内側に巻いて舟形に。上唇は4裂し、これはシソ科の花では珍しいのだそうです。
| 流紋岩の岩塊 |
さっき見上げた巨岩のところまでやってきました。ぱっと見、3m四方くらいの大きさがあります。流紋岩はこのような岩塊を残すことが多いのだそうです。
中国山地の中西部は広く花崗岩に覆われていて、この地に暮らす方には身近な岩石です。仮に花崗岩は知らなくてもそれが風化した「マサ土」はみな知っているでしょう。一方、同じ成分の岩石でありながら流紋岩が大規模に広がっていないのは、この地方の地形が隆起準平原で地質が古く、かつての地表面が消失しているところも多いからではないでしょうか。
| マツムシソウ |
マツムシソウの頭花はたくさんの花が集まってできているもの。一見キクの仲間のようでもありますが、キクとはあかの他人です。
下から見上げると立方体のように見えましたが、真横から見るとこんな感じでした。まるでお立ち台みたいです。yamanekoも上がってみようと思いましたが、女の子二人組が居座っていたのでやめておきました。
来た道を見下ろすとこんな感じ。グリーンシャワーも随分小さいです。視線を上げると南の方角にある遠方の山々も見えました。ここから25kmほど先にある大峯山や東郷山だと思います。
さて、山頂に向かいます。ここからの標高差は50mほど。
| ヤマラッキョウ |
シャンデリアのようなヤマラッキョウの花。こんなに華やかなのにネギの仲間です。
いよいよ山頂はすぐそこに。腹減ったぞー!
| 山頂 |
そして12時45分、山頂に到着しました。登り始めから2時間15分。花に出会うたびに立ち止まって写真を撮りながら登ったにしてはまあまあのペースでした。
山頂には4、5組の登山者が腰を下ろしていました。yamanekoたちもリュックを下ろして昼食です。(後編につづく)