
三瓶山 〜懐かしの故郷の山(後編)〜
 |
(後編) |
【島根県 大田市 平成27年7月20日(月)】
11年ぶりの三瓶山。後編です。(前編はこちら)
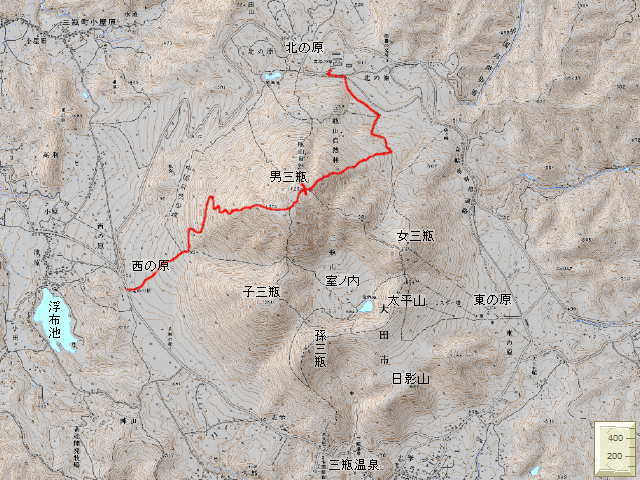 |
Kashmir 3D |
西の原から男三瓶の山体を直登しはじめ、樹林帯を抜け、標高も1千mを超えました。
| カワラナデシコ |
カワラナデシコ。涼しそうですな。雨に濡れると残念な感じになるんですが。
むむ、傾斜が急に緩くなりました。そろそろ山頂部か。
| 山頂部 |
男三瓶の山頂部は広くテーブル状になっていて、まるで空中に浮く草原のようになっています。その山頂部の中で一段上がってもう一段上がった写真左奥の部分が三角点のあるピークです。ここまで来たらもうまったく苦しくありません。
| シモツケ |
厳しい気象条件のこの場所にもたくさんの花が咲いています。これはシモツケ。バラの仲間です。
| シコクフウロ |
これはシコクフウロか。
一段上がってしばらく行くとルート脇に遊歩道的な木道が。何のためのものなのか不明です。周囲は裸地になっているにで植物観察のためではないでしょうし、その先の室ノ内を方面を覗き込むこともできません(崖になっていて危険です。)。可能性としては火山噴出物の堆積の様子を観察できるということかもしれません。確かに噴出物が層になっているのはよく見てとれました。
| 三段目 |
進行方向に向き直ると三角点のあるピークが目の前に。あとちょっとです。このピークはテーブル状の山頂部の北端にあり、幅20m、長さ100mの南北方向に細長い形をしています。登山道はそのど真ん中に上がるように延びています。
ピークに上がったら、まず木道を伝って南の端に行ってみます。室ノ内方面です。
| 室ノ内 |
眼下に火口のような室ノ内の窪みが大きく口を開けています。あそこが室ノ内です。その向こう、ちょうど正面に見える山が太平山。その左が女三瓶、右が孫三瓶です(パノラマ処理しているので平坦に見えますが、実際にはそれぞれかなり標高差があります。)。
以前は、この場所に今の三瓶山よりはるかに高く大きな一つの山があって、その山の大噴火で山頂部が吹き飛んだことによって環状にピークが残ったのが現在の男三瓶や子三瓶など5つの山、そしてこの時の噴火口が室ノ内ではないかと考えられていたようです。しかし、現在では、室ノ内での噴火はあったもののそれは小さなもので、5つのピークは大きな山体の一部分ではなくそれぞれ別個の噴火によってできた溶岩円頂丘であるとする説が有力なのだそうです。
| 三角点は |
さあ、折り返して、三角点のある北側に行ってみましょう。手前左手に立っているのは三瓶山山頂の標識。奥にあるのが方位盤で、三角点はその側にあります。
と言いつつも三角点の写真は撮り忘れたので、標識を。高さは3mくらいはあります。誰もいないように見えますが、このとき山頂には7、8人はいました。時刻は10時35分です。
| 三瓶山山頂神社 |
これは山頂神社。以前はもっと三角点の近くにあったような気がするのですが。
| 北方向 |
北側の行き止まりは20畳ほどの木製のデッキになっていて、その上のベンチに腰掛けました。そこから見える北側の風景がこれです。写真左端に大田市街。中央やや右には島根半島に続く弧状の砂浜が見えます。あの近くには出雲大社があります。
| 若者たち |
静かだった山頂に急にドヤドヤと若者が上がってきました。その数50人以上。しかも皆んな屈強な体をしています。声をかけてみると、石見智翠館高校のラグビー部の面々でした。ラグビーでは全国的な強豪校です(野球部の甲子園出場おめでとう!)。北の原から登ってきたようで、これから5つのピークをぐるっと巡って、再び北の原に下りるのだそうです。しばらく休憩していましたが、引率の先生のかけ声のもと、あっという間にいなくなってしまいました。
| 大田市街 |
昼食後、あらためて景色を眺めます。望遠レンズで捉えた大田市街。冒頭の写真はあの中のどっかから撮りました。
| 島根半島 |
島根半島方面にズーム。弧状の浜は「稲佐の浜」といい、神在月(出雲以外では神無月)に全国から出雲大社に集まってくる神々はこの浜から上陸するとされています。出雲大社はこの浜のすぐ近くにあります。半島の先端には日御碕灯台があります。子供の頃、「東洋一」の灯台と聞かされていました。何が東洋一だったかというと海面から灯りまでの高さだそうです。「東洋一」ってなんか昭和の匂いがしますね。ちなみに歴史的文化的価値の高い灯台と言われています。
反対の南方面。細く伸びるピークの外側にテーブル状の山頂部。広々とした景色で気分爽快です。
| 南東方向 |
山頂部南東方向。避難小屋が見えます。下山路はあの小屋の手前を左に折れていく道です。
11時15分、下山開始。ピークから一段下ったところにあるここの分岐を左に折れるのですが、その前に避難小屋周辺を散策してみます。
| 避難小屋 |
なかなかしっかりした造りの小屋。中はきれいにされていて、小屋の利用者が自由にメッセージを残せるノートが置いてありました。
振り返ってさっきまでいたピークの方を。
| ウツボグサ |
ウツボグサ。生き生きしていますね。
さて、あらためて下山です。山頂部の縁から森に入り、すぐに急降下していきます。
三瓶山の北側斜面には自然林が残っていて、大切に保護されています(三瓶山は大山隠岐国立公園の一部です。)。特に天然のブナ林はこの辺りでは貴重なのだそうです。温暖な中国地方ではブナが自生するのは標高900mくらいから上。これが関東地方ではだいたい600mくらいから出始めます。
| アカショウマ |
森の中の数少ない花、アカショウマ。赤くないけどアカショウマ。
| ヤマジノホトトギス |
ヤマジノホトトギス。何でこんな形に?
気持ちのいい山道。こんな感じの山道を延々と下っていきます。
| 天然スギ |
こちらは天然スギ。これから下りる北の原の約3km先には、直近の噴火(約4千年前)で流れ下った大火砕流が谷をそっくり埋めてしまい、そこに林立していた大スギをそのまま現代まで密封保存していた場所があります。平成の初め頃に圃場整備の過程で偶然発見された太古の森。三瓶小豆原埋没林といい、学術的にも大変貴重なのだそうです。現地にはミュージアムもありますが、訪れてみると広場にポツンと入り口があるだけ。ミュージアム本体は地下にあり(埋没林だけに)、地上部にはドアだけがあるという仕組みになっています。
その後も下り続け、ずいぶん傾斜が緩くなった辺りで分岐が現れました。目的地は左。右は…、トイレ? こんな森の中に?
しばらく行くとまた分岐。ここは右です。地図で確認すると、直進しても北の原に出るようですが、それまでに大きなアップダウンがあるようです。
| 下山完了 |
おっ、アスファルトの道に出ました。ここで山道は終了のようです。時刻は12時30分、下山を開始してから1時間15分でした。
| 青少年交流の家 |
しばらく歩くと国立三瓶青少年交流の家が現れます。ここにバス停があり、大田市街まで路線があります。当初の予定ではここからバスに乗るつもりでしたが、親戚が迎えに来てくれるというので、お言葉に甘えることに。 近くにある三瓶自然館サヒメルで時間を潰して迎えを待つことにしました。
帰りに寄った三瓶山のビュースポット。浮布池 の西岸にある小さな公園からの眺めです。池越しの三瓶山の構図がよく、観光パンフレットなどにここから撮影したものがよく使われています。ちょっと上空に雲が出てきて日差しが遮られましたが、やっぱりいい眺めです。
ここからだと孫三瓶もちょっと見えていますね。
今回、11年ぶりに三瓶山に登りました。やっぱり故郷の山は良かったです。なかなか帰省する機会も少ないので次にいつ登ることができるのか分かりませんが、今度はぐるっと一周したいと思います。