
大山 ~信仰の山で花々に出会う(後編)~
 |
(後編) |
【神奈川県 伊勢原市 令和5年5月26日(金)】
丹沢の名山、大山での野山歩きの後編です。(前編はこちら)
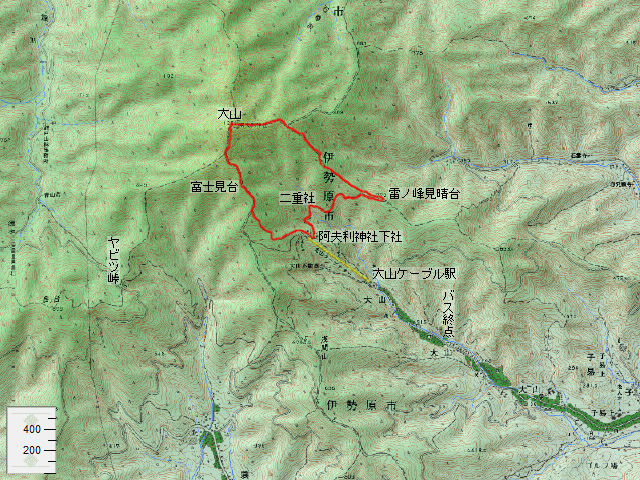 |
Kashmir 3D |
小田急の伊勢原駅からバスとケーブルカーを乗り継いで阿夫利神社下社へ。そこが今回の野山歩きの起点です。10時20分スタート。富士見台を経由して、12時10分に大山の山頂に到着しました。
| 本社 |
まずは阿夫利神社本社(上社)に参拝です。お膝元で遊ばせてもらっていることのお礼と、今日一日の安全をお祈りしました。
本社の東側は階段状の広場になっていて、登山者の多くはここでくつろいでいます。天気がよければ横浜方面の眺望が開けるはずです。
| 昼食 |
yamanekoもベンチに座って昼食です。定番のカップ麺。
| お客さん |
隣のベンチに座っていた二人組が「あっ、タヌキ!」 振り返ると人慣れした様子のタヌキがトコトコやって来ました。餌でもねだるのかなと思いきや、ふらっと冷やかして戻っていきました。特に痩せ細った感じではなかったので、食べるものには苦労していないのかもしれません。
| 下山開始 |
食事を済ませて少しまったりとしてから下山開始です。時刻は12時45分。登ってきた側とは反対側に下りていきます。
まずは雷ノ峰見晴台を目指します。
| 北東方向 |
山頂のすぐ下にも広場があって、そこからは橋本方面の眺望が開けていました。ずいぶん霞んでいますね。山水画か?
膝をいたわりながら、どんどん下ります。
ストックを持ってこなかったことを若干後悔しつつ、更にぐんぐん下ります。
| ミツバツツジ |
ミツバツツジの紫色の花。緑の中で目を引きます。丹沢にはトウゴクミツバツツジもあるので、念のために花冠の中を確認しました。遠目には違いが分かりませんが、ミツバツツジは雄しべが5個、トウゴクミツバツツジは10個あるのです。
| 不動尻への分岐 |
分岐が現れました。左に下れば不動尻(谷太郎川最深部)に至ります。yamanekoは右へ。
| 南西方向 |
南西方向、盆地に広がるのは秦野の市街地です。人口は16万人、かつては葉たばこの栽培が盛んだったと聞きます。街のど真ん中に専売公社の工場があったとか。「三公社五現業」、遠い昭和の響きを感じます。
| ツクバネウツギ |
ツクバネウツギ。漢字では「衝羽根空木」と書きます。羽根突きの羽根のことを衝羽根といい、この花の花冠が落ちたあとに残った萼片が衝羽根に似ているというのが名前の由来だそうです。
| ミツバウツギ |
今日出会った3つ目の「ウツギ」、ミツバウツギです。ミツバウツギ科なので本家のウツギの仲間ではありません。名前は、葉が3つの小葉からなっているから。この点さっきのミツバツツジと同じネーミングですね。
| マルバダケブキ |
小さな谷筋を埋めるマルバダケブキの葉。深山の湿ったところに生える大型のキクの仲間です。これから夏に向かって花茎を高く伸ばし、黄色い頭花を付けます。
| ヤマツツジ |
今日はこのヤマツツジの他、サラサドウダン、ミツバツツジの3つのツツジと出会うことができました。
眼下に阿夫利神社の門前町が見えました。昔は宿坊が立ち並び、大山詣での人々で賑わったのだと思います。
| ヤマボウシ |
ヤマボウシですね。ちょっと幽玄な雰囲気です。
| 鎖場 |
鎖場が現れましたが、凍結しているなどよっぽどのことがない限り安全に通過できそう。でもあるとありがたいです。
| 雷ノ峰見晴台 |
2時ちょうど、雷ノ峰見晴台に到着しました。急な下りはここまでです。ここでちょっと休憩を。
| ニシキウツギ |
ベンチで休んでいると目の前にニシキウツギがありました。今日4つ目の「ウツギ」。でもスイカズラ科なのでこれも本家ウツギとは他人の関係です。
| 分岐 |
見晴台の広場からは右手の小径に入ります。ちょっと見逃してしまいそうなほど存在感を消していました。間違えてこの分岐を直進すると日向薬師の方に下ることになります。
ここからは斜面をトラバースするかたちで少しずつ高度を下げていきます。滑落に注意との看板も。
| コゴメウツギ |
おっ、今日5つ目の「ウツギ」です。これはコゴメウツギですね。直径8mmほどの小さな花が寄り集まって咲いています。このウツギはなんとバラ科。完全に赤の他人ですね。
谷筋をパスするように架けられていた橋。結構高度感もありました。
| マルバウツギ |
その橋のたもとに咲いていたマルバウツギ。今日6つ目の「ウツギ」です。そしてこれはアジサイ科ウツギ属。まさに本家ウツギと同科同属で、兄弟と言ってもいいような関係です。ちなみに今日出会った「ウツギ」は、ノリウツギ、ツクバネウツギ、ミツバウツギ、ニシキウツギ、コゴメウツギ、マルバウツギ。卯の花とも呼ばれる本家「ウツギ」に出会えなかったのはちょっと残念。
| 二重社 |
阿夫利神社の摂社、二重社です。何が二重なんだろう。屋根? 下社も本社も尾根筋や山頂など明るいところに置かれているのに、この摂社が急な谷の奥に置かれているのはなぜだろう。祭神の高靇神が水の神だからか。いろんな疑問が湧いてきます。
| 二重の滝 |
二重社の脇にある二重の滝。水量は結構豊富でした。
ふむ、古の人々はこの滝に龍の姿を見たのかも。だからここに二重社を置いたとか(推測)。で、山頂の前社にも祀られているのにここにも祀るので「二重」だとか(こじつけに近い推測)。
| ??? |
登山道を歩いていると前を黒い鳥が横切りました。大きさはヒヨドリくらい。嘴と足は黄色です。鳴き声は聞いていません。帰宅後調べてみたのですが、少なくとも「フィールドガイド日本の野鳥」(日本野鳥の会発行)には該当する鳥はありませんでした。よく似ているものにクロウタドリというものがありましたが、足は黒いです。そしてなによりごくまれに迷鳥として確認される程度の出現率とのことなので、ちょっと違うかなと。九官鳥かなとも思いましたが、九官鳥には後頭部にはっきりとした黄色い部分があるようです。何だろう。しばらくして森に中に消えていきました。
2時45分、下社手前の茶屋まで戻ってきました。ここが今日の野山歩きの終点です。怪我もなく無事にゴールできました。
| 帰りも1号車 |
帰りもケーブルカーで移動です。
車内は混んでいて、座れずに立っていたのですが、変な体重のかけ方をしていたのか、下車後左膝が痛み始めました。階段を下るときに突き刺すような痛みが生じる例の腸脛靱帯炎です。下車後に歩く門前町は延々と階段が続いていて、バス停に着くまで地獄のような時間でした。普通に歩く分にはなんともないのですが、電車の駅でも苦痛に顔を歪めながら階段を下りました。
恐るべし大山。やっぱり今回も膝を痛めて終わったというオチでした。