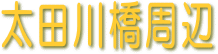
太田川橋周辺 〜水の流れの今昔し〜
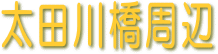 |
【広島県 広島市 令和5年3月5日(日)】
3月になりました。ようやく確かな春の訪れを感じるようになってきました。わが家のジンチョウゲも今満開になっています。
今回、諸々の用事があって広島に行ってくることになったのですが、せっかくなので久しぶりに広島自然観察会の定例観察会に参加させてもらうことにしました。yamanekoは10数年前までこの観察会でスタッフとして活動していました。自然観察の尽きない興味を教えてくれたyamanekoにとって恩人のようなグループなのです。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
さて、3月の定例観察会のテーマは「早春の太田川中流域周辺」。川辺をのんびり散策し、春を見つけましょう、というものです。
広島は「川の街」と呼ばれ、それを象徴するのが太田川です。市街地は太田川の河口部に形成されたデルタの上に広がっていて、昔は「広島七川」と称されたそうです。これは広島の街を東西に横切ると太田川が分かれた7つの川を渡ることになるということで、いかに川が多いかということを表した言葉です。現在は戦後の河川改修の結果、川は6つになっています。
| 上八木駅 |
集合は、9時45分、JR可部線の上八木駅前に。駅前の広場には時刻までに30人が集まっていました。スタッフは5人ほど。皆懐かしい面々でした。
可部線は電化はされていますが単線というローカル路線で、日中の車両はガラガラです。でも郊外の住宅地を結ぶ路線なので、朝夕の通勤時間帯はびっちり詰まるほど混雑したりします。上八木駅は1面のホームに上下線とも停車するシンプルな駅で、駅舎も看板がなければそれとは気がつかないほど住宅街に馴染んでいました。
さあ、ここに長居するご近所迷惑なので、とりあえずひとかたまりになって話ができる川土手の上まで移動です。
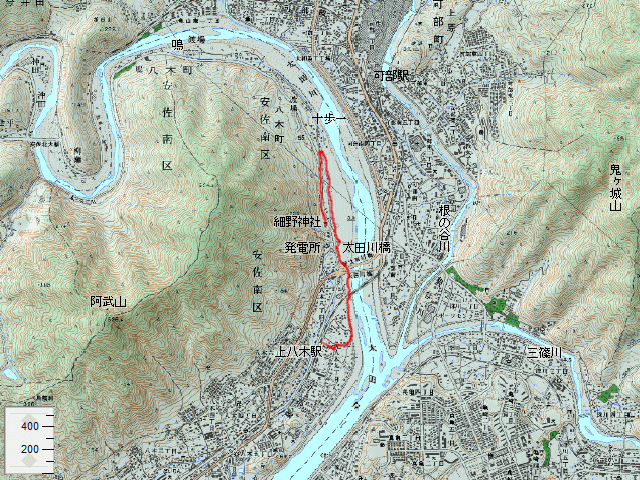 |
Kashmir3D |
今日のルートは、上八木駅から太田川の土手に上がり、上流に向けて歩きます。太田川橋(安佐南区と安佐北区を国道54号線で跨ぐ橋)をくぐって、八木用水沿いに北上し、途中で河川敷から車道に上がって終点の細野神社まで引き返すように歩きます。
路地沿いにある畑です。ホウレンソウが痛々しい感じに。ヒヨドリの仕業だそうです。
この辺りの畑の土は関東で普通に見る黒っぽい土ではなく、黄土色です。太田川が運んできた川砂が主体なのかも知れません。ということは中国山地の土ということか。
| 土蔵 |
途中、古い土蔵があり、その下部にこの地域で暮らす上での工夫の跡が見て取れました。石を積んで土台をかさ上げしています。つまり、この辺りは大水が出ると水に浸かっていたということだと思います。石が丸いところを見ると河原の石を利用したのでしょうか。長く水と折り合いを付けながら暮らしてきた地域なんでしょうね。ただ、大水には悪い面だけでなく、肥沃な土を運んできてくれ、そのためここ八木を始め、隣接する緑井、川内といった地区は畑作が主要な産業になったということです。特産の広島菜は有名ですね。
| 白梅 |
白梅の勢いがすごいです。五分咲きくらいでしょうか。
畑が広がっています。水田はなく見渡す限り畑ということは、この辺りは昔から水の便が良くなかったということなんでしょうね。すぐ横を太田川が流れているんですが、河床が低く取水できなかったということのようです。
| 土手の上 |
小径をぞろぞろと移動し、川土手に上がってきました。ここであらためてスタッフから今日の観察のポイントなどについて説明がありました。
目の前には太田川。この川は、広島県西部の吉和冠山に端を発し、上流域では北東に流れます。それが安芸太田町加計で90度折れて中流域では南西に向けて流れ、更に広島市安佐北区可部で90度角度を変え、下流域では南西に向けて流れます。最後は広島市街で6つの流れに分かれて広島湾に注ぐのです。(この90度ターンについてはこちらを参照)
| 水鳥観察 |
早速、水鳥を発見。この辺りは、山間を巡ってきた太田川が開けた場所に出る地点で、ちょうどここに支流の三篠川、根の谷川が合流してきて、なおかつすぐ下流に高瀬堰があるので、比較的川幅が広くなっています。鳥たちものびのびしているようです。
| キンクロハジロ |
遠くになにやら黒っぽいカモが。キンクロハジロです(カメラの性能的にこれが限界)。時折水中に潜り、ややあってちょっと離れたところに浮上します。
| モズ |
一方、陸地の方を見ると、畑に立てられた竿にモズが停まっていました。長い尾を回すように上下に動かし、地面の餌を探していました。時折飛び降りて、すぐにまた元の位置に戻ってきます。
この辺りは背後の阿武山と前面の太田川に挟まれた地形。昭和40年代以降、広島の中心市街地が拡大するにつれて住宅街が広がっていった地域で、昔からの家と比較的新しい家、そして畑地が混在する地域となっています。
| 南原ダム遠望 |
上流方面を見ると山並みが壁のよう。左手の尖った山は可部冠山です。正面には南原(なばら)ダムが見えていますね。このダムはロックフィル式という形式で、コンクリートダムではなく石積みのダムです。
土手の上をのんびり歩いて行きます。チュルピルチュルピル。頭上からヒバリの鳴き声が聞こえました。鳥類観察の指導を担当している方によると、そろそろ鳥たちがさえずりの練習を始める時期なのだそうです。
| カンムリカイツブリ |
カンムリカイツブリもいました。こっちも潜水カモです。ついこのあいだ葛西臨海公園で見かけました。
| 阿武山 |
阿武山。yamanekoも何回か登ったことがあります。平成26年の豪雨災害の際には山肌の谷筋という谷筋で土石流が発生し、麓に多くの被害をもたらしたと聞きます。今でもその痕跡がみてとれます。
| 右:太田川鉄橋 左:太田川橋 |
太田川鉄橋の下をくぐります。実はこの場所には3本の橋が架かっていて、下流側からJR可部線の太田川鉄橋、国道54号線上りの太田川橋、同下りの新太田川橋です。写真は太田川鉄橋と太田川橋との間で撮ったものです。昭和28年までは、鉄橋は太田川橋の北側(写真でいうと左側)に架かっていたのだとか。
| ノイバラ |
ノイバラの葉が展開し始めていました。黄土色一色の世界に緑が鮮やかです。
| JR可部線 |
安芸亀山発、広島行き普通電車。
太田川橋の下あたり、土手から水辺を覗くと道水管の出口があり、結構な量の水が放流されていました。これはこのすぐ先にある太田川発電所で水力発電に用いられた水で、ここで太田川に放流されているのです。
| 太田川橋 |
国道54号線下りの太田川橋はトラス橋。現在の橋は昭和32年に架けられたものだそう。yamanekoよりちょっと先輩です。
| 足跡 |
ぬかるみに獣の足跡が。これはシカの足跡だそうです。この辺りにも出没しているんですね。山に餌が不足しているということでしょうか。
| 太田川発電所 |
新太田川橋をくぐると、山側に発電所が現れました。中国電力の太田川発電所です。
太田川を遡ると川沿いにいくつもの発電所を見かけます。いずれも上流で取水し、その水を山中を貫く導水管を通して発電所の頭上まで運んで来て、そしてそこから山の斜面のパイプを通し発電所へ一気に落として発電しています。ここ太田川発電所も約10km離れた上流の間野平発電所で放流したものをすぐに取水して、山中を通して頭上40mのところに運び、落としているのです。すなわち、取水−導水(送水管)−発電−放水を繰り返し、ほとんど河道を通ることなく下流へ送られているということです。水の使い回し、というか有効利用ですね。
水を落としている導水管が見えますね。太田川の両岸に連なる山々の中には、この導水管がいくつもの発電所を経由しながら本当の川の流れとつかず離れず延々と走っているのです。いわば「隠れ太田川」ですね。この導水管、内径は約4mもあるのだとか。相当量の水が山の中を流れていることが分かります。
この導水管は、大きく2系統の導水ルートがあるようです。
ひとつは、芸北町八幡にある聖湖からスタートして三段峡下流の柴木を経て、戸河内町の土居で立岩貯水池からスタートした流れと合流、筒賀村の吉ヶ瀬を経て安佐北区の間野平に向かうルート。
もうひとつは、芸北町の王泊ダムからスタートして、加計・滝山で松原川からスタートした流れと合流し、加計町の安野を経て間野平に向かうルート。
この2つのルートが間野平で合流し、最終的に太田川発電所にやって来ているのです。
これらの発電所の多くが造られたのは大正から昭和初期。当時の技術をもってこれだけの構造物を造るのは並大抵のことではなかったでしょうね。
昔、川船が行き交っていた太田川はこの「隠れ太田川」ができたこともあって水量が減り、また、取水のための堰堤なども各所に造られたことから、船を通わせることはできなくなったといいます。
| 八木用水 |
発電所を過ぎてからは、八木用水に沿って歩いて行きます。幅1.5m。三面コンクリートの用水路ですが。この用水には長い歴史があるようです。
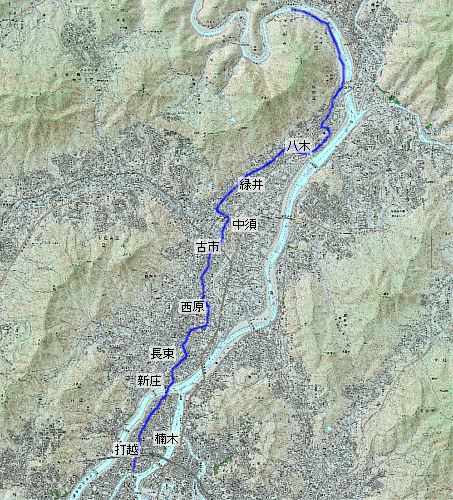 |
八木用水流路(おおまかに) |
江戸時代、現在の広島市安佐南区の太田川右岸側は水に乏しい地域だったそうです。広島藩が何度も灌漑工事を試みるもその都度上手くいかず、それを見ていた地元の卯之助という大工さんが、自ら測量し、全長15kmの用水をわずか25日間で完成させたのだそうです。その水は下流の9か村(八木、緑井、中須、古市、西原、長束、新庄、楠木、打越)を潤し、現在の横川駅付近で当時の福島川注いだとのこと。広島菜を始めとした野菜の生産は、この用水あってものだったのですね。
当初はこの先2kmほどのところにある十歩一というところで取水していたそうですが、水害や太田川の水位低下で、大正時代には更に上流の鳴というところから取水するようになったのだそうです。昭和になって太田川沿いに発電所ができ始めると川の水位が更に下がり、取水が困難になってきたことから、今度は逆に太田川発電所から出る水を分水し、その一部を八木用水に供給するようになったのだそうです。したがって、八木用水はここから下流では滔々と流れていますが、上流側(これから歩くあたり)はせせらぎ程度の水量しかありません。
| 太田川へ |
現在、鳴で取水された八木用水は、その流れの大部分をこの場所で太田川に流し、残りの流れに発電所からの水を加えて用水の下流部に向かって流れて行きます。
おや、こんなところに広島自然観察会の旗が。今日はこの辺りで観察会をやっていますよ、ということでしょうね。
| 頭骨 |
河原に骨が落ちていました。シカの頭骨のようです。ここで死んだわけではなく、他の動物がどこからか運んできたものではないでしょうか。
用水脇のコンクリート部分を歩いて行きます。
それにしても今日はポカポカ陽気で春本番といった感じ。花粉もハンパなく飛んでいるようです。
| センダン |
河原で見かけることの多いセンダン。流れてきた種子が定着しやすいのでしょうか。
両側に木が増えてきました。右手は人の手によって清掃がされているようでしたが、左手の法面の林床には大水で流れてきた瓦礫などが結構残っていました。
| シメ |
落葉した木の高い梢にシメが来ていました。太い嘴が特徴です。シメはいつもてっぺんに停まっているような気がしますが、実際どうでしょうか。
| ユキワリイチゲ |
ところどころユキワリイチゲの葉が見られました。まだ花を付けるといった段階にまで育っていないようでしたが。
| ヤマアイ |
これはヤマアイの若葉。山に生える藍という意味の名前で、藍と同様に染料になりますが、藍色ではなく緑色に染まるのだそうです。
| ユキワリイチゲ |
おお、ユキワリイチゲが咲いていました。以前はその数も多かったそうですが、ここ数年めっきり減ったのだそう。人の踏みつけで地面が固くなったのが原因の一つではないかとのことです。
用水の周りがそれっぽくなってきました。
| アラカシ |
アラカシの冬芽です。5つの稜があり、真上から見ると五角形っぽく見えます。
| ニワトコ |
ニワトコの混芽が展開し始めていました。一つの芽の中に花と葉の両方が格納されています。窮屈だった冬芽時代を終え、これから伸びやかに広がっていきます。
| ヤブツバキ |
通路脇にヤブツバキが。雪にも似合うし、今日のような春の陽射しにも映える花です。
用水沿いをしばらく歩いたら一段上を走っている車道に上がり、終点の細野神社を目指します。
民家(空き家)の脇にあったヤブツバキ。放置されているのか、繁り放題でした。でも花付きのいいこと。
| テングチョウ |
車道に出たら折り返す形で歩いて行きます。
道端でテングチョウが体を温めていました。成虫のまま越冬し、早春から飛び回るそうです。よく見ると頭部に天狗のような突起があるのが分かります。
| ホトケノザ |
春の使者、ホトケノザが咲いていました。野草界の「キング・オブ・のどか」です。
| 細野神社 |
12時20分、細野神社に到着しました。ここまでのんびりと歩いてきましたが、それでもうっすらと汗ばむくらい、いい運動になりました。
平成26年の豪雨の際には、神社の裏手の谷筋で土石流が発生し、この地にあった卯之助の顕彰碑が流失したそうですが、3年後に無事元に戻されたとのことです。神社の拝殿も全壊し今は再建されています(手前の壁が白い部分の建物)。その奥の本殿は難を免れたのだそうです。
| 閉会 |
境内の大タブの木陰で今日の振り返りをしました。今日は参加した方々はポカポカ陽気の下で自分なりの春を見つけることができたのではないでしょうか。
その後、観察会からの告知が。これまで毎月観察会を行ってきたのを、新年度から少しやり方を変えるそう。yamanekoがお世話になっていた頃のスタッフが今も行っているわけですから、高齢化もしているし、企画、現地との調整、下見、本番、会報の作成・発行など仕事や家庭と両立させながら毎月回していくのは相当大変だと思います。気まぐれに参加するお気楽なyamanekoとしては心苦しいばかりですが、これからも長く続いてもらえればと願うのみです。