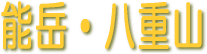
能岳・八重山 〜里近い山で秋を堪能(後編)〜
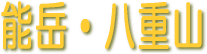 |
(後編) |
【山梨県 上野原市 令和5年10月22日(日)】
今回訪れた能岳や八重山は上野原の裏山的な存在。地元の人々の生活と深く関わってきた山です。そんな典型的な里山を歩く。その後編です。(前編はこちら)
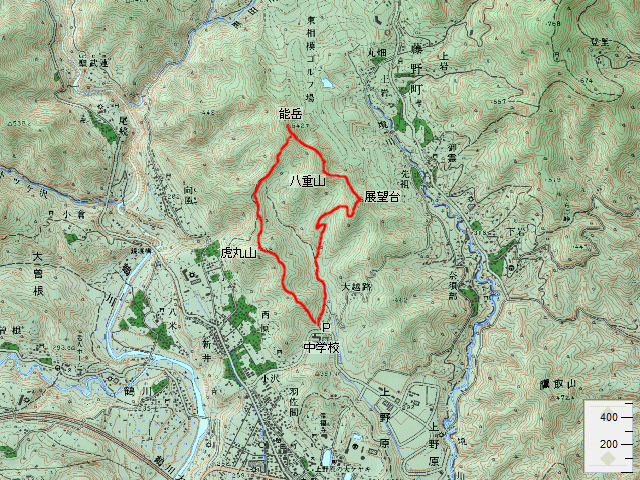 |
Kashmir 3D |
上野原中学校の裏にある駐車場をスタートし、谷筋を登って展望台へ。そこから稜線を歩いて八重山、能岳へと進み、虎丸山を経由して戻ってくるというルート。前編では展望台と八重山の間の鞍部にやって来たところまで紹介しました。
なだらかな鞍部を八重山山頂に向かって歩いて行きます。
階段が見えてきました。写真では分かりにくいですがそこそこの斜度です。
| もち? |
しんどい登りの途中、かわいらしいキノコを見つけました。炭火で焼いた餅みたいです。一応図鑑でも確認してみましたが、なんなのかよく分かりませんでした。
| 八重山山頂 |
鞍部からの標高差50mを一気に登り、八重山の山頂に到着しました。時刻は12時25分です。
| 八重山からの眺望 |
山頂には多少の木立はあるものの、概ね良好な眺望でした。写真は桂川が刻んだ地峡部分で、正面奥に三ツ峠山が見えています。
ちなみに、もともとは八重山という名前の山はなく、能岳から連なる名もなきピークの一つだったそうです。それが八重山と呼ばれるようになったのは、地元出身の水越八重さんという方の存在。昭和初期に八重さんが「お世話になったふるさとや、子どもたちのために役立てて欲しい」と30ヘクタールの山林を寄付され、それを機に八重山と呼ばれるようになったということです。
命名からもうそろそろ100年が経過しますが、現在、国土地理院の2万5千分の1の地図には八重山の記載はありません(能岳の記載はあり)。そう考えると山名の掲載基準ってどんなものなんだろうと興味が湧いてきます。
| 昼食 |
例によって食べ始めた後の昼食の図。空腹に負けてつい写真を撮る前に食べてしまうのです。今日はコンビニで調達したおにぎりと焼き鳥です。
| 鞍部 |
富士山が雲間から姿を現すことを期待して山頂で30分ほど休憩しましたが、一向にその様子がないので能岳に向かうことにしました。八重山からは40m下って50m登り返すことになります。
| 道祖神 |
鞍部から登りかけるところに道祖神がありました。ここが村境の峠だったんでしょうね。道祖神は塞ノ神(さいのかみ)ともいい、「塞」の字が用いられているとおり、病疫や災いの侵入を塞ぎ村に入ってこないよう祈願したもの。村境に置かれることが一般的です。地名として残っているところも多々あり、地域によっては幸ノ神とか才ノ神といった字が充てられているところもあります。
この道祖神をよく見ると左右に文字が彫ってあり、右側は「享和二年三月九日」と、左側は「西原村 施主 高橋礒○」と読み取れました。享和二年は1802年。全国的にみて道祖神が多く作られたのは18世紀から19世紀にかけてということで、ちょうど盛んな頃だったといえます。西原村とはかつて西麓にあった村で、現在も集落名として残っています。それにしても200年以上もここで災厄の侵入を防いでいるんですね。お疲れ様です。
うむ、なかなかの登りですな。
| テリハノイバラ |
これはテリハノイバラの果実でしょう。小葉がやや丸っこいところがノイバラと違うところ。
| エンコウカエデ |
エンコウカエデ。全く紅葉していませんね。葉は深く切れ込んで縁に鋸歯がなく、波打っているところが特徴です。
| 能岳山頂 |
木々の実や葉を見ながらゆっくり登ること10分。能岳の山頂に到着しました。時刻は1時10分でした。
| 山頂広場 |
山頂はベンチがあるだけの広場でした。広さは学校の教室くらいか。
もともと眺望のない山頂だったようですが、今は富士山が見える方向の樹木が切られていました。今日は望めませんでしたが。
| リンドウ |
秋の陽をたっぷり浴びて綺麗に開いたリンドウ。いい色です。
| 鞍部 |
能岳の山頂では長居をせずに下山を開始しました。道祖神のあった鞍部まで戻り、ここを右手に下りていきます。写真にも写っているとおり、ここのハイキングコースは分岐という分岐にしっかりとした標識が設置されていました。ありがたいです。
能岳から南に延びる支尾根を下って行きます。
| 夫婦岩 |
しばらく行くと、路傍にタイヤほどの大きさの岩が2つあり、「夫婦岩」との標識が立ててありました。いろいろ調べてみましたが詳細は不明。
またしばらく行くと右手に祠のようなものが見えました。
| 馬頭観音 |
斜面を上って見てみると馬頭観音でした。頭の上に馬の首が乗っています。冷静に考えるとコミカルですね。一般的に馬頭観音は憤怒の形相をしていますが、ここの観音様は口元がかすかに微笑んでいて、人間っぽい優しい顔でした。
| アズキナシ |
転ばないよう足下を見ながら下っていると、赤い実が落ちているのを見つけました。拾い上げると、これはアズキナシ。見上げると頭上にアズキナシの葉が茂っていました。
| カラカサタケ? |
キノコブラザースと遭遇。これはカラカサタケでしょうか。
| 虎丸山への分岐 |
1時35分、分岐が現れました。ここは斜め左に登っていきます。直進すると麓の山風呂という集落へ続いています。
| ホコリタケ |
このキノコはyamanekoでも分かります。ホコリタケですね。
| 急登 |
虎丸山の山頂直下の急坂にさしかかりました。一応道ジグザグになっている箇所もありましたがほぼ直登。ズリズリと足が滑ります。
| 虎丸山山頂 |
1時50分、虎丸山に到着しました。山頂広場の半分くらいをこの建物が占めていました。中には祠のようなものがあり、この建物自体は祠を保護する役割のもののようです。
| 秋の空 |
見上げると午後の空。考えてみれば能岳を発ってからここまでずっと樹林の中を歩いてきました。青空が気持ちいいです。少し白み始めているのは秋になって日が短くなってきたからでしょう。
| 分岐 |
虎丸山では休憩することなく、下山を続けました。すぐに分岐が現れ、ここは直進。この分岐を右手に下ると麓の西原集落に至ります。
| 石の祠 |
途中で見かけた石の祠。麓の西原集落の方を向いて鎮座していました。残念ながら刻まれていた文字は読み取れませんでした。
| ニオイベニタケ |
ピンク色のキノコ。ちょっと食べられているところも可愛いです。ニオイベニタケかと思うのですが、図鑑でも確証は得られず。
| カシワバハグマ |
派手に葉っぱが喰われていますが、これはカシワバハグマですね。
| 小ピーク |
最後の小ピークまでやって来ました。なぜかビールケースが置かれていました。イス代わりか?
さあ、ここからは駐車場に向けて下って行きます。時刻は2時半くらいですが、なんだかもう夕暮れのような日差しですね。
| |
もうほどんと下山完了というところに祠がありました。二つの祠が一つの建物で守られています。近づいて見ると、左の祠の後ろの壁に「山ノ神」と記されていました。山の神は基本的には祖先の神です。人は死んだ後は山に向かうと考えられていたからだそうです。一方、右の祠の背後には厄神と記されていました。厄神とは厄除けの神様でしょう。昔から人々はいろんな神様に心を寄せながら暮らしてきたんですね。そういうことに思いを馳せるのも楽しいです。
祠を過ぎると駐車場が見えてきました。トコトコっと下ればすぐですが、そこはそれ、粘り強いというか往生際が悪いというか、ぎりぎりまでキョロキョロしてしまいます。
| ヤブラン |
これはヤブランの種子。通常、黒くなったものを目にすることが多いですが、これはまだ若いのか緑色ですね。これはこれで綺麗です。
| リュウノウギク |
いわゆる野菊といった場合、キク科の中のキク属とシオン属が二大巨頭ですが、キク属のものはお彼岸に供えられる菊のような正統派感があります。その中で、関東の平野部に住んでいる人にとってはリュウノウギクが最も身近に感じられるのではないでしょうか。端正な姿をしています。
| 駐車場 |
2時50分、スタート地点の駐車場に戻ってきました。怪我もなく歩けて良かったです。あとは整理体操をして帰途につくのみです。
今日はのんびり里山の自然を堪能することができました。植物だけでなく道祖神や祠など地域の歴史に触れられたのも良かったです。
出発する前に渋滞情報アプリを見たところ、上野原ICで高速道路に乗った時点で渋滞の中に入っていく感じだったので、帰りは甲州街道(国道20号線)を走ることに。そして、思惑どおりこれといった渋滞にはまることもなく、順調に家まで帰り着きました。