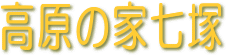
高原の家・七塚 ~自然探検隊で遊ぼう(2)~
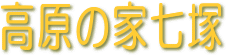 |
【広島県庄原市 平成16年10月17日(日)】
自然探検隊2日目。予想どおり今日も良い天気です。(1日目の様子はこちら)
午前中は近くの果樹農園に行ってリンゴ栽培の話を聞かせてもらいます。その後にはお楽しみの「もぎ取り」。おいしいリンゴが待っています。
| リンゴ農園で |
ここ岡島さんのリンゴ園は市民球場2個分の広さ。(東京ドーム何個分、といった表現でないところがローカルでしょ。ちなみに「市民球場」とは当然のこととして広島市民球場を指します。) 今年は度重なる台風の襲来によりほとんど出荷できない状況だそうです。1年間に1回しか収穫できない果樹。その無念さもいかばかりか。
| 落ちたリンゴ |
足下にはたくさんのリンゴが落ちていました。また、かろうじて枝に残ったリンゴも、強風にあおられ枝とこすれ合ううちにそこが傷になり、腐っていっています。見渡すと想像以上の被害です。
| 岡島さん | いただきまーす |
岡島さんは子どもたちにもわかりやすい言葉で、リンゴ作りの様子や自然を相手にすることの大変さなどを話してくれました。子どもたちはどんなふうに理解したかな。
それにしても、みんな朝ご飯をしっかり食べていたのに、ここでもリンゴ2、3個ペロリと食べていました。
リンゴ園の建物の軒下にキイロスズメバチが巣を架けていて、そこのハチがリンゴの果実を食べにやって来ていました。子どもたちも興味津々です。
野外での危険な生物ナンバーワンとしては、遭遇頻度、致命度からしてこのスズメバチを挙げなければなりません。昨日の山登りの際にもハチに出会ったときの対処について子どもたちに説明しましたが、巣に近づかないかぎり襲ってきませんし、こうやってリンゴを食べているハチを近くで観察しても、突いたり叩いたりしなければ何ともありません。不運にしてハチを怒らせてしまったら、まず姿勢を低くしてゆっくりとその場を離れることです。間違っても手を振り回して追っ払ってはいけません。ハチを興奮させるだけです。
午前11時、岡島さんにお礼を言って、高原の家に戻ります。
これからは午後のサツマイモ掘りの準備です。
| 芋畑 |
サツマイモ畑には、幅1m、長さ20mほどの畝が8本並んでいます。一班で1本の畝を担当して芋掘りをします。
現地に行ってみると、その畝の姿も定かでないほど葉が茂り、その下では蔓が縦横無尽に延び絡まっていました。
普通、学校行事などで芋掘りをする場合、この葉や蔓をすべて除去したところからスタートすることが多いので、本当のサツマイモの姿を見る機会は少ないと思います。
| ヨイショ! |
この蔓を引っぱがそうとしても大人でもビクともしません。蔓同士が複雑に絡まっているからです。なので、スタッフが畝と畝との間に渡っている蔓を切り、次いで地中へと延びている(すなわちそのすぐ下には芋が埋まっている)茎を切っていきます。そうして、まるでシーツでも剥がすように畝ごとに蔓の絨毯をめくっていくのです。
| スッキリしました |
やがて芋畑はマルチと呼ばれる黒いビニールシートに覆われた姿になりました。これは最初にサツマイモの苗を植えた時の姿です。葉っぱの下はこんな風になっていたのか。
さて午前中はここまで。実際に掘るのは昼食の後です。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| おぉ、あるある |
ふたたび芋畑にやってきました。昼食も済ませ、準備OKです。
さっそくマルチを剥がして、グループごとに畝にとりつきます。するとすぐにあちこちから歓声がわき上がりました。どのイモも予想以上にでかいのです。
| デカッ!? |
スーパーでは決して売っていないような形のイモに子どもたちは大喜びです。カボチャ型、グローブ型、胃袋型などいろいろありました。
あっという間にものすごい数のサツマイモが掘り出されました。あとはこれを焼き芋にして食べるだけ。しかもたき火で焼く正統派の焼き芋です。楽しみです。
| ①たき火 | ②熾き火にイモを |
①まず枯れ枝を集めてたき火をします。瞬く間に炎が立ち上がり近くには寄れないほど熱い。
②しばらくすると火がおさまり、熾き火になったところでアルミホイルに包んだイモを投入します。
| ③枯れ葉をかけて | ④できあがり |
③次にたくさんの枯れ葉を集めてきて、イモもろとも熾き火を覆い尽くして蒸し焼きにします。
④枯れ葉も全部灰になった頃、焼き芋もちょうどよくできあがります。たき火を始めてから1時間半程度でしょうか。
| はふ、はふっ うめーっ! |
アルミホイルを剥がすと香ばしい匂いが鼻腔に広がりました。でも、手で持つこともままならないほど熱くてしばらくは口にすることができません。やけど覚悟でかじってみると、ホクホクとした食感と素朴な甘みが絶妙なハーモニーを奏でています。(グルメ番組か?)
子どもたちも満足そうに頬張っていました。みんないい笑顔です。
そろそろ全てのプログラムが終わろうとしています。この二日間、子どもたちと密に接することができました。塾に習い事にテレビゲーム。子どもが野山で遊ばなくなったと言われていますが、どっこい彼らは逞しかった。大人たちが用意した自然体験プログラムだけでなく、子ども同士でいろんな遊びを考え出していました。棒があればそれでよし、水があればそれでよし、火があればそれでよし。彼らにとってはみんな格好の遊び道具です。
帰り際、子どもたちの口から「おもしろかったね。」とか「次もあるんじゃろ。絶対来ようや。」とかいった言葉を聞いたとき、疲れも一気にぶっ飛びました。自分自身も十分すぎるくらい楽しんでいましたし、来てよかったとホント思える二日間でした。