
宮古島 〜未知の花との遭遇(後編)〜
 |
(後編) |
【沖縄県 宮古島市 令和7年10月1日(水)〜4日(土)】
暦の上では秋なのに夏真っ盛り。南の島での野山歩きの後編です。(前編はこちら)
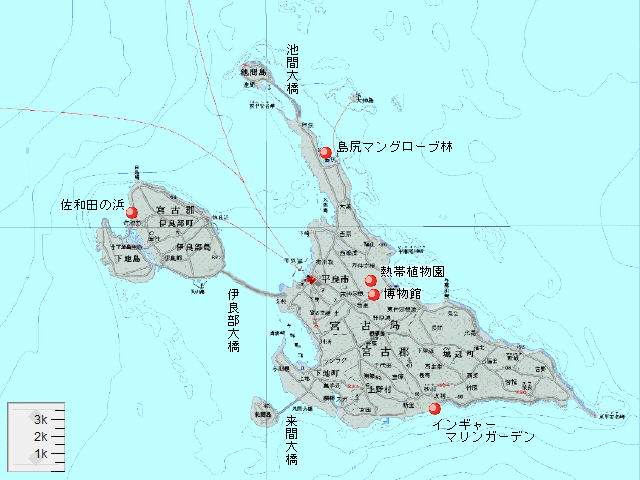 |
Kashmir3D |
午前中、伊良部島の佐和田の浜で植物を観たあと、午後には宮古島本島に移動して熱帯植物園を訪れました。
とにかく、どこに行ってもまあ暑いです。
| 熱帯植物園 |
右手から奥に見える丘の上を辿って、左手から庭園エリアに下りてきました。
| ハイビスカス |
ハイビスカス。あでやかですね。ハイビスカスには白色、黄色、ピンク色、赤色など様々な色のものがあります。ハイビスカスと言えばハワイ。黄色いマオ・ハウ・ヘレという品種がハワイ州の州花なのだそうです。
| ヒメゴクラクチョウカ |
南米のブラジルやギニアが原産というヒメゴクラクチョウカ。オウムバナ科だそうです。初めて聞く科名です。オウムバナがどんなものなのかまったく想像もつきません。
| アダン |
頭上にパイナップルみたいな果実が。これはアダンの実です。熟すと赤くなるとのこと。甘くていい匂いがするそうですが、ほとんどが繊維質で食用には適さないそう。もっぱら昆虫とかヤシガニなどがやってくるそうです。
| ざわわ、ざわわ… |
午後2時過ぎ、熱帯植物園を出ました。少し歩くと一面のサトウキビ畑です。近くに博物館があるようなので、そちらにも行ってみることにしました。炎天下での歩きです。
| イヌマキ |
民家の防風林としてイヌマキの生け垣がありました。近づいてみると面白いものが。緑色の球形のものが種子です。果実みたいですが、裸子植物なので果肉はなく、種子が露出している状態なのです。その付け根にある赤い円柱状のものは果床と呼ばれる土台の役割を果たすもの。甘くて弾力があり、食べられるそうです。
| ベニツツバナ |
ベニツツバナ。中南米原産で、もともとは庭木や公園樹として植栽されていたものだそうですが、ほぼ野生化して林縁で群生を作っていました。こんな花が普通に道ばたにあるなんて、南国っていいですね。
| 市立総合博物館 |
歩くこと500m。市立総合博物館にやってきました。案外距離がありました。この博物館では宮古島の歴史、民俗、自然などの展示があるそうです。この島がどのような軌跡を辿って来たのか、興味があります。
| 正面入り口 |
なんか、人の気配がしませんが…。まあ、一日で最も暑い時間に出歩く人はいませんか。
| ミヤコカナヘビ |
館内に入って、大げさでなく別の世界に来た気がしました。ほんと、エアコンって偉大ですね。
これは入口近くの目立つところに展示されていたミヤコカナヘビ(撮影可)。ちょっと特別扱いでした。なんでも沖縄本島にいるものと同種と考えられていたものが、30年ほど前に新種であることが判明したのだそうです。写真のものは全長20cmほどでしたが、成長すると30cmくらいにはなるそうです。保護されてはいるものの、インドクジャクやニホンイタチに食べられて数を減らしているという悲しい現実も。それにしても野良クジャクがいるってことですか?
| ゲットウ |
館内の展示を見学しながら体が芯まで冷えたところで博物館を出ました。玄関前に植栽されていたのはゲットウ。漢字では「月桃」と書きます。なんかロマンチックな名前ですね。本来の茎は地下にあり(地下茎)、横に這った地下茎からあちこちで偽茎を立ち上げるスタイル。その先に花序を付けます。写真のとおり今はもう果実の時期です。
この後、与那覇前浜ビーチに移動して家族と合流。伊良部島のホテルに戻りました。
| クロヨナ |
ホテルで一休みすると夕方に。すこし暑さが和らいできたので、付近の散策に出かけました。
これはクロヨナの花序。マメ科に特徴の蝶形花です。全体に傷んで薄汚れたものが多かったですが、その中で写真のものは本来の姿をとどめている感じでした。樹高は5mほど。本来もっと大きくなるようです。民家の近くだったので剪定されていたのかもしれません。
| テリハボク |
図鑑に「沖縄にはやたらと生えている」と書かれていたテリハボク。そんな言われ方もないもんだと思いましたが、確かに街路樹や防風林として植えられているのを見ました。南国の植物らしく葉が厚くテカテカですね。
| コトブキギク |
花冠だけ見たら間違いなくハキダメギクですが、なにしろ花茎がひょろひょろと長く、50cmくらいありました。これは熱帯アメリカ原産のコトブキギクだそうです。図鑑によると南関東の沿岸部でも見られるとのことですが、出会った記憶はありません。たぶん。
| ギンゴウカン |
あちこちで出会い、もうすっかり馴染みになったギンゴウカン。葉はマメ科の植物によく見られる2回羽状複葉です。白い球形のものは花が寄り集まった花序。ただ果実は鞘エンドウを2倍長くして褐色に干からびさせたような姿で、それが10個くらいまとまってぶら下がるのだそうです。いったいこの花からどうやってそんな果実ができるのか。イメージ変わりすぎです。
| 池間大橋 |
3日目は、シュノーケリングツアーに参加する娘を池間島の漁港に送っていって、そこから再び池間大橋を渡って本島側に戻ってきました。まずは細長い半島部にある島尻マングローブ林で散策です。
| 島尻マングローブ林駐車場 |
午後1時30分、マングローブ林の駐車場に到着。分ってはいますが、強烈な暑さです。これじゃ「散策」というような穏やかなものにはならないですな、実際。
| 回遊式木道 |
汽水域での観察なので、回遊式の木道を歩く形になります。
解説板によると、マングローブとは、熱帯・亜熱帯の海岸や河口の汽水域の泥土に生育する常緑低木−高木の総称で、宮古島では沖縄県内に分布する6種のうち、ヤエヤマヒルギ、オヒルギ、メヒルギ、ヒルギモドキ、ヒルギダマシ(宮古島が北限)の5種が見られるそう。ここのマングローブ林ではその5種すべてが見られるそうです。
| ヤエヤマヒルギ |
葉の形からするとこれはヤエヤマヒルギだと思います。葉の先端がちょっと尖るのが特徴。
| マングローブ林 |
この入江の奥の方まで全部がマングローブ林。マングローブは海水の中でも育つための排塩メカニズムを持っているそうです。根から吸い上げた塩分を葉や幹から排出するのだそうです。
木道の両側から様々な植物が覆いかぶさって来ています。ムンムンとした生命の圧を感じました。
| ヤエヤマヒルギ |
枝の先端はこんな感じ。強烈な日差しをものともしない、しっかりした葉です。先端に新しい葉芽がありますね。
| ヤエヤマヒルギ |
これは若い果実です。種子はこの果実の中で発芽して長さ20cmから40cmにもなる棍棒のような器官(胚軸)を作ります。写真のような小ぶりの果実から長い棒のようなものが伸び出すわけで、かなり目を引く姿です。その胚軸は成熟すると実から抜け落ち、まっすぐ落下。潮間帯のぬかるんだ地面に突き刺さり、その状態で新たな木として成長していきます。引力を利用した挿し木ですね。
ヒルギは漢字では「漂木」と書きます。これは親木から離れ落ちた胚軸が海を漂流して流れ着くことに由来するとの説があるそうです。
| トクサバモクマオウ |
どうみてもマツですが、立派な?被子植物。トクサバモクマオウです。松葉のように見える部分は、なんと枝(葉状枝)なのだそう。その細い1本の枝に、シダ植物のトクサにあるような袴状の葉(土筆(つくし)の袴と同様のもの)が輪生しているのだそうです。だから「トクサ葉」なんですね。また、花はこの枝の先端に付きます。花被はないとのこと。いずれも観察にはルーペが必要です。
木道の先端に到着しました。ここで引き返します。
| 支柱根 |
幹の下の方からたくさんの根を出し、幹を支えるように地面に伸びています。その名も「支柱根」。今は干潮で海水がありませんが、満潮時にはこの根が海水に浸かる状況となります。これぞマングローブといった姿ですね。
| オヒルギ |
これはオヒルギの花。正確には萼で、萼筒の先には10個程度の萼片があります。なんだか悪魔的な姿ですね。花はこの中に付きますが、時期的にもう落ちているようです。今後この萼筒から胚軸(長さ40cm!)が伸びだすという仕組みです。想像するとかなりグロテスク。
| オヒルギ |
これはオヒルギの葉です。赤い萼筒も見えますね。
| 石橋 |
熱中症にならないうちに駐車場に戻り、車内に逃げ込みました。これから向かうのは宮古島を南に縦断した先にある来間(くりま)島です。
| 来間大橋 |
来間島は人口150人ほどの小さな島ですが、宮古島とは来間大橋でつながっています。島内に集落は一つだけ。静かな島です。
| 竜宮城展望台 |
集落のはずれにある竜宮城展望台に上って眺望を堪能。海と空が嘘みたいに青いです。
| バナナ |
展望台から下りてきて駐車場の周辺を散策。
なにげなくバナナがありました。普通にあるんですね。バナナの花の構造を調べてみるとなかなかに複雑でした。
湾曲してしな垂れる偽茎の先端に巨大な蕾のようなものがありますが、これは苞葉。つまり花を保護する器官です。大きさはラグビーボールほどもありました。苞葉は何重にも重なっていて、外側のものが1枚めくれるとその内側にある花が咲き、結実します。次はその下の苞葉の番で、それがめくれると次の段の花が咲き、結実します。苞葉と花のミルフィーユですね。これを繰り返し、結果として苞葉が結実した実を置き去りにしながらどんどん下に向かって伸びて行くという仕組みです。ちなみにバナナの実の先端が黒くなっていますが、それが花が付いていた痕跡です。
| モモタマナ |
ちょっと変わった形の実を付ける木がありました。枝の下にも落ちたものがたくさん転がっています。これはモモタマナだそうです。丈は高く、枝を水平に広げて葉を繁らせるので、ちょうどよい木陰ができ、そのため集会所や墓地、公園などに植栽されることが多いそうです。
| モモタマナの果実 |
これが果実。桃の種のような形をしています。名前(桃玉名)に桃の字が入っているのは何か関係があるのでしょうか。自生する場所が海岸なのは、この果実がヤシの実のように海水に浮いて運ばれるためだそう。そういえばヤシの実をミニチュアにしたような形でもあります。
| シマオオタニワタリ |
シマオオタニワタリというシダの仲間。モモタマナが造った木陰で繁っていました。南国だからかシダもビッグサイズです。
さてそろそろ戻ります。この日は宮古島本島に宿泊。その前にもう一度池間島に戻って娘をピックアップせねば。
| インギャーマリンガーデン |
4日目(最終日)は宮古島南部の海岸、インギャーマリンガーデンで散策です。海岸から陸続きになっている小島に登ってみたいと思います。
| ハマゴウ |
砂浜の背後にハマゴウが咲いていました。この花を始めて見たのは宮島の「こなきり浜」だったか。自然観察会でのことだったと思います。自然観察を始めて間もないころのこと。懐かしいです。
| ミズガンピ |
佐和田の浜で見かけたミズガンピがここにも。まあ、この島では珍しいものではないということでしょうね。
ミズガンピはミソハギ科。花弁の縮れ具合がミソハギのそれに似ている気がします。
| ソナレムグラの仲間 |
水辺から少し上がったところで、極小の花に目が止まりました。図鑑で調べても正確には分かりませんでしたが、ソナレムグラの仲間であることは間違いないようです。花冠の大きさは5mm弱。花粉媒介者はアリでしょうかね。
| ハマビワ |
大汗をかきながら更に登っていくとハマビワがありました。花芽を付けている姿が面白いです。浜辺に生えていて葉がビワに似ているからハマビワ。でもクスノキ科なんですよね。この木は中国地方西部より南で見られるそうです。
| インギャーマリンガーデン |
ようやく島のてっぺんに到着しました。展望台があったので上がってみるとこの風景です。インギャーとは「囲まれた湧き水」という意味で、海に囲まれた入江の中に真水が湧き出ている地形のことを指すそうです。まさにこの入江には真水が湧くのだとか。
| コウシュンカズラ |
展望台の周りを観察。垂れ下がるように花を付けていたのはコウシュンカズラ。ツル性の常緑低木で、漢字では「恒春葛」。恒春とは台湾最南端にある地名のようです。沖縄県では野生の個体は稀だそうですが、ここのものは植栽なのだろうか。周囲の藪を見るとそうは思えませんでしたが。
| シャリンバイ |
小島の外洋側の斜面にはシャリンバイの群落が。果実がたくさん付いています。この木は暖地の沿岸部でもよく見かけ、植栽されていることも多いです。
| ネナシカズラの仲間 |
そのシャリンバイに覆いかぶさるようにのびていたネナシカズラの仲間。ハマネナシカズラかもしれません。ツル性の寄生植物で、光合成をするための葉はなく(寄生なので)、寄生状態が確立すると根までなくしてしまうという、超他力本願なやつです。
| 外洋 |
展望台から外洋を望む。手前にはサンゴの浅瀬。その奥の濃い青色のところは急に水深が深くなっています。いつまででも眺めていられる風景ですな。暑くなければ。
そして、楽しかった宮古島での野山歩きもそろそろ終わりです。
| 宮古うどん |
空港に移動する途中の食堂に入って、念願の宮古うどんをいただきました。あっさり味で、間違いない美味しさでした。
ところで二十四節気ではもうじき「寒露」です。二十四節気は中国の黄河中流域でできたものだそうなので、海に囲まれた日本で用いるには元々無理もありますが、ここ宮古島でも時候の挨拶などで話題になったりするのでしょうか。今日みたいな日に「もうじき寒露」とか言っても「飴か?」とか言われそうですが。「夏至」とか「大暑」だったら日常会話に出てきそうですね。