
宮古島 〜未知の花との遭遇(前編)〜
 |
(前編) |
【沖縄県 宮古島市 令和7年10月1日(水)〜4日(土)】
今年は夏が長く9月中旬まではTシャツ短パンで毎日を過ごしていましたが、さすがに秋分を過ぎた辺りから徐々に秋らしくなってきました。そして月が替わって10月。この日から南の島へ家族旅行です。向かう先は宮古島。娘から誘われたときに、こんな時期に?とは思いましたが、宮古島は沖縄本島から緯度にして2度(約220km)も南に位置していて、現地は余裕で真夏なのだそう。なんなら観光客が少し減って、いい感じに楽しめるのだそうです。娘一家や妻はマリンレジャーやホテルの食事が楽しみのようでしたが、yamanekoとしては普段見かけない南の植物に出会えることにテンションが上がります。とはいえ、東京は肌寒い雨の朝。長袖シャツを引っ張り出してきて、Tシャツの上に羽織る形で羽田空港に向かいました。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
羽田空港を飛び立って、雲を抜けると青空です(当たり前)。3時間弱の飛行で、午後1時半過ぎに宮古空港に到着しました。着陸前に上空を2、3回旋回しているときに(アナウンスでは管制塔の指示だそう)、島の様子を見ると山が全くない平べったい島であることがよく見て取れました。
到着ロビーの段階ですでに暑く、早速トイレでTシャツ短パンに着替えることになりました。外に出ると、真上から射貫くような強い日差し。今日から10月だよな、と半笑いになったほどです。
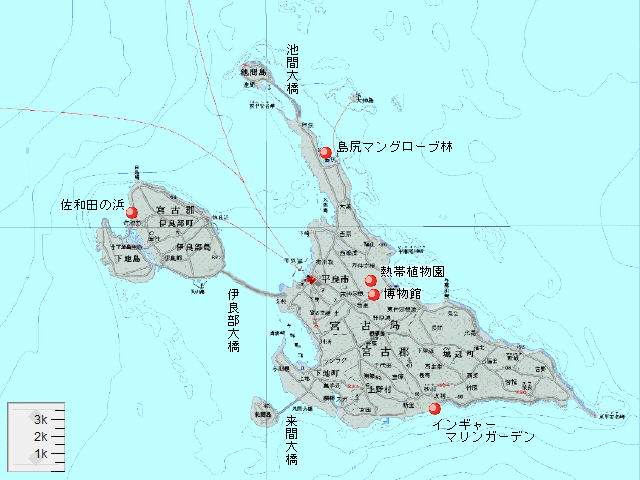 |
Kashmir3D |
今回の旅行では、ときに別行動をとったりしながら、複数個所で植物を見ていくことにしました。伊良部島の佐和田の浜、熱帯植物園、島尻マングローブ林、インギャーマリンガーデンなどで散策予定です。また、期間中レンタカーを借りているので、宮古島のウリでもある3つの長大橋を渡ってみたいと思います。
| 伊良部大橋 |
空港を出てからは市街地で買い物をしたりして、ホテルのある伊良部島へ向かいました。途中渡るのは10年前に竣工した伊良部大橋です。長さが3.5km以上もあり、本当に海の上を走っているような感覚になりました。
| ギンゴウカン |
そして翌日、午前中はホテル近くのビーチで海岸植物などの観察です。
そこまでの路傍にも見慣れない植物が。例えばこのポップな奴。道の両側に延々と茂っていて、歩道を侵食している箇所もあちこちに。調べてみると(というか、初見ばかりなので今回はほとんど全部帰宅後に調べたものです。)これは中米原産のギンゴウカンというマメ科の植物。漢字では「銀合歓」と書き、ギンネムとも呼ばれるそうです。おそらく雑木的な扱いがされていて、どの島に渡ってもあちこちで野生化していました。高さは5mほどにもなり、これが道の両脇で茂っていると、大げさでなく運転の邪魔になるほどでした。
| シロノセンダングサ |
これは本土でも見かけるシロノセンダングサ。世界の熱帯から暖帯に広く分布しているそうで、日本でも暖地を中心に広がっているそうです。全体の姿は多摩丘陵でも身近なコセンダングサそっくりですが、頭花に立派な舌状花が5個あるのが相違点。コセンダングサには舌状花ははく、あっても極小さいです。
| 佐和田の浜 |
10時30分、ビーチにやって来ました。佐和田の浜というビュースポットです。
強烈な日差し。日焼け止めは塗ってきましたが無駄なあがきでした。なにしろ汗が半端なく噴き出てきて、塗ったクリームごと全部タオルでふき取る破目になったからです。
| グンバイヒルガオ |
そんな陽射しの下でも植物は元気に生きているんですよね。これはグンバイヒルガオ。葉の形が軍配に似ているからですね。この環境にも負けないよう葉はしっかりとした厚さをもっています。
打ち上げられていたサンゴ。触ってみるとまだ柔らかかったです。宮古島は50万年くらい前に発達したサンゴ礁がその後石灰岩化し、それが隆起して島になったのだそう。つまりサンゴでできた島ということですね。
波が寄せないところまで植物が伸びてきています。「日陰、どこかに日陰はないか…」
| イソマツ |
ずっと砂浜を進んでいくと岩場になりました。大小の孔が多く、ゴツゴツと不規則な形をした岩で、琉球石灰岩(隆起サンゴ礁)と呼ばれるもののようでした。その岩の窪みに根を張るイソマツ。「松」の名を冠していますがマツの仲間ではなく、イソマツ科という科に属しています。なんでも茎がマツの樹皮に似ているから「磯の松」なのだそうですが、いや樹皮じゃなくて松葉だろう、と言いたくなります。
| ミズガンピ |
これも岩の上に生えていたミズガンピ。常緑の低木で、花は通年咲くそうです。さすが南国。名前のガンピは紙の原料となる「雁皮」のことだと思いますが、本家ガンピとの共通点が分かりません。
| モンパノキ |
こちらも岩の窪みに根を張って生きている植物。背の低い草本のように見えますが、高さ5mにも成長する樹木でモンパノキというそうです。一方、花は約4mmと極小。よく見ると萼や花序にはビロードのような毛が密生していました。
| モンパノキ |
見るからに樹木という姿のモンパノキ。ところでモンパって何だ?
| ハマゴウ |
おお、懐かしい。本土でも見かけるハマゴウです。君は遠い南の島でも生きていたんだね。
ハマゴウは砂浜ギリギリのところで生きている海岸植物で、実には薬のような香気があり、乾燥させてソバ殻枕に入れると安眠できるそうです。
| クサトベラ |
クサトベラ。葉の様子が樹木のトベラに似るからだそうですが、クサトベラも草本ではなく樹木です。花の形が面白いですね。花弁が同心円状ではなく扇子のように片方に偏って付いています。あと気づきにくいですが、花弁の付け根部分からキノコのような形の雌しべが直立しています。
| キダチハマグルマ |
ツル性の亜低木、キダチハマグルマです。キダチとは「木立」と書き、木のように立ち上がるという意味。茎には剛毛があって、他のものに引っ掛けて伸びるので、立ち上がるように見えるのでしょう。花冠の舌状花が8個あり、車輪のスポークのよう。「浜車」の名の所以です。
| オオハマボウ |
フヨウの仲間、オオハマボウ。いかにも南国の花ですね。ハマボウは本土でも見られますが、オオハマボウは種子島以南に分布するのだそうです。花も葉も木の丈もハマボウよりも大型で、防風林や防潮林として利用されているそうです。ちなみにオオハマボウは佳子様のお印なのだとか。
さて、午後は宮古島に渡って熱帯植物園を訪れてみたいと思います。
| 宮古島市熱帯植物園 |
午後1時過ぎ、熱帯植物園に到着。車を下りた瞬間にガーンと打ちのめされました。強烈な直射日光に。
入園してまっすぐ進むと広い芝生エリアがありました。家族連れなどにはいいですね。入園無料というのも有難い。ただこの天気なので誰もいません。それとも平日だからか?
この植物園の広さは12万坪だそう。正面の丘も園内で、その上を通る散策路もあるようです。これから右手に進み、反時計回りに歩きながらあの丘の上にも行ってみたいと思います。
| アリアケカズラ |
いきなり南国っぽい花です。アリアケカズラ、別名をアラマンダというのだそうです。カズラの名が示すとおり、半ツル性の常緑低木です。
| テイキンザクラ |
テイキンザクラ。漢字では「提琴桜」と書き、提琴とはバイオリンのことだそう。葉の形がバイオリンに似ているからとのことですが、花の周囲を見る限り似ているといえるものはありませんでした。ちなみにトウダイグサ科に属していて、サクラ(バラ科)とは無関係です。
| アリアケカズラ(八重咲き) |
これは何だといろいろ調べましたが、どうやらアリアケカズラの八重咲き品のようでした。
| タイワンフウ |
3裂した掌状の葉の陰に球形の果実が見えます。これはタイワンフウですね。街路樹でときどき見かけます。
| ブーゲンビリア |
超有名どころの南国の花、ブーゲンビリア。レイに編み込まれている花ですね。ピンク色の花弁に見えるものは葉が変化した苞葉。本当の花は中心の白い小さなものです。
| シコンノボタン |
これはシコンノボタン。ブラジル原産ですが関東地方以西では越冬できている植物だそうです。名前のシコンとは「紫紺」のこと。花の色を示しているんですね。ちなみに「立てば芍薬、座れば牡丹」のボタンとは無縁です。
| ハイビスカス |
ブーゲンビリアと双璧をなす南国花、ハイビスカス。フラを踊る人の髪飾りに定番の花ですね。
| ハイビスカス |
こっちのハイビスカスの方がより定番かもしれません。
昔、職場の窓際にハイビスカスの鉢植えがあって、毎年ちゃんと花を咲かせていました。室内とはいえ冬には冷え込むところで、案外寒さに強いんだなと思ったことがあります。
ついつい木陰に沿って歩いてしまいます。
| オウコチョウ |
これはまた派手な花。葉を見る限りマメ科の植物だろうと察しが付きます。これはオウコチョウ。漢字では「黄胡蝶」と書くそうです。円錐状の花序を取り囲むように最も外側の花数個ががぐるっと開花しています。これから順に内側の花が咲いていくんだと思います。花弁は黄色く縁どられ、ひだ状に。まるで西部劇で出てくるラインダンサーのスカートみたいです。
| フウリンブッソウゲ |
汗を拭きつつ、丘に登る道を行きます。こちらは若干日陰が多めで助かります。
これはフウリンブッソウゲ。確かに風鈴のようにぶら下がっていますね。たくさんの花がよりあつまっているように見えますが、これは花弁が細かく裂けている姿。全体で1個の花です。垂れ下がっている雄しべで分かるとおりハイビスカスの仲間で、ブッソウゲ(仏桑華)とはハイビスカスの和名だそうです。海外ではコーラルハイビスカスと呼ばれ、裂けた花弁の様子がサンゴ(コーラル)のようということだそうです。
| ショウベンノキ |
これは調べるのにちょっと苦労しました。おそらくショウベンノキだと思います。若い果実ができていて、一つの果序の長さは、写真のもので20cmほど。春先に枝を切ると樹液が大量に出てくるそうです。
| コウトウヤマヒハツ |
小ぶりのシャインマスカット? いや、これはコウトウヤマヒハツの若い果実。熟していくにつれ、緑→赤→紫→黒と色が変化していき、一つの果序の中で様々に色づくため、観賞用に庭木として用いられることも多いいそうです。
コウトウヤマヒハツは雌雄異株で、左の写真は雄花序。右は雌花序ですが、受粉が終わり子房が膨らみつつある状態です。
ところでコウトウヤマヒハツとは難しい名前ですが、「紅頭山+畢撥」という言葉の組み合わせだそう。紅頭山は台湾本島南東にある島の山の名前、畢撥はコショウの仲間でスパイスとして用いられる植物のことだそうです。
| 展望デッキ |
丘の中央部辺りに展望デッキがありました。庭園とは反対側(つまり熱帯植物園の背後)に向いています。
| 悠久の森 |
広大な亜熱帯の森。人工の構造物がまったく見えません。生き物の影が濃そうです。でも、この島は元々サンゴ礁が隆起してできたもの。ということは植物の種子が流れ着いたり、鳥に運ばれてきたりして、長い年月をかけてこの鬱蒼とした森が出来上がったということですね。
| トウヅルモドキ |
徐々に丘を下っていきます。これはトウヅルモドキ。葉の先端が巻きひげになるのが特徴で、これで樹木などに絡みつくのだそうです。ツルで絡みつく植物は多いですが、変わったテクニックを持っています。
階段を下って庭園エリアに戻っていきます。 ジャングルか?
| ホウオウボク |
園の左側に下りてきました。ホウオウボクの花が咲いていました。マダガスカル原産で、沖縄では街路樹として用いられているそうです。葉を見るとこれもマメ科のようですね。
| コダチヤハズカズラ |
南国って半ツル性の樹木が多い気がします。このコダチヤハズカズラもその仲間。垂れ下がった枝の先にポップな花を付けていました。熱帯アフリカ原産で、明治の終わりころに日本に入ってきたものだそうです。
| デイゴ並木 |
丘のふもとに沿って園を東西に貫く歩道がありました。その両サイドにはデイゴ並木。作業をしていた園の人に話を聞いてみたら、ここ数年害虫の影響で花を付けないそうです。
| パパイヤ |
高さ5m、幹の直径は30cmほどもある立派なパパイヤ。成長速度もかなり早いですが、そのせいか幹の強度は弱く、ちょっとした台風で簡単に倒れてしまうそうです。
| クワズイモ |
雨降りの日、家に帰って傘を開いたまま干しますよね。その傘をいくつも並べたような姿をしているのはクワズイモです。サトイモの仲間で、ミズバショウ同様に花は仏炎苞をまとっています。地中にできる根塊は食べられず、そのため「不喰芋」の名が付いたのだそうです。
ふと轟音に見上げると、宮古空港を飛び立った飛行機が。きっとたくさんの思い出を乗せて飛んでいるんでしょうね。(後編に続く)