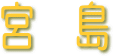
宮島 〜炎暑の中、瀬戸の島を歩く〜
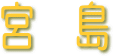 |
【広島県 廿日市市 平成27年7月26日(日)】
全国的に猛暑の日が続いています。もう35度とか聞いても驚きません。
今回は野暮用があり広島に行く機会があったので、時間をやりくりして宮島を訪れてみました。宮島も東京に負けず劣らず暑かったです。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午前10時過ぎにJR広島駅到着。コインロッカーに荷物を預けて山陽本線に乗り換え、宮島口駅に向かいました。途中、広島駅と横川駅との間に新白島という新しい駅ができていたのにちょっとびっくり。アストラムラインという新交通システムとの連絡駅のようです。目的地には30分弱で到着しました。
宮島口駅の駅前にはJRに併走して国道2号線が走っています。地下道で国道2号線をくぐって反対側に出ると、そこはもう宮島航路の乗船口です。ここにはJRと松大汽船の2社の乗り場があり、対岸の宮島桟橋まで同一区間を並んで営業しています。2社はお客さんの争奪でしのぎを削っているのです。お客さんはどちらかの乗り場に行き券売機キップを買うのですが、その際つい「往復」キップを買ってしまいがち。でもプロはそうはしません。なぜなら、両者は概ね5分間隔で交互に運行しているので、復路のキップをどちらかの船会社に固定してしまうと、帰りに先に出航する方に乗れずに待たされることがあるからです。活用するチャンスがごく稀なライフハックです。
| フェリーから |
yamanekoが乗ったのはJRの方の船でした。こっちが先に出港するタイミングだったからです。
出向するともう宮島がすぐそこにあります。もちろん港からも目の前に見えていましたが。
| JR船 |
これはすれ違うJRのフェリー。フェリーといっても車で渡る観光客はほとんどいません。島に渡ってから車に乗って移動するような場面がないからです。宮島の観光地はそれほど狭い範囲に集中しているということです。
| 朱の大鳥居 |
JRの方はわざわざ厳島神社の大鳥居の近くまで迂回して航行するというのがウリ。乗客の多くはデッキに出て写真を撮っていました。上の写真はそのときのものです。この時は干潮で、社殿が水中に建つ姿は見られませんでした。
| 弥山原始林 |
宮島の主峰、弥山(中央左)。標高は535mです。鞍部を挟んで右側のピークは駒ヶ林、509m。山腹の森は弥山原始林として世界遺産に登録されています。宮島は案外大きな島ですが、観光スポットだけでなく住民が住んでいるエリアも島の北端のほんの狭い地域に集まっています。そのほかは島のほとんどを急峻な山が占め、集落はおろか外周を回る道路すらありません。
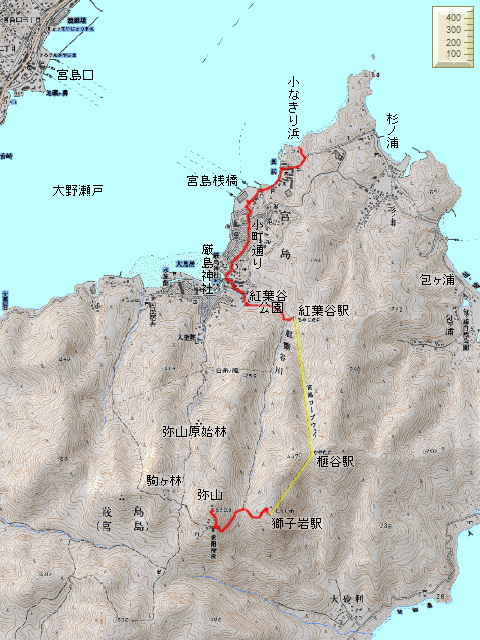 Kashmir 3D |
乗船時間わずか10分で宮島に到着。港の前の広場は大勢の観光客で賑わっていました。外国人が多いのはいつものことですが、この日は特に多いように感じました。
上陸後は、まず「小なきり浜」に行ってみることにしました。以前、海浜植物調査やビーチクリーンなどを行ったことのある場所です。上陸した観光客が訪れるのは厳島神社などがある右手(南方向)のエリア。小なきり浜は反対の左手に500mほど行ったところにあります。当然、そっちの方に向かう人はほとんどいませんでした。
途中で出会ったシカ。こういうのは宮島の日常に完全に溶け込んだ風景です。
| 小なきり浜への下り口 |
小さな峠を上りきったところに小なきり浜への入り口があります。観光客はまず100%訪れない場所でしょう。花崗岩が風化したマサ土はズルズルと滑りやすく、慎重に下りて行きました。
| 後背湿地 |
下りきると小さな池(というより水たまりの親分みたいな規模。)があるのは以前と変わっていませんでした。ここは海岸の背後にできる後背湿地ですね。
| ハマゴウ |
浜に出るとハマゴウがみっしりと茂っていました。
| 小なきり浜 |
やはり人っ子一人いません。太陽がジリジリと容赦なく照りつけてきます。
ハマゴウは満潮時でも波を被らない場所、すなわち砂浜と後背地との境界に生育する植物です。写真右の植物がハマゴウの群落です。以前は砂浜がゴミだらけ(主にカキ筏の部材など)でしたが、それはあまり見られませんでした。ひょっとして最近清掃が行われたのか、それとも湾内にカキひびが設置されていたので潮の流れが変わったのか。
対岸には阿品海岸が見えます。
| ハンゲショウ |
湿地に戻ってみました。ハンゲショウは花の時期を終え、もう実ができていました。
| ヒトモトススキ |
これはヒトモトススキ。大柄で強壮なカヤツリグサ科の植物です。別名のシシキリガヤというのはイノシシの皮をも切ってしまうほど硬いという意味でしょう。湿地のほとりに茂っていました。
小なきり浜でひとしきり観察した後、元の道路に上がりました。一段と暑いです。ここからまた港まで歩いて戻らなければなりません。水分補給をしながらのんびりと歩きました。さっき港で見た大量の観光客はいったいどこにいるのか(厳島神社とかでしょうが。)というほど静かな島の道です。
| 穴子丼 |
港に戻るとまた喧噪が待っていました。 あまりに暑いのでとりあえず食堂に入って昼食です。店内に入ると昭和40年代の雰囲気。おばあちゃん3人でやっている昔ながらの食堂のようです。で、迷わず宮島名物の穴子丼を注文。甘くふっくら柔らかで美味しかったです。きっと昔から守り継がれている味なんでしょうね。
さて昼食の後は宮島の最高峰、弥山に登ります。登るといっても途中まではロープウェイですが。まずロープウェイ乗り場のある紅葉谷公園まで行かなければなりません。
| 小町通り |
紅葉谷公園は厳島神社の裏手から山側に500mほど遡った先にあります。厳島神社までは海辺に近い土産物店が軒を連ねるメインの道路(表参道)を通るのが一般的ですが、プロはその道は避けて、一本裏手にある小町通りを歩いて行きます。町屋の中を通るこの道は昔の参道で(きっとこの辺りに波打ち際があったのでしょう。)、今では生活道路になっていますが、喧噪とは縁がなくなかなかいい雰囲気を醸し出しています。
| 小町通り |
小町通りを進むと塔の岡の五重塔が見えてきました。あの向こうは入江になっていてそこに厳島神社があります。
| 紅葉谷公園 |
今回は神社はパス。紅葉谷公園は紅葉谷川に沿って伸びていて「公園」というより「園地」と言った方が合っているでしょう。地味に上り坂なので汗が流れます。厳島神社は紅葉谷川の河口入江に建っているという位置関係です。
途中にはこんな涼しげな茶屋も。紅葉の季節はきれいでしょうね。
12時30分、ロープウェイ乗り場の紅葉谷駅に到着。右手の階段の奥に駅舎がありあります。
ここにも若い外国人がいっぱい。長蛇の列ができていて、その最後尾に並んだのですが、止まったとたんに汗がドバッと吹き出てきてサウナに入っているみたいになりました。ハンカチなどは全く役にたたないレベルです。
世界遺産ということもあり宮島はいつ来ても観光客で溢れています。特に外国人が多いのが特徴なんですが、この日は通常より更に多く、しかも首にチーフ(ボーイスカウトなどでつけているやつ)を巻いてリュックを背負っている若者がわんさかといました。ほとんどがティーンエージャーみたいで、保護者的な大人も結構いました。後でニュースで見たところによると、4年に1回開催される世界スカウトジャンボリーというイベントが40数年ぶりに日本で開催されるのだとか(メイン会場は山口)。今回は世界中から約3万人が集まり、2週間にわたってキャンプなどで共同生活を行うのだそうです。3万人も集まるのならそりゃ広島にもどっと繰り出してくるわな。
| 榧谷駅 |
ロープウェイは初めは循環式の8人乗りゴンドラで北側斜面の山腹を登っていきます。稜線上に出たところにある榧谷駅で乗り換え、今度は交走式の30人乗りの大型ゴンドラに乗車。反対側(南側斜面)の谷を渡る形で終点の獅子岩駅に向かいます。
| 獅子岩から |
獅子岩駅に到着して、駅舎の裏手にある獅子岩に登ってみました。そこからの眺めはこんな感じ。正面に弥山の山頂が見えています。獅子岩は弥山の山頂の隣にあるピークなので、ここからいったん鞍部まで下って再び登り返す必要があります。ここからだと同じような高さに見えますが、50m下って130m上ることになるのです。
| 広島湾 |
振り向くと広島湾の向こうに広島の市街地が見えました。
| 風化花崗岩 |
さて、弥山に向けて出発です。明るい黄土色の土は風化した花崗岩。調子に乗って小走りで下りたりするとズリっと滑るので要注意です。日本の伝統美として白砂青松という風景描写がありますが、その白い砂はこの風化した花崗岩なんですよね。関東の海岸ではなかなかお目にかかれません。
| コシダ |
ああ懐かしい。これはコシダですね。そういえばこれも関東ではあまり見かけません。マサ土の登山道にコシダ、瀬戸内の野山を歩いていることを実感しました。
| 鞍部 |
鞍部まで下りると標識が。ここが紅葉谷の谷頭に当たる場所で、紅葉谷コースの登山道がここに出てきます。ここに宮島の植生の貴重さを示す解説板がありました。「大正2年にベルリン大学教授のアドルフ・エングラー博士が宮島を訪れ弥山に登山した際、ヤマグルマやマツブサなど植物系統学上の貴重な植物を見て、大いに感激した。この世界的な、植物学者は「私は、できるならば一生ここに住んでここで死にたい。」とまで弥山の植物を激賞したとと伝えられている。(略)」 エングラー博士とは、エングラー式植物分類体系に名を残すその筋では高名な人(最近では遺伝子解析に基づくAPG体系という分類法を目にすることが多くなりました。)。希少種があるということの他に、北方系のモミと南方系のミミズバイが混在し、しかもこれらが標高0m付近から生息していることに大変驚いたのだそうです。
| サカキ |
さてここからは登りです。また汗がどどっと出てきます。そんな中でも植物観察は楽しみ。これはサカキの葉。テカテカですね。
| ウリハダカエデ |
こちらはウリハダカエデ。大ぶりな葉の下にプロペラ型の実がたくさんぶら下がっています。
| ホウロクイチゴ |
これはホウロクイチゴの葉ですかね。これもテカテカです。
| ハスノハカズラ |
ハスノハカズラ。蓮の葉のように葉柄が葉裏 に付いているので、上から見たら葉柄がないみたいに見えます。海岸に近い地域でよく見られるそうです。
| 霊火堂 |
1時25分、開けたところに出ました。ここまでの登山道でも例の外国人の若者たちとたくさん出会いましたが、ここにもたくさんいます。
ここには弥山本堂と霊火堂という仏閣があり、霊火堂には806年に弘法大師が灯したといわれる消えずの火が1千2百年経った今に至るまで燃え続けているとのこと。覗いてみると確かに熾火のようになって煙が出ていました。広島の平和公園の火はここから分けたものだそうです。でも、10年くらい前にこの霊火堂が火事になったことがあって、ニュース映像では消防が思いっきり放水して消火に当たっていましたが、きっと予備の火がどっかに保管されていたんでしょうね。たぶん。
霊火堂から先はこんな道。もう急な登りもありません。
| 観音堂・文殊堂 |
観音堂と文殊堂。軒先を失礼して歩いていきます。
| くぐり岩 |
くぐり岩。大きな花崗岩が組み合わさってできています。大人が普通に立って通れるくらいの高さがあります。おそらく元は一塊の岩であったものが割れてできたものでしょう。これが現れると山頂はすぐそこのはずです。
くぐり岩からしばし。おっ、岩の間から見えるのは山頂の展望台ではないか。
| 弥山山頂 |
獅子岩駅から歩くこと25分。弥山の山頂に到着しました。展望台がyamanekoが記憶するものよりずいぶん立派になっています。早速登ってみましょう。
| 南西方向 |
展望台は2層構造になっていて、最上部に上がります。
展望台の四辺からの眺望を。まずは南西方向。手前右に見える山上の裸地は駒ヶ林のピーク。戦国時代、毛利元就と陶晴賢とが宮島で相見えた厳島合戦で、追い詰められた陶軍の多くが最期とした場所といわれています。左手奥のやや薄く見える山は宮島の南端にある岩船岳。本土との間の海は大野瀬戸です。本土側のずっと奥には大竹市(岩船岳の右肩奥)や山口県の岩国市(同左肩奥)があります。
| 北西方向 |
次は北西方向。大野瀬戸を挟んで海にせり出すように市街地が広がっているのが見えますが、あそこは廿日市市です。その奥、陽が当たっている市街地は五日市市あたり。最奥の街並みは広島市です。
| 広島市街 |
広島の市街地をアップで。すぐ背後に中国山地が迫ってきているのが分かります。
| 北東方向 |
こちらは北東方向。正面の大きな島影は江田島と能美島。昔は独立した島だったようですが、浅瀬を埋め立て、現在では両島は陸続きになっています。ちなみに伊能忠敬の地図(江戸時代後期)では既に繋がっていたそうです。この島々の向こう側が呉市あたりになります。
| 南東方向 |
最後に南東方向。安芸灘が広がっています。遙か向こうは愛媛県。
山頂には花崗岩の巨岩がゴロゴロ。花崗岩の節理は立方体の各辺様に走っているので、割れるときにもこういった方形になりがちです。さっきは正面の大きな割れ目の間から登ってきました。中国地方の地表面は広い範囲で花崗岩が占めています。花崗岩は地中の深いところで溶岩がゆっくりと冷え固まったもの。それが隆起してきて広い範囲を占めているということは比較的長期間急激な地殻変動がなかったということではないでしょうか。中国地方に火山が少ないのもその表れかもしれません。
| 獅子岩 |
あらためて獅子岩駅の方を見てみると、ずいぶん下の方に見えますね。
| モミ |
ひとしきり眺望を楽しんでから下山しました。これは下りのロープウェイの中から撮ったモミ。宮島の特異な植生を表す風景です。
| 桟橋前広場 |
2時40分、宮島桟橋まで戻ってきました。いやぁ、それにしても暑かった。直近の出航がどちらの船かを確認し、そのキップを買って船に乗り込みました。
この日の夜はマツダスタジアムで確か巨人戦があったはず。当日券でもあるかと行ってみたのですが、完全に売り切れていました。残念。しかもこんなときに限って快勝するんですよね。