
岩船岳 〜やっぱ宮島は”奥が深い”ぞ〜
 |
【広島県宮島町 平成16年2月21日(土)】
前夜の天気予報では、今日は「晴れのち雨」 ここ数日来の春のような陽気のまま、今日も最高気温は18度の予報でした。
午前8時、宮島の桟橋前に集合したのは、パークボランティアのメンバー23人。
今回は、宮島の南端に構えている岩船岳に登り、その帰りに昨年コバンモチに取りつけた保護ネットの破損状況を点検するという企画です。
厳島神社や紅葉谷、ロープウェイで登れる弥山など、宮島の観光スポットは島の北端にあり、島全体から見るとごく狭い限られた地域に位置しています。民家もほとんど全てこの地域内にあり、その他の広大な地域には山が連なり深い森が広がっています。島の南半分には道路はなく、もちろん車で島を一周することはできません。
今日は10時間近くのハードな行程になりそうです。
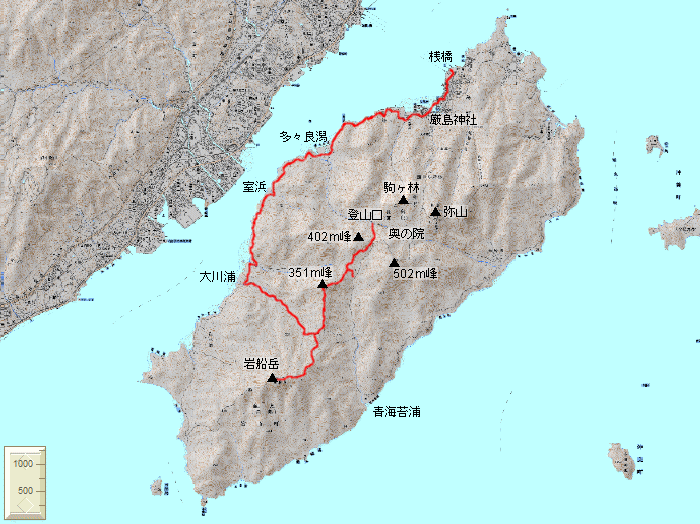 |
Kashmir 3D |
桟橋前からタクシーに分乗。登山口までの時間を稼がないと明るいうちに帰ってくることができません。厳島神社を迂回し水族館を過ぎると、あとはほとんど民家はありません。離合も難しいような海沿いの道を進み、多々良潟から奥の院へ向かう林道に入ります。道はさらに狭くなり、辺りの木々が覆い被さってくるようです。
| 登山口 |
林道途中の青海苔浦への分岐点が登山口になります。タクシーはここではUターンできないので、ずっと登って奥の院で方向転換をしなければなりません。
天気予報より早いペースで崩れはじめているのか、空はどんよりと曇っています。
8時30分、軽い準備運動のあと、デイパックのベルトを締めて出発。20歩も歩かないうちにいきなりの急登です。常緑樹の薄暗い林を稜線目指して登っていきます。
30分ほどで402m峰と502m峰との間の鞍部へ出ました。小休止です。さっそく上着を脱ぐ人続出。ここから谷筋に下りる道をとれば、島の裏側の青海苔浦へ。われわれが向かう岩船岳への道は、ここから標高を保ちながら山肌をまいていき、次の351m峰との鞍部で稜線に出ます。
| コシダの道 |
道は両側からコシダが生い茂り、まるで洗車機の中の車になったような気分です。コシダの茎は固く曲げても反発力が強いので、手袋をしていないと傷だらけになってしまいます。この辺りでは、まだみんな元気でワイワイしゃべりながら歩いていきました。
| タマミズキ |
色の少ないこの季節、タマミズキの赤が目に鮮やかでした。
目の前に山が迫ってきました。351m峰です。ここで道をそれて陶晴賢の終焉の地へ寄ってみることにしました。山肌を滑るようにして谷を下っていきます。今は梢をとおして陽が入ってくるのでそれでも少しは明るいのですが、梅雨場などは鬱蒼として寂しい場所でしょう。
1555年、安芸の支配をめぐって毛利元就と陶晴賢(すえはるかた)が火花を散らした厳島合戦は有名です。陶軍の圧倒的有利を奇襲で覆した元就は、手をゆるめることなく陶軍を追いつめました。10月1日、わずかな側近と共に山ひだの奥深くにたどり着いた晴賢は、武将としての最期のときを悟ったのか、わずかに開けた場所で静かに舞を舞ったのち自害したそうです。
10月1日といえば今の暦では11月上旬。この辺りに多いウリハダカエデの紅い葉が散る中の出来事だったかもしれません。
| 陶晴賢の碑 |
ひとしきり450年前のドラマに思いを馳せたら、またもとの稜線に戻ります。息を整えてから、ここから一気に標高差100mを登り351m峰へ向かいます。さっきの谷登りが相当こたえたのか皆黙々と歩を進めています。
| 命をつなぐ |
倒木が朽ちていく姿をあちこちで見かけました。長い一生を終えた命が、また次の命のために土に還ろうとしているところです。
351m峰のピークを越えると、今度はアップダウンを繰り返しながらなだらかに下っていきます。
天気はどんどん良くなっていくようで、頭上はすっかり青空になっていました。
| 天気は快方へ |
10時30分、大川浦への分岐点に到着しました。小休止です。ここは岩船岳との鞍部。帰りはここから大川浦に向かって下りることになります。
さあ、これからいよいよ目的地に向かっての登り。標高差は230m。気合いを入れ直して歩き始めます。今度はアップダウンではなくアップアップ。自分的にもあっぷあっぷです。(寒)
足元の土がマサ土(花崗岩が風化したもの)から赤土に変わっています。雨ならぬかるみそうですが、乾いているぶんにはマサ土より歩きやすいです。
| 351m峰(正面)、502m峰(右奥)、駒ヶ林(最奥の白い頂) |
胸を突くような登り。振り返ると502m峰越しに駒ヶ林が見えました。
荒い息がおさまるまでしばらく眺めていくことにしました。
| 急登 |
道は延々と続いています。足元はいつの間にかまたマサ土にもどっていました。
急に視界が開けました。
「ようやく頂上か」 いくつかカマボコ板も吊されています。しかし本当の山頂はさらに二つ向こうのピークだとのこと。ちょっとがっかりですが、汗を拭って再び歩き出すことにしました。
ここからは比較的緩やかなアップダウンがあるのみ。あとちょっとです。
| 本当の山頂 |
ここからの道はその両側に瀬戸の海を見ることができます。
| 大野瀬戸 |
眼下にはカキ筏が浮かぶ大野瀬戸が見えました。その向こうには経小屋山。穏やかな瀬戸の風景です。
| 由来の岩 |
途中、岩船岳の名の由来となった岩がありました。確かに船の舳先に見えます。この尾根道には花崗岩の奇岩がたくさんありあました。
| 山頂(眼下にうっすらと阿多田島) |
11時40分、とうとう頂上に到着。南に向かっての視界が開けています。7キロ先にある阿多田島が「雲海に浮かぶ山の頂のよう」と行ったのはM女史。確かに。西には大竹市の工場群、東には台形の島影が特徴的な能美島が見渡せました。
| 能美島 | 阿多田島 |
春本番を思わせる陽射しを浴びながら昼食。腹が減っていたのでペロリと食べてしまいました。あとはゆっくり昼寝でもできれば言うことないんですが…。
12時20分、先は長いので早めに出発することになりました。
| ヒトツバ |
下りには特に注意が必要です。狭い歩幅で慎重に下るため、思ったよりはかどりません。
大川浦への分岐に到着したのは1時10分。ここで道を左手にとって、コシダをかき分けながら延々と下っていきました。
| シロバイ |
この谷筋にはシロバイが多く見られました。クロキ、ハイノキ、サワフタギ、クロバイ、シロバイ、ミミズバイ、タカサブロウ…。宮島にはハイノキ科の樹木がたくさん揃っているのだそうです。
| コシダの海 |
2時15分、大川浦手前の分岐に到着しました。ここからは海岸沿いに北上。張ったふくらはぎにむち打ちながらコシダの海を泳いでいきます。
| 海辺の小径 |
昨年コバンモチの保護作業をした場所にさしかかりました。海に落ち込むような山肌に点在するコバンモチ。みんなで手分けして山の中に分け入ります。 (昨年のコバンモチ保護作業のようすは →こちら)
| コバンモチと防護ネット |
どの木の防護ネットも損傷はないようです。道なき道をもがきながら登ったり下りたりしたので、ここでさすがにヘトヘトになってしまいました。
時計の針は3時を回っています。傾いた陽が海に反射して眩しい。
| 広島大学の実験所 |
夕方4時、室浜にある広島大学理学部の実験所に到着しました。みんな疲労は隠せませんが、満足げな笑顔を見せています。ハードな山歩きだったにもかかわらず(平均年齢がかなり高かったのにもかかわらず)ケガをする人もなく、無事に解散となりました。
ところが、ここからが長かった。
重い足を引きずりながら、今朝タクシーで通った道を延々7キロ、宮島桟橋を目指して歩き通したのです。
5時15分、ようやく宮島桟橋から船に乗り込むことができました。