
三頭山 〜初夏の奥多摩で森林浴(後編)〜
 |
(後編) |
【東京都 檜原村 平成29年5月21日(日)】
グリーンのシャワーを存分に浴びる三頭山。後編です。(前編はこちら)
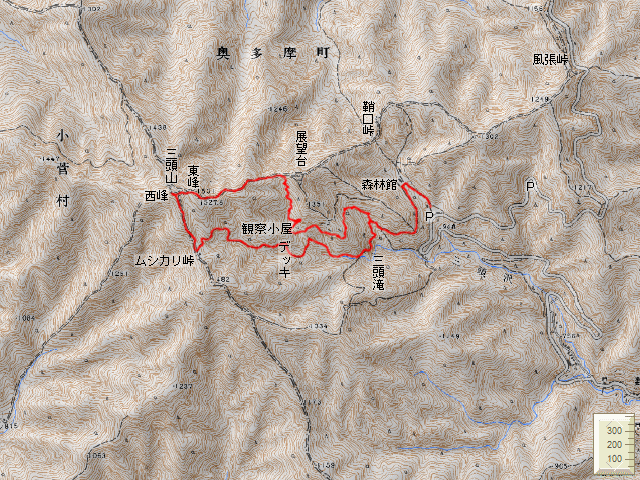 |
Kashmir 3D |
三頭滝や休憩デッキを過ぎ、ムシカリ峠に向けてのんびりと谷を登っていきます。
| クワガタソウ |
クワガタソウです。花冠の大きさは1円玉を一回り小さくしたくらい。模様があるのは1個の花弁だけなんですよね。春先に野辺で見かけるオオイヌノフグリと同じ仲間で、花冠の構造がよく似ています。
| ヤマウツボ |
枯れているのではなく、これが満開状態のヤマウツボ。全体に白いのは葉緑素を持たないからで、栄養はもっぱら樹木に寄生して得ているそうです。
| ワチガイソウ |
場違い、ではなく輪違草(わちがいそう)。これでもナデシコの仲間なんですが、ずいぶんイメージが違いますね。
少し上空が透いて来ました。稜線も近いか。
小さな沢を埋める岩々。飛び石のように伝って上っていきます。こんな自然の中で体を動かしていると、なんか仕事のゴタゴタとかどっかに飛んでってしまいますね。
| ムシカリ |
ちょうど目の高さにムシカリの花が咲いていました。輝くような白さで、ハッとしました。峠の名前にもなっている花です。
その峠はもうすぐそこ。頭上が開け、地面まで陽射しが降り注いでいます。それにしても気持ちいいですなー。
| ムシカリ峠 |
11時25分、ムシカリ峠に到着しました。ここでアンパンを食べてエネルギーを補給。
峠を南側稜線から見たところ。写真の右側から上がってきて、これから写真奥に向かって登っていきます。
ここでは10分ほど休憩してから出発しました。
| フデリンドウ |
足元にはフデリンドウの小さな株が。急な登りで視線が下に向きがちだったのが幸いして、見つけることができました。
清々しい稜線の道。
| 三頭山西峰 |
11時45分、三頭山の山頂に到着しました。山頂といっても三つのピークのうちの一つ、西峰(1525m)です。ここがもっとも広く、写真のとおり休憩する人も多いです。木々が葉を落とす冬場は富士山の綺麗な姿を望むことができますが、この時期はちょっと見にくいかも。
賑やかな山頂で昼食をとってから、三つのピークの縦走に。最も標高が高いのは中央峰(1531m)ですが三角点は東峰(1528m)にあります。
西峰から少し下って登り返すと中央峰。ここでも小グループが昼食をとっていました。
| 三頭山中央峰 |
ピークの標識は尾根上にありました。
| 三頭山東峰 |
中央峰からほぼ水平移動をしたようなところに東峰。三角点の周囲がすこし広くなっています。
| 展望台 |
標識の先には展望台が。東側の眺望が開けていました。
雄大な眺め。左手の大きな山体は御前山(1405m)、右奥のドーム型のピークは大岳山(1267m)です。
| リョウブ |
自らが発光しているかのようなリョウブの若葉。梅雨前のこの時期の太陽光には若葉を輝かせる効果があるようです。
展望台からは東側に向かって稜線上を下っていきます。
| 分岐 |
12時30分、分岐が現れました。今回は鞘口峠に向かわず、ここから山腹を下ります。
植林地の中をジグザグに急降下。行き交う人は全くいません。あまりにも人気(ひとけ)がないので一応熊鈴を装着しました。
| 野鳥観察小屋 |
かなり下ったところに野鳥観察小屋が現れました。こんな道から外れた山の奥にまで人が来るのかと思って覗いてみたら、小屋の中は満員でちょっとびっくり。失礼しました…。
| |
13時5分、チップの敷かれた散策路に出ました。ここからは朝通った道を逆に辿っていきます。
森林館を経由して、正面入口まで戻ってくると、ちょうど数馬駐車場までバスが出るところ。ラッキーでした。
毎年、梅雨入り前の野山歩きは気持ちいいです。今日も輝くような陽射しの下で清々しい森林浴をさせてもらいました。