
御岳渓谷 〜水波に涼を求めて(前編)〜
 |
(前編) |
【東京都青梅市 令和5年7月15日(土)】
梅雨も終盤。毎日暑い日が続いています。特にこの3連休の2日目、3日目には38度に達すると予報されています。さらっと38度です! 自分が子どもの頃にはこんなことはなかったと思うのですが、気にしてなかっただけでしょうか。
ということで、野山歩きは3連休の初日にすることに決めました(この日の予報も最高気温32度なんですが)。行き先は、涼を求めての多摩川上流部、御岳渓谷です。朝、朝食、洗濯、植木の水やりといつものルーティンをこなしてから駅へ向かいました。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ホームに着いて、来た電車に乗って、乗り換えること4回。JR青梅線の御嶽駅に到着したのは10時前でした。
| 御嶽駅 |
天気は曇。でも今日に関しては陽射しはいりません。いかに水際を歩くといってもジリジリと焼かれるのは辛いですからね。
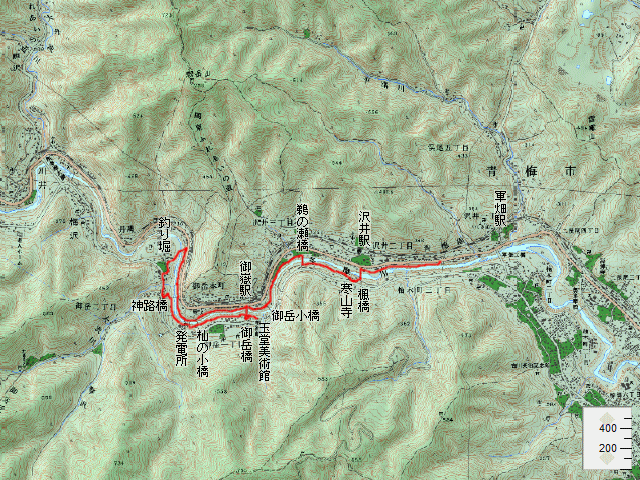 |
Kashmir 3D |
今日のコースは、ここ御嶽駅をスタートし、駅の前から多摩川の川辺に下ります。そこからまずは左岸(下流方向を向いて左側)の遊歩道を歩いていき、釣り堀が見えてきたらそこで対岸に渡って、今度は右岸を歩いて戻ってきます。スタート地点を通り過ぎたら御岳小橋を渡って左岸へ、次に鵜の瀬橋を渡って右岸へ、更に楓橋を渡って左岸へと往き来して、最後は青梅街道に出てゴールです。
| 駅前 |
青梅線の駅は青梅駅から数駅を過ぎると急に山の中といった立地になります。ここ御嶽駅もそんな駅の一つで、ホームが一番高いところにあり、一段下がって駅舎、更に一段下がって道路(青梅街道)という構図です。 多摩川の水面はその道路から20m以上も下にあります。つまり、急な山肌の中腹に線路と道路が通っているということです。
| 渓谷入口 |
さあ、スタートです。まずは川岸の遊歩道へ。駅前の横断歩道を渡って御岳橋のたもと、中華料理屋さんの脇に川へと下りていく路地がありました。
| 水際へ |
急傾斜の階段を下りていきます。濡れていたら滑り落ちるかも。
| 御岳橋 |
川岸に下りてきて見上げる御岳橋。結構高さがあります。谷が深いですね。もともとここには江戸時代から橋が架けられていたそう。洪水時には橋は流されるものという当時の常識を覆す、かなり高い位置に架けられた刎橋(はねばし)だったそうです。現在のものは昭和46年に架けられたもの。
| シロヨメナ |
最初に出会った花はシロヨメナ。
| シュウカイドウ |
シュウカイドウが咲いていました。江戸時代初期に園芸用として中国から持ち込まれたものだそうです。以来約400年。各地に帰化し、その名が俳句の季語になるほど日本に定着したようです。
川面に細いロープが張り巡らされていました。どうやらカヌーのスラローム競技の練習場のようでした。
| ノカンゾウ |
ノカンゾウ。野の萱草という意味の名です。花屋さんの店先にあってもおかしくない姿ですね。花被片は6個あって、花冠の根本で合着しています。
| クズ |
どこからともなくあの有名グレープジュースの香りが漂ってきました。それがクズの花の香りです。名前のせいなのか、雑草としてはびこるせいなのか、あまりちやほやされない花ですよね。
| 上流方向 |
多摩川の左岸を歩いて行きます。正面奥に見える建物は発電所。背後の山の斜面に大きなタンクがあって、そこから太い水道管が発電所まで下りているのが分かります。
水辺までの距離は近いところでは2、3mといったところです。
| ヤブラン |
ヤブラン。花自体は涼しげな姿をしているのですが、盛夏に咲くので、頭の中では「ヤブラン=蒸し暑い」といった構図で記憶されています。
| チダケサシ |
河原に近い藪の中にチダケサシが咲いていました。こんな環境でも生育できるのかと新たな発見。
| ヤマゼリ |
これはヤマゼリ。「山」と名が付いていますが、平地から山地まで生えるようです。
| マタタビ |
この時期のマタタビの葉は結構な割合で白くなります。これは虫を呼ぶための作戦として葉緑素をなくしてしまうから、と思いきや、葉緑素がなくなっているわけではなくて、白くなるのは葉の表面部分に空気が入っているから。なので、葉を水に漬けて白い部分を親指と人差し指で揉むと、空気が抜けて緑色になるのだそうです。
| キンミズヒキ |
なんとなくお目出たい名前のキンミズヒキ。金の水引(祝儀袋の帯みたいなあれ)ですから。秋も深まる頃に野山を歩くと、このキンミズヒキからごたくさんの祝儀をもらうことになります。実がひっつき虫になっていて、靴の紐などにびっしり付いてくるのです。面倒くさいご祝儀です。
| ヤブカンゾウ |
さっき見たノカンゾウの仲間、ヤブカンゾウ。名前は藪の萱草という意味です。ノカンゾウが一重咲きであるのに対し、このヤブカンゾウは八重咲き。花被片はヤブカンゾウと同じ6個で、それ以外のものは雄しべと雌しべが花弁のように変化したもの。したがって結実しないわけですが(地下茎で増える)、ならば八重咲きになってまで目立つ必要があるのか。派手になる目的は花粉を媒介する虫を呼ぶためではないのでしょうか。
| メマツヨイグサ |
オオマツヨイグサ(大待宵草)に対して少し小型なので、メマツヨイグサ(雌待宵草)。夜に咲く花です。
| 杣の小橋 |
御岳橋から遡って最初に現れる橋、杣(そま)の小橋。
| 多摩川第三発電所 |
対岸の発電所が近くに見えるところまでやって来ました。ここから8km上流にある白丸ダムから山の中ををくり貫いた水道管で水を引き、発電所の上にあるタンクに一回溜めて発電所に落としているそうです。
| ヘクソカズラ |
お馴染みのヘクソカズラ。どこででも見かけます。
| 神路橋 |
二つ目の橋が見えてきました。神路橋です。名前のとおり、御嶽神社の参道に通じる橋。
| コマツナギ |
マメ科の植物、コマツナギ。茎は細いですが、馬を繋いでおけるほど強いということで付けられた名前だそうです。
| ハグロソウ |
おお、ハグロソウですね。薄暗い山の中で見かける花です。花弁が4個、5個、6個の花が多い中で、花弁が2個というのは少数派。雄しべも2個です。
| ムラサキニガナ |
ムラサキニガナ。背丈が高く茎が細いので、しばしば写真のようにしな垂れています。まだ花もありました。
| タケニグサ |
タケニグサも本来であれば直立し背丈は2mくらいにもなるのですが、ここではしな垂れていました。頭上の木々は川にせり出し大きな庇のようになっているので、その下で光を求めて横に伸びているのか?
| ヨウシュヤマゴボウ |
ヨウシュヤマゴボウ。花序の先端にはまだ花が残っていますが、ほとんどは実になっています。秋には紅黒く熟します。ただし有毒。
遊歩道ではときおり散策している人とすれ違いました。植物観察をしていそうな人は少なかったです。蒸し暑いですからね。
| 奥多摩フィッシングセンター |
対岸に奥多摩フィッシングセンターという釣り堀が現れました。自然の川を区切って釣り堀状にしている方式です。この先で河原に下り、あの小橋を渡って右岸に出る予定。
| オオバギボウシ |
上品な花を並べて付けるオオバギボウシ。この花も本来は直立し…。まてよ、これは斜面に生えているから必然的に横に向かって延びているということか。さっきのタケニグサもそうだったのかもしれません。
分岐までやって来ました。釣り堀の幟が立っていますね。ここを左に折れて河原に下ります。
| ユウゲショウ |
流れに架けられた橋のたもとにユウゲショウが咲いていました。南米原産で明治時代に観賞用に移入されたものだそうですが、「夕化粧」という情緒のある名前をもらっています。確かに花はそんな雰囲気を持っているような。
| 吉野街道 |
橋を渡った先は釣り堀の敷地(?)で、そこからしばらくは水際は歩けそうになかったので、いったん車道に上がることにしました。民家の軒先の路地を登って、出たところが吉野街道です。地図によると、道路標識の先に左手に下る道があるようなので、そこまでは車道歩き。ちなみに、道路標識には「↑八王子
立川」「→御岳山」と表記されていました。(後編に続く)