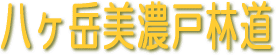
八ヶ岳美濃戸林道 ~幻の花ふたたび(前編)~
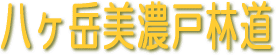 |
(前編) |
【長野県 茅野市 令和5年6月6日(火)】
八ヶ岳の麓に幻の花ホテイランが咲く。その話を聞いて脳内に広がったイメージは、幽玄な林内で微動だにせず咲いているホテイランの様子でした。その周りだけ浮き出るようにほの明るくなって。そんな想像が実際に正しいのかを確かめに行ったのが8年前のちょうどこの時期。そして、そこは期待を裏切らない異世界でした。(その時の様子)
今回、その感動にもう一度触れたくて、ドリーム号Ⅲを走らせて行ってみることにしました。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
梅雨入りが近いのか、雲は多め。でも雨の心配はなさそうです。午前6時前に出発。圏央道から中央道に入ります。平日の午前中ということもありスイスイと走れました。諏訪南ICで一般道に下りるとそこは扇状地の扇端部。そこから扇頂に向かって坂道をひたすら上っていきます。
| 八ヶ岳山荘 |
8時20分、今回の野山歩きの基点となる八ヶ岳山荘が見えてきました。ここに車を停めて美濃戸林道を歩きます。
この辺りを美濃戸口といい、ちょうど扇状地の扇頂部に当たります。「口」というからにはこの奥に「美濃戸」という場所があることになり、それが今回の目的地あたりになります。
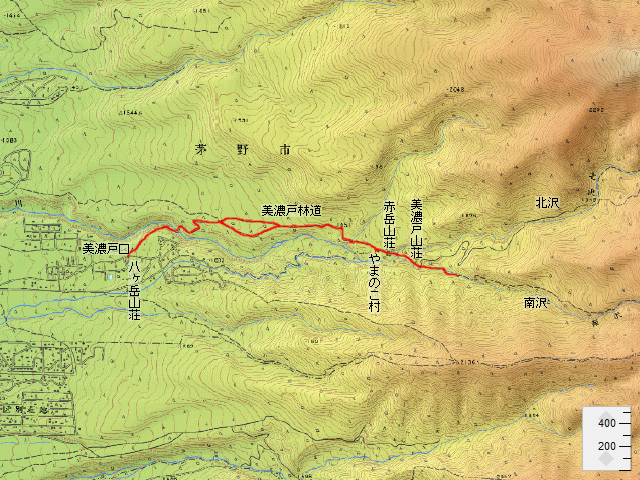 |
Kashmir3D |
今回のルートは、美濃戸口から柳川の川筋まで下り、そこから対岸を上り返してあとは少しずつ高度を上げていきます。林道を歩くのは美濃戸山荘まで。そこから南沢に沿う登山道に入り、しばらく行くとホテイランの群生地に至ります。復路は来た道を戻ります。
| 林道入口 |
8時35分、出発の準備をしていると、そこに男性4人が乗った車がやって来て、窓を開けてキョロキョロしています。聞くとその人達もホテイランを見に来たとのことで、車で林道を行くつもりだったようですが、道中にもいろんな植物が見られることを伝えると、じゃあ歩いて行ってみようということになったようです。駐車場に車を停めてやって来ました。
たまたまスタートが同じになったことから、自然の流れで一緒に歩くことに。先方の話では、4人のうちの一人はシンガポールだかマレーシアだかの植物学者(植物園の園長もしているとか)で、今回日本の野生ランを中心に観察に来ているとのこと。他の3人が数日間かけて岐阜、長野の数カ所を案内しているということでした。日本人3人のうちの二人は大学の先生でもう一人が案内役(この人も専門書を出版するほどの植物愛好家)とのことでした。
| ヒレハリソウ |
林道入口に咲いていたヒレハリソウ。もう花が落ちて萼だけが残っているものもありますね。
ヒレハリソウはヨーロッパが原産地で、明治時代にコンフリーの名で移入され、食用や薬用として利用されたのだそうです。今日の最初の花はこの帰化植物でした。
| 林道 |
林道は未舗装で、写真のような走りやすそうなところもありますが、奥に行くにしたがって急な傾斜や深く彫り込まれた溝などが現れ、ゴロゴロとした礫もあって、走るにはそれなりの技術と装備が必要です。
| シロバナノヘビイチゴ |
ヘビイチゴが野辺の草地で見られるのに対し、このシロバナノヘビイチゴは山地で見かけます。
名前に「シロバナ」(白花)が付く植物は数多くあり、例えば、エンレイソウの白花種はシロバナエンレイソウ、センダングサの白花種はシロバナセンダングサですが、ヘビイチゴの場合、「シロバナノヘビイチゴ」と間に「ノ」が入ります。このパターンのネーミングはちょっとめずらしいです。
| ササバギンラン |
低地の里山では一月前に盛りを迎えていたササバギンラン。この辺りの標高は約1500mもあり、その分時間を遡る形で観察することができます。秋の実りや紅葉などはその逆ですね。
| イカリソウ |
イカリソウ。こちらは二月ほどもタイムラグがあります。
| ベニバナイチヤクソウ |
写真の背景がゴチャゴチャしていてちょっと分かりにくいですが、ベニバナイチヤクソウの花が俯いて咲いているところです。亜高山帯の林内に咲くのだそうです。
| レンゲツツジ |
オレンジ系のツツジの代表選手、レンゲツツジ。里山というよりももう少し標高の高いところで見かけます。我が故郷の「市の花」になっています。
| エンレイソウ |
花期が終わり実が成熟しつつあるエンレイソウ。花を中心に3つの葉が綺麗に120度ずつ分け合って光を受けています。花の名を漢字で書くと「延齢草」。なんか縁起が良さそうですね。古くから薬効が知られていたことによるネーミングのようですが、裏腹で毒性もあるとのことで、素人判断で摂取したりしてはいけません。
| ヤマドリゼンマイ |
大型のシダ、ヤマドリゼンマイ。6個の葉を全体として漏斗状に広げていて、その直径は1mくらいにもなります。その中心から真っ直ぐに伸びているのは胞子葉。以前、山中の谷を埋め尽くすヤマドリゼンマイの群落を見たことがありますが、ちょっとした異世界でした。
| ヤマツツジ |
ヤマツツジ。さっきのレンゲツツジとともにオレンジ系ツツジの代表選手です。これは多摩の里山でもよく見かけます。
| イボタヒョウタンボク |
イボタヒョウタンボクです。フォッサマグナ要素の植物の一つだそうで、図鑑によると富士山、南アルプス、八ヶ岳などの山域の亜高山帯に分布しているとのことでした。写真で一つの花のように見えているのは2個の花が並んでいるもの。秋に実ができると並んだ2個の実がひょうたんのように見え、それが元で名前が付いたそうです。ちなみに、イボタは葉がイボタノキのそれに似ているからだそう。
| コデマリ |
花や葉の様子からするとコデマリだと思います。古い時代に中国から渡来したものだそうですが、それがこの八ヶ岳山麓に帰化したということでしょうか。
| マタタビ |
マタタビの葉。枝の上部に付く葉は花の時期になると白くなり、遠目には雪を被ったように目立ちます。花粉を媒介する虫を呼ぶための戦略でしょうか。木全体の葉を白くしないのは、それなりに目立ちつつ一方で光合成もしたいということでしょうね。
| コデマリ |
さっきのものより花冠から雄しべが長く飛び出していますが、これもコデマリでしょうね。
| 川筋へ |
9時5分、美濃戸の谷から流れ下る柳川の河原まで下りてきました。
| 柳川 |
橋の上から下流方向を望む。まあまあの水量がありました。
| クリンソウ |
川を渡るとまた林道を登り返します。これはクリンソウ。車輪状に付いた花が何段にも重なるのですが、写真は一番下の段が開花した状態。茎の先端にこれから伸びる部分がスタンバイしています。
| ミヤマガマズミ |
ガマズミが里山でも普通に見られるのに対し、このミヤマガマズミはより標高の高いところに分布しているとのこと。名前のとおりですね。葉の先端の尖り具合や葉柄の赤味の帯び方なども見分けポイント。
| サクラスミレ |
サクラスミレでしょうか。ナガバノスミレサイシンかと思いましたが、アップで見ると側弁に毛があるので、違うということに。
| ツマトリソウ |
清楚な印象のあるツマトリソウ。7個の独立した花弁があるように見えますが、よく見ると元の方で合着していて、深く切れ込んだ部分が着物の前を合わせたように重なっています。ツマトリソウは漢字では「褄取草」と書き、「褄」にはこの着物の重なる部分を示す意味があるとのことなので、それがこの花の名の由来かと思いきや、調べてみると「褄取」には別の意味があって、それは鎧の威(おどし:小板をブラインドのように編み込んだ防御板)の色目(カラーパターン)の一種の名前なのだとか。ツマトリソウの花弁の縁が紅色に縁取られるものがあり、それが「褄取」の色目に似ているからなのだそう。ん?まてよ。だとすると色目の「褄取」の由来はなんなのか(ツマトリソウが元ではないのか。)。
| オオヤマフスマ |
オオヤマフスマはナデシコの仲間。本来は花弁は5個ですが、写真のものは6個あるように見えます。名前は漢字では「大山衾」。「衾」は夜具の一種で、掛け布団的な役割の四角い一枚布のことだそうです。ただ、なぜこの花の名前がそうなったのか由来は不明とのこと。そもそも「大山・衾」なのか「大・山衾」なのかもよく分かりません。
| 美濃戸林道 |
林道は延々と上り坂です。偶然一緒になった四人組と楽しい植物談義をしながら歩いていたので、まったく苦になりませんでした。
| ウマノアシガタ |
ウマノアシガタの萼片は一見花弁のよう。黄色で金属光沢があります。別名をキンポウゲ。
| ササバギンラン |
ササバギンランは花よりも高く葉が伸びます。これがギンランとの大きな違い。
| イブキジャコウソウ |
これはイブキジャコウソウの葉。花は夏に咲きます。高山植物のイメージですが、くだんの大学の先生によると伊良湖岬でも見つかっているとのこと。高山に咲く花の図鑑にも確かに「低地~高山帯の岩場や乾いた草地に生える」とありました。
| ヒロハヘビノボラズ |
枝に刺があり、蛇も登れないということでヘビノボラズ。なんか直接的というか投げやりな感じのするネーミングですね。ヒロハは「広葉」です。
| ズミ |
ズミの花。花が終わって実が生長し始めているものもあります。ズミはリンゴの仲間で、実が酸っぱいことから「酢実」が名の元という説もあります。
| サラサドウダン |
サラサドウダンの花を一言で表すと「メルヘン」と言ったら、昭和だねと言われました。
| ズミ |
枝垂れるように花を付けたズミ。湿った土地を好むのだそうです。この花と初めて出会ったのは広島県西城町のクロカンパーク内の湿地だったと思います。
| イボタヒョウタンボク |
ここにもイボタヒョウタンボク。実の時期にも訪れてみたいです。本当にひょうたんみたいなのか。
| やまのこ村 |
10時20分、やまのこ村までやって来ました。登山者向けの山小屋です。
| サクラソウ |
サクラソウです。もう花期は終わりかけのようでした。
サクラソウの花は2タイプあるとのこと。花冠は横から見ると長い筒状になっていて、一つは雌しべが花から突き出ていて雄しべが筒の奥に引っ込んでいるタイプ。もう一つは雄しべが筒の出口付近にあって雌しべが奥に引っ込んでいるタイプ。これは同じ花で受粉することのないようにするためだそうです。
| 赤岳山荘 |
やまのこ村のすぐ先に赤岳山荘があります。この時刻、八ヶ岳に登る人は既に出立しているのでしょう。静かでした。
| ニッコウナツグミ |
蕾を付けたグミに出会いました。図鑑とにらめっこした結果、これはニッコウナツグミではないかと。東北南部から関東甲信地域に分布するとされていますが、個体数は少ない方だということです。ここ八ヶ岳山麓も観察ポイントの一つとされていました。
| 南沢の合流点 |
赤岳山荘を過ぎ、南沢の合流点までやって来ました。時刻は10時30分です。これまで林道とつかず離れず流れていた柳川はここで南沢と北沢が合流して一つになったものなのです。
さあ、目的のホテイラン自生地まではあとわずか。ワクワク感が高まります。(後編に続く)