
飯盛山 ~冬隣りの晴天の下で(後編)~
 |
(後編) |
【長野県 南牧村 令和6年11月19日(火)】
冬とすぐ隣り合わせのこの時期。晴天の下での野山歩きの後編です。(前編はこちら)
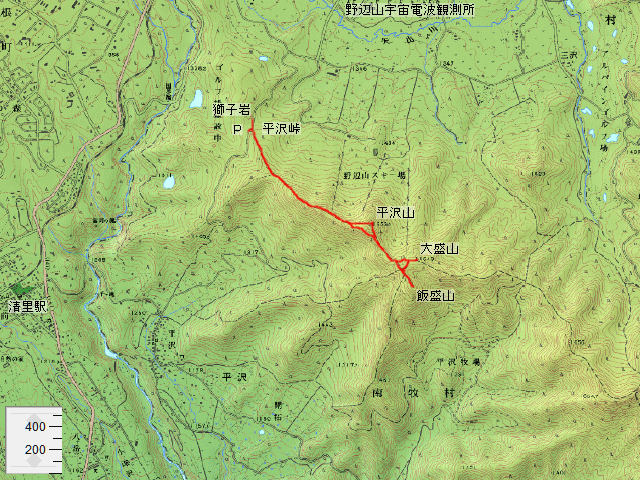 |
Kashmir3D |
10時25分に平沢峠の登山口を出発。飯盛山へ向けて稜線を歩き、1時間で山頂に到着しました。
誰もいない山頂で、とりあえず時計回りに360度の眺望を満喫することに。
| 東方向 |
まずは東方向。(写真にマウスポインタを乗せると山名表示) 目に飛び込んでくるのは秩父山地の南西端に位置する山塊です。中でも金峰山の山頂にある天然のオベリスク、五丈岩はよく目立っていました。視線を右に移すと茅ヶ岳。その向こうに甲府盆地があります。茅ヶ岳は日本百名山で有名な深田久弥氏の終焉の地。急な登山道の脇にポツンと小さな碑が置かれていて、以前登ったときに、山に抱かれて逝ったんだなと神妙な気持ちになったのを覚えています。そして、茅ヶ岳のずっと奥にある富士山。いつ見ても神々しいですね。
| 富士山 |
♪あたまを雲の上に出し…。唱歌「ふじの山」の歌詞そのままの姿ですね。まさに「かみなりさまを下に聞く」状況です。ところで最近の子供は、この歌を含めyamanekoたちが小学校で習ったような歌を学校で教わるのだろうか。「夏は来ぬ」とか「たきび」とか。
| 南方向 |
更に視線を右に移して南方向。ほぼ南アルプスで視界が占められています。南アルプスは今も成長(隆起)し続けている若い山々。標高国内第2位の北岳、第3位の間ノ岳をはじめ、ベスト10のうち4つの峰が属しています。高さだけではなく、甲斐駒ヶ岳や仙丈ケ岳(写真では甲斐駒ヶ岳の後ろに隠れている)、悪沢岳、赤石岳、鳳凰三山など山好き憧れの山々(それでもみんな3千m前後の高さ!)も連なっています。南アルプスの左側には富士川が削った低地が駿河湾まで続いています。甲府盆地だけでなく、さっき平沢峠から歩いて来た登山道を境としてその南側に降った雨はみんなあの低地を流れて太平洋に注ぐのです。一方登山道の北側に降った雨は千曲川に合流し、長旅を経て新潟で日本海に注ぎます。そう、さっきまで歩いていた登山道の稜線は中央分水界だったのです。あの富士川の低地を見ていてあらためて気が付きました。
| 北岳 |
北岳の雄姿です。クライマーの聖地、北岳バットレスの岩壁が見えていますね。ちなみに北岳は火山ではありません(南アルプスに火山なし)
| 西方向 |
次に西方向。八ヶ岳がドカーンとそびえています。南東麓には清里の街並みも見えます。八ヶ岳は、日本の屋根と呼ばれる北アルプス(飛騨山脈)、中央アルプス(木曽山脈)、南アルプス(赤石山脈)のいずれにも属さない、フォッサマグナの中央にポツンと立っている独立山塊です。その孤高の山容から古来信仰の山として敬われ、面白い神話などもいろいろあるようです。例えば、むかしむかし、富士山と八ヶ岳が背比べをすることになり、両山の山頂に筒を渡してどちらに水が流れるかで勝負したそう。結果は八ヶ岳が勝利したのですが、怒った富士山がその筒を持って八ヶ岳の頭を叩いたので、八ヶ岳の山頂部が八つの峰になったというもの。荒唐無稽すぎて面白いですね。
| 清里 |
清里の街並みです。yamanekoを含む80年代に若者時代を送った者にとって清里は、ある種特別な思いを持って聞く地名だと思います。メルヘン(死語)でファンシー(死語)で、まあ恋人たちの聖地って感じでしたから(多少のやっかみあり)。平成に入ってからはほとんどその名を聞かなくなりましたが、最近また徐々に賑わいを取り戻しつつあるようです。
| 北方向 |
そして北方向の眺めです。目の前の大盛山の向こうには野辺山高原が広がり、その先は標高を下げながら佐久盆地へと続いています。最奥には浅間山などの大きな山塊が。こちら側に降った雨は日本海に向かうんですね。正面の御座山は関東山地の北西端辺りに位置していて、標高は2千mを超えていますが、yamanekoはこれまでこの山のことは知りませんでした。なんとなく魅力的な姿をしています。ちなみに、関東山地はその北部を秩父山地、南部を丹沢山地といい、両者を桂川が隔てています。
以上、ぐるっと一周しました。
そうこうしているうちに年配夫婦の登山者がやって来ました。話を聞くと、富士山北麓の富士吉田からで、今朝急に思い立ってここまで来たとのこと。アクティブですね。こちらの夫婦とは復路でも何回か行き会い、世間話をさせてもらいました。一人で野山歩きをしていると知らない人に話しかけたくなるんです。
| 大盛山へ |
山頂は吹きっさらしで長居は辛いので、早々に次の大盛山に向かいました。山と言ってもここから見るとなだらかな丘です。
| モチツツジ? |
この真紅に紅葉しているのはひょっとしてモチツツジでは? 関西でよく見かけるツツジですが、一応山梨県も分布範囲には含まれています。大阪在住時には生駒山とか金剛山とかの奈良県境の山々で頻繁に出会いました。
| 大盛山 |
見ようによってはどこかの公園みたいでもある大盛山の山頂部。
| 大盛山山頂 |
11時45分、大盛山の山頂に到着しました。標識があるのみです。ん? 標高は「一六五〇米」と記されていますね。地理院地図では1643mとなっていますが。その差の7mはなんだろう。
| 平沢山越しの八ヶ岳 |
西を見ると…。こんもりとした山はこれから登る平沢山です。
| ピラミッド |
南にはさっきまでいた飯盛山が。それにしても三角ですね。作り物みたい。
さて、下山です。今日は天気が良いから問題ないですが、このあたりは隠れるところがないですね。急な天候の変化があったりすることを考えると侮れない山なのかもしれません。
やがて左手から飯盛山からの登山道が合流してきました。往きにはそちらに進んだのです。それにしても人に出会いませんね。
無音です。こんなところを一人で歩いていると、遠い旅人になったような、変な感覚に陥ります。
| 急登 |
ほどなく平沢山の急登に取りつきました。なんかようやく山に登っている感じになってきました。
| 平沢山山頂 |
そしてすぐに山頂です。ここは標識すらなし…、と思ったら三角点がありました。
| 三角点 |
「三角点」の文字が旧字体です。かなり古いもののようですね。三等三角点で、標高1653.2mだそうです。ということは飯盛山や大盛山よりも高いということですね。
この三等三角点は、1辺15cmの四角形で、地表に出ている部分は20cm弱。地面の下に埋まっている部分は60cmくらいあるそうです(ここのは表土が流失したのか、本来埋まっている部分が少し地上に顔を出していました。)。その重さは65kg。ヘリコプターなどない時代には山の上まで人力や馬などで上げたんでしょうね。しかも、その石の下に土台となる36cm四方、重さ30kgの石も埋まっているそうですから、トータル100kgを運び上げるということになります。近代国家への礎を築いた先人たちに感謝です。ちなみに、一等三角点は更にこれより一回り大きいのだそうです。トータル130kgくらいだとか。
平沢山からの下り。この時間でも日陰の植物には霜が降りたままです。
| 飯盛山分岐 |
飯盛山方面との分岐点までやって来ました。往きには正面からやって来て、ここを写真左手に折れたのです。その先には日当たりの良い場所があったはずなので、そこで昼食にすることにしました。
| ランチ |
ベンチこそ設置されていませんが、広くなだらかな斜面はいかにもここで休憩してくださいと言わんばかりの場所です。さっき飯盛山で出会ったご夫婦もここで休んでいました。yamanekoも腰を下ろしさっそく昼食の準備を。といっても水筒の熱湯をカップ麺に注ぐだけですが。この時期、山火事になってはとバーナーの使用を控えるようにしています。
昼食で体の内側から温まりました。さて再スタートです。立ち上がって振り向くとさっきの分岐点です。ここを左へ。
葉を落とした木々にツルウメモドキが巻き付いて、その朱い実で寂しくなった枝々を飾っていました。
| ツルウメモドキ |
その実をアップで。固い殻が3つに裂けて反り返り、朱色の仮種皮(種子を包んでいる)が露出しています。
| クロウメモドキ |
この黒っぽい実は…。ちょっと悩みましたがクロウメモドキのようです。ところでツルウメモドキとクロウメモドキ。名前は似ていますが、ツルウメモドキはニシキギ科。クロウメモドキはクロウメモドキ科で、近縁ではありません。つる性なのでツルウメモドキ、黒い実なのでクロウメモドキ、じゃあただのウメモドキってのもあるのかって話になりますが、あります。モチノキ科。ややこしいですね。更にこの3つのいずれもウメとは無関係。ウメはバラ科です。そういえば、植物の名前ってウメを引き合いに出すものが多いように感じますが、どうでしょうか。ダンコウバイとかウメバチソウとか。
野辺山高原です。八ヶ岳の穏やかな裾野にはキャベツ、レタスなど高原野菜の畑が広がっています。また、牧場などもあちこちに。
ところで、自然環境が厳しいこの地で人々は昔から暮らせていけたのだろうか。と思って調べてみると、江戸時代中期までは甲斐から佐久に抜ける道があるのみで、集落はおろか人家はまったくなかったのだそうです。そのため幕府が旅人の安全を確保できるよう、幾つかの村を置いたとのこと。よっぽど荒涼とした場所だったんでしょうね。無理やり連れてこられた人たちはたまったものではなかったでしょう。
半ば凍結している登山道に落ち葉が張り付いていました。ハウチワカエデとミズナラのものです。
| ヤマアジサイ |
ドライフラワー状態のヤマアジサイ。風雨にも耐えて残っているのをよく見かけます。
もう冬枯れと言っていいくらい見通しの良い森。その中をのんびりと下っていきます。今日もいい野山歩きができたなと充実感を感じるひとときです。
もうずいぶん下ってきました。八ヶ岳に今日のお礼を。
ツツジの仲間でしょうね。今枝についている葉はこのまま冬を越す葉でしょう。
| 鉄道最高地点? |
眼下に見える辺りがJR最高地点ですね。中央東線の小淵沢駅から標高差約500mの急傾斜をぐんぐん登って1375mの峠に達したところにあります。峠に上がってみるとその先はなだらかな高原で、片峠と呼ばれる地形になっています。ところで、この場所、JR最高地点であって鉄道最高地点ではないんですよね。じゃあ鉄道最高地点はどこなのか。法令上「鉄道」の範囲はかなり広く、ケーブルカーやモノレールなども含まれるのだとか。その意味で現在鉄道最高地点とされているのは、立山黒部アルペンルートの立山トンネルトロリーバスの室堂駅だそうです。明確にバスと言っているのに鉄道なんです。ただ、このトロリーバス、11月30日をもって運行を終えるのだとか(電気バスに移行)。その後はもしかしたらここが鉄道最高地点に、と思いきや、まだ同じアルペンルートのケーブルカー黒部平駅が高いところにあるのだそうです。残念。(ロープウェイまで鉄道に含めると話は違ってきますが。)
この絶景が名残惜しいので八ヶ岳の写真を何度も掲載します。
| 下山完了 |
12時55分、登山口まで戻ってきました。下山完了です。
| 獅子岩 |
んんっ? あれが獅子かも!ここから見ると、獅子が身を低くして獲物を狙っているように見えますね。なるほどです。
| 駐車場 |
無事に駐車場に到着です。今日は絶景の中に身を置いて非日常を十分に堪能しました。さあ整理体操をしてから帰途につきましょう。
と、この後ちょっとした事件が。
ドリーム号Ⅲのドアを開けようとドアノブのスイッチを押しましたが、もうんともすんともいいません。
あっ、そういえば今朝バッテリーが弱っているような感じだったが、バッテリーが上がったか。こんなところで。スマートキーのカバーを外して、旧来のキーを使ってドアは開きました。あとはエンジンです。頼む!掛かってくれよと念じつつイグニッションボタンを押したのですが…、やはりこちらも無反応です。ヤバい、こんな周囲に民家もない峠の駐車場でバッテリー上がりとは。夜までいたら凍死しかねないぞ。いろいろなことが頭を巡る中、やはりここはロードサービスに電話をするのが最善手との結論に至りました。
まいったなと思いつつ電話をしたのですが、まずこの場所を説明するのに一苦労。バッテリーが上がった旨伝えると、オペレーターからは、エンジントラブルも想定されるのでこういう場合レッカー車を手配するが、場所が場所だけに業者が見つかるか、見つかったとしても仮にエンジントラブルの場合には東京までの搬送を引き受けてくれるか分からないという不安な回答。こうなったらなんとかバッテリー充電でエンジンが掛かってくれることを祈るだけです。
業者が見つかったら折り返し電話する、ただし、見つかってからでも到着まで1時間ほどかかるとのことなので、ここはコーヒーでも飲みながら腰を据えて待つことにしました。今朝コンビニで買ったカップコーヒーです。幸いここからは見飽きることのない雄大な八ヶ岳が望めるではないですか。
コーヒーを飲み干して一息ついて、しばらく経ったのでエンジンが掛かったりしないか、もう一度車に乗り込みイグニッションボタンを押したのですが、やはり無反応。諦めきれず何度か長押ししていたら、なんと掛かったのです、エンジンが! おお、このエンジンを止めてはいけない! 走ってバッテリーを少しでも充電し、なんとか家まで辿り着こう。すぐにロードサービスに電話をしてレッカーをキャンセルし、エンジンが止まらないうちに東京に向けて走り出しました。
運転していても何かの拍子にエンジンが止まらないか不安です。ドリーム号Ⅲは普段アイドリングストップ機能を使っているので、信号で停まったりすると自動でエンジンが切れるのですが、そのままかからなくなったらマズいので、慌ててその機能をオフにしました。そしてなんとか帰路の140kmを走り切りました。ただ自宅の駐車場は機械式なので、そこでバッテリー充電はできません。なので自宅は素通りしてオートバックスへ直行です。ピットの受け付けで状況を伝えバッテリーを観てもらいたい旨伝えると、「それはスマートキーの電池切れじゃないですか?」、「レジでボタン電池売ってるので取り替えてみてください。」
へっ?そういうことっすか? 急いでレジに行って300円で電池を買って入れ替えると、一発で掛かるじゃないですか。なんと。
エンジンはただイグニッションボタンを押すことで起動すると思っていましたが、その際近くにスマートキーがあることを感知しないと起動しないということを認識していませんでした。スマートキーが電池切れだと感知しないのです。そうだったのか。
それにしてもあのままレッカーを待っていたらと考えるとゾッとしました。長時間待った挙げ句にようやくやって来たレッカーからバッテリーチャージしても当然にエンジンは掛からないわけで、そこから車を東京まで搬送することになったと思います。ヘタをしたら搬送を断られ、小淵沢辺りの自動車修理工場で一晩預かってもらって、悪くもないバッテリーを交換していたかもしれません。自分は電車を乗り継いで帰って翌日また戻って来るか、どこかに一晩泊まるか。とんだドタバタです。おお怖っ。ただ、あのとき何でエンジンが掛かったんだろう。ボタンを長押ししたことで電池に残っていた僅かな電力が働いてくれたのだろうか。いずれにしても幸運でした。