
پ@
”رگ·ژRپ@پ`“~—ׂè‚جگ°“V‚ج‰؛‚إپi‘O•زپjپ`
پ@
 |
پ@پi‘O•زپj |
پy’·–ىŒ§ “ى–q‘؛پ@—كکa‚U”N‚P‚PŒژ‚P‚X“ْپi‰خپjپz
پ@
پ@‚P‚PŒژ‚ة“ü‚ء‚ؤ‚و‚¤‚â‚ٹe’n‚©‚çچg—t‚ج•ض‚è‚ھ“ح‚‚و‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پBٹe’n‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚àƒeƒŒƒr‚جڈî•ٌ‚ب‚ج‚إ—L–¼ٹدŒُ’n‚ج—lژq‚خ‚©‚è‚ب‚ج‚إ‚·‚ھپA‚¢‚¸‚ê‚àچ¬ژG‚ئڈa‘ط‚ھƒZƒbƒg‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ؤپA‚ئ‚ؤ‚àڈo‚©‚¯‚و‚¤‚ئ‚¢‚¤‹C‚ة‚ب‚ê‚ـ‚¹‚ٌپBچg—t‚ًٹy‚µ‚ق‚ج‚ب‚ç‹كڈٹ‚جڈ¬ژR“à— Œِ‰€‚إ‘S‚‚à‚ء‚ؤڈ\•ھ‚إپA‚ق‚µ‚ëگأ‚©‚ةڈH‚جگ[‚ـ‚è‚ًٹ´‚¶‚ç‚ꂽ‚è‚·‚é‚ٌ‚إ‚·‚و‚ثپBŒ©چ ‚ـ‚إ‚ ‚ئ”¼Œژ‚ظ‚ا‚©‚©‚è‚ـ‚·‚ھپB‚»‚±‚إچ،‰ٌyamaneko‚ھڈo‚©‚¯‚½‚ج‚حپA’·–ىŒ§گ¼•”پA–ى•سژRچ‚Œ´‚ة‚ ‚é”رگ·ژRپi‚ك‚µ‚à‚è‚â‚ـپjپB’·–ىŒ§‚ج“ŒگM‚ئŒؤ‚خ‚ê‚é’nˆو‚ج“ى’[‚ةˆت’u‚µ‚ؤ‚¢‚ؤپA“Œ‹•û–ت‚©‚çŒü‚©‚¤‚ئژR—œŒ§‚ً”²‚¯‚ؤ‚·‚®پA’·–ىŒ§‚ة“ü‚ء‚½‚ج‚©پH‚ئ‚¢‚¤‚‚ç‚¢‚ج‚ئ‚±‚ë‚ة‚ ‚è‚ـ‚·پiچsگ‹وˆو‚إŒ¾‚¦‚خ“ى–q‘؛پjپB”ھƒ–ٹx‚جگâچD‚جƒrƒ…پ[ƒ|ƒCƒ“ƒg‚إ‚ ‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپA‚R‚U‚O“x‘fگ°‚炵‚¢’–]‚جژR‚إ‚·‚ھپA‚¨‚»‚ç‚‚à‚¤چg—t‚حڈI‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚ؤپA‰½‚ب‚ç“~‚ج‘•‚¢‚ًژn‚ك‚ؤ‚¢‚éچ ‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@![]() پ@پ@
پ@پ@![]() پ@پ@
پ@پ@![]() پ@پ@
پ@پ@![]() پ@پ@
پ@پ@![]() پ@پ@
پ@پ@![]() پ@پ@
پ@پ@![]() پ@پ@
پ@پ@![]() پ@پ@
پ@پ@![]() پ@پ@
پ@پ@![]()
پ@
پ@Œك‘O‚Vژ‚Q‚O•ھپAƒhƒٹپ[ƒ€چ†‡V‚إڈo”پBژش‚ةڈو‚èچ‚قچغ‚ةƒhƒAƒچƒbƒN‰ًڈœ‚ج”½‰‚ھ“ف‚©‚ء‚½‚èƒGƒ“ƒWƒ“ژn“®‚ة‚ي‚¸‚©‚ةƒ^ƒCƒ€ƒ‰ƒO‚ھ‚ ‚ء‚½‚èپA–锼‚©‚ç‹}‚ة—₦چ‚ٌ‚¾‚¹‚¢‚©ƒoƒbƒeƒٹپ[‚à”\—ح’ل‰؛‹C–،‚ج‚و‚¤‚إ‚µ‚½پB
پ@Œ—‰›“¹‚©‚ç”ھ‰¤ژq‚i‚b‚s‚إ’†‰›“¹‚ة“ü‚èپA‚»‚±‚©‚ç‚ح‚ذ‚½‚·‚çگ¼گiپB•½“ْ‚ئ‚ ‚ء‚ؤژش‚àڈ‚ب‚ڈ‡’²‚بƒhƒ‰ƒCƒu‚إ‚µ‚½پBچb•{–~’n‚ً‰ك‚¬پA’·چâ‚h‚b‚إˆê”ت“¹‚ضپB‚»‚±‚©‚ç”ھƒ–ٹx‚جچL‘ه‚بژRگ‚ً–kڈم‚µ‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚·پB“r’†‚ة‚ ‚éگ´—¢‚ًƒoƒCƒpƒX‚إ”²‚¯‚é‚ئ‚»‚جگو‚©‚ç‚ھ’·–ىŒ§پBŒ§‹«‚ة‚ح“S“¹چإچ‚’n“_پi‚i‚qڈ¬ٹCگüپj‚ھ‚ ‚èپA‚»‚ج‹ط‚ة‚ح—L–¼‚بڈêڈٹ‚ج‚و‚¤‚إ‚·پB’·–ىŒ§‘¤‚حچ‚Œ´‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ؤپAˆê–ت‚ةچL‚ھ‚é”_ڈê‚ئ‰“‚‚ةکA‚ب‚éژRپX‚ھ’·ٹص‚ب•—Œi‰و‚ج‚و‚¤‚إ‚µ‚½پB‚»‚µ‚ؤپA‚»‚±‚©‚çچ،“ْ‚ج–ىژR•à‚«‚جٹî“_‚ئ‚ب‚镽‘ٍ“»‚ً–عژw‚µ‚ؤچX‚ة•Wچ‚‚ًڈم‚°‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚µ‚½پB
| پ@ژ‚ژqٹâ’“ژشڈê |
پ@‚P‚Oژ‚P‚T•ھپA•½‘ٍ“»‚جژ‚ژqٹâ’“ژشڈê‚ة“’…پB‚©‚ب‚èچL‚ك‚ج’“ژشƒGƒٹƒA‚ة‚حگو‹q‚ھ‚P‚Oگ”‘ن’â‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‘هŒ^ƒoƒXگê—p‚ج’“ژش‹و‰و‚à‚ ‚èپA‹x“ْ‚ة‚حƒcƒAپ[‚ج“oژR‹q‚à‘½‚¢‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پBمY—ي‚بƒgƒCƒŒ‚à•¹گف‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB
| پ@”ھƒ–ٹxپi“ى”ھƒ–ٹx“Œ–تپj |
پ@‚»‚µ‚ؤ‚±‚ج’“ژشڈê‚©‚ç‚ج’–]‚ھ‚±‚؟‚çپB”ھƒ–ٹx‚ج“Œ–ت‚إ‚·پB‚à‚¤‚±‚ê‚إ‹A‚ء‚ؤ‚à‚¢‚¢‚‚ç‚¢‚جˆ³ٹھ‚ج•—Œi‚إ‚µ‚½پBچ،“ْ‚ح‰_ˆê‚آ‚ب‚¢گ°“V‚إ‚·‚ھپA‹Cˆ³”z’u‚ح“~Œ^‚إپA‹َ‹C‚ھژh‚·‚و‚¤‚ة—₽‚¢‚إ‚·پB‘ه‚«‚‘§‚ً‹z‚¤‚ئ”x‚ھ—₽‚‚ب‚é‚ج‚ھ•ھ‚©‚é‚‚ç‚¢‚ةپB
پ@’“ژشڈê‚ة‚ح‚±‚ٌ‚ب—§”h‚ب•Wژ¯‚àپBپu–ى•سژRچ‚Œ´ •½‘ٍ“»پv‚ئ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚±‚ج’“ژشڈêژ©‘ج‚ھٹدŒُ–¼ڈٹ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ٌ‚إ‚·‚ثپB
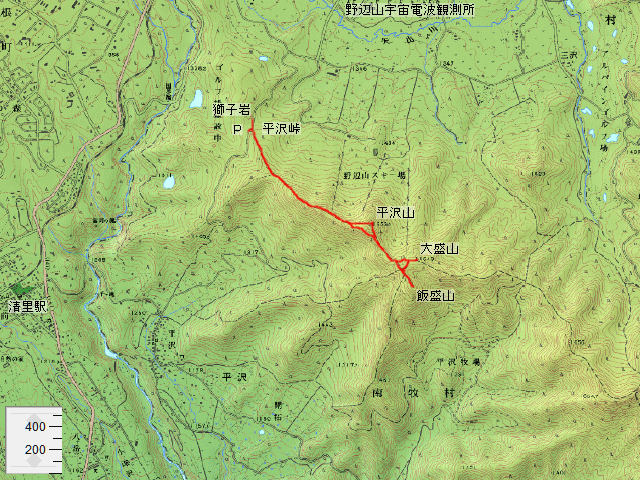 |
پ@Kashmir3D |
پ@چ،“ْ‚جƒ‹پ[ƒg‚حپAژ‚ژqٹâ’“ژشڈê‚ج“oژRŒû‚©‚ç‚ـ‚ء‚·‚®‚ة—إگü‚ً•à‚«پA”رگ·ژR‚جژR’¸‚ضپB‚»‚±‚إ’–]‚ًٹy‚µ‚ٌ‚¾Œم‰؛ژR‚ئ‚¢‚¤ƒVƒ“ƒvƒ‹‚ب‚à‚جپB“r’†‚ج•½‘ٍژR‚â‘هگ·ژR‚ح•œکH‚ة—§‚؟ٹٌ‚è‚ـ‚·پB
| پ@“€Œ‹ |
پ@ڈ€”ُ‘ج‘€‚ً‚µ‚ؤ‘•”ُ‚ًگ®‚¦پA‚³‚ؤڈo”‚ئ•à‚«ڈo‚µ‚½‚ئ‚±‚ëپA’“ژشڈê‚جƒtƒFƒ“ƒX‚ةپuژ‚ژqٹâپv‚ئ‚جٹإ”آ‚ھپB’“ژشڈê‚ج‚·‚®‰،‚ة‚ ‚é‚و‚¤‚ب‚ج‚إپA‚ئ‚è‚ ‚¦‚¸چs‚ء‚ؤ‚ف‚邱‚ئ‚ة‚µ‚ـ‚µ‚½پBƒtƒFƒ“ƒX‚ًڈo‚é‚ئ’n–ت‚ح“€‚ء‚ؤ‚¢‚ؤƒJƒ`ƒJƒ`‚إ‚µ‚½پB
| پ@ژ‚ژqٹâ |
پ@‚إپA‚·‚®‚ة‘ه‚«‚بٹâ‰ٍ‚ھ‹ڈ•ہ‚شڈêڈٹ‚ةپB‚±‚ج•س‚è‚ھژ‚ژqٹâ‚ج‚و‚¤‚ب‚ٌ‚إ‚·‚ھپA‹ï‘ج“I‚ة‚ا‚ج•”•ھ‚ھژ‚ژq‚ب‚ج‚©چ،‚ذ‚ئ‚آ”»‘R‚ئ‚µ‚ـ‚¹‚ٌپBچX‚ة‰œ‚ـ‚إ“¹‚ح‘±‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚ئ‚è‚ ‚¦‚¸ژ‚ژqٹâ‚ج’T‹پ‚ح‰؛ژRŒم‚ة‚·‚邱‚ئ‚ة‚µ‚ـ‚µ‚½پB
| پ@“oژRŒû |
پ@‚ ‚炽‚ك‚ؤƒXƒ^پ[ƒg‚إ‚·پBژچڈ‚ح‚P‚Oژ‚Q‚T•ھ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBƒNƒ}‚ح‚»‚ë‚»‚ë“~–°‚جƒVپ[ƒYƒ“‚إ‚·‚ھپAˆê‰ŒF—é‚ً•t‚¯‚ؤ•à‚«‚ـ‚·پB
| پ@ŒF—é |
پ@‚±‚جŒF—éپAگ^èJگ»‚إ‚©‚ب‚èچ‚‚¢‰¹‚إ–آ‚é‚ج‚إ‚·‚ھپA‚±‚ê‚ھƒNƒ}‚ھ”Fژ¯‚µ‚â‚·‚¢‰¹ˆو‚ئ‚ج‚±‚ئپB‚µ‚©‚à‚RکA‚إ•t‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‰¹—ت‚à‘ه‚«‚¢‚إ‚·پB‚ب‚ج‚إپA‘OŒم‚ةگl‚ھ‚¢‚é‚ئ‚«‚â‚·‚êˆل‚¤ژ‚ة‚حژè‚إˆ¬‚ء‚ؤ‰¹‚ھ–آ‚ç‚ب‚¢‚و‚¤‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBژg‚¢ژn‚ك‚ؤ‚Q‚O”N‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپAٹvگ»‚ج“y‘ن‚àٹـ‚ك‰َ‚ê‚é‹C”z‚·‚ç‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپBپiژتگ^‚ح‚R”N‘O‚ةژB‚ء‚½‚à‚جپj
پ@—t‚ً—ژ‚ئ‚µ‚½ڈ½‰z‚µ‚ة—zژث‚µ‚ھ“ح‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA“oژR“¹‚ح“€Œ‹‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB“oژRŒû‚ج•Wچ‚‚ح‚P‚S‚T‚Om‚ئ‚ج‚±‚ئ‚إپA‹َ‹C‚ح–j‚ً—₽‚ژhŒƒ‚µ‚ـ‚·پB
| پ@‘ڑ’Œ |
پ@‰H–ر•z’c‚ج’†گg‚©پH‚ئ‚¢‚¤‚‚ç‚¢گL‚ر‚½‘ڑ’ŒپB“¥‚ق‚ئƒVƒƒƒٹƒVƒƒƒٹ‚ئ‰¹‚ً—§‚ؤ‚ؤچس‚¯پA‹Cژ‚؟‚¢‚¢‚إ‚·پB
پ@‚µ‚خ‚ç‚•à‚¢‚ؤگU‚è•ش‚é‚ئپA”ھƒ–ٹx“Œک[‚ج‚ب‚¾‚ç‚©‚بƒ‰ƒCƒ“‚ھ–]‚ك‚ـ‚µ‚½پBژR’¸•”‚جچrپX‚µ‚¢ٹâ—ن‚ئ‚ح‘خڈئ“I‚إ‚·پBŒأ‚ج•¬‰خ‚ة‚و‚镬ڈo•¨‚ھچ~‚èگد‚à‚ء‚ؤ‚إ‚«‚½‚à‚ج‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·‚ھپA—Lژjˆب—ˆپA•¬‰خ‚ج‹Lک^‚حژc‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚¾‚»‚¤‚إ‚·پB‚»‚ê‚à‚»‚ج‚ح‚¸پA‚ئ‚ ‚镶Œ£‚ة‚و‚é‚ئپA”ھƒ–ٹx‚ج‰خژR‚ئ‚µ‚ؤ‚جٹˆ“®ٹْٹش‚ح–ٌ‚Q‚O‚O–œ”N‘O‚©‚ç–ٌ‚P–œ”N‘O‚ـ‚إ‚جٹش‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚؟‚ب‚ف‚ة‚±‚جٹˆ“®ٹْٹش‚ح“ْ–{‚ج‰خژR‚ج’†‚إ‚àچغ—§‚ء‚ؤ’·‚¢‚ج‚¾‚»‚¤‚إ‚·پB‚إ‚à‚ـ‚ؤ‚وپA‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ح‚»‚ج‚Q‚O‚O–œ”N‚جٹش‚ة‚حٹˆ“®‚ً‹x‚ٌ‚إ‚¢‚éٹْٹش‚ھ‚P–œ”N‚ً’´‚¦‚é‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚ح‚¨‚»‚炉½‰ٌ‚à‚ ‚ء‚½‚إ‚µ‚ه‚¤‚©‚çپA‚±‚ê‚©‚ç”ھƒ–ٹx‚ھٹˆ”‚ةٹˆ“®‚µژn‚ك‚邱‚ئ‚àڈ\•ھچl‚¦‚ç‚ê‚ـ‚·‚ثپB‹xŒeڈI‚ي‚èپI‚ء‚ؤٹ´‚¶‚إپB
| پ@‹{ژi‚ج‘ê•ھٹٍ |
پ@‚P‚Oژ‚S‚O•ھپA‹{ژi‚ج‘ê‚ض‚ج•ھٹٍ‚ھŒ»‚ê‚ـ‚µ‚½پBژ–‘O‚جƒٹƒTپ[ƒ`‚إ‚ح‹“‚ھ‚ء‚ؤ‚±‚ب‚©‚ء‚½’n–¼‚ب‚ج‚إپA‚ ‚炽‚ك‚ؤ’²‚ׂؤ‚ف‚é‚ئپA‚±‚±‚©‚ç–ٌ‚Vkm‚à‰؛‚ء‚½گو‚ة‚ ‚é‘ê‚ج‚و‚¤پB‚ا‚¤‚â‚ç‚»‚±‚ً“oژRŒû‚ئ‚µ‚½”رگ·ژR‚ض‚ج“oژR“¹‚ھ‚±‚±‚ـ‚إ‰„‚ر‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إپA‚±‚ج•Wژ¯‚ح‚»‚±‚ض‚ج‰؛ژRŒû‚ًژ¦‚·‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤ—‰ً‚µ‚½•û‚ھ—ا‚³‚»‚¤‚إ‚·پBٹشˆل‚ء‚ؤ‚؟‚ه‚ء‚ئ—§‚؟ٹٌ‚ء‚ؤ‚ف‚و‚¤‚ب‚ا‚ئ‰؛‚肾‚·‚ئ‚¦‚ç‚¢–ع‚ةچ‡‚¢‚ـ‚·پB
پ@“o‚èژn‚ك‚ؤ‚©‚炸‚ء‚ئ—إگü•à‚«‚إ‚·‚ھپA‚ز‚ء‚½‚è”ِچھ‹ط‚جگ^ڈم‚إ‚ح‚ب‚”÷–‚ة–k‘¤‚ة‚¸‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA—zژث‚µ‚حٹî–{–ط—§‰z‚µ‚إ‚·پB‚±‚ê‚ھ—إگü‚ج“ى‘¤‚ً’ت‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ—zژث‚µ‚ً‚½‚ء‚ص‚è—پ‚ر‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚ئژv‚¤‚ج‚إ‚·‚ھپB
| پ@–ى•سژRچ‚Œ´ |
پ@ژ‹ٹE‚ھٹJ‚¯‚ؤ‚¢‚éچ¶ژèپi–k‘¤پj‚ً–]‚ق‚ئپAچL‘ه‚بچ‚Œ´‚ھŒ©‰؛‚낹‚ـ‚µ‚½پB–ى•سژRچ‚Œ´‚إ‚·پB‚ق‚ق‚ءپH‰½‚©•د‚ي‚ء‚½چ\‘¢•¨‚ھپcپB‚»‚¤‚©پA‚±‚ê‚حچ‘—§“V•¶‘ن‚ج–ى•سژR“d”gٹد‘ھڈٹ‚إ‚·‚ثپB‘¶چف‚ح’m‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚±‚ٌ‚بٹJ‚¯‚ء‚ز‚ë‚°‚ب‚ئ‚±‚ë‚ة‚ ‚é‚ئ‚حپB
| پ@‰F’ˆ“d”gٹد‘ھڈٹ |
پ@‚إ‚ء‚©‚¢ƒpƒ‰ƒ{ƒ‰ƒAƒ“ƒeƒi‚إ‚·پB’²‚ׂؤ‚ف‚é‚ئپA‚±‚ê‚ح“d”g–]‰“‹¾پBƒpƒ‰ƒ{ƒ‰‚ج’¼Œa‚ح‚S‚Tm‚à‚ ‚é‚»‚¤‚إ‚·پB‰ًگà‚ً“ا‚ٌ‚إ‚à“‚·‚¬‚ؤ‰½‚ًٹد‘ھ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©‚و‚•ھ‚©‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB‰F’ˆ‚©‚ç—ˆ‚é“d”g‚©‚牽‚©‚ً’²‚ׂؤ‚¢‚é‚ٌ‚إ‚µ‚ه‚¤‚ثپA‚«‚ء‚ئپB
پ@“~Œح‚ê‚ج–ط—§‚؟پBچ،“ْ‚جگ°“V‚ح‘©‚جٹش‚ج‹x‘§‚إ‚µ‚ه‚¤‚ثپB
| پ@•½‘ٍژR |
پ@گ³–ت‚ة•½‘ٍژR‚ھŒ©‚¦‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB‚±‚جژR‚ة‚ح•œکH‚إ“o‚é‚ج‚إپA‚±‚جگو‚ج•ھٹٍ‚إ‰Eژè‚جٹھ‚«“¹‚ةگi‚ف‚ـ‚·پB
| پ@گَٹشژR‰“–] |
پ@—§‚؟ژ~‚ـ‚ء‚ؤڈ¬‹xژ~پB‘oٹل‹¾‚إچ¶ژè—y‚©‰“‚‚ة’ءچہ‚·‚éگَٹشژR‚ً’‚ك‚ـ‚µ‚½پBژR‰ٍ‰E’[‚ج‘نŒ`‚جژR‚ھگَٹشژRپB‚»‚جچ¶‚ھٹO—ضژR‚إپA‚ذ‚ئ‚«‚يگë‚ء‚½ƒsپ[ƒN‚ھچ•”ءژR‚إ‚·پBچX‚ةچ¶ژèپA‚½‚ب‚ر‚‰_‚ة‰B‚ê‚»‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھچ،”N‚VŒژ‚ة“o‚ء‚½کUƒm“oژR‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB‚±‚±‚©‚ç‚ج‹——£‚ح‚T‚Okm‚؟‚ه‚ء‚ئ‚ ‚è‚ـ‚·پB
| پ@ƒcƒ‹ƒEƒپƒ‚ƒhƒL |
پ@چ،‰ٌ‚ج–ىژR•à‚«پA‰ش‚حٹْ‘ز‚إ‚«‚ب‚¢‚ـ‚إ‚àژہ‚ب‚牽‚©‚ ‚é‚©‚à‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚±‚ê‚حƒcƒ‹ƒEƒپƒ‚ƒhƒL‚جژہ‚إ‚·‚ثپB‘N‚â‚©‚بƒIƒŒƒ“ƒWگF‚ھچD‚ـ‚êپAƒٹپ[ƒX‚ج‘fچق‚ب‚ا‚ةژg‚ي‚ꂽ‚肵‚ـ‚·پB
| پ@•½‘ٍژR•ھٹٍ |
پ@‚P‚Pژ‚؟‚ه‚¤‚اپA•½‘ٍژR‚ئ‚ج•ھٹٍ‚ة“’…‚µ‚ـ‚µ‚½پB’¼گi‚·‚é‚ئڈم‚èچâ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB‚±‚±‚ح‰Eژè‚ةگـ‚êپA—إگü‚ج‰E‘¤‚ةپi“ى‘¤پj‚ةڈo‚ـ‚·پB
| پ@“ى–ت‚ض |
پ@”ِچھ‚ً‰z‚¦‚é‚ئ‚±‚ج•—ŒiپB“ى–ت‚ة‚ب‚é‚ج‚إ—zژث‚µ‚½‚ء‚ص‚è‚إ‚·پBژتگ^چ¶ژè‚ةچ،“ْ‚ج–ع“I’nپA”رگ·ژR‚جƒsƒ‰ƒ~ƒ_ƒ‹‚بژp‚ھŒ©‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ثپB‚»‚µ‚ؤ‚»‚ج‰Eژ艜‚ج‰_‚جڈم‚ة•xژmژR‚جژp‚à–]‚ك‚ـ‚·پB
| پ@—ى•ô•xژm |
پ@•xژmژR‚ً–]‰“‚إپB‚ـ‚³‚ةپu—ى•ôپv‚ئŒؤ‚ش‚ة‚س‚³‚ي‚µ‚¢گ_پX‚µ‚³‚إ‚·پB
| پ@“ىƒAƒ‹ƒvƒX |
پ@•xژmژR‚©‚çژ‹گü‚ًچ¶‚ةˆع‚·‚ئ’·‘ه‚ب“ىƒAƒ‹ƒvƒXپBگ³ژ®‚ة‚حگشگخژR–¬‚إ‚·‚ثپB“ى–k–ٌ‚V‚Okm‚ة‚à‹y‚ش“ْ–{‚ً‘م•\‚·‚éژR–¬‚إپA•xژmژR‚ةژں‚®چ‚‚³‚ج–kٹx‚ًژn‚كپA‚X‚آ‚ج‚Rگç‚چ•ô‚ً•ّ‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚µ‚ؤچ،‚à”Nٹش‚Smmƒyپ[ƒX‚إ—²‹N‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚»‚¤‚إ‚·پBپiژتگ^‚ةƒ}ƒEƒXƒ|ƒCƒ“ƒ^‚ًڈو‚¹‚é‚ئژR–¼•\ژ¦پjپ@
| پ@ƒJƒ‰ƒ}ƒc |
پ@‚³‚ؤپAژR’¸‚ةŒü‚¯‚ؤ•à‚«ڈo‚µ‚ـ‚µ‚ه‚¤پB
پ@گآ‹َ‚ً”wŒi‚ةƒJƒ‰ƒ}ƒc‚ج‰©—t‚ھ‰f‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBگj—tژ÷‚إ‚ ‚è‚ب‚ھ‚ç—ژ—tژ÷‚ئ‚¢‚¤•د‚ي‚èژزپBٹ؟ژڑ‚إ‚حپu—ژ—tڈ¼پv‚ئڈ‘‚‚±‚ئ‚àپB
| پ@ƒ„ƒ}ƒcƒcƒWپH |
پ@‘N‚â‚©‚بچg—tپB—t‚جŒ`‚â•t‚«•û‚ج“ء’¥‚©‚烄ƒ}ƒcƒcƒW‚©ƒIƒIƒ„ƒ}ƒcƒcƒW‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئپB‰ش‚جژٹْ‚ب‚ç‹و•ت‚µ‚â‚·‚¢‚ج‚إ‚·‚ھپB
پ@‚µ‚خ‚ç‚چs‚‚ئ•½‘ٍژR‚©‚ç‰؛‚ء‚ؤ‚«‚½“¹‚ھچ¶‚©‚çچ‡—¬‚µ‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB•œکH‚إ‚ح‚±‚±‚©‚畽‘ٍژR‚ةŒü‚©‚¢‚ـ‚·پB
| پ@“~Œح‚ê‚ج–ى |
پ@–زڈ‹‚¾چ“ڈ‹‚¾‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚½‰ؤ‚àپA‚¢‚آ‚ـ‚إ‚à‰ؤ‚ج‚و‚¤‚¾‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚½ڈH‚à‚±‚جژٹْ‚ة‚ب‚é‚ئ‚â‚ء‚د‚艓‚´‚©‚ء‚ؤچs‚«پAچJ‚ة‚à“~‚ج‹C”z‚ًٹ´‚¶‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB•½’n‚إ‚»‚¤‚ب‚ج‚إپA•Wچ‚‚Pگç‚چ‚ً’´‚¦‚邱‚جچ‚’n‚إ‚ح‚à‚¤ٹ®‘S‚ة“~‚إ‚·پBچ،“ْ‚ح“V‹C‚ھ—ا‚¢‚ج‚إ‚ـ‚¾–¾‚é‚¢‹Cژ‚؟‚إ‚¢‚ç‚ê‚ـ‚·‚ھپA‚±‚ê‚ھ“V‹C‚ھˆ«‚©‚ء‚½‚è‚·‚é‚ئپA‰“‚¢ˆظچ‘‚جچr–ى‚ةژو‚èژc‚³‚ꂽ‚و‚¤‚بژ₵‚¢‹Cژ‚؟‚ة‚ب‚邱‚ئ•K’è‚إ‚·پB
| پ@•½‘ٍژR |
پ@گU‚è•ش‚é‚ئ•½‘ٍژR‚ھپB‚ ‚جچ¶‘¤‚ًٹھ‚¢‚ؤ‚±‚±‚ـ‚إ‚â‚ء‚ؤ—ˆ‚ـ‚µ‚½پB
| پ@’†‰›ƒAƒ‹ƒvƒX |
پ@‰Eژè‚ة“ىƒAƒ‹ƒvƒX‚ًŒ©‚ب‚ھ‚ç•à‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ئپA‚ٌ‚ٌ‚ءپH‚ ‚جژR‚ح‰½‚¾پHپ@“ىƒAƒ‹ƒvƒX‚ھ–k‚ةŒü‚©‚ء‚ؤچ‚“x‚ً‰؛‚°‚ؤ‚¢‚•س‚è‚ةپA–¾‚ç‚©‚ة‹——£ٹ´‚جˆل‚¤ژR•ہ‚ف‚ھŒ©‚¦‚ـ‚·پB‘oٹل‹¾‚إٹm”F‚µ‚ؤ‚ف‚é‚ئ“ء’¥“I‚ب—إگüپB‚»‚¤پA‚ ‚ê‚ح’†‰›ƒAƒ‹ƒvƒX‚ج–؟ژهپA–ط‘]‹îƒ–ٹx‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚·‚©پB‚±‚±‚©‚ç‚ج‹——£‚ح–ٌ‚U‚Okm‚ ‚ء‚ؤپA“ىƒAƒ‹ƒvƒX‚جŒ¨‰z‚µ‚ةٹç‚ً‚ج‚¼‚©‚¹‚ؤ‚¢‚éٹ´‚¶‚إ‚·‚ثپB’†‰›ƒAƒ‹ƒvƒX‚à“ْ–{‚ً‘م•\‚·‚é‘ه‚«‚بژR–¬‚إپAگ³ژ®‚ة‚ح–ط‘]ژR–¬‚إ‚·پB
| پ@“ى”ھƒ–ٹx |
پ@Œ¢کA‚ê‚ج“oژRژز‚ئ‚·‚êˆل‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚»‚جŒمپAگU‚è•ش‚ء‚ؤ‚ف‚é‚ئ‘ه‚«‚ب”ھƒ–ٹx‚ھ‚±‚؟‚ç‚ًŒ©‰؛‚낵‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBˆ³“|“I‚ب‘¶چفٹ´‚إ‚·پB
پ@ˆê”ت‚ة”ھƒ–ٹx‚ئ‚¢‚¤ڈêچ‡پA‰ؤ‘ٍ“»ˆب“ى‚ج“ى”ھƒ–ٹx‚ًژw‚·ڈêچ‡‚ئپA‚±‚ê‚ة“V‹çٹx‚â–k‰،ٹx‚ب‚ا‚ج–k”ھƒ–ٹx‚ًچ‡‚ي‚¹‚½ƒGƒٹƒA‚ًژw‚·ڈêچ‡پA‚³‚ç‚ة‚±‚ê‚ç‚ةنّ‰بژR‚ًٹـ‚ك‚½“ى–k‚R‚Okm‚ة‚ي‚½‚é”ھƒ–ٹxکA•ô‘S‘ج‚ًژw‚·ڈêچ‡‚ھ‚ ‚é‚و‚¤‚إ‚·پB‚±‚جژتگ^‚ةژت‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ح“ى”ھƒ–ٹx‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پBچإچ‚•ô‚حگشٹxپi‚Q‚W‚X‚X‚چپj‚إپA‘¼‚ة‰،ٹxپi‚Q‚W‚R‚O‚چپjپAˆ¢–ي‘ةٹxپi‚Q‚W‚O‚T‚چپjپA—°‰©ٹxپi‚Q‚V‚U‚O‚چپjپAŒ Œ»ٹxپi‚Q‚V‚P‚T‚چپj‚ب‚ا‚جƒsپ[ƒN‚ھکA‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚؟‚ب‚ف‚ة”ھƒ–ٹx‚ئ‚¢‚¤ƒsپ[ƒN‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB
| پ@‘هگ·ژRپiچ¶پj‚ئ”رگ·ژR |
پ@‚³‚ؤپAگiچs•ûŒü‚ةژ‹گü‚ً–ك‚·‚ئپA”رگ·ژR‚ح‚à‚¤‚·‚®‚»‚±‚إ‚·پB‹دگ®‚جژو‚ꂽژR‚إ‚·‚ثپB‚»‚جچ¶ژè‚ج‚ب‚¾‚ç‚©‚بژR‚ح‘هگ·ژRپB”رگ·‚ة‘هگ·‚ئ‚حپA–½–¼‚ة‰½‚â‚çH‚‚ھ‚ ‚è‚»‚¤‚إ‚·‚ثپB
پ@کH–T‚جƒTƒTپB“ْ‚ھ“–‚½‚ء‚ؤ‚¢‚éڈêڈٹ‚ب‚ج‚ة—t‚ة‰؛‚肽‘ڑ‚ھ—Z‚¯‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپBچ،“ْ‚ج‹C‰·‚ج’ل‚³‚ً•¨Œê‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ثپB
| پ@‘هگ·ژR•ھٹٍ |
پ@‘هگ·ژR‚ئ‚ج•ھٹٍ‚ـ‚إ‚â‚ء‚ؤ—ˆ‚ـ‚µ‚½پB‚±‚±‚ح‰Eژè‚ةŒü‚©‚¢‚ـ‚·پB
| پ@‚¢‚´”رگ·ژR‚ض |
پ@چإŒم‚جƒAƒvƒچپ[ƒ`‚جژè‘O‚حچL‚¢ڈêڈٹ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB•—‚â‰J‚ھ‹‚¢‚ئ‚«‚ب‚ا‚حگg‚ً‰B‚·‚ئ‚±‚ë‚à‚ب‚گh‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚ثپB
| پ@ژR’¸’¼‰؛ |
پ@‹}‚بچ⓹‚ً“o‚é‚ئ‚·‚®‚ةژR’¸‚إ‚·پB‚»‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚à–طˆê–{گ¶‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB•\“y‚ج—¬ڈo‚ً–h‚®‚½‚ك‚©پAگخ‘g‚ف‚â”آ‚ھ–„‚كچ‚ٌ‚إ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB
| پ@”رگ·ژRژR’¸ |
پ@‚»‚µ‚ؤ‚P‚Pژ‚Q‚T•ھپA”رگ·ژR‚جژR’¸‚ة“’…‚إ‚·پB‚R‚U‚O“x‚ج’–]‚ً“ئ‚èگè‚ك‚إ‚·پB
پ@‚ئ‚±‚ë‚إپA•Wژ¯‚ة‚ح‚P‚U‚S‚R‚چ‚ئ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپAچ‘“y’n—‰@‚ج‚Q–œ‚Tگç•ھ‚ج‚P‚ج’nŒ`گ}‚ة‚ح—ׂج‘هگ·ژR‚ھ‚P‚U‚S‚R‚چ‚ئ•\‹L‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ؤپA”رگ·ژR‚ة‚ح•Wچ‚‚ج•\‹L‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB‚ظ‚ع‚ظ‚ع“¯‚¶چ‚‚³‚ب‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB
پ@‚³‚ پA‚R‚U‚O“x‚ج’–]‚ًٹy‚µ‚ف‚ـ‚µ‚ه‚¤پBپiŒم•ز‚ة‘±‚پj
پ@
پ@