
経ヶ岳 〜前衛から丹沢の盟主を眺める〜
 |
【神奈川県 愛川町 平成26年6月1日(日)】
今日から6月。野山の緑もすっかり濃くなりました。このところ連日夏日を記録し、梅雨入り前の日差しはもう夏のそれと遜色のないくらいです。
引越し後のこまごまとした用事もようやく収まってきて、日々洗濯物を干したり植木に水をやったりしながら丹沢の山々を眺めるにつけ、野山に出かけたいゲージがジワジワと上昇してくるのを感じていました。 なので今回は自宅からも見える経ヶ岳(633m)へ行ってみることにしました。相模川の対岸にあって丹沢の前衛に位置する山で、ここならゆっくり登っても午後の早い時間に帰ってくることができそうです。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午前7時45分、橋本駅南口のバス乗り場から田名バスターミナル行きの神奈中バスに乗車。今日はバスを乗り継いで登山口近くまで行きます。橋下駅を出発するとしばらくして坂を下り始めました。バスの路線は相模川の河岸段丘を横断する形になるのです。一段下るとそこには広大な平地があり、のどかな住宅街が広がっていました。バスターミナルはこの段にあります。
| 田名バスターミナル |
田名バスターミナルは想像していたより広かったです(でも人影はまばら。)。そこで10分程度待ち合わせて、次に半原行きに乗車。バスはすぐにもう一段段丘を下りました。今度は長閑な田園風景です。
相模川の河原には早くも水遊びの人たちの車がたくさん停まっていました。相模川を渡ってから一旦段丘を登り、そして今度は並行して流れる中津川の流域に下って行きました。
川沿いにしばらく走り、田代というバス停で下車。ここからが歩きのスタートです。
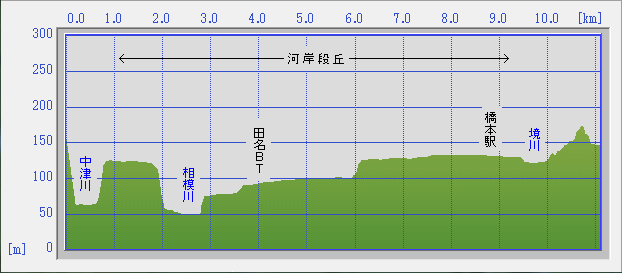 Kashmir 3D |
これが相模川の河岸段丘の断面図。相模川右岸の段丘面と橋本駅が乗っている段丘面とがほぼ同じ高さだということが分かります。相模川がこの段丘を削っている間、大きな地殻変動はなかったということでしょうね。
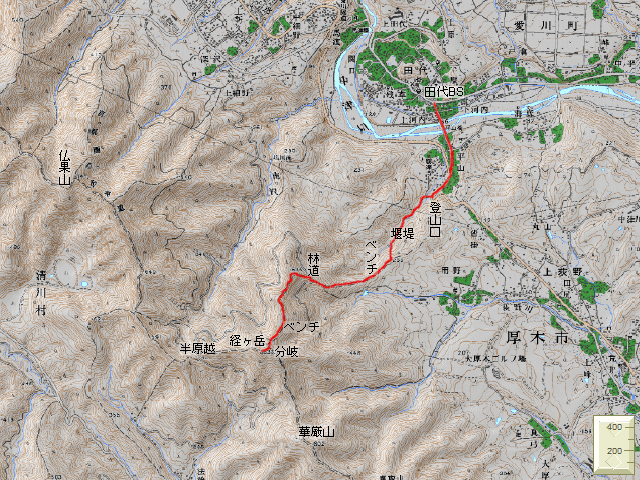 Kashmir 3D |
準備運動をして、午前9時ちょうどにスタートです。今日はここと経ヶ岳とをピストンするルート。 はじめは舗装路を歩いて登山口に向かいます。それにしても日差しが眩しく、登山口に到着するまでに消耗してしまいそうです。
| 平山大橋から |
歩き始めてすぐに中津川を渡りました。川岸には鮎釣りの人がずらっと並んで竿を出していました。そういうシーズンなんですね。その橋の上から今日登る山を展望。経ヶ岳は手前のピークに遮られて、ぎりぎり頂上部分が見えている感じ。お隣の仏果山も同様です。この位置からだと丹沢の盟主たちはこれら前衛の山々に遮られて見えないんですね。なるほど。
| |
道路は川べりから一段高いところを通っている国道412号線へと上っていきます。この道は厚木から津久井方面に抜ける近道になっていて、交通量も多いです。みんなビュンビュン飛ばしています。
| 登山口 |
しばらく車道を歩いて登山口にやってきました。夏のような日差しが暑いです。時刻は9時15分。これから奥の暗い森の中に入っていきます。
| |
歩き始めは沢沿いの草むした林道。路面はところどころぬかるんでいて、さっき登山口で見たヤマビル注意の看板が頭をよぎります。ヤマビルは喰いつかれても痛くないので気がつきにくいのだとか。唾液に血液を固まらせない成分が含まれていて、ダラダラと満腹になるまで(約1時間)吸い続けるのだそうです。嫌なやつです。
| ウツギ |
ウツギの花が咲いています。ちょうど花の時期なんでしょう。この先でもあちこちで見かけました。 ♪卯の花の匂う垣根に〜 「夏は来ぬ」好きな歌です。ところで卯の花の匂いってどんなんでしたっけ。
| |
近くでサンコウチョウが鳴いているんですが、立ち止まってねばってみても姿は見えませんでした。サンコウチョウは沢沿いの針葉樹林などによく営巣するのだそうです。
| テイカカズラ |
テイカカズラの花の盛りはまだこれから。蕾がたくさんスタンバっていますね。花弁はスクリューのようにねじれています。
| |
|||
| フサザクラ |
特徴的な葉をもつフサザクラ。といっても桜の仲間ではありません。花には花弁がなく、濃いピンク色をした雄しべの葯が10数本束ねたようにして垂れ下がる姿が、遠目に桜に見えたのかもしれません。花の時期はちょうど桜のそれと重なっています。右の写真は果実です。
旺盛に茂った植物の間を縫うようにして沢沿いの道を遡って行きます。
| ミツバウツギ |
おっ、この面白い形のものは。これはミツバウツギの果実ですね。折り紙で作る奴さんの袴の形によく似ています(折り紙なんてもう何年もやったことないなあ。)。ちなみに奴さんは上半身と下半身の二つのパーツからなっていて、両方とも途中までは折り方が同じなんですよね。どうでもいいか。
| 堰堤 |
しばらくするとコンクリート製の堰堤が現れました。右側の山肌に付けられた階段を上って下りてこれをパスして行きます。この後もう一つ堰堤がありました。
| 涸れ沢 |
二つ目の堰堤を過ぎてしばらく行くと、ちょっと広くなったところがあって、そこの涸れ沢を渡ると登山道は本格的に山の斜面にとりつきます。
| クワゴマダラヒトリ |
展開し始めたウバユリの葉の上に毛虫が。なかなか嫌悪感を湧き起こさせる姿をしています。これも生き残るための戦術でしょうか。帰ってから調べると、クワゴマダラヒトリという蛾の幼虫でした。明らかに成虫の方が小さいというのはどういうことなんだろう。
木漏れ日の差す森の中をゆっくりと登っていきます。ときどき止まって深呼吸を。ああ、こういうのびのびとした気分になれるのも野山歩きをやめられない理由の一つなんですよね。
| 支尾根へ |
しばらくすると支稜線に出ました。ここからはスギの林の中を行く道となり、周囲の雰囲気が変わります。
| オカタツナミソウ |
花のシーズンは過ぎたとはいえ登山道脇にはいろいろ面白いものが目につきます。これはオカタツナミソウ。シソの仲間で、こういった半日陰のようなところを好みます。タツナミソウは漢字では「立浪草」と書き、波頭が立っているような花の形をしているからこの名が付いたということです。
| マムシグサ |
マムシグサ。実が熟す前の緑色のときは瑞々しい印象を受けますが、これから果実が熟して赤くなるにつれだんだん毒々しくなっていきます。現に有毒なんですけど。
| 北方向 |
木立の間から初めて遠くが見渡せました。コンパスを出してみると方角的には真北になります。ということは高尾山とその周辺の山々でしょう。
しばらく行くと大きなヤマザクラが現れ、その根元にベンチがありました。ここで小休止です。
| 北東方向 |
ここからは北東の方角が見渡せました。ちょうど真下が登山口の辺りです。写真中央の丘が中津川と相模川を隔てている段丘で、その向こうに薄く白く広がっているのが相模原や橋本の街のある平坦な段丘になります。その遙か向こうには多摩丘陵が広がっているはずです(見えませんが。) 。
それにしても大きなヤマザクラです。根元から株立ちになっていてその一本一本が太いこと。なかなか風格があります。
ベンチに腰掛けて水分補給をし、ついでにあんパンで栄養補給もして、筋肉が硬くなる前に再び歩き始めました。
| ニガナ |
これはニガナ。舌状花の数が少ないので、なんだか涼しげな印象を受けます。
| オカタツナミソウ |
ここにもオカタツナミソウ。標高が高いところに咲いているものほど生き生きとしているようです。麓の方で見かけたのは、もう花の落ちているものもありました。
| 林道 |
傾斜が一段ときつくなり、ほぼ直登といった感じになってきて、そこを頑張って登り切ったら林道が現れました。林業用のものでしょう。
時刻は10時30分です。
舗装されたそこそこ立派な林道ですが、路面に小さな落石などが散乱していて、とても自分の車でここまで来ようとは思いません。辺りはしーんとしていて、当然車の気配などはありません。
| 左の小径へ |
林道を右手に30mほど行くと左側にまた山に入っていく入り口が現れます。ここを入ります。ここからまたひたすらの上りです。
| |
長い花茎の先端に何かの蕾が付いていました。なんだろう。葉はヤブレガサのものに似ています。キク科の植物でしょうか。
手入れされた植林地の中を登っていきます。斜面は結構急で、足を滑らせたらかなり下の方まで転がっていきそうです。
| |
これは鹿除けのフェンスに取り付けられたゲートですね。ただ、ゲートはあっても左右のフェンスがもうガタガタに傷んでいて、鹿も通り放題といった感じでした。
| ヤマジノホトトギス |
足下に斑点のある葉を見つけました。これはヤマジノホトトギスの葉。なんか涼しげでいいですね。
| |
主稜線に出てしばらく、尾根上にベンチが現れました。やれやれここでまた小休止です。水分補給をして休んでいると、一組の夫婦が登ってきました。「ヤマビルにやられていませんか?」と聞かれたので、一応ズボンの裾をたくし上げて確認してみましたが、特にやられてはいませんでした。どうやら奥さんの方がヒルにとりつかれて、すんでのところで血を吸われるところだったのだとか。丹沢はヤマビルの被害が多いんですよね。血を吸ったらその後卵を産んで繁殖するらしいので、行政も血を吸ったヤマビルを引き剥がしたら放置せずに必ず殺すように指導しているそうです。でも、生命力が強そうなので、半分にぶった切っても平気で生きていそうな感じですね。
| 分岐 |
休憩を終えて歩き出すと、ちょっときつめの上りがあって、それを登りきると華厳山方面への分岐が現れました。ここは直進。ここまで来れば山頂は目と鼻の先です。
| |
すぐに山頂らしきところが見えてきました。
| 経ヶ岳山頂 |
11時10分、経ヶ岳の山頂に到着しました。ベンチとテーブルが2セットあり、さっきの夫婦も休憩しています。それほど広くはありませんが、木立の中でも休憩できそうなところはいくらでもあります。 一つベンチが空いているのでそこで昼食です。直射日光が暑く、木陰に腰を下ろした方が良かったかも。
| |
経ヶ岳の名の由来は、ここの山頂直下に弘法大師が経文を書いたという大きな板状の岩があることによるもの。登ってきた方とは反対側の稜線上にあるらしいのですが、yamanekoは見に行かなかったです(今思えば見ておけば良かったと軽く後悔。)。
| 南西方向 |
山頂は木立に囲まれていましたが、西側の眺望は開けていて、表丹沢の主稜線が一望にできました。
| ヤマザクラ |
昼食後、山頂広場を観察。これはヤマザクラの実でしょうか。
| |
さっきの夫婦も町田からやってきたとのこと。これから仏果山の方へ縦走するといって出発していきました。 さて、yamanekoも下山開始です。来た道を戻ります。前回の御正体山のときは下山時に何時もの膝痛(腸脛靭帯炎)に苦しみましたが、今回はそうならないよう細心の注意を払って下っていきます。
| 林道へ |
ひたすら下って林道に合流。11時55分です。
| クサイチゴ |
これはクサイチゴの実ですね。瑞々しいです。
| 登山口に帰還 |
12時35分、登山口まで下りてきました。幸い膝に痛みもなく、無事に下山することができました。ズボンの裾をたくし上げてヤマビルに食いつかれていないかチェック。大丈夫のようでした。
ここからまだ車道歩きが待っています。炎天下と言っていいくらいの陽射しの下を田代のバス停まで歩きます。アスファルトの照り返しが厳しいです。
そして、なんと間の悪いことか、バス停まであと50mというところでバスが行ってしまいました。時刻表を見てみると次の便は30分後です。ががーん。
でも、まあ、待っていればバスは来るもので、きちんと30分後にやってきました。さすがどんな田舎に行っても公共交通機関は時間に正確です。
帰りのバスの中ではウトウト、というか船を漕ぎまくり。でも、乗り過ごすことなく無事に橋本駅まで帰り着きました。
| ニュー甲州 |
バス停まで帰る途中に見かけた民家のような旅館。そのネーミングにグッとくるものがありました(現役で営業しているようでした。)。