
仏果山 〜低山の紅葉を楽しむ〜
 |
【神奈川県 愛川町 平成23年11月13日(日)】
ここ1箇月ほど週末になると雨模様になっていましたが、ようやく晴天の休日がやってきました。そうなると出かけたい虫が騒ぎ出します。でも気がつくと11月も半ば。山ではもう紅葉も終わりかけでしょう。いや、まだ間に合うか! この時期だとすると関東平野の辺縁部ならまだOKかもしれません。
ということで、神奈川県は丹沢山塊の前衛に位置する仏果山に行ってみることにしました。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午前8時13分発の小田急線に乗り、新宿から神奈川県の中央部、厚木市に向かいます。多摩川を越えて神奈川県に入るとやがて電車は多摩丘陵に分け入り、里山と住宅地が入り交じった風景の中を走ります。町田を過ぎると相模川の河岸段丘地帯に入って一気に見晴らしが良くなります。下車するのは本厚木駅。一つ手前に厚木駅という駅がありますが、なぜかこれはお隣の海老名市にあって(別に海老名駅もちゃんとある。)、厚木市のメインステーションは本厚木駅になります。わざわざ「本」と付けているあたりがなんか曰くがありげです。
本厚木駅には9時3分着。西口のバス乗り場から愛川町半原行きのカナチューに乗って、国道412号をのんびりと40分走ります。終点近くの野外センター前バス停で下りると、そこから「ふれあいの村」を目指します。
| 愛川ふれあいの村 |
バス停から山手に向かって5分ほど舗装道路を登ると、なだらかな斜面に「愛川ふれあいの村」はあります。この施設は県立の野外学習センター。ちょうどこの日は「紅葉まつり」という大規模なイベントが行われていて、賑やかな音楽とかが聞こえてきていました。マイカーで登山に来た人は、事前に連絡すればここに駐車できるようです。
| 登山口 |
野外学習センターの脇の道を更に登っていくと、宮ヶ瀬ダムに向かう大きな道路に行き当たり、その道をくぐると登山口が現れます。バス停からこの登山口までの標高差は100m。結構エネルギーを使いました。とりあえずあんパンで腹ごしらえをしてから登山開始です。
| |
10時30分、スタート。いきなり山肌をジグザグに上り、尾根筋を目指します。今日は気温が高いので日陰でも寒く感じません。
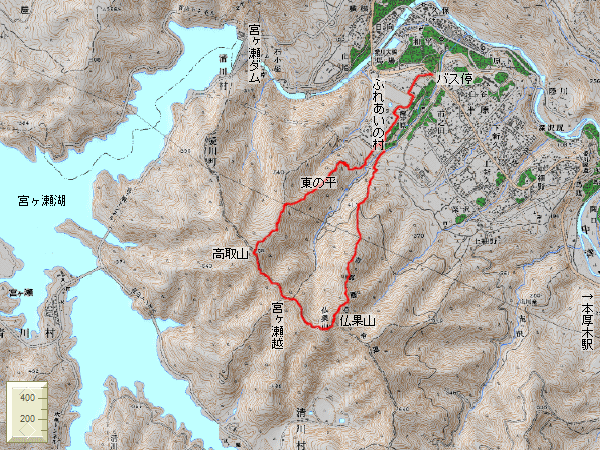 Kashmir 3D |
今日のルートは、この尾根筋を登ってまず高取山を踏み、そこから稜線を南下して仏果山へ。還りは往きの1本東側の稜線を下り、元のふれあいの村に戻ってくるというものです。
| オオバイノモトソウ |
それにしても色の少ない季節になりました。これはオオバイノモトソウ。普段は地味なシダですが、朝日を透かして羽片が輝いています。
| |
スギの植林地は暗く、晩秋ということもあって花の姿はありませんでした。地面もしっとりと湿っています。
黙々と登っていくとこの時期でも結構汗をかきます。なので、1枚、また1枚と脱いで体温調節をします。
| |
10時50分、開けた場所に出ました。ここで林道を横切るようです。
| ヤクシソウ |
林道から上は明るい尾根道になっていました。そうなると秋の残り花がちらほらと。このキクはヤクシソウです。里の道ばたなど明るいところで見かける花です。
| 東の平 |
10時55分、「東の平」という少し開けたところに出ました。ちょっとした休憩スポットです。
| ノハラアザミ | コウヤボウキ |
キク科2種。これらも日当たりの良いやや乾いたところを好む植物です。さっきのヤクシソウといい、やっぱり秋はキク科の花が目立っていますね。
| コナラ |
この辺りの山は昔から里の人々と深い関わりを持ってきたのでしょう。コナラの根元には過去に何度も伐採された痕跡がありました。人々は山からの恵みが絶えないように上手に利用してきたんでしょうね。
| |
そのコナラの葉。傷み具合が絶妙でいい味を出しています。
| |
こちらはヤマザクラ。何色と表現すればよいのか。真紅にならない紅葉というのもいいものです。
| ヤマザクラ |
この葉が育ったヤマザクラの木がこちら。あらかた葉を落としています。冬への備えですね。ずいぶんと齢を重ねてきたように見えるこのヤマザクラ。これまで幾年も幾年もこの木の下を通り過ぎる人々に、満開の花を、一面の落ち葉を、ただ静かに見せてきたのでしょうね。街の桜とは違ってヤマザクラにはそんな木訥とした生き様を感じます。
| |
山道は明るい森の中を行きます。下草が刈られ、よく手入れされている森です。明るくて、歩いていても気持ちがいい。
| |
かと思えば、ときどき真っ暗なスギの植林地の中を通ったり。空気のしっとり感や聞こえてくる音など、この環境の違いを感じてみるのも興味深いです。
| |
頭上が開けてきました。山頂が近いのか?
| クマノミズキ |
足下に珊瑚のような小枝が。クマノミズキの花序です。この黒い実は鳥たちの大好物。花序の枝が赤いのもよく目立って鳥たちにアピールしているのだそうです。それにしてもまだ実が付いたまま花序を落としてしまっては、せっかくの戦略が台無しなのでは。
| 高取山 |
11時35分、高取山(705m)の山頂に到着しました。登山口から1時間あまりです。何グループかが休憩したり、早めの昼食をとっていたりしました。山頂には展望塔があって、上まで登れば360度の展望のようですが、仏果山の山頂にも展望塔があるあらしいので、そこまで楽しみにとっておくことにしました。
| 東方向 |
山頂からの眺めはこんな感じ。東方向の展望が広がっていました。ふもとには今朝バスを降りた愛川町半原地区の街並みが見えます。ここは昔から撚糸を産業としてきた街なのだそうです。「撚糸」とは文字どおり糸を撚ることだと思いますが、撚糸の行程だけで一つの産業になるというのですから、様々なバリエーションとか技術とかあって、多様なニーズもあったのでしょうね。今はどうなのか分かりませんが。
遠くに広がる平坦なところは、相模川が堆積させた平地です。霞んでいて見えませんがその先は横浜です。この風景を見ると、ここが関東平野の辺縁部であることがよく分かります。
| 仏果山へ |
高取山では腰を下ろすことなく、そのまま仏果山へ向かいます。木立の向こうにその仏果山が見えてきました。こうして見るとまだずいぶん距離がありそうですね。
| |
高取山から仏果山までは細い尾根の道。明るく風通しも良く、乾燥した環境です。
| マルバウツギ |
頭上にペルシャ絨毯が覆い被さっているような状況。これはマルバウツギですね。
| 仏果山 |
高取山山頂から20分。おお、仏果山の山頂がすぐそこに。これから右手の稜線を回り込んで山頂を目指します。
| |
山頂の直下に張られてるロープ。使わなくても登れます。
| 仏果山山頂 |
12時10分、仏果山(747m)の山頂に到着しました。疎林の中に木製ベンチがあちこち配置されていて、いい雰囲気です。眺望はありませんが、鉄骨の立派な展望塔があって、そこに登れば展望を楽しめます。早速登ってみましょう。
| 南東方向 |
展望塔の高さは15mほど。ちょうど木立の上に顔を出せるような高さです。
南東方向には経ヶ岳へと続く尾根がどどーんと。左手奥の白い街並みは相模川の河川敷に広がっている工業団地か。
| 北方向 |
北の方向には手前に高取山。その向こうに隠れて宮ヶ瀬ダムがあるはずです。奥の白い雲の下あたりにミシュラン3つ星の高尾山が。ちょうど今日は妻が会社の仲間と登っているはずです(帰宅後に聞いたところ、高尾山は凄まじい人出だったそうです。)。
| 西方向 |
西には眼下に宮ヶ瀬湖が。その奥には丹沢の分厚い山塊です。ちょんと飛び出たピークは蛭ヶ岳です。宮ヶ瀬ダムは計画から30年を経て平成12年に完成した多目的ダムで、奥利根の奈良俣ダムなどと肩を並べる関東屈指の大きさを誇る巨大ダムなのだそうです。
| |
ひとしきり眺望を楽しんだ後、展望塔を下りてきました。ベンチに腰を下ろし、昼食とすることにしました。今日はカップラーメンとおにぎりです。木立をくぐって差し込む日射しが暖かい。ラーメンの出来上がりを待つ間にも穏やかな気持ちになれます。
ところで「仏果山」とななにやら曰くありげな名前ですが、調べてみるとどうやらお坊さんの名前のようです。室町時代にこの山のふもとにお寺を開いた仏果禅師という人がいたそうで、そのお坊さんが座禅修行したのが今の仏果山だということです。
| |
こんな侘び寂な紅葉を見ながらの昼食(ただしカップラーメン)、日本に生まれて良かったと思います、ほんと。
| |
名前は忘れましたが皮ごと食べられるブドウ。やや固めの食感も新鮮です。
| |
山頂で30分ばかり休憩して下山にかかりました。登山道の周りの植生は上りにとった登山道のそれと基本的に同じです。
| クロモジ |
森の入口とかあまり明るすぎないところを好むクロモジ。こういう黄葉もシックでいいですね。
| 高取山 |
谷をはさんだ向こう側に高取山が見えました。ここから見える稜線は今日歩いてきた道です。
| ダンコウバイ |
ダンコウバイの葉はもういつ落ちてもおかしくない状況ですが、冬芽はちゃんと準備ができているようです。
| |
1時25分、ふれあいの村近くまで下りてきました。一人での山歩きではつい黙々と歩いてしまいがちで、今回の下りは40分あまりでした。もっとゆっくりと歩いても良かったのではと少し反省。
それにしても今日は暖かい一日でした。小春日和というより「小夏日和」と言ってもいいくらいだったかも。さて、ここから車道を歩いてバス停に向かいます。本厚木に向かうバスはジャスト1時間に1本。バス停に着いてみると次のバスまで50分もありました。ついてないと思いつつ、こんなことは日常ではないことだし、のんびりとバスを待つのもいいかと思い直しました。
暑い暑いと言っていた季節もいつの間にか過ぎ去って、ふとした折りに冬の訪れを意識するようになりました。今年もあと1箇月半。でも、まだまだ野山に出かけたいと思います。