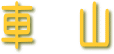
車山 ~やっぱり高原は涼しかった(前編)~
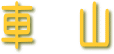 |
(前編) |
【長野県 諏訪市 令和7年8月24日(日)】
エアコンが過労死しそうな猛暑が続いています。時たまゲリラ豪雨が降ったりするもの、連日ギラギラの太陽光線が容赦なく降り注いでいます。これはもう熱帯の気候なのでは。日本が赤道上に移動したか、地球の地軸が傾いたとしか考えようがありません。
先月、涼しさを求めて湯沢高原に行って期待を裏切られたので、今回こそは涼しいところで野山歩きをしたいと考えました。そして思いついたのが長野県の車山(1925m)。霧ヶ峰の主峰で、山頂近くまで車で上がれるので、体力低下気味のyamanekoにぴったりの場所です。片道3時間。夕方に予約を入れている散髪にも間に合いそうです。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午前6時15分、ドリーム号Ⅲで出発。八王子JCTで若干流れが滞ったものの、そこからは大きな渋滞もなく中央道をひた走りました。諏訪ICで一般道に下りて、県道40号で霧ヶ峰高原まで一気に上ります。そしてスタートから約3時間後の午前9時、今日の野山歩きの起点となる車山肩駐車場に到着しました。車山の山頂を人の頭とすると、まさにその肩辺りに当たる場所です。
| 有料駐車場 |
この時間で既に駐車場は満車。駐車を諦めて走り去る車もあります。遅かったかと舌打ちをしつつ周囲をよく見てみると、道の反対側に有料駐車場があり、そちらは結構空いているようです。迷わずそちらに車を入れました。yamanekoが入ろうとしていたのは無料駐車場だったようです。有料駐車場の料金は「1日1000円」。無料の方は駐車をあきらめる車がいるほど混んでいて、こちらが空いているというのは、つまりここ(車山肩)を訪れる人の多くはちょっと立ち寄って風景などを楽しむのみということなのでしょう。一方、長時間駐車しているのは登山やハイキングなんでしょうね。
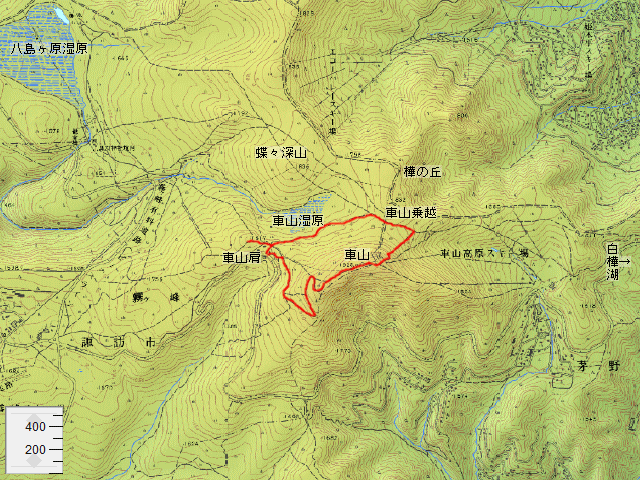 |
Kashmir3D |
今日のコースは、車山肩から草原状の山腹を登って車山山頂へ。そこから反対側(白樺湖方面)に下って、途中車山乗越から車山湿原に入ります。車山湿原は、周囲を車山肩、車山、樺の丘、蝶々深山に囲まれていて、その窪みにできた湿原です。湿原の南西斜面を上がると車山肩に戻ってきます。
| スタート |
ストレッチをして、装備を整え、9時15分、車山山頂に向けてスタートしました。標高差は120mあまりです。
小石が転がる道を歩いていきます。車山の上空にのみ黒雲があって、それ以外は夏の青空。涼しくてありがたいのですが、なんか変な感じです。そう、涼しいんです! 風が吹いたりすると更に。やっぱり標高2千m近いと下界とは違うんですね。
| ヤマハハコ |
最初に出迎えてくれたのはヤマハハコ。小さな頭花がボール状に寄り集まっています。これから開花を迎える状態ですね。名前は母子草の山地バージョンということでしょう。ハハコグサとは別の属に分類されていますが。
| オノエイタドリ |
オノエイタドリ。イタドリの仲間で、山地に生え、全体に小ぶりです。市街地や里山でのイタドリはまるで樹木のようになるものもありますが、このオノエイタドリは華奢です。
| ヤマノコギリソウ |
多摩丘陵では見かけることのない花が次々に出てきて、ワクワクします。これはヤマノコギリソウ。葉が鋸みたいです。先ほどのヤマハハコもそうですが、秋が近いからかキク科の花が目に留まります。
| ミヤマアキノキリンソウ |
こちらもキク科のミヤマアキノキリンソウ。名前にもう「秋」の字が入っています。
| ハクサンフウロ |
ハクサンフウロはフウロソウ科。ハクサンは北陸の霊峰白山のことです。じゃあフウロって何だろう。漢字では「風露」と書くようですが。なんだか雅な感じです。風呂とは関係ないですよね。
| ノアザミ |
おおここにもキク科。ノアザミです。夏前から咲き始めるノアザミの花期はもうそろそろ終わりです。
| ウスユキソウ |
これはウスユキソウですね。本当に薄く雪をまとったような姿をしています。頭花は花茎の先端に数個が集まって付きますが、写真のものはまだ未熟のようです。おっと、これもキク科です。
多士済々なキク科。ちなみにここまでに見たヤマハハコ(ヤマハハコ属)、ヤマノコギリソウ(ノコギリソウ属)、ミヤマアキノキリンソウ(アキノキリンソウ属)、ノアザミ(アザミ属)、ウスユキソウ(ウスユキソウ属)は、すべて違う属でした。キク科は最も種類の多い双子葉植物だそうで、国内のキク科植物は約70の属に分かれているそうです。キク科軍団というか一大派閥ですね。
| オトギリソウ |
これはオトギリソウか。この仲間の写真を撮るときは、花冠のアップの他に葉の裏表もアップで撮ります。種の見極めに花弁や葉の表面にある線や点が決め手になることが多いからです。シナノオトギリとかオクヤマオトギリとか似たものが多いのです。
| ハナイカリ |
むむ、これは見かけない花です。調べてみるとハナイカリだそう。花冠が深く4裂していて、それぞれの裂片の下の方が角のような距になっています。一見してイカリソウの仲間かなと思いましたが、イカリソウはメギ科。ハナイカリはリンドウ科だそうです。
| 霧ヶ峰 |
西南西の方角。こののっぺりとした地形が霧ヶ峰の頂上部。標高は概ね1700m前後です。霧ヶ峰は台地状の火山で、最高峰は今登りつつある車山。霧ヶ峰というピークはないです。ただ、地理院地図をはじめyamanekoの持っているいくつかの地図でも写真正面奥の樹林帯あたりに「霧ヶ峰」の表記がされています。何か理由があるのでしょうか。
こぶし大の石にときどきズリッとなりながら登っていきます。左右の植物などをきょろきょろと探しながらなので、どうしても足元がおろそかに。怪我には注意ですね。。
9時45分、登山道がナイフの刃先のように突き出したところまでやって来ました。展望が利く場所で、ベンチが整備されていました。yamanekoは歩き始めてまだ30分なので、ここはスルーして進みます。
| ウメバチソウ |
高原の花、ウメバチソウ。明るい草原が似合う花です。とはいえ湿ったところも嫌いなわけではなく、尾瀬ヶ原などでもよく見かけます。
吹き渡る風が涼しいこと。なんとかこの風を家まで持って帰ることができないものか。
| ヤマハハコ |
おっ、このヤマハハコは頭花が開いていますね。白く細かな花弁状のものは総苞片で、中心の黄色い部分が筒状花の集まりです。いずれもごくごく小さいです。
| マツムシソウ |
これはマツムシソウ。たくさんの花が寄り集まっていて、外側から咲いていきます。外側をぐるっと取り囲む花はそれぞれ花冠が5裂していて、その中でも一番外側のものが舌状に大きくなっています。中央に盛り上がるように集まっている花はみな筒状花です。これはまだ咲いていませんね。こういう風にたくさんの花が集まって全体として一つの花のように見えているのが不思議です。
| カシガリ山 |
南側の風景。遠く雲を頂いているのは八ヶ岳連峰です。その西麓の低地を挟んでここ霧ヶ峰があります。手前に見えているのはカシガリ山(1617m)。霧ヶ峰の山頂台地が南側に張り出した突端に当たります。
こういう道を見ると車山が火山であることをあらためて知らされます。
なんとなくハイジとペーターが出てきそう。
| タチコゴメグサ |
なんかアートみたいな花。タチコゴメグサ。花茎が立ち上がっているコゴメグサ(小米草)という名前ですね。多摩丘陵では見かけない花です。
| 霧ヶ峰ポイント |
振り返ると徐々に高度が上がってきているのが分かります。あのポツンとある樹林辺りが「霧ヶ峰」ポイントです。
| オトギリソウ |
岩の隙間からオトギリソウが。名前の「弟切草」は、平安時代の物語から。この花から作る秘伝の薬の製法を漏らした弟を、鷹匠をしている兄が斬り殺したという話です。その秘薬は鷹の傷を治す家伝のものだったとか。花弁や葉にある点はその時に飛び散った血の跡とのことです。
| ミヤマアキノキリンソウ |
ササ原から顔を出すミヤマアキノキリンソウ。姿勢が良いです。
写真右側に車山肩の駐車場が見えています。あそこから歩いてきました。
こうやって広い範囲を眺めてみると、山頂部の概ね真ん中あたりに「霧ヶ峰」ポイントがあることが分かります。そういうことか。
| グライダー |
頭上から「シュー」という音が聞こえてきました。見上げると大きなグライダーが旋回していました。「霧ヶ峰」ポイントの奥の一段下がったところにグライダーの滑空路があるので、そこから飛び立ったものでしょう。気持ちよさそうです。
| ダンジョン? |
おお、荒野の行く手にダンジョンが。いや、RPGのセーブポイント感満点ですが、あれは山頂にある気象レーダー観測所です。
| ウスユキソウ |
ウスユキソウ。こちらの頭花は既に花期を終えているようです。
山頂が近づいてきました。たくさんの人で賑わっているようです。
山頂手前から見た南方向。中央のチョンと飛び出たピークはカシガリ山です。その向こうには八ヶ岳西麓の大扇状地が広がっています。胸のすくような風景ですね。早起きして、長距離を運転して、ここまで登ってきて良かった。
| 車山気象レーダー観測所 |
10時20分、車山の山頂に到着しました。気象レーダー、でかいです。放射した電波の跳ね返りを観測するドップラーレーダーで、球体の中ではパラボラアンテナが回転しているそうです。
| 山頂標識 |
山頂の標識には「八ヶ岳中信高原国定公園 車山山頂 標高1,295米」とありました。なんだか軽装の女性もいますが、実は白樺湖側(yamanekoが登ってきたルートの反対側)から山頂直下までリフトで上がってくることができるのです。つまり山頂にいた人の多くはリフトで上がってきた人たちだったんですね。
レーダーの向こう側はこんな感じ。ん?鳥居が見えますね。
| 車山神社 |
鳥居をくぐると4本の御柱が建っていて、その中央に祠がありました。参拝の列ができています。
| 祠 |
ここは車山神社。苔むした石造りの祠ですが、創建は昭和初期だそうです。スキー場整備の際に麓に建立され、その後車山開発に合わせてこの場に遷宮されたのだそうです。そういう経緯の神社もあるんですね。yamanekoはこの山で楽しませてもらっていることへのお礼と、無事に帰宅できることをお願いしておきました。
さて、下山はリフトのある方に向かいます。(後編に続く)