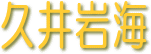
久井岩海 〜海岩に潜む悪魔の一撃〜
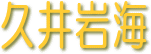 |
【広島県久井町 平成15年7月13日(日)】
梅雨まっただ中の7月定例観察会。今回は広島県御調郡久井町(くいちょう)にある「久井岩海」をステージとして、その成因や周辺環境などについて考えてみようという企画です。
| 久井岩海 |
「岩海」とは見てのとおり、大きな岩が累々と重なりまるで氷河のように山腹を覆っている地形のところをいいます。
ただ、氷河と異なるのは、これらの岩が山の上の方から流れ転がって来たものではないという点です。
もともとこの場所にあった大きな基盤岩石(久井岩海の場合は花崗閃緑岩=閃緑岩の成分を多く含んだ花崗岩)がその節理にそって割れていき、その過程で出た小さな破片が水に流されたことによって大きめな岩だけが残ってできたものなのです。
花崗岩の節理は方状なので、豆腐を賽の目に切るような、あるいはルービックキューブのような状態で割れていくのだそうです。花崗岩は地中深くでマグマがゆっくりと冷えて固まってできたもの。節理とは岩石が冷えて体積が小さくなる過程でできる割れ目のことです。
この花崗岩の節理が造った特徴のある地形が広島県西部の広範囲に広がっています。→こちらを参照
| 開会 |
午前10時、岩海手前の駐車場に集合。雨の中のスタートです。
雨足は決して弱くはありませんが、月に一度の観察会、みんな目を輝かせてレクチャーに聴き入っています。
そして雨の中、岩海に向かいます。
サイコロ状に割れた岩は、その角から風化していき少しずつ丸みを帯びてきます。
中にはまるで皮をむくように割れていくものもあり、タマネギ状風化とも呼ばれています。
| タマネギ状風化 (下見時) |
岩海は雨に濡れ滑りやすくなっています。
おやっ、岩の間には白いツユクサが。ここはひとつ写真でも… 不安定な岩の斜面にしゃがんで…
と、そのときです。 ビッキーン!
…来ました。2年ぶりのぎっくり腰です。
《観察会の途中でしたが、やむなく離脱となりました。》
集団と離れて、ひとり脂汗を流しながら丘を下るyamaneko … しばらく静養です。