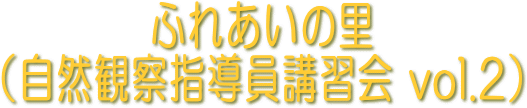
ふれあいの里(県立青年の家) 〜NACS−J指導員講習会2〜
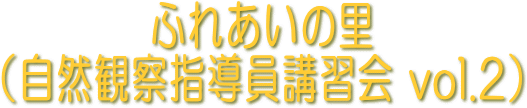 |
【広島県御調町 平成14年9月15日(日)】
指導員講習会2日目です。
明け方までの蒸し暑さと、同室の方が奏でる5.1サラウンドのイビキのおかげで完全な寝不足状態です。にもかかわらず、やさしいスタッフ仲間からの容赦ないモーニングコールで早朝観察に出かけました。
うぅ、眠い…
朝食後、たまたま出会った受講者2人とプチ観察会をしてみました。3年前の講習会での実習を思い出しながら。
近くにあった湿地の様子とその周囲の植物(特にサワギキョウ)をテーマにしてやってみたんですが、はたしてうまく伝わったでしょうか。その後、某スタッフ所有のキャンピングカーの中でモーニングコーヒーをごちそうになって、スッキリと目が覚めました。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
今日も日中は野外実習です。
午前中は地元講師陣の登場。テーマは「地域の自然を理解しよう」です。
3つのグループに分かれて、動物、地質・地形、植物の各講師の元をローテーションしながら実地で勉強していきます。
| 大丸講師のネイチャーゲーム |
yamanekoが同行したグループは、まず動物担当の大丸さんの元でレクチャーを受けました。
ここの森は開発の手が入ってはいるものの、まだまだ昔ながらの里山の様相を色濃く残しています。哺乳動物にこそ出会いませんでしたが(人間を除いて)、多くの鳥や昆虫の生態を観察することができました。
ネイチャーゲーム中に、偶然、スズメバチが自分の体の2倍はありそうなキリギリスを捕らえて飛んでいるところに遭遇して、みなさん「オォー」って感じでした。講師もタイミングを逃さずスズメバチの話。
実際の観察会ではこういったハプニングも大事にすることが大切なのです。
| 片山講師のレクチャー |
次は地質・地形担当の片山講師のところです。
広島県の地形の特徴は3段構造の隆起準平原(→02.8.25「山野峡」参照)です。
それを遠景の山並みを見ながら分かりやすく解説していただきました。ちなみに遠くに見える山々の山頂部の連なりで構成する面(標高400m〜600m前後)を「中位面」、または「吉備高原面」ともいいます。
地質の特徴としては花崗岩の占める割合が大きく、これが風化してできた比較的粒子の大きい土を「マサ土」と呼んで主に園芸などに用いることで有名です(たしか)。
| 加藤講師の得意技 「カレンダー再生フリップ」 |
最後は植物担当の加藤講師です。
西日本の平野部(御調町周辺のような丘陵部も含めて)では、人間が定住する以前の自然植生はシイやカシなどの常緑広葉樹林だったと考えられています。やがて人間が定住し森を利用することによってコナラやアカマツの2次林に遷り変わっていったのだそうです。今では点在する寺社林が大昔の森の姿をとどめているのみです。
これは人間が主に薪炭材の供給地として森に手を加え続けてきた結果で、こういった環境の場所には様々な生物が住むことができ、安定した生態系を維持してきました。自然のなるがままに任せることも大切ですが、こういった場所の多様な生物を保護するためには、定期的に人間が手を加えることが必要な場合もあるのだそうです。フム、フム。
ところが伐採が再生のスピードを上回ってしまうとヤバイです。特に山陽地方では沿岸部での製塩と山間部でのたたら製鉄のために、樹木は薪炭として猛スピードで伐採され、裸地となった森では表土の流出が起こりました。中でも岡山県の児島半島は昔は立派な島で、その間に航路までありましたが、わずかな期間で埋まってしまいました(もちろん直接には干拓の結果ですが。)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午後も野外実習です。テーマは「自然観察のテーマ探し」で、NACS−Jの講師陣が担当です。
自然観察会を開催するにはテーマ選びが重要であることはよく理解できるのですが、それがいざとなるとなかなか思いつかないんですよ。
そういったときのネタをいくつか披露してもらいました。特に「五感を使った観察会」はいろんなバリエーションを創れそうです。
| アキノノゲシ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
夜はまたまた講義。テーマは「自然の観察」。講師はNACS−Jの佐藤さんです。
自然観察会を開催する意味、「自然に親しんでもらって、自然を知ってもらって、自然を守る気持ちを持ってもらう」という考え方を柱にして、様々なノウハウを教わりました。
明日の個別野外実習(受講者それぞれがリーダーになって行う観察会シミュレーション)に大いに参考になります。
みんな明日のリーダー役が気になって、ちょっと浮かない顔をしていました。中には完全に開き直っている人もいましたが。
しかし、まぁ、なるようになる。(経験上、物事なるようにならなかったことは一度もありませんから。)