
小菅村 ~松鶴のブナを守る vol.1~
 |
【山梨県 小菅村 平成19年11月17日(土)】
「山梨県北都留郡小菅村」 人口1千人を割り込む山あいの小さな村。ここは東京から多摩川をさかのぼること100㎞あまり、都県境を越えて山梨県に入りその流れが小菅川と名を変えたその源流部に位置する緑豊かな村です。
詳しいいきさつは後述するとして、今回、この小菅村に1泊2日でブナの保全のお手伝いにやってきました。どんなことをするのか想像がつきませんでしたが十分に楽しんで(ついでに少し役に立って)帰ろうと思いました。
 |
奥多摩駅 |
JR中野駅、午前8時21分発「ホリデー快速奥多摩3号」の車内はトレッキングシューズを履いてザックを抱えた中高年で満席でした。「あぁ、やっぱり始発の新宿まで戻って乗ればよかった。」車内に入って後悔しました。なぜなら山歩きの乗客のほとんどはおそらく終着の奥多摩駅か、その一つ手前の御嶽駅まで席を立たないからです。これから1時間半、立ちっぱなし決定です。
それでも車窓から朝の中央線沿線住宅地を眺めながら時間をつぶし、9時50分、ようやく奥多摩駅に到着しました。やはり満席のまま終着駅に到着でした。
そして改札をくぐって駅前に出てびっくり。「今日は祭か?」と思ってしまうくらいの雑踏です。温暖化といわれつつもここ奥多摩は紅葉シーズンを迎えていて、多くの登山客で賑わっていました。とてもローカル線の終着駅とは思えません。事前に届いた案内ではここが集合場所となっていましたが、多くの団体が同様のようで、めざす受付がどこなのか右往左往してしまいました。それでもいくつかの団体が駅前を発っていった後にようやく受付を見つけ、車体に「kosugemura」と描かれたマイクロバスに乗り込みました。
 |
紅葉(奥多摩湖畔) |
バスに乗っているのは20人くらい。大学生っぽい若者が数人と、あとは中高年のようです。バスは奥多摩駅から3、40分かけて目的地の小菅村に向かいます。まずは青梅街道を西に向かい、やがて現れる奥多摩湖の湖畔に沿って走ります。途中から支脈に分かれ湖水の幅が狭まってくるとそこから先は小菅川。しばらくするとやがて余沢という集落が見えてきます。まっすぐ行けば役場や学校のある川池地区ですが、バスはここを左手に分かれ、白沢地区に向かいます。気温8度。車窓からはちょうど見頃の紅葉が楽しめました。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
話は10月27日(土)にさかのぼります。朝食を終えて新聞を広げていると、地方版の紙面に載っていたブナ保全のボランティア募集の記事に目がとまりました。「古道再生プロジェクト」 場所は山梨県の小菅村、多摩川の源流の森に生き続ける「松鶴のブナ」を登山者による根の踏み固めから守るため、柵の設置などをするとのこと。まず、おや、と思ったのは、多摩川の源流というところ。そうか、多摩川の源流は都県境を越えた山梨県にあるのか。多摩川と山梨というのがイメージとしてなかなか結びつかずちょっと新鮮な感じがし、また、標高1300mを超える尾根に立つブナの巨木という点にも興味がわきました。
主催は小菅村と多摩川源流研究所とあります。さっそく新聞を片手に小菅村役場に電話。概要を教えてもらい参加することにしたのです。
| 白沢地区(源流大学前) |
バスは狭い谷筋の道をたどり、ほどなく白沢地区に入りました。
小菅村には8つの地区があり、それぞれの地区はいくつかの集落が集まってできています。村の面積の約94%は森林。各集落は小菅川が削り込んだ谷の斜面に点在していて、平地はほとんどありません。
この白沢地区にはかつて小菅小学校の分校があったそうですが、平成4年の春に休校となっています。その分校の校庭にバスは停まりました。
| 多摩川源流大学(旧小菅小学校白沢分校) |
めいめい荷物を背負ってバスから下りました。ひんやりとした空気を吸い込んで玄関のひさしを見上げると、天然木の銘板に「多摩川源流大学」とあります。
多摩川源流大学とは、東京農業大学が文科省の補助事業「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」(現代GP)に申請して採択された「多摩川源流域における地域再生と農環境教育」という取組みのことだそうで、ここ小菅村で分校の校舎を借り受け、実際に農大の学生がここに来て実学に勤しみ、単位も取得できるというもの。ちゃんと現地スタッフ(「慎吾くん」と呼ばれる脱サラ農大OB)も常駐しています。この取組みは去年の春スタートしたのですが、農大は6年前から小菅村とその住民の方、関連企業などと連携して森林再生事業に取り組んできていたそうで、この多摩川源流大学の発足により、さらに下流域の大学や住民などを含めた幅広い連携へと広がっていくのだそうです。
農大のキャンパスは世田谷区にあり、そこは多摩川下流域にあたります。源流部にあってひとときも欠くことなく豊かな水を供給してくれてきた小菅村とは浅からぬ因縁があったのかもしれません。
今回の「古道再生プロジェクト」には多摩川源流大学は東京電力と共に共催という形で関わっていて、講師の派遣と教室の提供などをしています。
| 中村文明氏(研究所所長) |
教室に入ると床も壁も白木でリフォームしてあり、木目が明るくホッとする感じ。でも、寒い。さすがは小菅村、この辺りの標高は約600mです。
開会式の挨拶は多摩川源流研究所の所長、中村文明氏。皆さん、親しみを込めて「文明さん」と呼んでいました。(実は例の新聞記事を読む前から中村文明さんの名前は知人から聞いて知っていて、この文明さんが先頭に立ってやっているプロジェクトであるということもこれに参加しようとした大きな理由の一つだったのです。) 文明さんの人となりやプロフィールを紹介すると一冊の本になるくらいなので割愛しますが、yamanekoも最初の挨拶を聞いただけで、その人を引きつける魅力に引き込まれるような気がしました。「一途」という言葉がぴったりとはまる人のようです。
ここで多摩川源流研究所の説明をしておきましょう。(以下、研究所発行の季刊誌「源流の四季」より)
この研究所は、多摩川の源流部に着目し、源流を活かし源流にこだわったまちづくりを進めるために小菅村が設立したもので、村の職員や専従の研究員、スタッフで運営されています。その設立は平成13年春。2年後には、「多摩川源流百年の森づくり」を目標として掲げた「森林再生プロジェクト」をスタートさせ、3年間で延べ1600人のボランティアが参加する一大事業として18haもの森林を整備しました。
平成18年からは「古道再生プロジェクト」として、年間5回、それぞれ1泊2日で、再生のための調査、実際の作業などを学ぶことができるものにリメイクされています。再生を手がける古道とは、多摩川の源流域を馬蹄形に取り囲む尾根筋の小径のことで、周辺の森や人、暮らしにまつわる古来からの知恵、巨樹や草木に秘められた歴史、文化をひもときながら、荒れた古道を整備していこうというものです。多摩川源流を育んできた「百年の木」を大切に使い、そして育てる「百年の森づくり」です。
さて、文明所長の挨拶が終わった後は、軽井沢在住の詩人・脚本家である丹治富美子先生から、万葉集の中に詠まれた広葉樹について興味深い話を聞かせてもらいました。丹治先生もこのプロジェクトに深く関わっておられて、毎回このような文化的な側面からのレクチャーをしていただいているようです。今回はブナの保全なので、広葉樹が詠み込まれた歌を採り上げられたとのこと。それにしても先生の所作や言葉遣いは「上品」の一言。毎回きれいに製本された教材を作られて、自らの筆でしたためられた万葉の歌を紹介されています。
| 丹治先生作 「いにしへの草々」 |
万葉集は7世紀半ばから約130年間もの間に、天皇から庶民までの多くの人々によって詠まれた4516首の歌を集めたもの。今回の教材にはその中から4首が採り上げられていました。
| あずさ弓 ひかばまにまに 依らめども のちの心を しりかねるかも (巻二の九八 石川郎女) |
| 意味:思いを寄せてくれるのは嬉しいけれど、後に心変わりをするのではないかと思うと…。(あずさ弓とは、梓(=ミズメ)で作った弓のことで、「引く」にかかる枕詞) |
| 瓜はめば子ども思ほゆ 栗はめばまして偲はゆ いづくより来たりしものそ まなかひに もとなかかりて 安眠(やすい)しなさぬ (巻五の八〇二 山上憶良) |
| 意味:瓜を食べるたびにこれを好んで食べていた子どものことが思い出される。栗を食べたりするとさらに偲ばれる。どこからやってっくるのか目の前に子どもの面影がちらちらして、よく眠れないほどに子どもが恋しい。 |
| 山科の 石田の小野のははそ原 みつつか君が 山路こゆらむ (巻九の一七三〇 藤原朝臣宇合) |
| 意味:山科の石田の小野にあるははそ林を眺めながら、あなたは山路を越えて行ったのですね。(ははそ=コナラ) |
| 紅は うつろうものそ 橡(つるばみ)の なれにしきぬに なほしかめやも (巻一八 大伴家持) |
| 意味:貴人が身につけている紅(くれない)で染めた衣はやがて色褪せてしまうが、私たちが着る橡で染めた衣は地味ではあるがいつまでも色あせることはない。(紅=アカバナ、橡=クヌギ) |
ちなみに、ブナは万葉集にはほとんど登場していないとのこと。当時都のあった西日本では、ブナはかなり標高の高いところにしか出現せず、人々が暮らす里では目にすることがほとんどなかったからだと考えられているそうです。
丹治先生のレクチャーで午前中は終了。その後は持参した弁当で昼食です。
昼食後、保全作業の現地に向かうまでの時間を使って、来年行う広葉樹の植林について、東京電力環境部のグリーンサポートグループでマネージャーをしている矢野康明さんに説明してもらいました。東京電力はCO2を削減して地球温暖化防止につなげていく「ECOサポートプラン」の一環として、地域と一体となった持続可能な森林保全を行うことによって、CO2の吸収・固定に寄与する森林づくりに貢献する活動を展開しています。そして、この古道再生プロジェクトにも共催という形で関与しているのです。
| 矢野康明氏 | 実生の苗 |
源流大学の校庭の隅にネットで囲まれた苗床がありました。これは去年、古道に点在する巨木の周辺から採集したドングリを発芽させたもの。種類によって異なりますが、大きいものでは高さ50センチくらいに育っています。あえて日陰で育てているのは、植えた後のことを考えてのこと。この辺りの山々は谷が険しいので、日陰でも強く育っていくように寒さに慣らしているのだそうです。
永く風雪に耐えてきた大きな木、すなわちこれは強い木ということですが、その強い木の種子は、やはり強いのだそうです。来年の春以降、荒廃が進む人工林に植えて混交林に変えていく活動が始まります。
今から約50年前、エネルギー革命が起こり日本全国で人々の生活が一変しました。それまで主要燃料であった薪炭から石炭・石油の化石燃料に変わったのです。人々は柴刈りや萱刈りをしなくなり、山に入る必要がなくなったことから、山はしだいに荒れていきました。また、戦後の木材需要を満たすために国策として進められた針葉樹の植林地が安価な輸入材の進出により放置されはじめたこともこれに拍車をかけました。間伐などの手入れをしていない針葉樹の森は真っ暗です。適度に光が入り豊かな下草に覆われた林床は、雨水をたっぷりと染み込ませゆっくりと時間をかけて川に流すことができるのですが、真っ暗で裸地のような林床では雨水を保っておくことができず、表土ごと流してしまい、山をさらに荒廃させていくのです。
そこで豊かな水源の山を守っていくために混交林を広げようという活動が、今全国各地で始まっています。植林にはしっかりと育つ広葉樹の苗が、そのための強い種子が、そしてその種子を生み出す強い母樹が必要となるということなのです。今回のブナの保全も、ただ単にシンボルツリーを守ろうというイベント的なものではなく、強い木を永く残すことによって強い子孫を多く生み出そうということなのです。
| 松姫峠 |
12時45分、再びマイクロバスに乗って松姫峠に向かいます。ウネウネとした道を登ること20分、急に視界が開け、松姫峠に到着しました。標高1250m、いつの間にか日差しもかげり、はっきりいって寒いです。ここからはめいめいが測量道具や鍬、鎌、鉈などを携えて、古道をたどる尾根道を行きます。
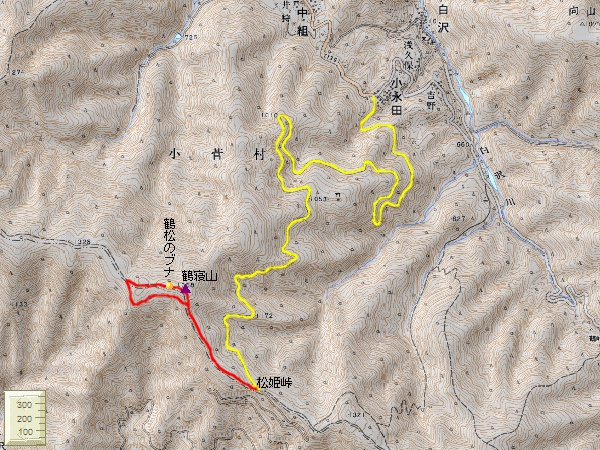 Kashmir 3D |
この尾根道の北斜面に降った雨水は小菅川から多摩川へと流れ、東京湾に注ぎます。一方、南斜面に降った雨水は葛野川から桂川、そして相模川となって相模湾に注ぐのです。
| 古道を往く |
辺りの木々はあらかた葉を落としていて見通しがきき、正面の鶴寝山もよく見えます。あの山を越えたところに松鶴のブナが待っているのです。ところで、この2日間、NHKの取材クルーが5人ほど同行していて、保全活動の一部始終を記録していました。数日後の夕方の「首都圏ネットワーク」の中で放映するのだとか。でも、肝心の山梨県では放映されないのだそうです。
| クマの爪痕 |
途中、ヤマザクラの幹にまだ新しいクマの爪痕を見つけました。この辺りは完全に彼らの活動範囲内です。
| 松鶴のブナ |
1時40分、松鶴のブナに到着しました。全体の姿を収めきれないほどの大きさ。予想外です。葉を落としてこの大きさですから、夏の葉の茂った頃に見たらもっと大きく感じるでしょうね。他のみんなも一様に感嘆していました。
| 地元講師の皆さん |
現地での作業を開始する前に地元講師の方が紹介されました。森林組合の方や造園業(兼樹医)の方などです。木の皮のむき方、チェーンソーの使い方、土壌の検査の仕方などを指導していただきます。今回の保全作業の詳細は既に小菅村と源流研究所との間で決まっていて、その前段として様々な現地調査がなされています。今日、これからやる準備作業は、現地調査とはどのようなことをするのかといったことを体験するのがメインで、あとは明日の作業の下準備として、木道に使う材の仕上げなどです。
| 根元の苔 |
ブナの根元には苔が張り付いていました。今まで苔がつくことは保水効果もあって木にとって有益なことだと思っていたのですが、講師の方によるとこれはかえって樹皮を痛める原因となるのだそうです。あと、全体の枝の張り方や折れた枝の様子、木槌で幹を叩いたときの音なども樹木診断の重要な判断要素だそうです。
| 土のpHの測定 | 土の硬さ(締まり具合)の測定 |
ブナの周りの土を、尾根上、斜面上と区分けして採取し、それを水に溶いてpHを測定したり、また、土の硬さを測って保水能力の違いを確認したりしました。土壌の酸性度は場所による違いはあまりなく、どこも良好な状態でしたが、土の硬さについては斜面上がふかふか(土壌の厚さは約1m~1.5m)だったのに対して、やはり尾根上は硬く(約30㎝)、登山者にかなり踏み固められていることが分かりました。
| 苔落とし | 木道敷設の準備 |
さっき見た樹皮の苔をタワシでこすり落としていく人や、鎌で木道に使うスギ材の皮をむく人。柵の杭を打ち込む位置に目印の木札を差し込んでいく人。なにしろ寒いので何か動いていないと辛いということもあり、みんな積極的に作業に取り組んでいました。
| 作業終了 |
3時30分、現地作業終了。後片付けと明日の準備をして、寒さに震えながら下山です。松姫峠で待っていてくれたマイクロバスに乗り込んでホッと人心地がつきました。バスはここから「小菅の湯」に直行。小菅の湯とは村内の中組地区にある温泉宿泊施設で物産館も併設していることから、この村を訪れる人のほとんどは立ち寄るのではないでしょうか。実際に週末には多くの入浴客で賑わっています。
温泉で体の芯から温まった後は、今日の宿泊場所である古家旅館へ。地物の食材を使った美味しい料理が待ってくれているはずです。
| 食事後の「源流ばなし」 |
荷物を部屋に片付けて、広間で夕食。待ってましたです。ヤマメの塩焼きやイワナの刺身、山菜にコンニャク、そのほかにもあれやこれやと腹一杯で、締めには手打ち蕎麦と、大満足でした。食後には文明さんから源流との出会い、その素晴らしさや魅力について熱い話を聞かせてもらい、みんな引き込まれるように聞き入っていました。
山里の夜は早いです。美味しい料理とビールで完全に満足してしまい、ほとんどの人は9時くらいには床についたようです。yamanekoと数人の中高年、あと農大の学生数人、源流研究所の職員で今回のコーディネーターの中川青年などが居残って、森の話、森に住む生きものの話、村の暮らしなど、話題の移ろうに任せて話をしていました。それでも10時過ぎには部屋に戻りましたが。
寒々とした冬の空に枝を広げる松鶴のブナ。あなたはいったいいつからここにいるのか。いったい何回の嵐を乗り越え、何回の雪解けを迎え、そしてあなたが作るその大きな木陰でいったい何人の人を休ませてきたのか。
このブナの長い生命の中の一瞬と自分の人生の中の一瞬とが、今日こうして交差したことが何かとても貴重なことのように思われ不思議な感じがしました。
さあ、明日はいよいよ作業本番です。(次回に続く。)