
茅ヶ岳 〜秋の花と眺望を楽しむ(前編)〜
 |
(前編) |
【山梨県 甲斐市 平成28年9月5日(日)】
9月に入ってからというもの台風や秋雨前線のおかげで日照時間は極端に少なく、週末も雨ばっかりです。天気予報を見ているとどうもキーワードは「太平洋高気圧」のようで、こいつが例年とは違う位置にいるのが原因の一つのようです。そんな中、ようやく巡ってきた晴天。前日も雨だったので天気予報を疑いつつも、やっぱりこのチャンスを逃すことなく山に行くことにしました。目的地は山梨県北杜市と甲斐市に跨る茅ヶ岳。「日本百名山」を記した作家で登山家の深田久弥の終焉の地としても(一部では)有名な山です。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
朝5時起床。この時期の5時はまだ真っ暗です。ずいぶん日の出が遅くなったものです。支度を済ませドリーム号を発車させたのは5時50分でした。この時点ではすっかり明るくなっていて、射し込みつつある朝日に今日の晴天を確信しました。
中央道は車の量は多いですが流れは順調。空は快晴かというほど晴れ渡っています。ところが笹子トンネルを抜けて甲府盆地に入ると一転して曇り空。まるで盆地に蓋をしたかのような空模様です。それでも徐々に雲が晴れつつあるようで、目的地最寄りの韮崎ICで高速を降りる頃には上空の雲は半分程度になっていました。このまま晴れてくれればいいですが。
ICから登山の起点となる深田記念公園の駐車場までは一本道。裾野をまっすぐ上って行くだけで、迷いようもありません。
| 深田記念公園駐車場 |
8時、駐車場に到着しました。スペースは8割方埋まっていましたが、無事に駐車できました。 ここは、公園を訪れる人用というより、完全に登山者用ですね。準備体操をしてから、8時15分、スタートです。
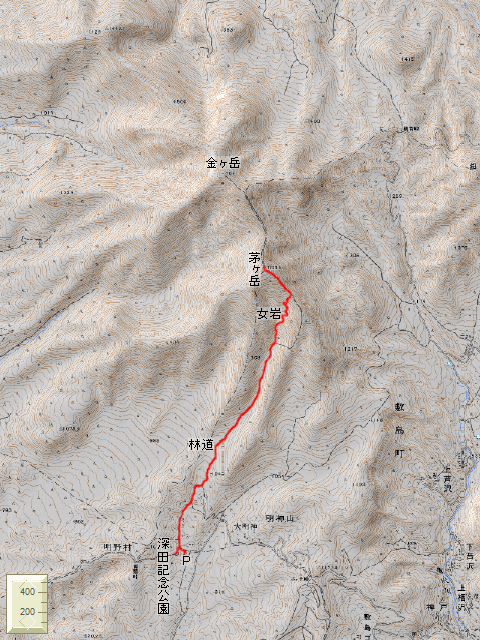 |
Kashmir 3D |
今日のコースは、茅ヶ岳南麓の女沢をひたすら登り、谷がいよいよ詰まったあたりから山腹に取り付きます。ここからが傾斜がきつくなるところ。やがて稜線に出たら山頂を目指してラストスパートです。復路は来た道を戻ります。
茅ヶ岳は北西にある金ヶ岳とともに数十万年前に活動していた火山だそうです。地図を見ると、金ヶ岳はカルデラ地形の縁にある山であることが分かります。
駐車場を出て30mほどで分岐があり、左に行くとすぐに深田記念公園がありますが、これは帰りに寄るとして、ここは山頂を目指して右手に向かいます。
| ダンコウバイ |
しばらくはほぼ平坦な森の中を進みます。この特徴的な形はダンコウバイの葉。森の中はまだしっとりと濡れています。
| ハナトラノオ |
野山ではあまり見かけない花。シソ科っぽいですが柳葉のように細く縁に鋭い鋸歯がある葉が気になります。結局その場では何だか分かりませんでした。帰ってから調べてみたらどうやら園芸種のハナトラノオが野に逸出し半野生化したもののようでした。
| 登山道 |
木々の密度が高くなってきました。天気は回復傾向ですが、曇り空の下だと薄暗く感じます。
| ヤハズハンノキ |
おや、これはヤハズハンノキの葉か。高山でしか出会えないものと思っていて、ちょっと疑いましたが、地図で確認するとこの辺りの標高は約1000mあり、そこそこの高地でした。
| ヤクシソウ |
露に濡れたこの花、よく見るとヤクシソウでした。普段の印象とはちょっと異なります。写真では分かりにくいですが、葉の基部が茎を抱くのがこの花の特徴の一つです。
| シロヨメナ |
シロヨメナ。関東近郊の野山ではよく見かけるキクです。 ただ、似たようなものが多く、ぱっと見で見分けることは難しいんですよね。写真を撮る際には、花、葉、茎に加え、総苞片(花の基部の漏斗状になっているところ)を忘れないようにしています。そうしないと図鑑でも特定しきれません。
| シラヤマギク |
こちらはシラヤマギクです。燃え尽きる前の線香花火みたいな儚さを感じる花冠ですな。
はからずもキク科3連発となりましたが、ヤクシソウはキク科のオニタビラコ属、シロヨメナとシラヤマギクはシオン属になります。キク科は、最も進化し、最も分化しているグループなのだそうです。
足元に岩が多くなってきました。でもまだ傾斜は緩やかです。
| ナンテンハギ |
これはナンテンハギですね。別名をフタバハギといい、葉が2個対生するのが特徴です。写真では4個輪生しているように見えますが、よく見るとちゃんと2個でした。
| ダンコウバイの実 |
ダンコウバイの実。ダンコウバイはクスノキの仲間で、実もよく似ています。
| オニドコロ |
ハート型の葉をもつツル性の植物。いい色になっていますね。葉が互生しているところを見るとオニドコロでしょうか。たしか対生ならヤマノイモ(自然薯)。
| カシワバハグマ |
カシワバハグマ。葉が若干革質化しているのが気になりますが。これもキク科の植物。コウヤボウキ属だそうです。花はもう終わりですね。
| 林道 |
スタートして30分、林道が現れました。これは横切ります。ちょっと分かりにくいですが、登山道はまっすぐ奥に続いています。
林道の奥。なんか風景に変化がありませんね。
| ヤマアジサイ |
ヤマアジサイ。両性花の花期が終わってしまって装飾花のみが虚しく残っている状態です。
ちょっと森が開けたところに出ました。昔ここに何かあったのかもしれません。作業小屋とか。
| 秋の空 |
上空には青空。まだ若干雲は多めですが、清々しい秋の空です。
| 傾斜増す |
この辺りから斜度が少しずつ増してきました。足元の岩も更に多くなってきています。
| 小休止 |
写真の木の下にリュックを下ろして小休止しました。出発からここまで1時間弱かかりました。
| 水場 |
再スタートしてすぐ、ここが最後の水場との看板が。もともとこの先にある女岩のところにも水場があったそうですが、崩落の危険があるため女岩周辺が立ち入り禁止となっているようです。
| 行き止まり |
しばらくすると「立入禁止」と書かれた黄色い規制線が行く手を塞いでいました。これ以上谷を遡ることはできません。この先50mに女岩があるようです。登山道は右手の山肌に取り付いていました。
| 登山道 |
ここから急傾斜の岩場を登っていかなければなりません。両手も使って登るほどの斜度です。
岩場は20mほどで終わりましたが、その後もこの傾斜。つづら折れで高度を稼いでいきます。しかも足元がぬかるんでいて、滑りやすくなっています。気をつけねば。
山腹をトラバース。登山道が微妙に谷側に斜めっていて、結構気を使います。
| アキチョウジ |
そんな中、花に出会うとホッとしますね。これはアキチョウジ。久しぶりに出逢いました。
道は相変わらずぬかるんでいます。岩の上に乗るのは危険なので、結局ぬかるみを歩くことになるんですよね。靴底が重たいです。
| ヤマトリカブト |
これはヤマトリカブトでしょうか。主に花の付き方や葉の形で見分けますが、似たようなものが多くて難しいですね。
| サラシナショウマ |
おや、シライトソウかと思いましたが、よく考えたら春の花。葉を見るとサラシナショウマであることが分かりました。写真のこれは花がすべて落ちた後の花穂なんですね。
| オオトウヒレン |
こっちは花期が過ぎたオオトウヒレン。またまたキク科です。どこかアザミに似ていますがトウヒレン属。
| 稜線 |
おお、稜線が見えてきました。ようやく山腹の道が終わります。時刻は10時5分です。
稜線に出たら左手に折れて山頂を目指します。足元が乾燥した赤土に変わりました。これまでと比べて格段に歩きやすいです。
| 深田久弥碑 |
しばらく行くと「深田久弥先生終焉之地」と彫られた碑が現れ、いろいろお供えがしてありました。yamanekoは今日のに登山の安全をお願いして手を合わせました。
「日本百名山」 この言葉は昨今の登山ブームに大きく寄与しているでしょうね。「百」とか一定数セレクトされた何かにコンプリート欲が出てくるのは人間の常。ネット上でも百名山を踏破した、また、挑戦中といった記事をよく目にします。テレビでも百名山を取り上げた番組が頻繁に放送されていますし、旅行会社の登山ツアー商品でも百名山の文字が付くと人気が高いと聞きます。50年以上前に出版された本なので、ご本人にはそんな意図は全くなかったと思いますが、ちょっとしたブランドになっていますね。
(後編へ続く)