
観音崎 ~黒潮望む岬巡り~
 |
【神奈川県 横須賀市 平成27年2月11日(水)】
毎日寒いです。空気もからっから。まだ、スギ花粉が飛んでいないだけましですが、春が待ち遠しい今日この頃です。
さて、今日は休日なのでそんな寒さから逃れどっか暖かいところでまったりしたいところ。しばらく考えて、三浦半島にでも行ってみるかということになりました。南関東の沿岸部は沖を暖流(黒潮)が流れているので、冬場は特に暖かく感じるのです。半島の先端部は、東に観音崎、西に城ヶ島とメジャーなスポットがありますが、今回は観音崎を目指します。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
出発時刻は11時半。ドリーム号に乗って東京環状(国道16号)を南下します。この道をとにかく真っ直ぐ進めば途中から自然に保土ケ谷バイパス、そして横浜横須賀道路(通称「横横道路」)に乗る形になり、あとは終点の馬堀海岸ランプまで一本道。海辺に出たら観音崎はもうすぐそこです。
途中、若干の渋滞はありましたが、県立観音崎公園の駐車場に入ったのは午後1時過ぎ。激しい渋滞が日常茶飯事の16号にしては上出来の方です。駐車場は休日とあって混みぎみ。でも運良く待たずに停めることができました。
さて、ここ観音崎、訪れるのは9年ぶりになります(前回の様子)。
| 駐車場 |
駐車場の背後には照葉樹の森。全体的にモコモコしていますね。
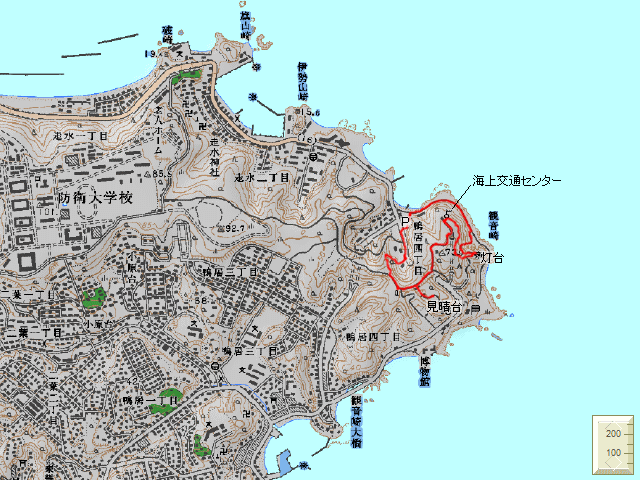 Kashmir 3D |
今日のルートは、駐車場から時計回りに岬を巡り、途中から山の上に登って観音碕灯台へ。そこからは山腹を水平移動して海上交通センターに向かいます。その後、見晴台などに寄ってから元の駐車場に戻って来るというものです。
| 東京湾 |
歩き始めてすぐに海辺に出ました。東京湾。穏やかな海です。
| 第二海堡 |
沖の平べったい陸地は第二海堡だと思います。大正時代に東京湾の防衛を目的として造られたものだそうです。ちなみに関係者以外は立入禁止。
| ヤブツバキ |
海岸に沿って歩いて行こう。森の袖にはヤブツバキ。寒い時期に咲く花なので、花期は長いです。この時期は虫による花粉の媒介はあまり期待できないので、蜜をたっぷりと分泌してメジロなどの鳥に来てもらっているようです。
磯では多くの家族連れがタイドプールを覗き込んで遊んでいました。水もそんなには冷たくなさそうです。
| イソギク |
いい具合に枯れたイソギク。葉の裏が銀白色で、表から見ると白い縁取りに見えます。花冠はドライフラワー状態です。
| カジイチゴ |
この大きな葉はカジイチゴのもの。葉の大きさは人の頭ほどもあります。野イチゴにありがちな刺がないのが特徴。
| コウボウムギ |
岩場のわずかな土の上で頑張っているのはコウボウムギですな。右の写真は雄花で、ふさふさしているのは葯です。漢字では「弘法麦」と書き、かつて茎の繊維で筆を作っていたことによるのだそうです。いくら弘法筆を選ばずといってもこの筆は使わないだろう。
| ツルナ |
砂地の隅っこにツルナが生えていました。ゴミにまみれていたので取り除いて少し綺麗にしてから写しました。海浜植物に特有の肉厚な葉をしています。昔から(今でも)食用にする地方は多かったようです。花はごく小さく、7mm程度。厳しい環境でよく耐えているものです。感心、感心。
| ノゲシ |
浜から一段上がったところには野の花が。 このちょっといかつい雰囲気の花はノゲシ。葉には棘がありますが、軟らかく触っても痛くありません。早春から咲いてくれる花です。
海岸を離れて山の上に登っていきます。重なる地層を抱きこむように大きな木の根が伸びていました。この辺りの地層はシルトや火山灰などが深海に堆積してできたもので、逗子層や池子層と呼ばれています。概ね400万年前に堆積したものとのことなので、地質年代でいうと新生代第三紀末。ようやく類人猿から猿人への分化が始まった頃になります。(理科年表より)
よく地層や化石などの話のときに何万年とか何千万年とか何億年とか耳にしますが、地質年代全体を通した物差しが頭の中にないので、どのくらい前のことなのかなかなかピンと来ないことがしばしばです。それにしてもその頃あったものが今も目の前にあるということがなんか不思議な感じがしますよね。よく考えたら山とかそこいらじゅうのものがそうなんですけどね。
2艘のトロール船が網を引きながら過ぎていきます。水面からそう深くないところで網を流しているように見えましたが、外洋での漁を終えて港に帰るところでしょうか。
| 観音碕灯台 |
坂道を登り詰めると観音碕灯台が現れました。日本最古の洋式灯台だそうで、関東大震災などで被災し、現在のものが三代目だそうです。 参観料200円を払って上ってみることにしました。ここに上がるのは25年ぶりくらいになります。
どうでしょう、この眺め。灯台なので当たり前といえば当たり前の眺望ですね。眼下には浦賀水道。東京湾の玄関口に当たり、一日に500隻もの船舶が往来するそうです。対岸の房総半島が霞んで見えますが、実際には思ったより近く、もっとくっきりと見えていました。
下を覗き込むと、さっきコウボウムギやツルナの写真を撮った小さな磯が。灯台は海面からの高さは56mだそうで、ずっと覗き込んでいると平衡感覚がグラグラしてきそうです。
目の前には海上保安庁の東京湾海上交通センターが。別名「東京マーチス」。ここから24時間365日、浦賀水道や東京湾内の航行管制を行っているのだそうです。ご苦労様です。
| フレネルレンズ |
これが灯台の心臓部のレンズです。フレネルレンズというのだそうで、ツルッとしたひと塊りのガラスではなく、レンズを同心円状に分割してその厚みを薄くし(土台部分をなくすと断面は三角形になる)、材料を節約して軽量化も図れるというものだそうです。そう考えると、確かにレンズは表面の曲面だけ残せばその背後の厚みはそう意味はないということですね。これで光を35㎞先まで届けているのだそうです。
だんだん足元がぞわぞわしてきたので、適当なところで下りました。そこからはさっき見えていた海上交通センターに向かいます。
途中の小径に繁っていたシダ。緑色の濃いのがヤブソテツ。その周りの薄いのがイノモトソウ。どちらもyamanekoでも識別できるくらい超メジャーなシダです。
| 海上交通センター |
森の小径を抜けて海上交通センターに出ました。海の管制塔です。入り口奥に何やら展示コーナーがあるようでしたが、この日は休日のせいか入口が閉まっていました。海面からの高さは84mとのことなので、観音埼灯台よりもずっと高いですね(土台の山が高いということか。)。
玄関前のウメの蕾。わずかにほころびかけています。この辺りは春の訪れが早いでしょうね。
| ヤツデ |
ここからは山頂部に延びる道を歩いていきます。これはヤツデ。株の広がりは約2.5mもありました。周りに争う植物がいないとこんなに立派になるんですね。堂々たる姿をしています。
時刻は2時40分。少し陽が傾いてきたようです。今日は風もなく長閑です。
| 相模湾 |
途中から左手に折れてトンネルを抜け、見晴台というところに寄ってみました。観音崎には戦前は砲台など軍関連の施設があって、ちょうど東京湾の外側が見えるこの見晴台も立地的にそんな感じの場所でした。
| トベラ? |
これはトベラか。やや葉が小ぶりのような気がしますが。
見晴台の日向でまったりとしていたネコ。風格あり過ぎです。それにしてもノラにしては栄養状態良すぎないか?
元の道に戻ってまたぶらぶら歩いていきます。
途中で右手の森の小径へ。ここからスタート地点の駐車場近くに下りられるのです。通る人もいない静かな道でした。
3時5分、駐車場に戻ってきました。この時間でも駐車場には多くの車が停まっています。みんな暖かな陽射しを求めてやって来るんですね。
さあ、ぼちぼち帰途につきますか。
そういえば今日は祝日で、まだ週の半ばでした。楽しい野山歩きでリフレッシュできたので、明日からまた頑張れそうです。