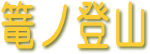
篭ノ登山 ~高山と湿原のお得セット(後編)~
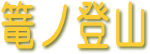 |
(後編) |
【長野県 東御市 令和6年7月22日(月)】
猛暑が続く中、涼を求めてやってきた篭ノ登山。その後編です。(前編はこちら)
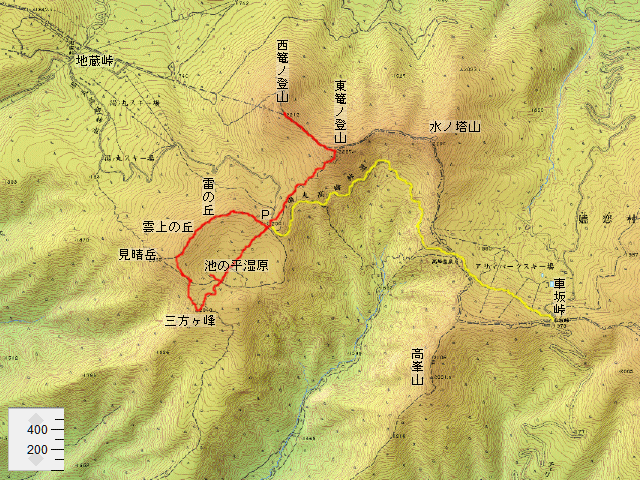 |
Kashmir3D |
9時20分に池の平駐車場をスタート。東篭ノ登山に登ってから西篭ノ登山まで足を伸ばし、折り返して同じ道を歩いてまた駐車場に下りてきました。時刻は12時ちょうどです。
| ランチ |
ベンチに腰掛けて昼食を。コンビニのおにぎり2個とメロンパンというメニューです。
ところで、おにぎりの海苔って優れものですよね。ご飯をまとめるシートでありながら、味のアクセントにもなっていて、食感もいい。それをまたパリパリの状態で提供する技術も秀逸です。
| ウツボグサ |
昼食後は池の平湿原を歩きます。その湿原に向かうまでにも様々な植物が。これはウツボグサ。戦国時代に矢を収納する入れ物を靭(うつぼ)といったそうで、花序がその靭に似ているということで名付けられたとのことです。
| カワラナデシコ |
これはカワラナデシコか。標高的にはタカネナデシコでもおかしくはないとは思いますが、花弁の裂け方がちょっと違う印象です。タカネナデシコはもっと深く細かく裂けるのが特徴。
| 池の平湿原 |
さて、ここから池の平湿原。まずは湿原の中央部に向かって緩やかに下っていきます。
| ゼンテイカ |
最初に出会ったのはゼンテイカ。別名のニッコウキスゲの方がポピュラーかもしれません。漢字では「禅庭花」と書きますがその由来ははっきりしないそうです。
| シャジクソウ |
この日の湿原散策の主役だったシャジクソウ。あちこちに咲いていて、ちょうど花期のど真ん中だったようです。名前の「車軸」は小葉が輪生状に出るからだそう。葉が車輪、茎が車軸のようだということなんでしょう。
| アサマフウロ |
ご当地のアサマフウロにも会いました。花弁の先端が丸いところが、今朝見たイブキフウロとは異なる点です。
| ノアザミ |
うーむ、これはノアザミか。ぷっくりとした総苞が特徴的。
| キバナノヤマオダマキ |
湿原にもキバナノヤマオダマキがありました。花弁の後部が長い距になっていて、しかもその先端が球状になっている不思議な形。トランプのジョーカーが被っている帽子みたいです。
樹林帯の中を下っていきます。この辺りはまだ湿原の縁になります。
| マルバダケブキ |
マルバダケブキの花序。もうじき開花です。深山に生える花で、開花後の舌状花はややレロレロな感じ。yamanekoの好きな花の一つです。
辺りが開けました。湿原の中央部に出てきたようです。
どこかの小学校の生徒が小グループに分かれて自然観察をしていました。野外学習でしょう。子供はこの暑さの下でも元気です。
池の平湿原。標高2000mに広がる天上の湿原です。容赦なしに日差しが降り注ぎますが、はやり下界の暑さとは全く違います。この先正面の丘に向かい、三方ヶ峰で眺望を楽しむ予定。そこからは右手に尾根をたどって駐車場に戻ります。
| ノハナショウブ |
カキツバタと間違われがちなノハナショウブ。この写真ではちょっと分かりにくいですが、外花被片の基部にある斑紋が白色なのがカキツバタ。黄色だとノハナショウブです。いずれも水辺や湿地を好む植物ですが、どちらかというとノハナショウブの方がやや乾き気味の場所に生えています。
右手には湿原の北側を囲む丘が見えています。この尾根上に見晴歩道という道があり、そこを歩く予定です。
湿原の奥に池があり、その手前まで木道が伸びていたので行ってみました。静かな水面が青空を映し、そこにもう一つの世界があるかのよう。池の遥か後方には午前中に登った篭ノ登山が。広々として心身ともに開放される空間でした。
| グンナイフウロ |
湿原の縁の樹林に入りました。これはグンナイフウロ。今日3種目のフウロソウです。グンナイは「郡内」と書き、これは山梨県の東部の昔の呼び名だそう。ざっくり、大月や富士吉田など桂川流域を郡内、甲府を中心とした富士川流域を国中(くになか)と呼んだのだそうです。郡内と国中は何かとライバル視しているのだと郡内出身の知人が面白おかしく言っていました。地域ネタあるあるですね。
| アヤメ |
湿地に生えているイメージのあるアヤメですが、実際には山中の開けた草地で見かけることが多いです。アヤメは花被片の基部が名前のとおり綾目模様になっているので、カキツバタやノハナショウブとは見分けやすいです。
| イブキジャコウソウ |
イブキジャコウソウです。強烈な日差しに写真が若干白飛びしていますが、本来は濃い赤紫色をしています。麝香草というくらいなので芳香があるのかと鼻を近づけてみるのですが、人一倍嗅覚kの鈍いyamanekoはついぞ匂ったことはありません。
湿原の南側の縁を上っていきます。この先が三方ヶ峰。
| 三方ヶ峰 |
12時55分、三方ヶ峰に出ました。標高2041m。ここから南側の眺望が一気に開けています。
眼下に広がるのは御牧ヶ原台地。佐久平の西側に広がる高原地帯です。遠くの稜線は、写真左側の山塊が八ヶ岳連峰。稜線のほとんどは雲に隠れいていますが、蓼科山だけが鋭いピークを見せています。そこから右手に緩やかに下ってその先の高まりが霧ヶ峰や美ヶ原。つまり稜線の向こう側は諏訪盆地や松本盆地ということになります。
| クガイソウ |
三方ヶ峰からは尾根道を歩きます。これはクガイソウ。輪生する6個の葉が特徴的です。花序は伸びていますが個々の花はまだ開いていません。
| 池の平湿原 |
尾根上から見下ろす池の平湿原。左手の森の中を下ってきて、湿原を横切り、そのまま三方ヶ峰に上ってここまで尾根道を回り込んできたことになります。奥には浅間山の雄大な姿。この湿原を見下ろしているかのようです。
尾根道を歩いていると高校生の一群が。野外活動のようでした。元気よく挨拶してくれました。
| コウリンカ |
丘に上がってくると湿原とはまた違う花々に出会えます。これはコウリンカ。「紅輪花」の名のとおり舌状花が濃いオレンジ色をしています。山地の草原で見かける花です。
| ミネウスユキソウ |
ここにもミネウスユキソウが咲いていました。やっぱりここは標高2千mを超える高地なんだなと実感。
| シモツケ |
シモツケはバラの仲間。そういえば先月、筑波山の山頂でも出会いました。
この見晴歩道を歩く人は多くはないようです。あまり人とは出会いませんでした。
| グンバイヅル |
グンバイヅルは、浅間山周辺や志賀高原、美ヶ原など長野県北東部を中心とした限られた地域に分布しているのだそうです。今日ここで出会えて良かった。
| オオヤマフスマ |
ナデシコの仲間、オオヤマフスマです。漢字では「大山衾」。衾とは掛け布団のような夜具のことだそう。ただ、この花の姿から布団の要素はどうしても見つけられないのですが。
| 雲上の丘 |
1時30分、尾根道上の小ピーク「雲上の丘」までやってきました。遠くに東西の篭ノ登山が見えていますね。小休止です。
ここからはまた違った角度で池の平湿原を見下ろせました。湿原の右端に池が見えていますね。さっきあの池の畔まで木道をたどりました。三方ヶ峰はその右手の丘を上ったところにあります。
| ヤマブキショウマ |
これはヤマブキショウマですね。葉がヤマブキの葉に似ていることからのネーミングです。じゃあショウマとは?
ショウマとは「升麻」と書き、サラシナショウマというキンポウゲ科の植物の漢方での呼び名だそう。で、これと似たような花序を持つ植物に◯◯ショウマという名前のものがいくつもあり、ヤマブキショウマもそのうちの一つということ。結局ヤマブキでも升麻でもないのですが。
| チダケサシ |
ちょっとヤマブキショウマに似ていますね。◯◯ショウマなのかと思いきや、これはチダケサシ。
| 雷の丘 |
尾根道を更に進んで「雷の丘」までやって来ました。ここが何で雷なのか特段の説明書きなどはありませんでした。かつて落雷があったとか?
ほどよい木陰を歩いていきます。道は若干下り基調。快適です。
| 分岐 |
しばらく行くと分岐が現れました。右手に下る方に「池の平駐車場→」の道標があったのでそちらに向かいます(直進する道はどこに続いていたのか)。
| ヤマハハコ |
これはヤマハハコですね。先端の白いものが頭花で、まだ固く寄り集まっている状態です。
| シュロソウ |
褐色の花を付けるシュロソウ。これが緑色の花だとアオヤギソウ。お互い兄弟みたいなものです。
| カラマツソウ |
カラマツソウ。花弁はなく、細長いのは雄しべです。これがカラマツの葉を連想させるのだそう。
尾根道を下り切りました。ここが野山歩きのゴールです。この左手にビジターセンターや駐車場があるはずです。
時刻は午後2時。ビジターセンターに立ち寄ってから駐車場に向かいました。
今日は日差しは強かったですが、時折吹く風は清々しく、下界とは比較にならないほどの快適さでした。そして、そんな中、山と湿原といった異なる環境で野山歩きができ、更に日頃見かけない植物も次から次へと現れて、本当に心踊る一日になりました。
| ドリーム号Ⅲ |
駐車場で待っていたドリーム号Ⅲ。風でいくらかは砂埃が落ちていましたが、ルーフの上は真っ白のままでした。
この後、小諸に下りてから高速に乗るまでの間にガソリンスタンドに立ち寄って、洗車機できれいに洗い落としてから帰途につきました。