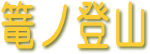
篭ノ登山 〜高山と湿原のお得セット(前編)〜
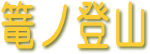 |
(前編) |
【長野県 東御市 令和6年7月22日(月)】
今年の梅雨は、遅く入って例年どおりに明け降水量もそれなりという、短期集中型だったようです。その梅雨が明けた後は、待ってましたとばかりの連日の猛暑日。熱中症警戒アラートが出されまくっています。そんな中でも出かけたいyamanekoとしては、猛暑の街を抜け出して涼しいところで自然観察をすることにしました。場所は篭ノ登山(かごのとやま)(2228m)。標高2千mオーバーの山なので、それなりに涼風くらいは吹くのではと期待したわけです。
ちなみに、標高だけ見ると健脚向けの山と思われがちですが、ほぼほぼ山頂近くまで車で上がれるので、悪天候でもない限り実質的には初級者向けの山です。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
篭ノ登山は長野県と群馬県の境にあり、東京から向かうと軽井沢の更に先になります。今回は移動に時間がかかるので、前日のうちに長野県側の麓の小諸に入り、一泊してから登ることにしました。ということでのんびり準備をして午後2時半に自宅を出発。給油をしてから高速へ。圏央道、関越道、上信越道と走り継いで、小諸に着いたのは5時半過ぎ。佐久盆地も十分に暑く熱せられていました。
上の写真は、翌朝、ホテルの窓から撮ったもの。ここから稜線までの標高差は1千mほどあります。稜線上の鞍部に高峰高原、湯の丸高原といったスキー場を中心とした観光地があるので、そこまで車道が整備されていて直接車で上がることができるのです。
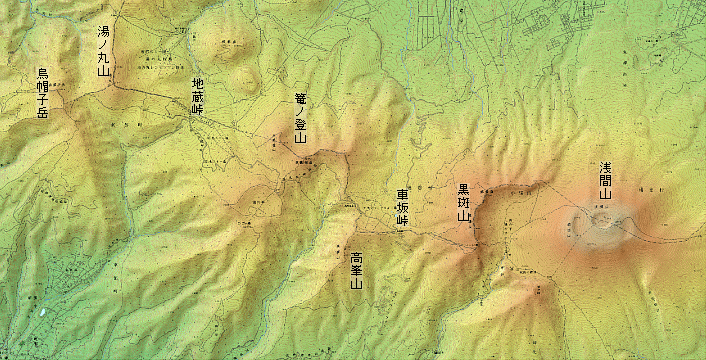 |
Kashmir3D |
東西に伸びるこの稜線を俯瞰すると、南側が急峻な傾斜で北側がなだらかな傾斜となっているいわゆる「片峠」の地形。したがって、車坂峠の北側に高峰高原が、同様に地蔵峠も北側に湯の丸高原が、それぞれ広がる形となっています。
さて、午前8時にホテルを出て、チェリーパークラインという道を走って斜面を直登するように(イメージです)稜線に向かいました。車坂峠で稜線に出るとそこが高峰高原。そこからは篭ノ登山の山腹をトラバースするように付けられた林道を走ります。この林道が久々に走る砂利道。道は整備はされていますが自分が巻き上げた砂埃で車が真っ白になりました。
| ビジターセンター | 池の平駐車場 |
そして9時10分、野山歩きのベースとなる池の平駐車場(標高2060m)に到着しました。後で知ったのですが、西側の湯の丸高原から駐車場にアクセスする林道は舗装路だそう。うーむ、情報収集が足りていませんでした。どうりでまったく砂埃を被っていない車がたくさんあると思いました。
| 2つのピーク |
駐車場から眺めた篭ノ登山。東西2つのピークからなっていて、右が東篭ノ登山(2228m)、鞍部を挟んで左が西篭ノ登山(2212m)です。
なお、写真手前の運動場のようなところは、一般駐車場の一段下にある観光バス用駐車場です。
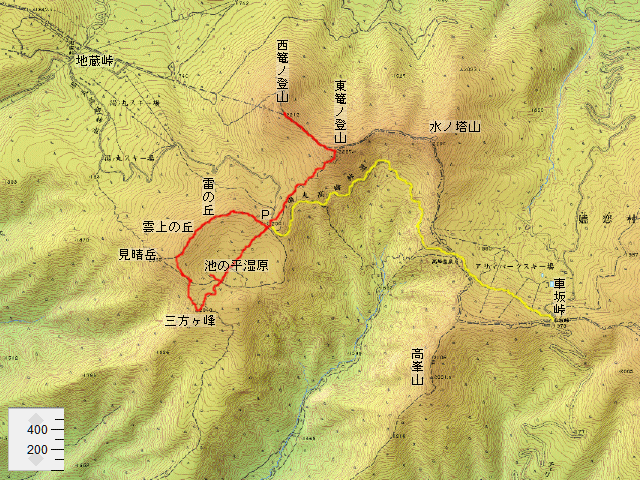 |
Kashmir3D |
今日のコースは、まず池の平駐車場から東篭ノ登山を経由して西篭ノ登山に登ります。同じ道で下山して来て、次に池の平湿原へ。湿原の縁に当たる三方ヶ峰まで行ってから、北側を巻く尾根道を通って駐車場に戻ってくるというものです。山の花、湿原の花、そして広々とした眺望。今日はいろいろ楽しめそうです。
| 登山口 |
準備が整ったところで登山開始。時刻は9時20分です。
| イブキフウロ |
最初に出会った花はイブキフウロでした。花弁の先端に切れ込みが入るのが特徴です。
| キバナノヤマオダマキ |
樹林の中に入るとキバナノヤマオダマキが。幽玄を感じさせる姿です。「キバナノ」と名がついているのは濃紫色のヤマオダマキの黄花品だから。自然界では白花品というのはままありますが、黄色に変異するものもあるんですね。
木漏れ日の下を歩くのは気持ちいい。出掛けに駐車場の人に熊出没の情報を聞いてみたのですが、「このあたりでは聞かないねえ」とのことでした。標高が高いのでクマもやって来ないということか。
| シナノオトギリ |
シナノオトギリはオトギリソウの仲間のうちでも標高の高いところに生えるもの。それにしても花冠から雄しべが飛び出しすぎです。これではかえって受粉しにくいのでは。
| 東篭ノ登山 |
木立の向こうに東篭ノ登山が見えました。これからあのピークに登ります。
| カキラン |
これはカキランでは。残念ながら開花にはまだ間があるようです。yamanekoの好きな花ですが、開花しているものにはもう20年くらい出会えていないです。
だんだん傾斜がきつくなってきました。
| ゴゼンタチバナ |
足元にゴゼンタチバナ。白い花弁のように見えるものは総苞で、中央にある雄しべみたいなもの一つ一つが花です。総苞が虫へのアピールの役割を担っているんでしょうね。
| コイワカガミ |
このテカテカした丸い葉はコイワカガミのもの。花の時期はもう終わっています。
| グンバイヅル |
このグンバイヅルは初めて見る花です。オオイヌノフグリと同じゴマノハグサ科。茎は蔓のように地面を這って、各節から根を張るという成長の仕方で、その節から花茎を伸ばして花をつけるという構造です。この花に出会えただけで遠路はるばるやって来た甲斐があるというものです。
登山道の傾斜は更に増してきました。加えて岩がゴロゴロしてきて、若干歩きにくくなってきました。
| ジンヨウイチヤクソウ |
イチヤクソウの仲間、ジンヨウイチヤクソウです。これも初めての花。ジンヨウとは漢字で「腎葉」と書き、丸っこい腎形をしていることによります。確かに普通のイチヤクソウの葉とは違うのが分かります。
頭上が開けてきました。こうなると直射日光が厳しいです。ただ、明るい環境を好む植物が出てくるので、それはそれで楽しみでもあります。
| タカネニガナ |
タカネニガナです。ハナニガナの高山型で、根生葉が長いヘラ型になるのが特徴です。
夏空に白い雲。いよいよ山頂も間近のようです。
| ミネウスユキソウ |
ミネウスユキソウはエーデルワイスの仲間です。白い花弁のように見えるものは苞葉といい葉の変化したもの。花はその中心に数個付いています。名前は、葉の上に薄雪が積もったようということで薄雪草。ミネは峰で、高山に咲くという意味です。
| コケモモ |
美味しそうなコケモモの実。ジャムやアイスなどに加工されて観光地の売店などで売られていますが、もともと野生ではそんなに多くあるものでもないので、きっとどこかで栽培しているのだと思います。それともコケモモ「風味」とかの商品なのか?
| 東篭ノ登山山頂7 |
10時10分、東篭ノ登山の山頂に到着しました。人影はまばらです。とりあえず休憩を。
| 東〜南方向 |
東の方角には浅間山の大きな山影が。外輪山の黒斑山も見えています。麓に向かって流れる稜線上のピークは高峯山。その遥か向こうには佐久平が広がっているのが見えます。
浅間山は驚くほど大きな山で、以前住んでいた新宿の自宅からもその姿を見ることができました。直線距離で130kmくらい離れているのですが。
| 南〜西方向 |
南側、眼下には山上の楽園みたいになっている池の平湿原。写真右端(西方向)のピークがこれから向かう西篭ノ登山。その左奥にあるのが湯ノ丸山。更にその左奥の山塊が烏帽子岳です。ここ東篭ノ登山から最奥の烏帽子岳までの距離は5kmほどになります。
| 北方向 |
こちらは逆に北方向。見えている範囲の大部分は群馬県になります。目の前の赤茶けた山肌を見せている山は水ノ塔山。篭ノ登山から高峰高原に伸びる稜線を成している山です。奥に広大な農地が広がっているのが見えますが、これは高原野菜で有名な嬬恋村あたり。その背後に四阿山や草津白根山などの山並みが横たわっています。
| ミヤマアキノキリンソウ |
東篭ノ登山の山頂で眺望を楽しんでから次は西篭ノ登山に向かいます。
これはミヤマアキノキリンソウ。
| 西篭ノ登山へ |
手前に西篭ノ登山。その左奥に湯ノ丸山。更に左奥に烏帽子岳です。ああ、夏空がきもちいい!
両側から背丈を超える木々が迫る小道。それを急傾斜で下っていきます。あまりの角度に、後でここを登るのかとうんざりしました。
| 鞍部 |
ほどなく鞍部に出ました。明るく開けています。
南側が砂礫地になっていて、ここにコマクサが自生しているようです。
| コマクサ |
花の盛りは若干過ぎていた感じでしたが、見える範囲内に何株かは元気なものもありました。
| リンネソウ |
鞍部を過ぎて再び樹林帯へ。ここからは上りです。
これはリンネソウ。はじめて出会う花です。亜高山帯から高山帯の林内に生えるものだそうで、基準標本(学名を付ける際に元になった標本)はラップランドだそうです。そんな寒冷地で生きている植物なんだと感心しきり。
| 西篭ノ登山山頂 |
10時50分、西篭ノ登山の山頂に到着しました。誰もいません。
| ハクサンオミナエシ |
休憩を兼ねて植物観察を。これはハクサンオミナエシ。よく似るキンレイカとの相違点は花冠の後ろに長い距があるかないか。距があるのがキンレイカです。
そうこうしているとご夫婦と思われる二人連れの登山者が現れて、しばらく雑談を。こういうところだとなぜが気軽に話しかけられるんですよね。
| 東篭ノ登山 |
さて、東篭ノ登山にもどります。また鞍部まで下ってそこからの登り返しが待っています。
| ハクサンシャクナゲ |
ハクサンシャクナゲの残り花。他の花序はもう花期を終えてみんなしぼんでいました。
再び鞍部に到着。さあまたあの急傾斜が待っています。
| |
ムシカリ。葉が虫喰いで穴だらけになるので「虫喰われ」からきた名前だそうです。別名をオオカメノキともいいます。若い実ができていました。
東篭ノ登山の山頂は広々としています。けっこう人影が見えますね。
| イワインチン |
これはイワインチンですね。開花は秋です。初めて出会ったのは17年前のこと。篭ノ登山の隣りの黒斑山でした。
| 現役の活火山 |
東篭ノ登山の山頂には数グループが休憩していました。yamanekoも小休止。
浅間山の火口部をアップで見ると…、白煙(水蒸気?)が上がっているのが分かります。まさに生きているんですね。現在、噴火警戒レベル2で、火口周辺には立ち入り規制がかけられています。
| 下山開始 |
さて、下山にかかります。滑って捻挫などしないように気をつけて下らなければ。
| オンタデ |
亜高山帯に生えるタデの仲間、オンタデです。雌雄異株で、これは雌株のようです。
| ホシガラス |
おお、ウラジロモミの枝先にホシガラスが。こちらのことは認識しているようでしたが距離が20mほどあったのでリラックスしていました。カラスの仲間なのでダミ声で鳴くとのこ。そういえば生で聞いたことはないような気がします。
| ハクサンシャクナゲ |
ここにもハクサンシャクナゲの残り花がありました。花序の大きさはソフトボールくらいで、なかなか豪奢な雰囲気です。
だんだん傾斜が緩くなってきました。森の中を歩くのは気持ちいいです。
| 寄り合い所帯 |
木の根元部分の土が侵食されず盛り上がるように残っていて、そこにたくさんの種類の植物が寄り集まって生えていました。木の根がしっかりと土を保持しているからでしょうね。こういうのを見るとなんか生命の力強さを感じるんですよね。
| 下山完了 |
12時ちょうど、登山口まで戻ってきました。登って降りて2時間40分ほどかかったことになります。
さて、この林の中のベンチで昼食を取って、午後は池の平湿原を歩きたいと思います。今度はまた違う植物に会えるでしょう。楽しみです。(後編に続く)