
城ヶ島 ~南風が春を連れてきた(後編)~
 |
(後編) |
【神奈川県 三浦市 令和7年3月22日(土)】
強い南風が吹いた関東地方。いやな花粉や黄砂だけでなく春本番も連れてきたようです。そんな中で野山歩きに出かけた先は三浦半島の先端にある城ヶ島。その後編です。(前編はこちら)
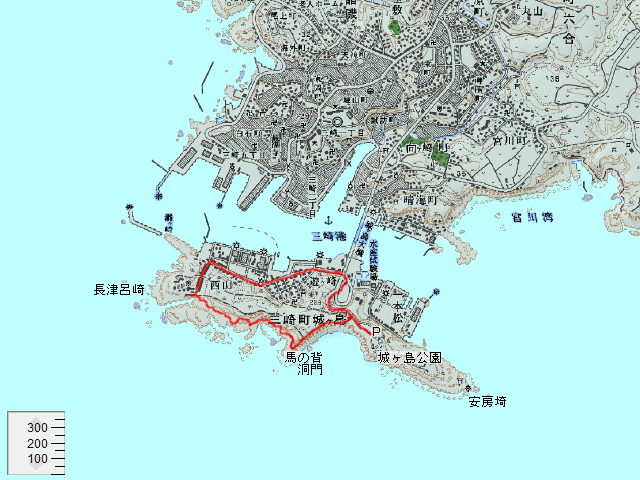 |
Kashmir3D |
午前10時に城ヶ島公園の駐車場をスタートし、海食崖の上のハイキングコースを歩いて馬の背洞門で浜に下りました。ここから磯を歩いて時計回りに島を半周します。
| 馬の背洞門 |
時刻は11時20分。馬の背洞門を後にして海岸を歩いていきます。何かおもしろい植物はないかと探しながら歩くのですが、岩場や砂地にはほとんど見られないので、もっぱらその背後の藪との境界辺りを辿っていきます。
| ハマダイコン |
ハマダイコンの花が咲いていました。海岸の砂地に生えるアブラナ科の植物です。大根が野生化したものと言われていて、肥料を与えて育てると普通の大根になるのだそうです。それにしても、なぜわざわざ海岸の砂地で野生化したのだろうか。
| ハマニガナ |
こちらも砂浜に生えるハマニガナ。地上部は小ぶりですが地下茎を広く張り巡らしているのだそうです。強い風が吹きつける砂浜で生き抜く知恵ですね。ところで、海辺の砂浜に生える植物には「ハマ」の名を冠するものがいくつもあります。これは浜に生えるニガナに似た植物なのでハマニガナですね。
| ソナレムグラ |
ソナレムグラは砂地から少し陸側の土が主体の場所に生えます。地面に張り付くように広がっていて、今は肉厚の葉がやや褐色を帯びていますが、初夏になると濃い緑色になって、その後白く小さな花を付けます。荒磯で風雪に耐え地面に低くなびくように生えている松のことを「磯馴松」(そなれまつ)というそうで、そこからソナレの名を冠しているとのことです。ムグラは「葎」と書き、ヤエムグラとかカナムグラとかと同じアカネ科の一グループに用いられてる名前です。
| ラセイタソウ |
この微細な皺が寄った質の厚い葉はラセイタソウのもの。この春に展開した新しい葉のようです。ラセイタとは毛織物の名前で、このシワシワな質感がラセイタに似ているのだそう。yamanekoはその毛織物を手に取ったことはありませんが、ヨーロッパから入ってきた布で、やや高級な合羽や羽織の素材として用いられたそうです。教会の神父さんがまとっているマントみたいなものの素材がそれかも。
時々波打ち際も歩いてみます。潮が引いた後にできるタイドプールは一時的な閉鎖空間。イソギンチャクなどがのんびり過ごしていました。子供の頃、イソギンチャクの触手の真ん中部分に指の腹を当てる遊びがありました。きゅっと吸い付くような感覚が面白かったのです。
| 海辺の風景 |
砂浜から陸側を眺めるとこんな風景。砂と土が混ざって押し固められたような荒れ地に丈の低い植物が広がっています。その奥に高さ30mほどの崖があり、まるで剪定して整えたかのような照葉樹林が一部を覆っています。強い日差しと潮風の下で極相に達したかのような風景ですね。それぞれの条件下でそれに適した(耐えられる)種が生きているということでしょう。
| イソギク |
再び歩みを進めます。これはイソギクの葉。白く縁どられているように見えますが、これは葉の裏が銀白色で、縁の部分にそれが見えているからです。分布は限られていて、千葉県の犬吠埼から静岡県の御前崎までの沿岸部・島しょ部のみで見られるのだそう。南関東に住んでいるとお馴染みさんなんですが。
| タイトゴメ |
この大仏の螺髪のような植物はタイトゴメです。さっきのソナレムグラ同様に今は褐色を帯びて地面に伏していますが、夏になると緑色になって高さも10cmくらいまで伸びます。花はマンネングサに似た黄色の星形です。名前は「大唐米」と書き、粒々状の葉の様子から付けられたもの。大唐米は小粒で味は悪いが炊くとよく増えるのだそう。すなわち大唐米とは今で言うところの外国産米のことだったようです。
| ボタンボウフウ |
樹木のようなしっかりとした茎を持つボタンボウフウ。葉がボタンの葉に似ているからその名が付いたそうです。植物の名前には「ボタン」を用いたものがけっこうあります。ボタンヅルとかルイヨウボタンとか。写真のものは去年の花や葉がドライフラワー状になって残っている状況です。
| マルバグミ |
マルバグミ。葉にも果実にも短毛が密生していて、銀白色を帯びています。ちょうど果実が成熟しつつありました。今は紡錘形ですがもう少しぷっくりするはずです。
| ハマエンドウ |
エンドウの花に似ていて海岸に生えるからハマエンドウ。マメ科に特有の蝶形花です。果実もエンドウに似ていますが野生種だけあって大きさも小さく、鞘の中の豆(種子)も薄く小さいです。逆に、エンドウの方が食用に適すよう改造されたものということですね。
姿勢がかがみがちなので、たまには腰を伸ばして辺りの風景を見回してみましょう。まずは歩いてきた方向。馬の背洞門がずいぶん遠くになりました。そこからここまで、海、岩場、砂地、荒れ地、崖といった構成がずっと続いています。
視線を正面に向けると太平洋。広々として爽快です。よく見ると黒潮の長大な流れが…見えるわけないか。
そしてこれから向かう方向。ごつごつした岩場ですが、一応ハイキングコースとされているので、歩くのに困ることはありません。
| テリハノイバラ |
これはテリハノイバラですね。漢字では「照葉野茨」。葉に光沢があるノイバラで、見た目そのまんまのネーミングです。テリハノイバラはバラの園芸品種の接ぎ木用台木に使われるのだそうです。
| スカシユリの蒴果 |
スカシユリの蒴果がドライフラワー状になったもの。これはこれで花みたいなシルエットですね。
| コウボウムギ |
これはコウボウムギ。別名を「筆草」というのだそうです。昔、地中にある古い葉の繊維を筆に用いたそうで、筆といえば弘法大師ということでの名前だそうです。「弘法も筆の誤り」とか「弘法筆を選ばず」とかの諺があるとおり。ムギは穂の様子からの命名です。
| ツルナ |
これはツルナですね。肉厚な葉はおひたしなどで食用とされていたそうです。漢字では「蔓菜」。名前に「菜」が付く植物はだいたい食用とされていたとのことです。海外では「ニュージーランドのホウレンソウ」という意味の名前も付けられているそう。花は1cm弱と小さいです。
| 城ヶ島灯台 |
いつの間にか島の西端にある城ヶ島灯台の近くまでやってきていました。
ここから北側に向けて丘を越え、商店や民家のある西山地区に向かいます。
| 昼食 |
時刻は12時過ぎ。途中の食事処で昼食をとることに。今日のもう一つの目的である三崎マグロを味わいました。ここにもインバウンドの波が押し寄せていて、並んでいる列には外国人の方も多かったです。
| 西山地区 |
食後、島で一番賑やかなエリアへ。以前、正面の建物内の店でもマグロを食べたことがあります。今日、そこにも入店を待つ列ができていました。
| 城ヶ島漁港 |
城ヶ島漁港を左に見ながらのんびり歩いていきます。対岸が本土側の三崎漁港。
| メジロホオズキ |
ここからは道端の植物を見て歩きます。
これはナス科の植物っぽいですが、yamanekoには何なのか分かりませんでした。帰宅後図鑑で調べても掲載がなかったのですが、ネットで画像検索したところ、メジロホオズキではないかということに。日本にも自生しているようなのですが、それが在来のものなのか帰化したものかもよく分かりませんでした。
| オオキバナカタバミ |
こちらは園芸種が逃げ出したもの。和名ではオオキバナカタバミというそうです。確かにカタバミに似た形の花で、大きさはカタバミの3倍くらい大きかったです。
| カジイチゴ |
これはカジイチゴの葉。まだ伸びきる前のようでした。今は柔らかく瑞々しい感じがします。
| フキ |
これはフキ。食用にするフキノトウがそのまま成長するとこうなります。これでも十分に鑑賞に堪えますね。
| オオイヌノフグリ |
路傍のオオイヌノフグリ。花茎が立ったものもあるので、タチイヌノフグリかもしれません。それにしてもこの花には万人を微笑ませる力があるように思います。
| テイカカズラ |
茂みに何かがぶら下がっていますね。これはテイカカズラの果実。鞘が縦に裂け、らせん状によじれて開いているところです。中にあった種子にはタンポポのような綿毛が付いていて、風に乗って遠くまで飛ばされていきます。写真のものも既に種子は残っていませんでした。
丘を上る坂道。この先にドリーム号Ⅲを停めた駐車場があります。
| 城ヶ島公園 |
13時40分。城ヶ島公園の駐車場に戻ってきました。スタート時よりもずいぶん車が増えています。
今日は、沿岸部での野山歩きということもあって、強風ではありましたが、春の訪れを感じました。この先、寒の戻りが何回かはあるでしょうが、春は確実にそこまで来ています。いや、もう春本番といっていいですね、少なくともここ城ヶ島では。暖かい潮風がそれを教えてくれていました。