
城ヶ島 ~南風が春を連れてきた(前編)~
 |
(前編) |
【神奈川県 三浦市 令和7年3月22日(土)】
数日前に降雪を伴った南岸低気圧が通過し、その後は晴天が続くものの気温はあまり上がりませんでした。それが今日は南風が吹いて気温も上がるとの予報。花粉に加えて黄砂もバンバン飛んできていますが、ここはより暖かいところに行って自然観察を、ということになりました。場所は三浦半島の先端、城ヶ島です。ここでの野山歩きはかれこれ18年ぶり。ずいぶん久しぶりです(その間に単にマグロを食べに来ただけということは何度かありますが)。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午前8時、ドリーム号Ⅲで出発です。渋滞の保土ヶ谷バイパスから横浜横須賀道路に入り、衣笠ICで三浦縦貫道路へ。この辺りまで来ると車の量も少なくスイスイ走れました。ところで三浦縦貫道路の料金収受は未だに有人ゲート。やっぱり地元の雇用創出のためでしょうか。一般有料道路もETCが珍しくなくなった今となっては、一旦止まって小銭を出すのはやっぱり面倒です。
| 城ヶ島公園 |
そして10時ちょうど、城ヶ島公園の駐車場に到着しました。今日はここに車を停めさせてもらいます。一日500円で、島内に5か所ある公共駐車場を利用できるとのことでした。商業施設のある方へも車で移動できますよということですね。
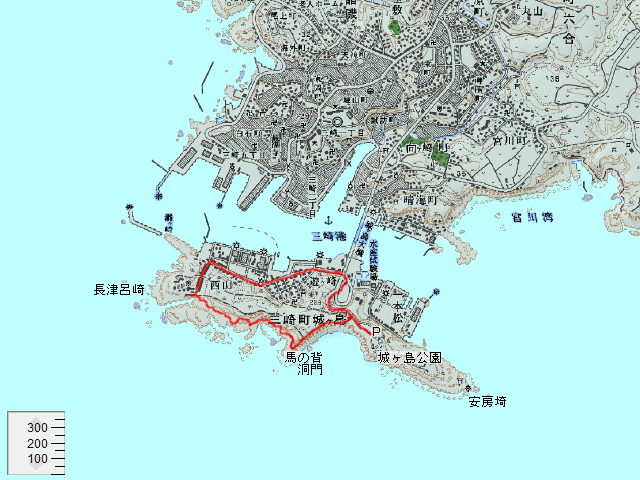 |
Kashmir3D |
島は東西に細長く横たわっていて、対岸にある三崎漁港の天然の防波堤になっています。外洋に面した島の南側は厳しい環境で、集落などはなく、海食崖の下には磯や小さな砂地が帯状に連なっています。島の丘の高さと対岸の丘の高さが約30mとほぼ同じなので、元は一体だったのでしょうね。
今日のルートは、駐車場からしばらく海食崖の上を歩き、馬ノ背洞門のところで島の南側の海岸に下りていきます。その後は海岸線に沿って島の西側まで磯を歩き、対岸に面した西山地区へ。こちら側には商店や民家が連なっています。そこからは車道沿いに歩いて、駐車場に戻ってくるというものです。
| カントウタンポポ |
まずは駐車場の周辺から。春に咲き出す花、タンポポです。これはカントウタンポポでした。カントウタンポポは在来の種で、近年外来種のセイヨウタンポポに押され気味なのだとか。
ところでこのタンポポ。可愛らしい響きを持つ名前ですが、その由来には諸説あるとのこと。有力なものとしては、鼓を打つ「タン!ポポン!」という音からという説があるそうです。タンポポの茎を管状に切って両側に数か所切り込みを入れると切った部分が反り返って全体として鼓のような形になり、これが子供の野遊びの定番ツールだったそう。このことから別名を「鼓草」とも言ったそうです。つまりはタンポポと鳴る鼓に似た花だから「タンポポ」となったということです。
| 土筆 |
これも春の定番、土筆です。こんな姿をしていますがシダ植物なんですよね。植物の名前としてはスギナで、土筆はその胞子葉。一般にスギナと呼ばれるものがスギナの栄養葉になります。
| カタバミ |
この黄色の花はカタバミですね。生命力が強く、過酷な環境下でも生き生きと育っています。わが家の植木鉢群にもいつの間にか侵入して蔓延っています。
| オオバヤシャブシ |
歩道の脇にぽつねんと立っていたのはオオバヤシャブシ。ちょうど雄花序が満開の状態で、既に花粉を飛ばし終え地上に落ちているものもたくさんありました。ぱっと見、大型のイモムシみたいです。枝に残っている楕円形のものは昨年の果穂。松ぼっくりみたいに細かい隙間に堅果がたくさん詰まっていたものです。
| シャリンバイ |
これは生け垣として植栽されていたシャリンバイの果実。ブルーベリーくらいの大きさで、若干白い粉を吹いている様子も似ています。シャリンバイには幹が直立して小高木になるタイプと、株立ちになって写真のように背の低いままのタイプがあるそうで、前者は葉先が尖り、後者は丸っこいのだそうです。生け垣にするなら背の低いタイプが適していますね。名前は「車輪梅」と書き、ウメと同じバラ科の植物なのでウメとは親戚くらいの関係です。
| タブノキ |
タブノキの芽吹き。花芽と葉芽が一緒に入っている混芽というタイプの冬芽で、今まさにそれらが展開しようとしているところです。タブノキは北海道を除く地域で見られるそうですが、比較的暖かいところを好む樹木で、関東地方以西では内陸部でも見られるものの、東北地方の分布は沿岸部に限られるのだそうです。海洋は熱源ですからね。確かに海辺の照葉樹林で見かけることが多いです。
| 「エサ、置いてっていいよ」 |
ネコが居住まいを正してこっちを見ていました。「エサ、くれるんなら置いてっていいよ」と、あくまでもネコたるプライドを維持しつつおねだりをしている感じでした。
| ツワブキ |
洗面器くらいの大きさの葉を持つツワブキ。花茎は既に枯れていますが、葉はつやつやしています。これが「艶蕗」の名の由来。葉は厚みがあり触るとひんやりとしていて、子供の頃、腕や足などに火傷を負ったときにおばあちゃんがツワブキの葉を採ってきて患部に貼ってくれた記憶があります。全国的に行われていたことなのか気になってネットで検索してみたところ、葉には強力な抗菌作用のある物質が含まれているそうで、葉をすり潰したものを患部に塗るのが正しい利用方法とのことでした。そういわれてみると貼ったのか塗ったのか、記憶が揺らいできました。
| 城ヶ島ハイキングコース入口 |
駐車場の手前から城ヶ島ハイキングコースに入ります。
| ヒメオドリコソウ |
ヒメオドリコソウ。植物の名前に「ヒメ」(姫)と付く場合は「小さな」という意味で、ヒメオドリコソウは小さな踊子草という名前になります。確かにオドリコソウをぎゅっと圧縮したような姿をしています。いずれもシソの仲間です。
| キュウリグサ |
こちらはキュウリグサ。普通に歩いていると普通に見逃す小さな花冠です。その大きさはわずか3、4mm。でもルーペで覗いてみると、デザイナーの村上隆さんの描くポップな花のようで、ちょっとした驚き。
| アケビ |
ハイキングコースの両側には背丈の倍くらいの笹が密生していて、まるで細長い回廊を歩いているようです。
これはアケビの花序。伸びきる直前といった状況でしょうか。で、この写真を撮っていると、yamanekoの後ろをウエディングドレスを着た女性とタキシード姿の男性が通って行きました。一瞬状況が呑み込めませんでしたが、おそらく婚礼写真の前撮りをしていたのだと思います。この先に見晴らしの良いところがあるので。それにしても今日は相当風が強かったろうに。
| ハイキングコース |
ハイキングコースの先が開けているようです。両側の木立がゴーゴーと風に揺さぶられています。
視界が開け、道幅も広がりましたが、両側には依然背丈ほどの笹が茂っています。
| ウミウ展望台から |
途中、「ウミウ展望台」というビュースポットが。東に向かって延びる高さ30mほどの海食崖が望めました。その崖がウミウの繁殖地なのだそうです。今日はあの丘の上にある駐車場からここまで歩いてきました。駐車場は防風林に囲まれていて、それなりに風が強いことは木々の様子から分かっていましたが、この展望台は完全に吹きっさらしで、大洋から吹き付ける強い南風にあおられそうになるほどです。
| シロダモ |
シロダモも照葉樹林を代表する樹木です。今年芽吹いた若い葉は黄金色の軟毛に覆われていて、ビロードタッチが気持ちいいです。この軟毛は成長するときれいに抜け落ち、その後は固くテカテカした濃緑の葉になります。
| モチノキ |
モチノキの花序。まだ蕾の状態です。雌雄異株で、これは雄花序だと思います。モチノキの「モチ」は鳥糯(とりもち)のこと。この木の皮から鳥糯を作ることからだそうです。yamanekoの記憶でも鳥糯を作ったり使ったりしたことはないです。昭和30年代前半までの生活道具でしょうか。
| 分岐 |
10時50分、分岐が現れました。右に行くとこのまま台地の上を進む道に。yamanekoたちは直進し、海岸に下りていきます。
| エノキ |
分岐に立っていたエノキ。去年の実が枝にたくさん残っていました。エノキは里の木というイメージで、あまり海の近くで見かけた覚えがないのですが、きっとそんなことはないんだと思います。
木立の隙間から海が見えました。風が強いせいか白波が立っていますね。この辺りから道は急な下りになります。
写真ではいま一つ分かりにくいですが、道はかなりの急傾斜。つまづいたらそのまま転げ落ちそうなほどです。
おお、海が見えてきました。風がゴーゴーと鳴っています。
| 赤羽根崎 |
視界が一気に広がりました。柵があるので安心ですが、結構な高さがあります。
| トベラ |
トベラの葉と果実。葉は固く厚く湾曲していて、いかにも沿岸部の過酷な環境に順応した姿をしています。果実は去年のもので、熟して果皮が開裂し、中から粘りのある赤い種子が顔を出している状況。
西側にはこれから歩く波打ち際が見えています。波頭が白いです。
足元を見るとかなりの高さがあり、磯に砕けた白波が渦巻いています。2時間ドラマだと真犯人が自白するシチュエーションですね。
階段から浜に下りていきます。結構な数の観光客がいる模様。
| 馬の背洞門 |
浜に下りるとこんな風景が。ここは馬の背洞門といい、長い時間をかけて波に削られできた自然の造形物なのだそうです。風化が進んでいて洞門の上の岩に立ち入ることは禁止。yamanekoたちは写真左端辺りに設けられていた階段で下りてきました。
正面に回り込んでみると、おお、洞門越に向こうの水平線が見えているではないですか。元旦に初日の出が見えたりすると更にいいですね。
波打ち際では波が砕けて東映のタイトルバックみたいになっていました。ここの平らな磯もあの波が何千億回と打ち寄せて削って造り上げたものなんでしょうね。
| タイドプール |
磯のあちらこちらに小さなタイドプールがありました。覗き込むと小さな魚やカニなどが慌てて隠れていました。
| イソヒヨドリ |
yamanekoの家にもよくやってくるイソヒヨドリ。名前からすると本来はこういう環境で見られる鳥なのかもしれません。ここには水を飲みにやって来たのか。それ塩水だぞ。
| 上昇気流 |
強い南風が海食崖を駆け上がり、上昇気流を作っていました。それに乗っかって弧を描くトビの群れ。数えると10羽以上も。なんだこれ、多すぎないか?と思ったら、その真下で高校生のグループがバーベキューをしていました。なるほど、その食材を狙っていたのか。ときおり急降下してくるトビに高校生たちも戦々恐々としていました。バーベキューどころではないだろうに。ただ、それも楽しんでいるようで、若いっていいなと遠い目になるyamanekoでした。好々爺か。
さて、ここから海沿いを歩いていきます。(後編に続く)