
稲含山 ~信仰を育んだ偉容の山(前編)~
 |
(前編) |
【群馬県 下仁田町 令和4年6月25日(土)】
ここのところ梅雨明けでもしたかのような猛暑、炎暑の日が続いています。テレビでも熱中症に警戒するよう繰り返していて、それがまた体感気温を上げているような気もします。暑さの”名所”群馬県の伊勢崎市では、昨日最高気温40℃を記録したとのこと。まだ6月なんですが。
さて、今月の野山歩きは、群馬県南西部にある稲含山(1370m)。短いアプローチで大絶景を楽しめるということで、この暑さの中ではもってこいの山です。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午前7時前にドリーム号Ⅲで出発。圏央道に乗ると既に八王子JCTに向けて渋滞していましたが、車の多くは中央道に向かっているようで、JCTから先はスイスイと流れていました。鶴ヶ島JCTから関越道に入っても順調。更に藤岡JCTで上信越道に入ってからはガラガラでした。
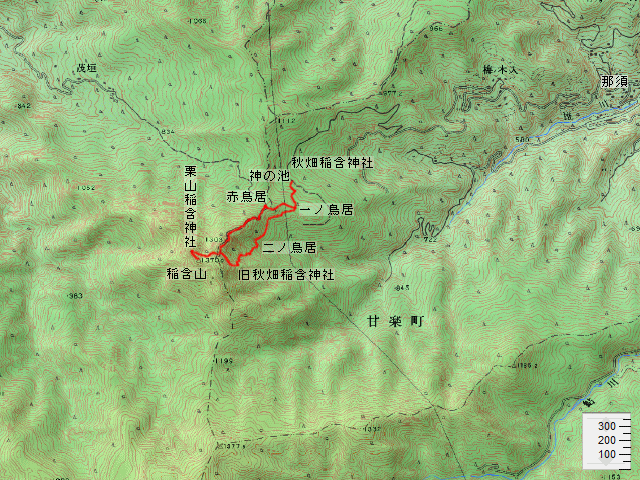 |
Kashmir3D |
富岡ICで高速を下りて県道46号線へ。甘楽町の山間に向かって南下していきました。そして、最後の集落「那須」から山肌を縫う林道に入り、稲含山の登山口に向けて高度を上げていきます。対向車が来たら一発アウトのような狭い道でした。稲含山は甘楽町と下仁田町のほぼ境に位置していて、今回は甘楽町側からアプローチしたわけです(下仁田町側からの林道はかなりハードな状況との情報があったので。)。
| 秋畑稲含神社 |
山側から枝が飛び出し、頭上からは蔓が垂れ下がってくるようなワイルドな林道を進んでいくと、唐突に神社がありました。比較的新しい社殿です。
ここは「秋畑稲含神社」といい、山頂近くにあった稲含神社を平成19年にここに下ろしたものだそうです。秋畑とはこの辺りの字の名前のようです。いったん下車して、今日の安全を祈願しました。
| 神の池公園 |
神社のすぐ先に駐車スペースがあり、そこが今日の野山歩きの起点になります。この辺りは「神の池公園」ということで整備された形跡があり、いや現役の公園だと思うのですが、いかんせん利用者が少ないのかかなり自然に帰りつつある感じでした。ちゃんとトイレもあり、その新しさから神社の移設と同じタイミングで作られたのではと推測。ひょっとしたら公園整備もそのタイミングだったのでは。
ちなみに、このまま林道を登って行くとほどなく峠に出て、そこにはかなり広い駐車広場があるようでした。そこからも登山道が出ていますが、今回はもともと行程が短いので、ここからスタートすることにしました。
| 登山口 |
登山口はトイレの手前(駐車スペースの正面)にありました。準備運動を入念に行い、日焼け止めをしっかりと塗って(日焼けは疲労の元なのです。)、9時45分、スタートしました。
| 神の池 |
登山口から一段上がったところに池が。これが神の池でしょうね。奥には東屋もありのんびりできるようになっていました。
ところで、もともとは山頂近くにある神社の祭礼などの際に地元の人々が登ってきていて、ここにあった池を神聖視していたということは想像できるのですが、近年ではおそらく登山者以外人も行き交わないここを「公園」として整備しようと考えたのはなぜだろう。「公園」とすることで何かと人の手が入りやすく、神域が藪に覆われてしまうことが防げるということでしょうか。
| ヤマアジサイ |
木立の中をゆっくりと登って行きます。これはヤマアジサイの若い花序。装飾花が出始めています。
| コアジサイ |
こちらはコアイジサイ。満開の状態ですね。コアイジサイには装飾花がないのが特徴です。
陽射しはギラギラですが、木々の梢がそれをいい感じに遮ってくれていて、快適です。
| 林道 |
しばらく登ると林道を横切ります。写真左側のガードレールの切れ目から上がってきて、写真右側の斜面に続く登山道へ。林道はドリーム号Ⅲを停めた場所からしばらく行ったところで舗装が途切れて砂利道となり、ここに続いています。大きく迂回する林道を登山道がショートカットしている形ですね。この林道をもう少し進むと広い駐車スペースのあるところに出ます。
| フサザクラ |
見上げるとフサザクラの葉が覆い被さっていました。質が薄いのか光を透かすようできれいです。
再び山の中に入り登山道を進みます。前方に大きなヤマザクラの倒木が横たわっていました。
| 一ノ鳥居 |
ほどなく鳥居が現れました。一ノ鳥居です。この道は紛れもなく稲含神社の参道なんですね。
| 分岐 |
鳥居をくぐったところで道は二手に分かれていました。yamanekoは直進。谷の山肌をトラバースするように伸びている「参道」を行きます。ちなみに右手の小径を辿ると、茂垣峠を経て尾根筋を登るルートになります。こちらは下山時に使う予定。
マーブルの木漏れ日。適度に風もあって気持ちいいです。
| ツクバネソウ |
ツクバネソウ。この葉を羽根つきの羽根に例えたというネーミングです。写真の状態から更に5cmくらいの花茎を伸ばして、その先に緑色の花を付けます。
| ヒトリシズカ |
これはヒトリシズカの葉ですね。テカテカしています。花の時期はもう終わっています。
結構な角度の斜面を歩いて行きます。
ここは斜面が崩れていて幅が狭くなっていたところ。山側に手をかけて慎重に通りました。写真は通った後に振り返って撮ったもの。
その先で谷はどん詰まり。登山道は流れの横を更に傾斜を増しながら続いています。
| 小滝 |
谷の源頭には小さな滝がありました。その上を跨ぐように横切って左上に登って行きます。
もう水音は聞こえなくなりました。代わってハルゼミの鳴き声が響いています。
| 二ノ鳥居 |
急な山道を登っていくとまた鳥居が現れました。二ノ鳥居です。
| 「二十二丁」 |
雑木林の登山道沿いに不自然に大きなスギが何本か立っていました。信仰の道なのでむやみに伐採することはなかったのでしょう。そのスギの根元に古い石碑がありました。「二十二丁」と読めたので、神社までの行程を示す丁石のようです。
| |
立ち止まって山肌を見上げると、のしかかってくるような斜度でした。小休止して息を整えます。セミの声しか聞こえない中に一人、逆に静寂を感じるひとときでした。
| マンネンタケ |
これはマンネンタケか。花が少ないのでキノコにも目が行きます。
| オクヤマコウモリ |
まだ丈は低いですが、これはオクヤマコウモリでは。葉が戦闘機のようなシルエットをしています。
頭上に建物が見えてきました。稲含神社でしょうか。この辺りはまだ8合目辺り。深い森の中です。
10時35分、支尾根の上に出てきました。この尾根上にさっきの建物がありました。
秋畑稲含神社の門です。以前は氏子の皆さんがここまで登ってきて祭礼を執り行っていたのでしょう。境内脇にあった解説板によると、この神社は530年ころの創建で、祭神は豊稲田姫とのこと。豊稲田姫は印度から渡ってきて日本に養蚕、稲作を広めたのだそうですが、その際、稲を持ち込むのに苦労し、どこに隠しても見つかってしまうので、口に含んで持ち込んだのだそうです。それで「稲含」なんだ。なるほど。
| 旧秋畑稲含神社 |
門をくぐると社殿が現れました。戸板もはずれて廃社の状態です。
幕末の頃、この神社の領有を巡って下仁田町栗山との間で争いが起こり、結果、甘楽町秋畑が勝ったのだそうです。この時点で稲含神社は秋畑のものとなったのですが、その後栗山が別に稲含神社を建てたことから、向こうを栗山稲含神社、こちらを秋畑稲含神社と呼ぶようになったのだそうです。まあ栗山の人の立場になって考えると、千年以上も信仰していた神社がよそのものになってしまったのですから、「おらが稲含神社」を建てて信仰を繋げたいという思いも分からないこともありません。もともとどちらのものなどと争わなければ単純に「稲含神社」で済んでいたものを。
| 狛犬 |
社殿は朽ちかけていましたが狛犬はまだしっかりしていました。よく来たな、と話しかけられたような気がしました(気のせいです。)。
さて、ここで一休みしたら山頂を目指してもうひと頑張りしましょう。(後編へ続く)