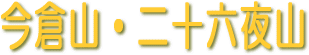
今倉山・二十六夜山 ~道志山塊の絶景展望台(後編)~
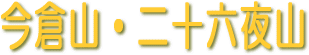 |
(後編) |
【山梨県 都留市 平成25年4月28日(日)】
道志山塊の今倉山から二十六夜山への山歩き、後編です。(前編はこちら)
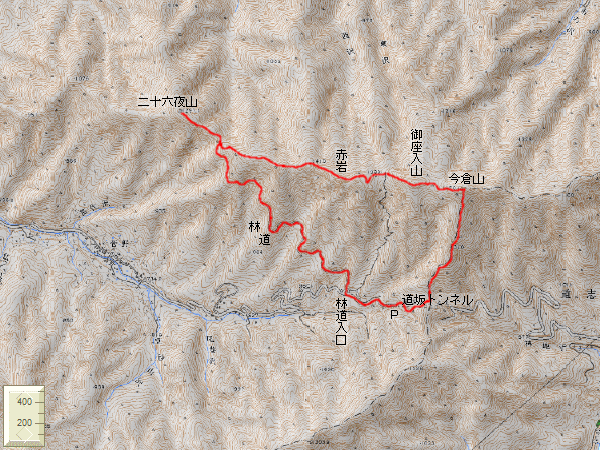 Kashmir 3D |
御座入山の先から富士山の大パノラマを楽しんだ後、赤岩に向かって歩いて行きます。
| 氷点下の証 |
なんと岩陰には霜柱が。夜明け前には気温が氷点下になっていたという証ですね。今、yamanekoは半袖で歩いていますが。
| 鞍部 |
11時20分、赤岩との間の鞍部に到着しました。ここから南に下る登山道がありますが、直進です。
| エンレイソウ |
成長しはじめのエンレイソウに出会いました。まだ高さ15㎝ほどです。見るからに柔らかそうですね。
鞍部からはえっちらおっちらと登っていきます。
しばらくすると細長くなだらかな山頂部に出ました。これといったピークはなく、同じような高さで続いています。それにしても、この風景。日射しは初夏ですが木々の様子は早春です。
| ミズナラ |
おもわず抱きつきたくなるようなミズナラの大木。いったい何歳くらいでしょうか。「私にパワーを…」と妻。
やがて目の前に小さなピークが。この先が赤岩のようです。ちょっと気持ちがはやります。
そして11時40分、赤岩に到着しました。既に何組かの登山者が眺望を楽しんでいます。記念撮影もそこそこにyamaneko達も眺めてみることに。
まずは南から西に向かっての眺望。 富士山が別格であることが誰にも納得できます。
そして西から北へ。大月盆地を挟んだ山並みです。
さらに東から南へ。これまで歩いてきた方角です。
ぐるっと360度。どこを見ても見飽きない、いつまででも眺めていられる風景でした。
絶景の赤岩で昼食をとることも考えましたが、ピークはそう広くない上に、どこに座ってもビューポイントで他の人に迷惑がかかりそうなので(というより落ち着いて食べられそうになかったので)、二十六夜山までお預けということにしました。ここからはまた下っていきます。
なんとも気持ちのいい山歩き。でもこんな季節はあっという間に過ぎていってしまうんですよね。
道ばたでこんなものを拾いました。おそらくヤマドリの羽根だと思います。胸の部分でしょうか、フワフワでした。
| フデリンドウ |
高さ3㎝ほど。フデリンドウは控えめな花ですが、顔を近づけてみるとその造形の美しさに驚かされます。
| ユキザサ |
これはこれから伸びていこうとしているユキザサです。葉がちゃんと光が差す方を向いていて、栄養(糖類)の増産体制を整えていますね。今は縮こまっている花穂もググッと伸びて白い花をたくさん付けるでしょう。
| ブナ |
登山道沿いには興味深いいろんなものがありますね。ブナの若葉にはしなやかな長い毛が密生しています。葉が成長するにつれ取れてしまうのですが、若いうちには寒さなどから葉を守る役目をしているのだと思います。
| 林道 |
赤岩から下ること40分、眼下に林道が見えてきました。
| 二十六夜山 |
林道に下りるとこれから向かう二十六夜山が現れました。こんもりとしていてなんだか優しげな山ですな。
林道を20mほど上ると、二十六夜山への登山口がありました。
山頂に行けば昼食が、という思いから足どりも早くなります。
そして午後1時、二十六夜山の山頂に到着しました。やっほーい、ようやく昼食だ!
| 南方向 |
その前にここからの眺望は、と。
おお、赤岩からのそれに劣らない見事な富士です。
| 北方向 |
そして北側も、大月盆地が一望です。眼下の山は九鬼山ですね。山体をリニア実験線が貫いている山です。南向きは眩しいので、こちらの方を向いて昼食をとることにしました。
| 十十六夜 |
二十六夜山とは変わった名前ですが、山頂の解説板には次のような説明がありました。「山名は、江戸時代に盛んとなった旧暦の正月と七月の二十六日の夜に、人々が寄り合い飲食を共にしながら月の出を待つ二十六夜待ちの行事に由来します。この日の夜半の月光に現れる阿弥陀仏、観世音菩薩、勢至菩薩の三尊の姿を拝むと平素の願いがかなうと信じられ、かつては、この二十六夜山の山頂で、麓の村人達によって、遠く道志山塊から上がる月を拝む月待ちの行事が行われました。」 当時の人々にとって夜中まで遊べる滅多にない楽しみな行事だったんでしょうね。写真の石碑(?)は江戸時代のものだそうです。
| トウゴクミツバツツジ |
山頂では30分ほど休憩。食事を終えて一休みしてから下山開始です。
軽く体を伸ばしてから歩き始めます。途中、斜面に立つツツジを見かけました。そのまま縮小したら趣のある盆栽になりそうな、渋い姿です。近づけないので判然としませんが、たぶんトウゴクミツバツツジではないかと。
| 林道を下る |
山頂から15分で林道に戻ってきました。これからここを下っていきます。写真では奥の方に向かっての上りのように見えますが、実は下っているのです。ところでこの林道、治山作業用のものらしく、一般車両の進入はできないようになっています。この日は休日だったからか作業用の車両に出会うことなく、のんびりと歩くことができました。
カーブを回り込むたびにこんな景色が現れます。全山が淡い色で輝いています。
谷筋に沿うカーブの最奥部がこんな状況に。はじめは何なのかよく分かりませんでしたが、どうやら谷筋に雪が残っていて、その上を落ち葉が隙間なく覆っているようです。今日は山頂部には霜柱はあったものの残雪などはまったくありませんでした。ここでは落ち葉が断熱材の役割を果たし、今でも雪が残っているのだと思います。真ん中の穴は人工的に開けたものか。人が立ち入ると危険ですからね。なにしろ深さは2m以上もありましたから。
| ムラサキケマン |
可憐なムラサキケマンの花。標高が下がってきたしるしですね。
| |
2時40分、林道の終点に到着しました。ゲートの前でピースです。背後に見えている道路を左に300mくらい上ると道坂トンネル。そこでドリーム号が待っています。
いやあ、今回の山歩きは絶景の連続。富士山も十分堪能させてもらいました。花をはじめ様々な面白いものにも出会ったし。大満足の山歩きでした。
帰りはトンネルを抜けて道志の道へ。神奈川県の相模原に出て、東京の多摩ニュータウンを抜けて、渋滞箇所の先にある稲城ICから中央道で帰りました。でもなんだかんだで3時間くらいかかりましたが。