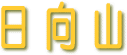
日向山 〜秩父の山里で往く春を惜しむ(後編)〜
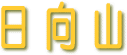 |
(後編) |
【埼玉県 横瀬町 令和6年5月4日(土)】
春と初夏の間で楽しむ野山歩き。日向山の後編です。(前編はこちら)
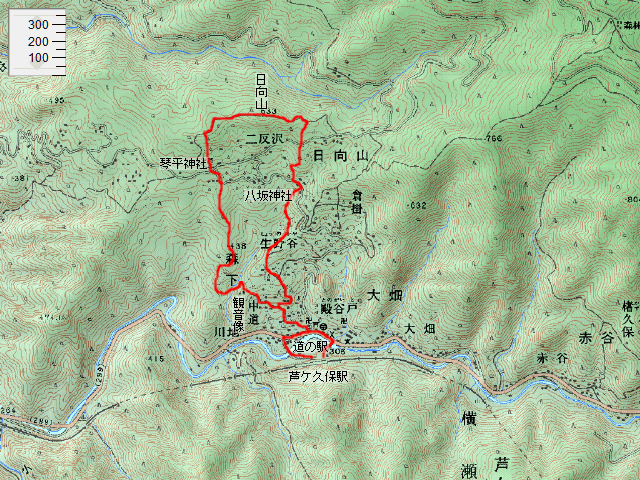 |
Kashmir3D |
9時半過ぎに芦ヶ久保駅に到着。そこから国道を少し歩いて反対側の山の斜面を登り始めました。果樹農園が点在する長閑な野辺の道です。八坂神社を過ぎて、11時35分、日向山の山頂直下までやって来ました。
 |
この辺りは若干園地のようになっていました。歩きやすいです。
 |
日向山山頂に続く稜線に出ました。ここからは木漏れ日の中を登っていきます。
 |
ズミ |
これはズミの花ですね。明るい日差しがよく似合います。関東地方の高原に多いそうですが、yamanekoが初めてみたのは中国山地でした。リンゴに近い種で、リンゴの台木として利用されていたそうです。
 |
マルバアオダモ |
マルバアオダモも花盛り。なんだがもじゃもじゃしています。一つの花には4個の細長い花弁があり、その花が多数集まって花序を作っているのです。標準和名はマルバアオダモですが、ホソバアオダモという別名も持っていて、いったいどっちなんだと思いました。でもよく考えると、Aに比べると葉は丸っこく、Bに比べた場合には葉は細い、といったことはあり得ますね。つまり絶対的な形容ではないということ。
 |
ミツバウツギ |
白い花が続きますね。これはミツバウツギです。よく見ると雄しべと雌しべが筒のようなものに囲まれています。これは5個の花弁が直立して筒のようになっているもの。その後ろのいかにも花弁っぽく見えるものは萼片です。いろんな花の形があるものです。
 |
オトコヨウゾメ |
もう一つ白い花、オトコヨウゾメ。ガマズミの仲間で葉や花の形が似ていますが、ガマズミのように花がびっしりと付かないところに風情を感じます。秋の山道で花と同様にまばらに付く赤い実を見ると、季節の深まりを感じたりします。
 |
ジュウニヒトエ |
地面にも白い花がありました。シソの仲間、ジュウニヒトエです。まだいきいきしていますね。多摩丘陵では花期はあらかた終わり頃。
 |
フデリンドウ |
日向にはフデリンドウ。みんな自分の好むところで咲いています。
 |
花があるたびに足を止めていてまるで牛歩のようでしたが、山頂が見えてきました。
 |
12時5分、山頂に到着しました。先客は一組だけ。のんびりできそうなところでした。
 |
展望デッキ |
展望デッキがあったので早速眺望を楽しむことに。昼食はその後です。
 |
南方向 |
おお、やっぱり武甲山は目立っていますね。ここからだと山体が大きく削り取られているのがよく分かります。左手前の少し尖った山は二子山(882m)。その麓にあるのが芦ヶ久保の駅辺りです。。
 |
コハウチワカエデ |
コハウチワカエデの花。カエデの仲間の花序はこのように垂れ下がるタイプが多いです。よく見ると、花序の上の方には翼を広げたような形の若い実が付いています。
 |
コバノガマズミ |
こちらはコバノガマズミ。さっきあったオトコヨウゾメと葉も花もよく似ています。ただ、花の密度が明らかに違うし、個々の花も雄しべや雌しべが花冠から飛び出していますが、オトコヨウゾメは花冠の中に収まっています。
 |
山頂風景 |
そうこうしているうちに山頂には人が増えてきました。我々も昼食とします。
 |
ランチ |
岩のテーブルのうえに豪華ランチを並べます。コンビニおにぎりと助六寿司。あとはキャラメルとかプリッツとか。山の上で食べるとなんでも美味いです。
 |
下山開始 |
山頂での滞在は45分ほど。12時50分に下山を開始しました。
 |
ヤマツツジ |
ヤマツツジの季節もそろそろ終わりですな。
 |
長い尾根道を下っていきます。木漏れ日が気持ちいい。
 |
ツリバナ |
その名のとおり吊り下げられたように花をつけるツリバナ。だいたい目線より高い位置にあります。ちょっとした風にも揺れるので写真を撮るのが難しいです。
 |
しばらく歩いて尾根道を外れ山腹を急降下する道に入りました。直進しても同じ場所に出ますが、やや遠回りに。
 |
急傾斜 |
写真では分かりにくいですがなかなかの斜度。ちょっと先は更に斜度が増してこの位置からは見通せていません。
 |
琴平神社 |
膝がガクガクなりつつもひたすら下っていくと社殿が現れました。琴平神社だそうです。ここは静かに手を合わせ「お邪魔しています」とお礼を。
 |
社殿から階段を下りると鳥居があり、その前は車道になっていました。鳥居の隣には綺麗に整備されているトイレもあり、この地域の方のおもてなし精神に頭が下がります。
 |
車道からは眺望がひらけていました。果樹農園のビニールハウスが並んでいます。
 |
車道を横切る形で直進し少し下って振り返ると、さっきまでいた日向山の山頂が見えました。今日は楽しませてくれてありがとう。
 |
再び樹林帯に入ります。ここからの斜度もなかなかのものでした。
 |
我が家の野山歩きは妻が先行するスタイル。面白しろいものを見つける目というか勘というかとにかく鋭く、yamanekoが普通に見逃してしまうものも見つけてくれます。ただ、その分ペースはゆっくり。yamanekoはずんずん行くタイプなので、はからずも時々前に出たりするのですが、そんなときは「ん゛んっ」と咳払いされ、後ろに回るよう促されます。
 |
ここの分岐は右へ。ルートのナビはもっぱらyamanekoの役割です。
 |
しばらく下ると川沿いに出ました。写真では分かりにくいですが、山道の右手は切れ落ちていて5mくらい下に川の流れがあります。
 |
オウギカズラ |
これはオウギカズラですね。ずいぶん前に高尾山で見た記憶があります。足元の枯れ草に紛れるように咲いていました。これはyamanekoが発見。
 |
ノリウツギ |
ノリウツギが谷間の上に枝を伸ばし、その先に花を付けていました。園芸種のアジサイと同じように花序の中央が両性花、その周囲を取り巻いているのが装飾花です。
 |
セリバヒエンソウ |
森を抜けると明るい場所を好む草花が顔を見せます。これはセリバヒエンソウ。花冠の様子をツバメが飛ぶ姿に例えて飛燕草だそうです。セリバはセリの葉に似ているから。中国原産の外来種です。
 |
突然開けた場所に出ました。巨大な観音像(後ろ姿)が見えます。何かの宗教施設でしょうね。道はこの敷地の縁を通っているようでした。
 |
麓からこの施設へ向かう道路を下っていきます。ここが今日一の斜度でした。
 |
坂道を降っていくと、はるか下方に芦ヶ久保駅が見えました。これからあそこまで歩いていきます。
 |
合流 |
往きに分岐した場所まで下ってきました。立派な生け垣がある辻です。往きは写真右手から登ってきて奥の坂道に向かいました。
 |
道の駅 |
2時20分、芦ヶ久保の道の駅まで戻ってきました。西武線の駅は奥の一段高いところ(擁壁が見えている)にあり、ここで次の電車まで30分ほど休憩です。とりあえず多くの人で賑わう売店などを覗いてお土産をゲットしました。
帰りも朝と同じルートを逆に辿ります。ただ、東飯能駅での八高線への乗り継ぎが悪く、往きよりも30分近く時間がかかってしまいました。どうやら我々が芦ヶ久保駅を出た電車の次の電車も同じJR電車に乗り継ぐことになるようでした。八高線、便数少なすぎでは。
ゴールデンウィークも終盤。今日は初夏のような陽気でした。花に満たされた季節から緑鮮やかな季節へ。名残惜しいような気もしますが、その時々の自然を楽しむことが野山歩きの醍醐味ですね。またどこかに出かけたいと思います。妻の三歩後ろを歩くスタイルで。