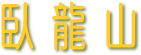
臥龍山 〜ブナの山は晩秋の装い〜
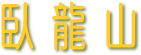 |
【広島県北広島町 平成17年11月12日(土)】
11月もそろそろ半ば。街中の街路樹も色づき始めてきました。ということは、山の方はもう次の季節を迎える準備が整っている頃かもしれません。幸いこの週末の天気予報は「晴れ」。なので、今日は職場の後輩といっしょに臥龍山に行ってみることにしました。この春、新緑の頃にも登りましたが、今日はまた違った表情を見せてくれることと思います。
広島ICから高速道路に乗り、中国道戸河内ICで下りてから国道191号線を島根県方面へ。ぐんぐん標高を上げていきますが、やがて深入山を過ぎたあたりから高原状の地形が広がるようになります。ここは北広島町(旧芸北町)の八幡高原。そしてその八幡高原の南側で山里の生活を見守るように穏やかに座しているのが臥龍山(1223m)です。
| 朝の森 |
9時30分、千町原の登山口に到着。身支度とストレッチを済ませてから出発です。臥龍山にはいくつかの登山道がありますが、今日はもっとも一般的な北斜面を登るコースをとります。
スタート直後の草原を過ぎて森の中に入っていくと、足下はクマザサに覆われた道になります。葉を落とした木々が多いので森の中は明るく、また、登山道も刈り払われ整備されていたので、快適に歩くことができました。
| コマユミ |
この時期、コマユミの実が色づいています。深紅の皮が裂けて、中からオレンジ色の種子が顔をのぞかせています。この木はこれからもあちこちで見かけることになりました。今日の主役の一人です。
| ガマズミ |
今日は熊鈴を使っていないので、ありのままの森の音を聞くことができます。落ち葉を踏みしめる音、背後の谷筋から聞こえる沢の音。そして山全体の木々を揺らすゴーッという風の呻り。見上げると樹冠を透かして青空が見えます。秋の空というより「冬晴れ」といった方がしっくりくる感じです。
ガマズミの葉は黄色から深紅まで、そのカラーバリエーションが豊富です。赤なのか黄色なのかはどうやら日当たりも影響しているようです。
| 落ち葉の道 |
少しずつ勾配がきつくなってきました。ついつい足下に視線を落としがちになります。でも落ち葉を見て木の存在に気づくことも。例えばハウチワカエデ、ウリハダカエデ、イタヤカエデ。足下一面に広がるそれらの葉を見て、あらためて上を見上げて木々を確認する。そんな楽しみもありました。
| クヌギ |
風にうねるクヌギの枝。クヌギは薪炭材として昔から人々に活用されてきた背の高い木です。里山では伐採を繰り返され根元から株立ちになったような姿のクヌギをよく見かけます。
| 分解者 |
倒木にキノコが並んでいました。森の分解者です。名前も分からないのでさすがに食べる気にはなりませんが、見た目は生き生きとして美味しそうです。そういえば森の生き物たちもキノコを食べるのでしょうか。でも毒キノコに当たって倒れているイノシシとか見たことないですが。食べ分けているのかもしれませんね。
そもそもキノコが毒を持つ意味とは何でしょうか。例えはヘビやカエルやタコなどの中には猛毒を持つものがいますが、これらは外敵から我が身を守るためですよね。(きっと) じゃあ、キノコは? いわゆるキノコの部分(子実体)を食べられても菌糸が残っていればまたキノコを形作れるはずです。??? さらに、シキミ、ハシリドコロなど毒を持つ植物は? 動物に食べられて種を遠くに運びたいのではなかったのか? 謎が深まります。毒をもって外的から身を守るといっても食べられてしまってはこちらも死ぬわけですから、いわば「差し違え」ですよね。意味がないような気もします。それとも一定の犠牲を払って敵に学習させるのでしょうか。
生物を三分する動物、植物、そして菌類。そのそれぞれに猛毒を持つ者がいる。このことに何か意味があるのでしょうか。ひょっとして生物界の総個体数を調整する役割をそれぞれが果たしているとか。(まさかね)
| ブナ林 |
標高が900mを超え、あちこちにブナが見られるようになりました。どの木もすっかり葉を落として冷たい風に吹きさらされています。今年はブナの実も豊作だったと聞きます。この辺りにもいるであろうツキノワグマたちにとって、里に降りて行かなくてもすむ幸せな秋になったことと思います。
| 山頂からの眺め |
登り始めてから1時間半、わりとあっけなく山頂に着きました。眺望は北方向のみ。登山口のある八幡高原の山里を眼下に望むことができました。その先には県境の山々が並んでいます。視界さえよければ日本海まで見えそうな感じですが、空には少しずつ雲が広がってきました。
| 一等三角点 |
山頂には一等三角点が設置されています。三角点とは三角測量をする際に緯度、経度、標高の基準として用いるもの。ここの三角点の正式な点名は「苅尾山」で、緯度は「34°41′24″」、経度は「132°11′48″」、標高は「1223.2m」だそうです。数字だとなかなかピンときませんが、緯度では伊豆半島の南端と同じくらいで、暖かいことで知られる房総半島でいえばその先端よりも南に位置することになります。ちょっとビックリです。
| コマユミ&サワフタギ |
風が冷たくて、昼食を食べている間にもどんどん体が冷えていくようです。デザートに買ったゼリーも食べる気がしません。こんなときはさっさと歩き始めましょう。下山は山頂からほぼ水平の尾根道を西に向かって歩いていきます。道の左右には赤いコマユミと青いサワフタギが並木のように並んでいてなかなか華やかでした。
しばらく行くとテーブル状の大きな岩が。いかにも上がってみてくださいといわんばかりの形をしています。上がってみると南方向のすばらしい展望が広がっていました。
写真右手に聖湖。その奥には恐羅漢山。写真左手には深入山。正面遙か向こうには広島市街があるはずです(当然見えません。)。あいにく雲が多いので、立ち枯れした木のシルエットと相まって寒々とした風景に見えてしまいます。
| 空の陣取り合戦 |
さて再び歩き始めることに。この展望岩の先から下り傾斜がきつくなってきます。ブナの森の中を降りていくのですが、上空に再び青空が戻ってきたおかげで気分も明るくなってきました。太い幹から血管のように枝を巡らせ、大空の陣取り合戦です。この枝にびっしり葉がついている姿を想像すると、地上からはまったく空を見ることができないことが分かります。すなわち日光を地上に漏らすことなく、無駄なく葉で受け止めているということです。これこそがブナの生命力の根源でしょう。
| クロモジ |
急な山道をしばらく下っていくと、その先が四つに分かれた小さな空き地に出ました。道に迷いやすいところですが、ここは一番右の道をやや手前方向に向かって折れて、さらに下って行きます。この道は四駆であれば車で上がってこれそうな道です。
道の脇に見事に黄葉しているクロモジがありました。本来は低木のクロモジにしては大型です。陽を受けて木全体が明るく輝いていました。
ほどなく車道にでました。ここ臥龍山には山頂近くに「雪霊水」という銘水ポイントがあって、そこまで舗装された車道が通っているのです。せっかくの自然豊かな山にあって興醒めな道路ですが。ここの湧き水は結構人気があるようで、ここを目指してわざわざ遠くから来る人も少なくないそうです。
道幅は車がようやく離合できるくらい。舗装されているとはいえ、今は落ち葉が降り積もっていて、それが車が通るたびに舞い上げられてなかなか風情があります。まるでドイツあたりの古い街道のよう。(行ったことないです。)
ここから先はふもとの登山口までこの道を歩いて下ります。くねくねと蛇行しながら高度を下げていくので、結構長めのウォーキングになります。
立ち止まり耳を澄ましても聞こえてくるのは風の音のみ。鳥の鳴き声もほとんどなく、森全体が静かな午後を楽しんでいるかのようです。
紅葉といえば赤や黄の鮮やかな色彩を求めがちですが、この山道のように茶色を基調とした落ち着いた紅葉というのもなかなかいいものです。
樹種はクヌギ、ミズナラ、ホオノキ、ブナなど。少し標高が下がってくるとカラマツなども目立ってきます。カラマツは漢字で「落葉松」と書くとおり、針葉樹にしては珍しく落葉樹です。松葉もアカマツやクロマツなどとは異なりかなり短く、落ち葉となってもきめ細かく、「降り積もる」という表現がピッタリです。
これから木々は葉をすべて落とし、厳しい寒さと乾燥に耐える準備をしていきます。ここは中国山地の最深部。思ったより早足で冬が近づいてくることでしょう。この森に最初に白い雪が舞う日まで、そう遠くはないかもしれません。
| 臥龍山 |
午後1時30分、登山口に到着しました。
振り返ると、臥龍山が晩秋の午後の陽を浴びています。光線の斜角が小さいからかやや白っぽく見えました。優しい姿をした山です。
| 紅葉の代表選手たち |