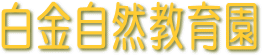
白金自然教育園 〜リアル都会のオアシスへ〜
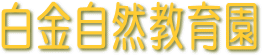 |
【東京都 港区 令和7年5月20日(火)】
多摩丘陵西部に住むyamaneko。都心まで電車で小一時間かかるので、通勤の必要がなくなった今ではめったに都心を訪れることもなくなりました。たまに孫のところに行くか、数か月に一度検査のために新宿の総合病院に行くくらいです。
今回、その通院のために新宿まで行き、せっかくなので検査が終わってから港区にある白金自然教育園に行ってみることにしました。平成の初め頃この近くに住んでいたことがあり、当時頻繁に自然教育園に足を運んでいたので、懐かしいスポットでもあります。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
昼前に病院を出て、小滝橋通りにある「さつき」という定食屋さんで腹ごしらえ。味、ボリュームとも申し分がなく、サラリーマンに大人気の店です。この日はエビフライ定食を注文。
食後、新宿駅まで歩き、そこから山手線で目黒駅へ。目黒通りを都心方向にしばらく歩くと自然教育園が見えてきます。
通りを歩いていると唐突に現れる入口。ここから森の中に入っていきます。入園料は大人320円。もう10数年前にはなりますが、年間パスを買って毎月1回自然観察に来ていました(こちら)。ちなみにこの年間パス、ここだけではなく、上野の科学博物館本館やつくばの実験植物園でも使えるお得なパスです。
| 路傍植物園 |
時刻は12時55分。虫よけを塗ってからスタートです(蚊に好かれやすいので)。
まずは入口から北に向かって真っすぐに伸びる園路を歩きます。その両側は路傍植物園とされていて、様々な植物が植栽されています(自生のものもあるのかも)。
| ヤブレガサ |
ヤブレガサがスッと花茎の伸ばし、先端に若い頭花をいくつか付けていました。キク科の植物の花は筒状j花と舌状花で構成されているものが多く、このヤブレガサは筒状花のみでできています。他に、タンポポは舌状花のみで、ノジギクなどキク属の花はその両方でできています。
| ウツギ |
ウツギが咲いていました。卯の花ですね。旧暦の四月を卯月というのは卯の花が咲く月という意味のようです。旧暦四月を新暦にすると4月末から5月下旬頃。ということはこの日はギリ卯月で、まさに旬の花に出会えたということになりました。
| サイハイラン |
サイハイランです。今が満開の状態。この姿が武将の振るう「采配」に似ているということでのネーミングだそうです。日本の野生ランは控え目な風情でいいですね。南国のものはトリッキー過ぎてちょっと。
| ハナミョウガ |
ハナミョウガの花序。満開の一歩手前くらいの状態です。関東地方以西の暖地に生えると図鑑にありましたが、yamanekoの田舎では見かけることはなかったです。暖地ではなかったということか。
路傍植物園を見ながら歩く。木漏れ日が気持ちいいです。平日ということもあって、行きかう人もまばらでした。
| 分岐 |
しばらく行くと分岐が現れました。ここは右手へ。この後園内をぐるっと回って、左手からこの分岐に戻ってくることになります。
分岐を右手に折れると道は下り坂に。谷戸の底に向かって下っていきます。
| 物語の松 |
途中、巨大なクロマツが。写真右側に分かれていく方の幹でも、大人一人が腕を回して届かないくらいの太さでした。この松は、江戸時代にこの場所が松平讃岐守の下屋敷だったときに回廊式庭園の植木として植えられたものだそうです。以来おおよそ400年。ここまで長生きだと天狗とか何かが棲んでいても不思議ありませんね。
| ひょうたん池 |
坂を下りきると池があります。こちらはそのうちの一つのひょうたん池。ここも庭園の一部だったのでは。以前は冬にここでオシドリなども見ましたが、今でも来ているでしょうか。
| 東屋 |
池の畔には東屋があります。外人さんのカップルが昼寝をしていました。
| 水生植物園 |
東屋を挟んでひょうたん池とは反対側には水生植物園。こちらは開けたロケーションになっていて、池と湿地で構成されています。園路は二手に分かれ、一つは水生植物園を巡るように伸びているので、そちらの方をゆっくり歩いてみることにしました。(もう一方は池の縁(写真右側)に沿って対面する森にまっすぐ伸びています。)
| キショウブ |
水際にキショウブが咲いていました。黄色の花被片が強い陽射しを跳ね返しています。菖蒲といえば和製のものという感じがしますが、キショウブは明治時代にヨーロッパから移入されたものだそう。既に日本に帰化しているとのことです。
| |
水生植物園の奥に広がる湿地。水から立ち上がっている植物が何なのか、近づけないのでよく分かりませんでした。イの仲間かなんかでしょうか。
| アイイイロニワゼキショウ |
アイイロニワゼキショウ。別名をオオニワゼキショウとも言います。ニワゼキショウ自体が北アメリカからやって来たものだそうですが、これも同郷。花丈はニワゼキショウより大きいですが、花冠はむしろこちらの方が小さいです。
湿地の中を通る園路を行きます。この日は風もなくちょっと暑いくらいでした。
| チョウジソウ |
これはチョウジソウですね。わが家のプランターでも毎年花を咲かせます。チョウジソウを初めて見たのは深山の幽玄な沼の畔。20数年前のことでした。そのときの印象は今でも色あせることはありません。(こちら)
| ケキツネノボタン |
ケキツネノボタン。片仮名だとどこで区切って読んでいいか分かりにくいですが、「毛・狐の牡丹」です。これとは別にキツネノボタンというものもあり、それよりも全体に毛が多いところから名づけられました。キンポウゲの仲間です。
| カキツバタ |
カキツバタは日本産。紺色の花被片の基部にある白いラインがスタイリッシュです。アヤメやノハナショウブなど類似の植物の中では最も水に近いところに生え、ここでも水の中から立ち上がって咲いていました。
| スイカズラ |
水生植物園を過ぎ再び森の中へ。スイカズラが咲いていました。ツル性の常緑植物です。漢字では「忍冬」と書き、その名のとおり葉を葉巻のように丸めて冬を耐え忍んでいます。
| 森の小道 |
森の小道という園路を行きます。
| イイギリ |
道ばた一面に緑色の何かが散らばっていました。拾い上げてみるとたくさんの雄しべがありました。これはイイギリの雄花。イイギリは高さ15mほどになる高木で、その枝々から降り注ぐようにこの雄花が落ちてくるのです。
| ハリグワ |
道は丘の上に向かって上りになりました。この丸っこいものはハリグワの雄花序。yamanekoは初めて見ました。調べてみると、ハリグワは中国原産。日本ではカイコの餌用に栽培されてきたのだそうで、中には野生化しているものもあるのだそうです。それがここ自然教育園にあるというのはどういうことだろう。戦後この場所で栽培していた経緯があるのか。それとも展示用として植栽したものか。でも外来のものをわざわざ自然教育園に植栽するだろうか。
ちなみに日本には雌株はほとんどないそうです。なんで?
| キジョラン |
この丸っこい葉はキジョランのもの。漢字では「鬼女蘭」と書き、なんだか曰くありげな名前です。優雅なチョウ、アサギマダラの食草だそうです。写真中央の丸いものは若い実。キジョランの果実は結実の翌年秋に熟すそうで、その時にはマンゴーくらいの大きさに。これは今年の果実だと思います。
| 武蔵野植物園 |
丘の上にやって来ました。ここからは武蔵野植物園と呼ばれるエリアです。
| マルバウツギ |
yamanekoの好きな花の一つ。マルバウツギです。確かに武蔵野や多摩丘陵でよく見かけます。
| アカショウマ |
こちらはアカショウマ。見たところ赤い部分はありませんが、それもそのはず,、赤いのは土の中の根茎だそうです。
開けた場所に出ました。ベンチが何脚かあったので、休憩場所のようです。
| おろちの松 |
園の南西側に向かいます。これは「おろちの松」。物語の松と双璧をなす巨木でしたが、2019年の台風19号通過後に突然倒れたそうです。高さ25m、幹周4m、推定樹齢350年の巨木の最期。園ではあえてそのままに残して、根の張り具合などが分かるよう展示しているのだそうです。
| いもりの池 |
さらに進むと、いもりの池。以前ここで子育て中のカルガモを観察したことを思い出します。
| ハマクサギ |
ハマクサギ。小さな流れに覆いかぶさるように枝を伸ばし、そこに小さな花をたくさん付けていました。近畿地方以西に自生するものだそうなので、これはいつの頃かに植栽されたものでしょう。
| スイカズラ |
ここにもスイカズラが。花は初め白く、次第に黄色に変わっていきます。
| 水鳥の沼 |
道を突き当りまで行くと現れるのが水鳥の沼。ただしyamanekoはここで水鳥を見た記憶がありません。なにしろすぐ後ろには首都高2号線が通っていますからね。
道は池を前にして折り返すような形で坂を上っていきます。
| 館跡 |
森の中を歩いていくと白金長者の館跡が現れました。白金長者とは、室町時代にこの場所に館を構えていた柳下上総之介という豪族のことだそう。その者が銀をたくさん持っていたので「銀=白金」で白金長者と呼ばれたのだそうです。
| ホウチャクソウ |
路傍植物園に戻ってきました。これはホウチャクソウの若い実です。秋にはパチンコ玉くらいに大きくなり、碧黒く熟します。
| フタリシズカ |
フタリシズカの花は白い米粒状。この白いものは花弁ではなく雄しべの花糸です(花弁はない)。花糸といえば文字どおり糸状に細くその先端に葯が付いているのが普通ですが、フタリシズカの場合は糸状にはならず、幅広で握りこぶしのように内側に巻いている構造。その中に雌しべを包んでいます。葯はどこにあるかというと花糸の基部にあります。およそ花のイメージからは程遠い姿ですね。ルーペがないと分からない世界です。
この道をまっすぐ行くと正面入り口です。なんだかあっという間でした。
2時35分。正門に戻ってきました。すぐには退出せず、左手の管理棟で展示を見て帰ります。園内でオオタカが繁殖する様子を解説してあったので。
ところで、この施設は入場の人数規制をしていて、以前は入場時にリボンを受け取ってそれを胸に付けて散策していましたが、この日はそれはありませんでした。平日で入場数が上限に達しないと見越してのことなのか、それともリボンを止めたのか。IT全盛の時代なのでモニターでカウントしているのかもしれませんね。
園を出たのは午後3時過ぎ。今日は用事のついでに自然観察をして、なかなか有意義な時間の使い方ができました。