
尾瀬沼 ~黄金の湖畔に深まる秋(後編)~
 |
(後編) |
【福島県 檜枝岐村、群馬県 片品村 平成22年10月8日(金)】
尾瀬沼の後編です。(前編はこちら)
沼尻平から先の道は、小さな湿原と樹林の中を交互に辿っていきます。
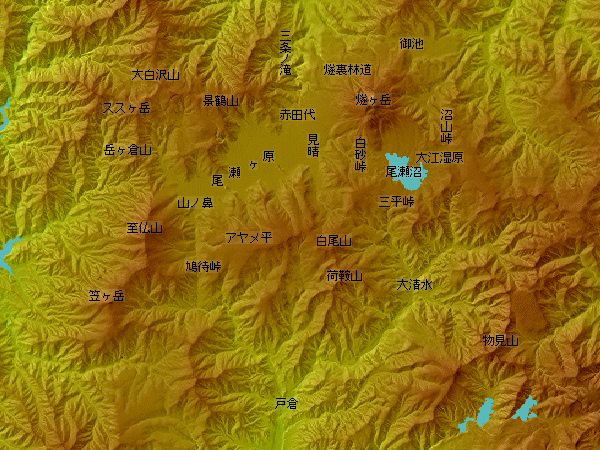 |
尾瀬エリア Kashmir 3D |
|
| 〔今回のルートを大きな地図で〕 |
ここから、尾瀬沼に半島状に突き出した部分を越えて、湾状になっている浅湖(あさみ)湿原、大江川沿いに北東に延びる大江湿原を通って、尾瀬沼ビジターセンターのある東岸地区に向かいます。そこで休憩した後に、さらに湖畔を進み、尾瀬沼南端のところから三平峠に向かって登り始めます。三平峠で尾瀬に別れを告げて深い谷を大清水に向けて下りていきますが、ここが結構距離もあり、最後の頑張りどころでしょう。大清水も、鳩待峠と並んで、尾瀬への入り口として古くから利用されてきたところ。そこから先は路線バスで戸倉まで戻ります。
| 皿伏山 |
逆光を避けてやや振り返りぎみに撮った写真。紅葉が水際に迫っています。遠くのなだらかな山は尾瀬沼の南西にある皿伏山(1916m)です。
森の中まで日光が届いています。木々のスリットを通すことにより、光りが柔らかくなっているような気がします。
| ツルリンドウ |
ツルリンドウの花と実。馴染みのある植物に出会うと、なんかホッとしますね。実ができても花弁が落ちず、タートルネックのようになるのがツルリンドウの特徴です。花弁が枯れて茶色になっても実の根元にくっついています。
| ゴゼンタチバナ |
なんとゴゼンタチバナの花に出会えるとは。急がないと実が成熟するまでに霜が降りてしまうぞ。
| 浅湖湿原 |
浅湖湿原までやってきました。北側には燧ヶ岳の荒々しい姿。この角度からだと俎嵓(右)と御池岳(中央)、赤ナグレ岳(左)がよく見えます。でも最高峰の柴安嵓はここからは御池岳の陰に隠れて見えません。
南側には遠くに山小屋が見えました。ここからだとまだぐるっと回って行くので、1㎞くらいの道のりがあるでしょう。背後の山は檜高山です。
| 長英新道分岐 |
何回目かの森に入ると長英新道との分岐がありました。ここはナデッ窪を上るルートより傾斜が緩く登りやすいとガイドブックには紹介されています。「長英」とは尾瀬保護の先駆けとなった平野長藏氏の息子。その長英氏が整備した道なのだそうです。父長藏氏の死後、長英氏を中心として尾瀬保存期成同盟が結成され、その活動は研究者や文化人、登山家など多くの賛同者の支援を得ていったとのことです。その後この期成同盟は日本自然保護協会(NACS-J)に発展していったそうです。yamanekoもNACS-Jのルーツが尾瀬の保護活動だったことは知っていましたが、今回色々調べてみて初めて知ったことが多かったです。
| ヤマシグレ |
ガマズミに近い仲間のヤマシグレ。果実ははじめ赤く、後に黒く熟します。これは鳥に存在を知らしめるためだそうで、二色効果というのだそうです。鳥は目がいいですからね。
| 大江湿原へ |
尾瀬の湖畔で最大の湿原、大江湿原が見えてきました。
| ヤマハハコ |
日向にヤマハハコが。この花は明るいところを好みます。雌雄異株で、この花は雄花のようです。
| 三本唐松 |
大江湿原のシンボルツリー、三本唐松です。この木の紅葉も見事ですが、時期は他の樹木よりも遅いのだそうです。
ここの突き当たりで左からやって来た沼山峠からの木道に合流します。この沼山峠からのルートは新潟や会津方面から尾瀬に入ってくるルートです。
| ギンブナ |
三本唐松のすぐ先で大江川を跨ぎます。小橋の上からみおろすと、魚たちがまるで宙に浮いているよう。すばらしい透明度です。大江川は大江湿原の中央を流れる川で、源流からの高低差もほとんどなく、流れはごくごく緩やかでした。川自体の長さも短いので拠水林も形成していません。
木道の合流点から振り返って見た燧ヶ岳と尾瀬沼です。この広々とした風景の中に身をおいているということ。心から幸せを感じますなあ。
| |
|||
| 尾瀬沼ビジターセンター | 長藏小屋 |
10時40分、尾瀬沼東岸に到着しました。ここにはビジターセンターの他、長藏小屋、尾瀬沼ヒュッテの2軒の山小屋があります。長藏小屋が経営する売店もあり、尾瀬沼でもっとも賑やか(?)なところです。
| 東岸からの燧ヶ岳 |
ここで小休止。山小屋脇の広場から燧ヶ岳の姿がよく臨めます。昼食にはちょっと早いし、アンパンで小腹を満たすことにしました。
11時10分、とちょっと長めの休憩の後、再び歩き始めました。
| あれれ? |
休憩している30分の間に空がこんな感じに。あっという間に雲に覆われてしまいました。山の天気は変わりやすいとはいえ、ビックリするほどの速さです。
| ムシカリ |
良い具合に紅葉しています。赤一色、黄色一色というのより、こういった微妙なグラデーションのものの方が好きですね。yamanekoとしては。
| 三平下 |
11時30分、尾瀬沼南端の三平下に到着しました。ここには尾瀬沼山荘という山小屋や休憩所があります。広場のベンチでは早めの昼食をとっている人たちもいましたが、yamaneko一行hはトイレ休憩のみで三平峠に向かいました。
| 森の中へ |
森の入口には入山カウンターと足ふきマットが設置されています。入山カウンターは、尾瀬地区に何人入って何人出て行ったかをカウントしている赤外線の機械です。足ふきマットは硬めの人工芝のようなビニール製のものでした(昔で言えば、体育館の入口に置いてあった、シュロと針金でできていた靴の裏の泥落としです。)。入山者の靴にくっついてきた外の植物の種子などを落とすためのものです。これは尾瀬のほかの入口にも設置されていて、もちろん鳩待峠にもありました。
| 三平峠 |
11時55分、標高差100mを登って三平峠に到着しました。さっき食べたあんパンのせいでお腹が空いていません。なのでここはスルーです。
| 三平見晴台 |
峠からしばらく行くと樹林を抜け、見晴らしの良い(はずの)稜線に出ました。ここは三平見晴台といい、見通しが良ければ遠くに赤城山まで見えるとのこと。でも今日はご覧のとおりです。
| 冬路沢 |
稜線からのぞき込むと、その先は深く切れ込んだ谷です。この谷は冬路沢といい、稜線との標高差は200m以上あります。これからここを一気に下っていくのです。
山肌をジグザグに縫うように急降下していきます。
| イタヤカエデ |
登山道脇の斜面に枝垂れていたイタヤカエデ。緑色とのマーブルで、清々とした印象です。
転げ落ちそうな斜度で、膝が笑っています。
途中で出会った滝。聞こえてくるのは水が岩を叩く音のみで、まさに深山幽谷です。
| 沢を渡る |
ずいぶんと下った後、ようやく傾斜が緩やかになってきました。
| ヤマウルシ |
形といい色合いといい見事ですね。炭火が熾っているかのような色の紅葉です。
| ノコンギク |
ノコンギクとかの野菊を見ると、里の近くに下りてきた実感が湧いてきます。
| 一ノ瀬休憩所 |
冬路沢を下りきり、林道に出てすぐのところに一ノ瀬休憩所がありました。こんな山深いところにぽつんと。もちろん付近に民家などはありません。
ここには軽食もありますが、yamanekoたちは山小屋で作ってもらっていたおにぎり弁当があるので、ベンチに腰かけてちょっと遅めの昼食をとりました。時計を見ると午後1時です。
30分ほど休憩をして、大清水に向かって林道を歩きはじめました。大清水発のバスは2時10分、3時、3時50分の3本。急げば2時10分のに間に合いそうですが、そんなもったいないことはしません。のんびり歩いても3時のバスには十分に間に合うので、キョロキョロしながら歩きます。
| ウワミズザクラ |
美味しそうなウワミズザクラの実。ツキノワグマの大好物です。黄、朱、紅、紫、黒。これも紅葉みたいです。
| ススキ |
日射しが戻ってきました。風にそよぐススキの穂。秋ですなあ。
| 大清水 |
2時20分、一ノ瀬から林道を3㎞歩いてついに大清水に到着しました。2日間にわたった尾瀬トレックも終了です。ケガもなく無事に下りてくることができました。
今回、念願かなってようやく尾瀬を訪れることができました。しかも紅葉ドンピシャの時期に。そして何より天気にも恵まれてラッキーでした。
尾瀬はやはり特殊な場所です。年間40万人もの人が訪れるにもかかわらず、空気は澄み、大木が育ち、生き物の影が濃いのです。「大自然」という言葉が違和感なく使える数少ない場所だと思いました。
尾瀬の自然を守るために莫大な資金が投入されています(例えば、木道の整備費は1m当たり約5万円。)。また、たくさんの人々の労力と「尾瀬への想い」も注ぎ込まれています。そして訪れる人たちには厳格なルール。ゴミは完全に持ち帰り。トイレではし尿処理のためにチップを支払い、山小屋では石鹸やシャンプーの使用もできません。マイカーの乗り入れも不可です。皆当たり前のようにこのルールを受け入れていているのは、尾瀬を訪れる人は尾瀬を保護する役割の一端を担うという意識があるからだと思います。しかもそれは誰かのためではなく自分自身のためでもあるわけです。なぜなら、次にここを訪れるときも写真で見るような「尾瀬」を楽しみにして来るのですから。
まあ、そんな理屈をぬきにしても、尾瀬の深く豊かな自然の中に身を置くと、やはりこれを壊してはいけないという想いが自然に湧いてくるのだと思います。
大清水からバスで15分、戸倉の駐車場に戻ってきました。ドリーム号は白線の中で行儀良く待っていました。しばらく休んでから東京に向かいます。今日は平日で、しかも逆向きなので、事故渋滞でもない限りおそらくスムースに走ることができると思われます。安全運転でのんびりと帰りましょう。
遙かな尾瀬。次は初夏に来てみたいと思っています。