
雲取山 〜深まる秋、奥多摩の盟主へ(前編)〜
 |
(前編) |
【東京都 奥多摩町、山梨県 丹波山村、埼玉県 秩父市 平成27年10月4日(日)】
雲取山。東京、埼玉、山梨の3都県に接し、標高は2000mを超える奥多摩の盟主です。東京都の最高峰でもあります。数ヶ月前、飲み会でその雲取山に登りたいという話が持ち上がり、その後もその話は立ち消えになることもなく、今回会社の同僚と2人で実行に移すことになりました。(うちの会社では飲み会での発言が現実のものとなることは少なくなく、酔っても滅多なことは言えません。) 同行するのは30代後半のNさん。屈強な肉体を持ち、プライベートで各地の水泳の大会に参加してはいつも上位入賞を果たしてくるという猛者です。山の経験は富士山に数回登ったことがあるということでしたが、もっぱら山より海派のようです。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
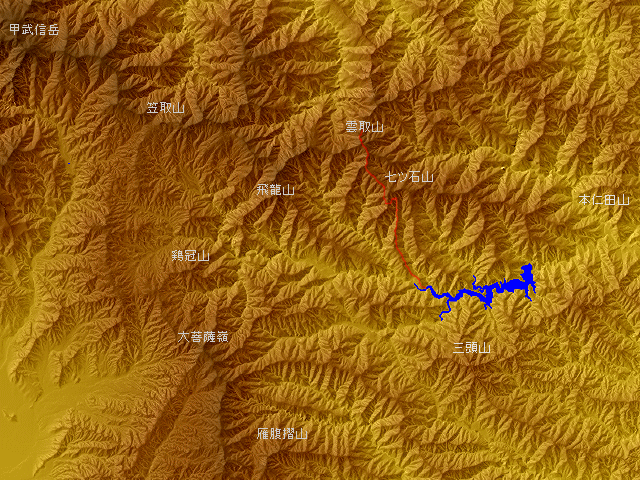 |
Kashmir 3D |
午前5時、起床。出発の準備をしているとNさんからなにやらメールが。「靴のソールが剥がれてしまいました。接着剤あったら持ってきてください。」 なんとNさん、自宅から最寄り駅に向かう途中でガムを踏んで、その粘着力で右足の前半分がめくれてしまったとのこと。そういえば飲み会の時にも靴底がめくれそうだとは言っていたんですよね。それにしてもガムに負けるとは。とりあえずリュックに接着剤を入れて6時過ぎの電車で出発しました。
橋本、八王子と乗り換え、立川でも乗り換えて青梅線へ。横浜から南武線でやってきたNさんとここで合流。ガラ空きの車内で早速靴の補修を始めました。青梅で4回目の乗り換えをして、終点の奥多摩駅に着いたのは8時13分。出発からここまでではや2時間経過。Nさんに至っては3時間が過ぎています。で、ここからまだ先があります。8時35分発のバスに乗って登山口のある鴨沢というところまで行くのですが、乗客(ほぼ全員が登山客)が多いので5分前に臨時便が出ることに。もちろんこれに乗り込みました。満員のバスに揺られること35分、ようやく鴨沢のバス停に到着しました。ここはもう山梨県です。
| 鴨沢バス停 |
鴨沢バス停は湖と山とに挟まれた細長い集落にありました。バス停の脇が登山口になっています。バスから下りると地元の警察官が待ち構えていて、登山届の提出を促していました。もちろんyamaneko達も提出。その後バス停横のスペースで準備体操です。Nさんはスタート前から靴がテープでグルグル巻きになっています。
 |
Kashmir 3D |
今回のルートは、鴨沢から七ツ石山を経由して雲取山山頂へ向かう標高差約1480mの鴨沢ルート。約11kmの行程で、危険箇所もほとんどなく、いくつかあるルートのうちでは雲取初心者にも安心なもののようです。
七ツ石山までは樹林帯の中を、それ以降は見晴らしの良い広い尾根道を歩きます。山頂に到達した後は反対側に少し下り、宿泊場所の雲取山荘へ。翌日は来た道を戻ります。
| 集落の中を |
9時25分出発。 急な斜面に張り付くようにして建っている民家の前を行きます。のっけから結構な坂道です。
すぐに民家が途切れますが、道はどんどん登っていっています。
山の重なりの向こうにこんもりとしたピークが。地図によるとあれは保之瀬天平というピークのよう。「天平」は「でんでえろ」と発音するそうで、高いところにある平らな場所という意味だと思います。ちなみに「保之瀬」は「ほうのせ」だそうです。
| 山道へ |
やがて案内板が現れました。ここから森の中に入っていきます。
薄暗い植林地を登っていきます。そこそこの斜度があり、登山らしくなってきました。
| シラヤマギク |
シラヤマギクに目が止まりました。路傍から「いってらっしゃい」と声をかけてくれたような…。
ずいぶん高度が上がってきました。遠くに累々とした山の連なりが見えます。そのうち最も高いのは黒川鶏冠山(1716m)です。
| 小袖乗越駐車場 |
スタートから25分後、小袖乗越(こそでのっこし)の駐車場に出ました。ここは林道(舗装路)の終点になっていて、車で来て鴨沢コースを登る人は概ねこの駐車場を利用するようです。この時間、既に満車状態でした。
| 小袖山 |
駐車場から東の方に見えるのは小袖山(1228m)。これから登る尾根から谷を挟んで東側の尾根筋にある山です。
| 再び森へ |
舗装路をしばらく歩くと、再び樹林帯の中に入る登山口が現れました。
地図によるとここから七ツ石山までは急な坂道が延々と続ます。体力差を見せつけるようにスイスイ登るNさん。常にyamanekoの10m先を行っています。一般的には傾斜が増すと歩幅を小さくしてゆっくり登るのが定石ですが、Nさんは斜度が増すとそこでギアチェンジしてよりパワーアップしようとするのです。
| ツリフネソウ |
ちょっと弱々しいツリフネソウ。この辺りは秋の訪れも早いでしょう。
広葉樹林は木漏れ日が明るいです。紅葉の時期もいい感じでしょうね。
しばらく行くと廃屋が現れました。まだ朽ちているといった感じではないので、今でも何かに利用されているのかもしれません。
| 小休止 |
スタートから1時間、ちょっとした広場で休憩です。ここでコッペパンを食べてエネルギー補給。クリームとあんこが入っていて700kカロリー超という、日常ではまず購入をためらうような高カロリー食品です。
相変わらず先を行くNさん。きっと単独行だったならもっとスタスタ登っていたかもしれません。
| 倒木 |
登山道に倒木が横たわっていました。ちょっと屈めば通り抜けられます。木の表面にはひこばえが。これはミズナラですね。
| 堂所 |
11時10分、堂所という場所までやって来ました。ここまでは尾根の東斜面を辿ってきましたが、ここで稜線に出る形です。
その昔、七ツ石山にある神社への参拝が盛んだった頃にはここ堂所で賭場が開帳されていたそうですが、こんな狭い稜線の一体どこで賭場を開いたのか疑問です。
| 補修中 |
Nさんも腰を下ろし、賭博ならぬ靴の補修です。
| 南方向 |
休憩後も黙々と登り続けます。たまに木立の間に眺望が開けることも。南方向、遠くの三角の山は雁ヶ腹摺山(がんがはらすりやま)。渡り鳥のガンが腹を摺るようにしてようやく越えていったというのが名の由来のようです。あの山の向こう側は大月盆地です。
| ブナ |
株立ちになった大きなブナ。足を止め、息を整えながら見上げます。無数の種子の中から選ばれた強運の持ち主ですね。でも森の木はみんなそうか。
| マムシ岩 |
11時55分、マムシ岩に到着。マムシが、いや登山客が岩の上で食事をしていました。ここで道は七ツ石山の山頂を踏んで行くルートと南側の山腹を巻いていくルートに分かれています(ただ、山頂に向かう道は細く気づきにくい。)。ここの標高は1490mで七ツ石山の山頂は1757m。標高差は250mほどあります。七ツ石山の山頂からは雲取山の姿が綺麗に臨めるとのことですが、それは復路の楽しみに取っておいて、というか既に疲れが溜まってきているのでパスして、巻道の方に進むことにしました。巻道といっても山頂越えルートとの合流地点の標高は1650mあるので、巻きながら150mほど登ることにはなります。
木漏れ日の中を歩いていきます。ちょっと日差しが薄くなってきたか?
| 分岐 |
しばらく行くと分岐が現れました。先行していたNさんが標識の下で休んでいます。この分岐を右に行くと先ほど分かれた山頂越えルートに合流します。我々はここを直進です。
| 紅葉 |
谷筋にこんもりと紅葉が。これは ハウチワカエデか。山が色づき始めています。
巻道は山腹をトラバース(斜面の横方向移動)する道なので、落石や崩落などで道が荒れていることもあります。そういえば1年前、道志の加入道山で崩落した箇所を岩肌に張り付くようにして通ったことがありました。あのときは怖い思いをしました。今考えてもゾッとします。
こんなふうに橋がかけてあれば安心です。
歩いているときには大して気になりませんでしたが、結構な斜度ですね。60度近くありそうです。
コハウチワカエデとミズナラ。紅葉のピークは2週間後くらいでしょうか。
やがて右側上方に稜線が見えてきました。山頂越えルートとの合流も近いようです。
| ブナ坂 |
12時45分、合流地点、ブナ坂(ブナダワともいう。)に到着しました。広い鞍部になっています。Nさんが見やるのは山頂越えルートの方向。
| 昼食 |
ここでちょっと遅めの昼食です。荷物にならないようコンパクトなメニュー。
| ブナ坂 |
長閑で静かなランチタイム。左手奥から下ってきているのが山頂越えルート、正面が巻道からの合流になります。なお、左側に唐松谷を経て日原に降りていく道もありましたが、崩壊のため通行止になっていました。
20分ほどの休憩後、再び歩き始めます。ここからは稜線の道。アップダウンを繰り返し、山頂までの標高差約350mを詰めていきます。道幅が2、3mと広いのは防火帯の役割を果たしているからです。
| マルバダケブキ |
稜線の南側斜面にはドライフラワーとなったマルバダケブキが一面に。花の時期には見事だったでしょうね。
| オオカメノキ |
オオカメノキが早くも冬芽の準備を整えていました。今年の葉は紅葉の最中ですが。
ブナ坂から雲取山山頂まではずっと南側の眺望が開けています。ところで、どうやら雲取山周辺の上空にのみ厚い雲が掛かっているようで、遠くは晴れているのに周囲は暗いといった状況になっています。変な感じ。
| 五十人平 |
しばらく行くと五十人平という平坦地に至りました。ここはテント場にも指定されています。そに手前にはヘリポート(といっても非舗装)がありました。遭難救助などに使われるようです。するとタイミング良くどこからともなくヘリのプロペラ音が。見上げると本当にヘリが近づいてきています。ここに降りるのかと思いましたが、そのまま山梨の方に飛んで行きました。
テント場を過ぎ、開放的な尾根道を更に進みます。
すぐに赤い屋根の建物が見えてきました。奥多摩小屋です。
| 奥多摩小屋 |
登山道脇から覗いてみるとこんな感じ。これぞ山小屋といった風情ですね。立派に営業中です。予約不要。電気は通っておらず、ランプと薪ストーブの山小屋だそうです。
| ヨモギノ頭へ |
奥多摩小屋を過ぎると「ヨモギノ頭」というピークへの急な登りになります。結構な斜度の上に、足場はずりずりと滑りやすく、体力を消耗します。
荒い息と共にピークに到着。標高1813mです。
| 今度は小雲取山へ |
ヨモギノ頭からはわずかに下り、その後にまた厳しい上りが待っていました。雲取山山頂の手前にある小雲取山と呼ばれるピークへのアプローチです。ヨモギノ頭との鞍部から標高差150mを一気に登っていきます。
| 飛龍山 |
午後の陽を受ける飛龍山。堂々としていますね。雲取山から西に延びる稜線に聳える山です。
急な登りはまだ続きます。続きは後編で。