
養沢川 ~東京の山にも春がやってきた~
 |
【東京都あきるの市 平成18年4月9日(日)】
4月3日に東京に引っ越してきて、それからしばらくは家の中が段ボール箱に占拠されていましたが、ようやくなんとか普通に生活できる態勢になってきました。そうなるとまた「どっか行きたい虫」がむずむずし始めます。そのへんは妻ももう諦めていて、まだ若干片づけが残っていたのですがわりとすんなりと出かけさせてくれました。
さてどこに行こうかと考えて最初に頭に浮かんだのは、以前何度かフライフィッシングに通ったことのある「養沢川」でした。幸い天気予報によると、今日は一日穏やかな晴天とのこと。絶好の野山歩き日和です。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
養沢川のある「あきるの市」は都心から見ると関東平野の西の端にあたり、渋滞がなければ1時間半で行くことができます。
午前10時、まずは初台ランプから首都高4号線に乗ります。ドリーム号は東京生まれ。今回故郷に帰ってきた格好です。両側を壁に挟まれ、急なカーブが連続する高速道路。久々に首都高を走る感覚はドリーム号にとっても懐かしいものだったでしょう。
道は順調に流れています。一般の高速道路と違ってランプの出入口が右側にあったり左側にあったりするので、頻繁に車線変更が必要になってきます。
4号線を西に向かって走ると高井戸からそのまま中央道に入っていきます。松任谷由実の「中央フリーウェイ」の歌詞の舞台となった府中あたり。「♪右に見える競馬場、左はビール工場~」。確かにそのとおりの位置関係です。
中央道も西に向かって快調に飛ばし、八王子ICで高速を下ります。あとは一般道を秋川渓谷方面に向かって走ります。
| 養沢川 |
11時30分、養沢川の中流域に到着しました。中流域といっても養沢川は多摩川の支流の秋川のそのまた支流なので、ご覧のとおり渓流といった佇まいです。まだ子供が小さい頃、ちょうどこの場所でデイキャンプをしたこともありました。
道ばたの駐車スペースにドリーム号を停めて、まずは腹ごしらえ。川面の岩の上でキセキレイが尾を振りながらさえずっています。のどかな昼食です。
| タチツボスミレ |
12時前、ようやく歩き始めました。まず出むかえてくれたのはタチスボスミレ。林縁の斜面でふりそそぐ日差しを浴びていました。
| ミヤマキケマン |
ミヤマキケマンの黄色に誘われて河原に下りてみました。流れの緩やかなところにニジマスの影が。水面上にはカゲロウの成虫が飛び交っています。夕方になるとニジマスが採餌のため水面に顔を出し始めるでしょう。フライフィッシングは主にそれを狙って釣るのです。
| キランソウ |
キランソウ。広島近郊でもよく見かけた野草です。別名「地獄の竃(かま)の蓋」。この植物には薬効があり、地獄の竃の蓋をして病人を死の淵から救い出す、といった意味があるのだそうです。地面に張り付くように生えているので普段なかなかじっくりと見ることはありませんが、ひざを着いて顔を近づけてみるとシソ科特有の可愛い唇弁花をアップで観察できます。
| アブラチャン |
これも水辺に生えていたアブラチャン。同じクスノキ科のダンコウバイの花とよく似ていますが、見分けるポイントは花柄の有無。こちらには約8㎜ほどの花柄がありますが、ダンコウバイには花柄はありません。名前のとおり樹皮や種子からは油が採れ、昔は灯火用として使われたとのことです。ちなみにアブラチャンの「チャン」は瀝青のことで、ピッチやコールタールなどの総称なのだそうです。
| 満開の桜 |
川をさかのぼっていくと、小さな集落がいくつかあります。
都心の桜はもうほとんど散ってしまいましたが、この辺りはこれから満開を迎えるといったところ。今年は引越のバタバタで落ち着いて桜を見ることができなかったので、遅ればせながらプチ花見ということにしました。
| 渓流の午後 |
ここが本当に東京都内? と問いたくなるような、自然度たっぷりの場所です。
この上流にはいくつか鍾乳洞もあることから、地質的には石灰岩が分布しているのでしょう。ここから先もどんなものに出会えるか楽しみです。
| ハナネコノメ |
水際近く、増水時にはしぶきがかかりそうな場所にハナネコノメの群落がありました。どちらかというとすこし日が陰るような場所を好むようです。中国地方で見かけるシロバナネコノメによく似ていますが、こちらは全体的に毛がまばらです。花びら(萼裂片)がやや丸みを帯びているところも相違点なのだとか。東海、関東、東北南部に分布すると図鑑にありました。
| ムラサキケマン |
こちらは日向が大好きなムラサキケマン。ケマンは漢字で「華鬘」と書き、仏前の梁などを飾る装飾品の一つだそうです。
| 野良仕事 |
畑仕事をしているご夫婦がおられたので声をかけてみました。これからネギを植えるのだとか。畑のぐるりがネットで囲まれているので聞いてみるとやっぱり猿よけなのだそうです。
| エイザンスミレ |
ヒノキ林の縁にエイザンスミレの小群落がありました。葉が細かく裂けるのが特徴です。
| フライフィッシング |
今日は休日なのでフライフィッシングをしている人があちこちで見かけられました。養沢川の中流域以上は毛鉤専用の釣り場になっています。普通、管理釣り場といえば、釣り堀かまたはせいぜい川の流れを区切ってその区画に四方から竿を伸ばすといった形態ですが、ここは自然の川がまるごと釣り場になっているので、川をゆっくりさかのぼりながら釣りを楽しむことができます。中流域は主にニジマス。上流域は主にヤマメが放流されているそうです。
関東近辺でフライフィッシングをする人でここ養沢川を知らない人はまずいないのではないでしょうか。それくらい人気のある、自然の中で気持ちのいい時間を過ごせる川なのです。
| 養沢神社 |
13時30分、養沢神社までやってきました。この神社の縁起などについて特に説明板などがなかったので、いつぐらいからここに建っているのか分かりませんでしたが、境内の巨大なトチノキの大きさからするとそれなりの由緒のある神社のようです。目通り約6m、高さはゆうに20mは超えているのではないでしょうか。この木はあきるの市の保存樹木に指定されているそうです。
| ミツマタ |
そろそろ最後の集落です。ここから先にはもう民家はありません。
庭先で飼われているニワトリが鳴いています。「コッケコッコーーー」 そういえばもう何年もニワトリの鳴き声など聞いたことがありませんでした。
| セントウソウ |
道ばたにウバユリの若葉が展開し始めていました。しっとりとつややかで、これがあんなにごつい葉になるとはとても想像がつきません。
その周囲に白い小さな花。よく見るとセントウソウでした。漢字では「仙洞草」と書きますが、その語源は不明だそうです。想像するに深山幽谷の洞穴に暮らす仙人がどうこうしたとかそんな話なのではないでしょうか。
| ニリンソウ |
土手の斜面に1本のケヤキの木。なんとなく存在感のある木だったので近寄ってみると、根元にニリンソウの群落がありました。思わず「おおっ」と声が出てしまいました。なんだかこの花たちに呼び寄せられたような感じです。
今年の春、この花たちはいったいどれだけの人にその姿を見せたでしょうか。誰に愛でられることもなく枯れていくと考えるともったいないような気もします。でも、本人(?)たちにしてみれば、人に見られようが見られまいがそんなこととは関係なく、毎年ここで一生懸命に生命の営みを繰り返しているのでしょうね。巷では山野草の盗掘が後を絶ちません。可憐な花と出会ったときに「家に連れて帰ってかわいがってあげよう。」なんて考えずに、花がそこに咲いている意味を今一度考えてみることが大切だと思います。そんなことを考えさせてくれたニリンソウたちでした。
| 奥養沢 |
かなり上流まで歩いてきました。ここから先は未舗装の林道になります。時計を見ると14時20分。そろそろこの辺りで引き返すことにしましょう。
ふと見ると、河面に沿ってカワガラスが低空飛行していきました。
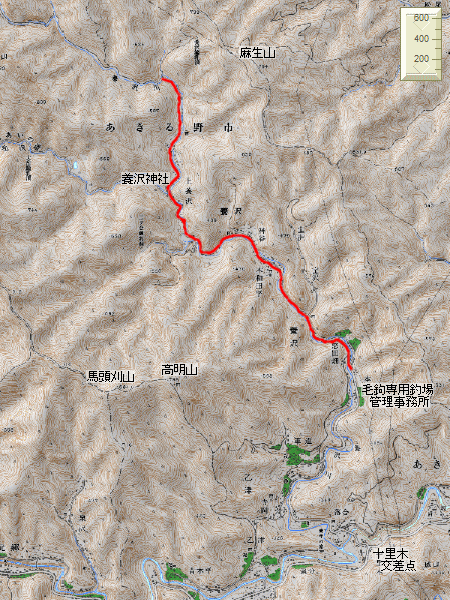 |
Kashmir 3D |
今日は穏やかな天気で、十分にリフレッシュできた一日になりました。やっぱり東京に引っ越してきても野山歩きはやめられそうにありません。