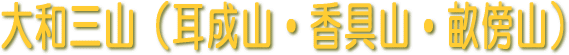
大和三山 ~万葉の野辺・夏の空(前編)~
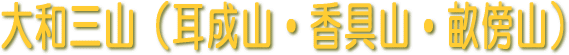 |
(前編) |
【奈良県 橿原市 平成30年6月24日(日)】
早いものでもう6月も下旬。いかにも梅雨らしい天気の日が続いています。ただ、天気予報によるとこの日曜日は梅雨の晴れ間になるとのこと。たまっている洗濯物を早朝に片付けてしまえば、久しぶりに野山歩きができそうです。ということで、行き先は奈良県橿原市にある大和三山に決めました。ネットで情報を収集すると、登る山ではなく散策しがてら眺める山、といった感じの山のようです。
さて当日、起きてカーテンを開けるとどよーんとした曇り空でした。というか、ついさっきまで雨が降っていたようで、空気もしっとり。大きな水たまりがあちこちにできています。晴れるとの天気予報を信じて洗濯と朝食を済ませ、自転車で家を出ました。まずは最寄りの駅に向かいます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
近鉄大阪線で府県境を越え、9時半前に大和八木駅に到着。奈良地方は天気の回復が大阪よりも遅くなるようで、改札を出た時にはまだ雨が上がったばかりのよう。晴れ間が出るまでにはしばらく時間がかかりそうでした。やむなく駅のミスドで今日2回目の朝食をとり、ノンビリと時間を潰しました。
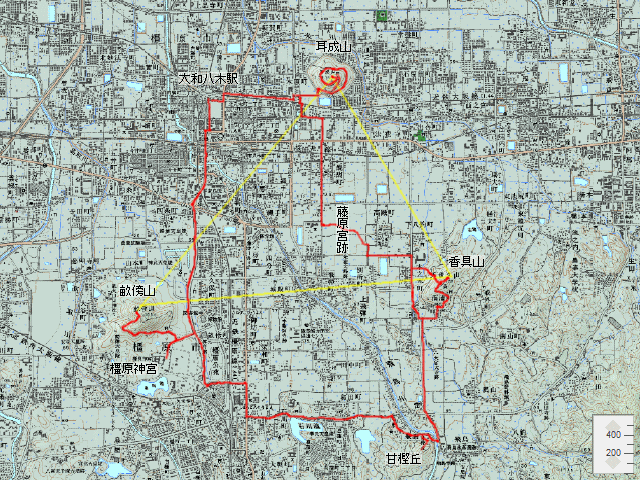 |
Kashmir 3D |
大和三山とは、万葉の時代、和歌(やまとうた)に多く詠まれた奈良盆地南部にある3つの低山で、耳成山(みみなしやま)、香具山(かぐやま)、畝傍山(うねびやま)のことを言います。標高は最も高い畝傍山で199m。ですが、そもそも橿原市付近の標高が70mくらいあるので、比高は100m前後です。3つの山はそれぞれ2.5kmから3kmほど離れていて二等辺三角形を成し、その三角形の中に藤原宮(藤原京の宮城)が位置していています。何か意味ありげですね。
今日のルートは、大和八木駅から東に向かい、まずは耳成山へ。次にそこから南下して藤原宮跡を経由し、香具山へ。そこからは直接畝傍山に向かうのではなく、更に南下して甘樫丘へ。ここは大和三山を一望できるポイントということです。そこからあらためて西に向かい、畝傍山へ。最後に北上して大和八木駅に戻ってくるというものです。
空が若干明るくなったところでミスドを出て、レンタサイクル屋さんに向かいました。
自転車は駅の前にある「かしはらナビプラサ」という観光交流センターで手続きをして借りることができます。普通の変速ギア付きの自転車が1日700円、電動アシスト自転車が1000円でした。ここはもちろん電動で。あと、係の女性が空模様があやしいからとビニール合羽まで貸してくれました。おもてなし精神ですね。
| 耳成山登山口 |
近鉄の線路沿いに延びる道を東方向へ。およそ700mほどで民家も途切れ、田んぼの中の小道を更に東へ進みます。雨上がりで泥濘む中、若干ハンドルをとられつつも電動パワーで耳成山の麓まで走りきりました。耳成山の周囲はぐるりと道路に囲まれていて、南側の登山口前に小さな公園とトイレがありました。ここに自転車を停めて登り始めます。時刻は10時15分です。
直登する登山道は、実質的には八合目にある耳成山口神社の参道で、登り始めてすぐに鳥居が現れました。ここから先は舗装されていない道になります。山肌から雨水が湧き出るのか、参道を小川のように水が流れていました。
| サカキ |
これはサカキですね。漢字では「榊」と書き、神事にも用いられたりするので、神社の社叢でもよく見かけます。名の由来は、神と人との境にあるものだから「境木」というのが有力なのだそうです。以前はツバキ科に属していましたが、最新の分類ではモッコク科です。
| ヤマモモ |
足元にヤマモモの実がたくさん落ちていました。甘くて美味しいのですが、誰も採る人はいないんでしょうね。子供の頃にはよく食べたものですが。
曇天の弱い日差しが木立に遮られて、参道は更に薄暗くなっています。晴天の予報はどうなったんだと愚痴りつつ登ることしばし、あっというまに神社の境内までやってきました。
| 耳成山口神社 |
境内はけっこう広めです。正面の階段の奥にこぢんまりとした耳成山口神社の社殿がありました。早速いつものとおり家内安全と世界平和を祈願です。
この神社は、大和国の山口社六社のうちの一社だそうです。この辺りに山口神社が6箇所あるということですね。
| 金比羅神社 |
これは摂社の金比羅神社。 …ん?
よく見ると黒猫が賽銭箱の上に鎮座しているではないですか。堂々として微動だにしません。どうもこの山には野良猫が多いようで、無責任に餌をあげる人もいるらしく困っているとのこと(地元の人談)。どうやら神の使いではないようです。
| 耳成山山頂 |
山頂は神社の裏手を更に少し登ったところにあり、写真のとおり眺望はまったくありませんでした。
笹薮の中に「明治天皇大演習御統監之地」と彫られた石柱が。明治天皇がここから軍の演習を視察したということでしょう。そのときにはこの鬱蒼とした樹林は伐採され眺めを良くしたでしょうね。
| 香具山 |
山頂から一段下がったところの木立の一角が伐られ隙間が作ってありました。南東方向になります。そこからは香具山の姿が。ここの次に向かう山です。山というより丘といった印象です。
| 二上山 |
もう一箇所、西の方角の二上山の姿も。金剛山地の北端に位置する山です。特徴的な姿で、河内平野に位置するyamanekoの自宅からもこの裏側の姿が見えます。
下山は直登してきた参道ではなく、山体をぐるっと巻く道を下ります。
| 畝傍山 |
南西の方角に畝傍山。ここからだと三角形の山容をしていますが、見る方角により台形にも見えるのだとか。
この時期、常緑樹の林内には花はほとんど見られないので、結果として普段注目しないシダなどにも目が行きます。これはカナワラビの仲間かな。
ようやく天気が回復してきたようで、木漏れ日が山道に届くようになりました。でも道には相変わらず水が流れている状況です。
| ヤブニッケイ |
テカテカして若々しい葉。ヤブニッケイですね。日光ってすごいですね。浴びるだけで生き物が輝いて見えます。
| アオサギ |
11時ちょうど、下山してきました。ゆっくり登って下りて45分でした。麓の田んぼにはアオサギが忍び足で獲物を探していました。長閑です。
| 耳成山 |
夏空の下の耳成山。田園風景にマッチしていますね。子供の頃、こんな用水路に沿って寄り道しながら学校から帰ったなあ。
| 産直市場 |
再び自転車にまたがり、今度は香具山を目指します。耳成山から南下し、近鉄線とJR線を渡って更に行くとこんな建物が。産直市場のようでした。駐車場は満杯でしたが、ナンバーからするとほとんどが地元の人たちのようでした。
| 藤原京跡 |
市場をさっと冷やかしてから更に南下していくと藤原宮跡が現れました。うーむ、何もない。往時の宮城は心眼で見るしかないようです。目を開けると…、奥に香具山が見えていますね。
見渡す限りだだっ広い空き地。でも良く見ると、オレンジ色の円柱群が数箇所にありました。おそらく建造物の遺構で柱の跡を示しているのだと思います。特段柵のようなものはなく何時でも誰でも入れる状態ですが、逆にこれだけオープンだと悪さをする者もいないのかもしれません。
| ハス |
藤原宮跡を過ぎて細い農道を進んでいくとハス田がありました。数株花を付けています。古の都にハスの花。風情がありますね。夏だなぁ。
| 香具山 |
この辺りには農業用と思われるため池が点在していて、そのうちの一つの畔りで小休止。香具山はもうすぐそこです。
| トイレと休憩所 |
12時5分、香具山の西麓に到着。ここには奈良文化財研究所の分館があって、その隣に公共のトイレと休憩所がありました。散策をする人にはありがたい施設です。yamanekoもここに自転車を停めて登ることにしました。
| ムラサキカタバミ |
民家の庭先を通って急坂を登っていきます。ムラサキカタバミの涼やかな紫色。いっとき暑さを忘れさせてくれます。
| ベニシジミ |
こっちはベニシジミ。1年のうちに何回か発生するそうですが、この時期に最も多く見られる小ぶりの蝶です。ところでそのアザミ、まだ蜜はあるのでしょうか。
| 登山口 |
登山口が現れました。この森の奥に入っていきます。
朝方まで降った雨のためか、登山道に棚田状に水たまりができていました。
| 國常立神社 高龗神社 |
ほどなく山頂に到着。広場の奥に小さめの神社がありました。良く見ると祠が2つ並んでいます。解説によると右が國常立神社、左が高龗神社で、双方とも雨の神様だそうです。
山頂はぐるりと木立に囲まれていましたが、西側の展望が確保されていました。写真の山は畝傍山。背景は金剛山地です(右端に二上山)。
| 畝傍山 |
この方角からだと均整のとれた姿をしていますね。
さあ下山です。この山には西側から登ってきましたが、南側に下る道を行きます。この道もかなり水が流れていました。
| オコジョ |
足元に注意しながら下っていると、10mほど前を素早く横切るものが。オコジョです。望遠レンズに付け替える余裕もなく、ようやく撮ったのがこの一枚。しかしこんなに民家に近いところにもいるんですね。こんな可愛い姿をしていますがオコジョは肉食で気性は荒いのだとか。
| 香具山 |
南側の集落に下りてきました。田植えの終わった田んぼ越しの香具山。yamanekoの故郷もこんな感じでした。昭和の頃から変わらない風景なんでしょうね。
さて、ここから自転車を停めておいたトイレのところまで戻らなければなりません。あまりの日差しの強さに、背に腹は代えられず、念のために持ってきた雨傘をさしてしまいました。「日傘男子」です。
| 飛鳥の里 |
自転車に乗って再び南下し、大和三山を一目にできるという甘樫丘に向かいます。左手には飛鳥の里。高松塚古墳やキトラ古墳などがある地域です(今日は時間の関係でパス)。
時刻は12時45分。お腹が空いてきてもおかしくないですが、そういえば今朝は2回朝食を食べたんだった。昼食はお腹がすいてきてからにしましょう。(続きは後編で)