
晃石山 ~歴史の息づく山々~
 |
【栃木県 大平町 平成21年12月13日(日)】
12月に入って寒い日が続いています。関東平野は雪こそ降らないものの、底冷えがするような毎日です。
そんな師走の休日は静かな冬の里山を楽しんでみるのがよいでしょう(雪山はちょっと…。)。ということで、今日はその関東平野の北の縁、栃木県の南端にある晃石山(てるいしさん)に行ってみることにしました。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
都心を起点として北に向かう高速道路は東北道です。渋滞のメッカとしてお馴染みですね。ちなみに東京からは高速道路が放射状に整備されているので、どこに行くにも便利です。空いていればですが。
で、その東北道を北上し、佐野藤岡ICで下りて一般道を北東方向へ。途中、朝のコンビニで食糧を仕入れました。白い息も凍てつく駐車場からはもう関東平野の北辺の山々がすぐそこに見えていました。
| 大中寺 |
午前9時15分、晃石山のふもとにある大中寺の駐車場に到着。準備を整えて、まずはお寺の境内に行ってみました。山門が切り取った境内が額絵のように見えます。冬枯れの静かな風景です。
この大中寺、なかなかの名刹のよう。平安末期の創建で、後に衰退した時期もあったそうですが、室町時代に再興され、江戸時代には全国の曹洞宗の寺院を管掌する位の高い寺になったのだそうです。何しろ大中寺を創建した禅師(実在)は雨月物語にも登場するほど。境内には今でも「七不思議」と呼ばれる怪異な言い伝えが残っているといいます。例えば「油坂」という言い伝え。右の写真の中央に白っぽい階段があり、その階段を上りきったところに横に棒が渡してあるのが分かりますか。これは太い竹を渡して人が上り下りできないようにされているのです(階段の下側にも竹が渡してありました。)。その言い伝えとは、昔、勉学に熱心なある学僧が、燈火がほしいあまり本堂の灯明の油をつい盗んでしまいました。それを見とがめられ逃げたひょうしに石段からころげ落ち、これが元で死んでしまったそうです。その後この石段を上がり下りすると災いに合うと云われ、今でも封印されているのだそうです。実際に見てみると石段はかなり朽ちていて、当時から補修もせずにそのままにされているのが分かりました。
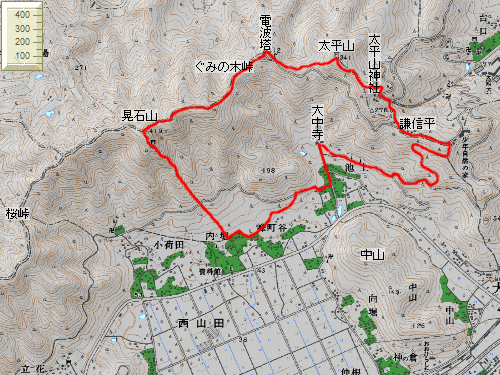 Kashmir 3D |
今日は、大中寺から東に向かって謙信平という尾根筋に出て、そこから尾根伝いに太平山(おおひらさん)、晃石山と歩く予定です。(はじめは桜峠まで回るつもりでしたが、ショートカットすることに。)
| 晃石山 |
山門脇の車道を緩やかに上っていきます。この道をまっすぐ行くと、謙信平まで車で上がることができます。振り返ると晃石山…ですが、手前の尖ったのではなく、一番奥のピークです。
| 登山口 |
ここから左手の山道に。
| カニクサ |
藪を這い上がるようなツル性の植物。これはシダの仲間のカニクサです。ビックリするのは写真左側に写っている部分の全体が1枚の葉であるということ。2mくらいになるのが普通です。写真右側は葉の一部を構成する羽片と呼ばれる部分です。
| 落葉広葉樹林 |
葉を落とした広葉樹林の中を行きます。聞こえるのは枝を渡っていく鳥たちの声だけで、それも行ってしまうとあとは静かな冬の里山です。
| ミツバアケビ |
枯れ色の山野にあって鮮やかな黄色の葉を見せているのはミツバアケビ。付近を探してもあの甘~い果実はもうありませんでした。そりゃそうですよね、10月くらいが時期ですから。アケビの葉なんて普段まじまじと見ることはないのですが、なかなか「和」のテイストで趣がありますね。
| カラスウリ |
少しずつ陽が差してきました。その陽を鈍く照り返すカラスウリの果実。日本の伝統色の「深緋(こきひ)」色です。
| 謙信平 |
しばらく登っていくと、おみやげ物屋が並ぶちょっとした昭和の観光地のようなところに出ました。ここが謙信平です。太平山の尾根筋から南に張り出した台地で、眼前に広がる関東平野の展望が素晴らしいです。
| 謙信平から |
謙信平から南西方向の眺め。広大な関東平野が広がっています。
解説板によると、戦国時代の頃、関東平定を巡って争っていた越後の上杉と小田原の北条とが、永禄11年(1568年)に大中寺の和尚の斡旋で和議を結んだという史実があるそうで、この場所の名前は上杉謙信がここから関東平野を眺めた(だろう?)ことから付けられたものなのだそうです。それにしても大中寺の和尚さん、なかなかの人物だったようですね。
| 名残の紅葉 |
謙信平には遅い紅葉がまだ残っていました。ここには桜もたくさん植えられているようで、季節ごとに観光客で賑わうのだと思います。観光バスの駐車場も整備されていましたから。
| オオモミジ |
謙信平から太平山神社に向かう途中でオオモミジの黄葉に出会いました。日本にはカエデ科の植物が20数種あるそうで、そのほとんどが日本固有種だそうです。紅葉を見るにつけ日本に生まれて良かったと思います、ホント。
| 隋神門 | 勅使門 |
しばらく行くと太平山神社の参道途中にある随神門にやってきました。随神門とは、8代将軍吉宗によって建立された門で、左右に仁王が配されています。昔は神仏が合わせて祀られていたのでしょう。この門のはるか下(写真では車道の右手下)から階段が連なっていて、この門をくぐって更に上へと伸びています。この階段が本来の参道です。
yamanekoは車道を歩いてきたので、途中から参道に入る形で随神門をくぐり、階段を上り始めました。すると50mくらい上に勅使門があり、その先が本殿です。
| 太平山神社 |
勅使門をくぐると正面に本殿があり、その右手に諸神を祀る社がずらりと20近くも並んでいました。縁起によると、平安初期に慈覚大師が開山したとあり、江戸時代には幕府の庇護も厚かったといいますから、ずいぶんと由緒のある神社のようです。(慈覚大師はここ下野の国の出身だそうです。)
| 奥宮へ |
登山道は境内右手の奥宮入口へと続いていて、ここから再び山道になります。もうしっかりとした日差しで、アウターを1枚脱いでから登り始めました。
| 登山道 |
木漏れ日の中をゆっくりと登っていきます。心地いいです。
| 栃木市 |
北東方向の展望が開けているところがありました。この辺りの標高は約280m。目の前に広がる街は栃木市です。
ちなみに栃木県の県庁所在地は宇都宮市ですが、このように県名と県庁所在地の名が異なっている府県は全国に16県、同じなのが23府県あるそうです。どうも調べてみると、もともと県庁所在地ありきの県名だったようで、県庁所在地の名前を県名とすることが原則だったようです。栃木県の場合廃藩置県の初期に宇都宮県と栃木県とが合併し、栃木市が県庁所在地となり県名も栃木となって、その後に県庁所在地が宇都宮市に移転したのだそうで、その移転の際に県名は変更しなかったという経緯があるようです。
戊辰戦争で負けたところは県庁所在地の名前を県名にさせなかったというまことしやかな話を聞いたことがありますが、どうも直接的にそのようなルールがあったわけではないようですね。
| 太平山へ |
落ち葉を踏みしめながらの山歩き。太平山神社から山頂まではゆっくり歩いても30分くらいです。
| 富士浅間神社 |
10時40分、太平山の山頂に到着しました。標高は341m。山頂には木立に囲まれて富士浅間神社が鎮座していました。祭神は木花咲耶姫命で、この地域の主だった山の頂には必ずと言っていいほど富士浅間神社が祀られているそうです。
小腹が空いたのでベンチに座ってアンパンを。その間に2人の登山者が通り過ぎていきました。
| 急坂 |
太平山から西に向かって稜線を下ります。この辺りはヒノキの林です。
| 明るい尾根道 |
急坂を下りきると、だらだらとした尾根道を登ったり下ったりしながら歩いていきます。辺りをキョロキョロしながら歩いているのですが、この時期、さすがに花はないなぁ。
| ヤマツツジ? |
と思っていたら、ツツジの花が。若干しおれ気味ですが、しっかりと咲いていました。この株だけのことかと辺りを見回すと、あっちにもこっちにも。こりゃ何だ? 色形からするとヤマツツジのようでもありますが。しばらく眺めているうちに、なんだか暖かい気持ちに。花の魅力のなせる業ですね。
| 電波塔 |
10時55分、電波塔のある小ピークに到着。ここはスルーです。
| ぐみの木峠 |
電波塔のピークを過ぎて再び下るとぐみの木峠に出ます。ここは大中寺から谷筋を直登する登山道と合流する地点です。道標は団体さんに占拠されていたので、通り過ぎてからパチリ。
| ? |
パッと見、コウヤボウキかと思いましたが、よく見ると枝の途中に付いているじゃないですか。しかも2つ。どっかで見たことあるような気がするのですが、何だろう?
| 中山 |
南東方向の眺め。眼下には大中寺の正面にある中山が、まるで海に浮かぶ小島のように見えました。実際、12万年前の大海進の時代にはこの辺りが波打ち際だったと考えられることから、中山が本当に島だった可能性もあるのです。
| 太平山 |
振り返ると木立の向こうに太平山が望めました。こうやってみるとずいぶん歩いてきたものです。
| ヒノキ林 |
ぐみの木峠から一気に100mほど標高を上げてからは、小さなアップダウンが続きます。この辺りはまたヒノキの林です。
| おぉ、これは |
登山道の脇の林がぽっかり空いていて、そこに10人くらいの人影が。一見してパラグライダーの人たちだと分かりました。どこかにいる仲間と頻繁に無線交信していて、どうやら離陸に必要な風を待っているようです。
ここにはパラグライダーの離陸ポイントとして整備された場所のようですが、車で上がって来られる場所じゃあないので、ここまで機材を上げるのが大変でしょうね。きっと飛んでいるときの喜びはより大きいかもしれません。
離陸の連続写真。ふもとから吹き上がる風に乗って、広大な関東平野に向かって飛び出していきました。気持ちよさそう。
| 晃石山山頂 |
11時40分、晃石山山頂に到着しました。山頂はパラグライダーの離陸ポイントのあったピークからいったん下って上り返したところです。謙信平でもそうでしたが、ここ晃石山の山頂にもアマチュア無線を楽しんでいる人がいました。いずれも中高年の男性で、学生の頃にハマったくちなのではないでしょうか。
とりあえずベンチに腰かけて昼食です。朝、コンビニで買ったおにぎりを食べて、ひとごこちがつきました。その後は風もなくポカポカとした陽を浴びて、のんびりとした時間を過ごすことができました。
| 日光連山 |
山頂から北方向には遠く雪を頂く日光連山を眺めることができました。なんとも気持ちのいい風景。ここまで登ってきた甲斐があるというものです。
| 日光白根山 | 男体山 |
今年の8月に登った日光白根山。ここから約55㎞先で「よっ、久しぶり」と言っています。周りの稜線から頭一つ飛び出ている溶岩ドームが特徴的です。男体山はその5㎞ほど手前。こっちはいずれおじゃましたいと思っています。
| 馬不入山 |
南西方向には桜峠をはさんで晃石山の西に連なる馬不入山がそのすそ野を広げていました。向こうには三毳山がこれも島影のような姿を見せています。冬の白い空気が微妙なグラデーションを演出していますね。
| 下山 |
山頂で十分に楽しんだ後、下山です。登りはじめのときには晃石山から桜峠に出て、そこから下山するつもりでしたが、上空の雲が予想より早く広がりだしたので、晃石山からまっすぐ南に下る道を下りることにしたのです。
| 上空には |
ふと見上げるとさっきのグループのパラグライダーが。ずいぶん高いところを飛んでいます。あきらかに離陸地点より高度が上がっています。
| 謎の岩 |
下山途中で見かけた謎の岩。なんかむちゃくちゃな褶曲を見せています。はじめは人為的に彫り込まれた模様かとも思いましたが、近づいてい見るとはっきりと層構造をなしていました。大きさは見えている部分だけでも2m×3m×3mくらいはありました。誰かがわざわざこんな山中に持ってこようにも、どうこうなるような大きさではありません。不可思議です。
| アオキ |
つやつやとしたアオキの実。真っ赤になったやつより美味しそうに見えるのは何故?(でも食べても美味くありません。)
| 落ち葉 |
ヤマザクラですね。秋の名残のような落ち葉です。
| 晃石山 |
午後1時、大中寺まで戻ってきました。今日は花こそほとんどありませんでしたが、冬の穏やかな里山でリフレッシュし、ついでに素晴らしい景色を楽しむことができました。由緒のある寺社もあり、どこにでもその土地土地に連綿と続く歴史があるんだとあらためて感じました。冬場はこういう山を訪ねるのがいいですね。
上の写真は帰る途中にドリーム号を停めて撮ったもの。正面左の最も高いピークが晃石山、その右がパラグライダーの離陸ポイント、ぐっと右にパンして写真右端が太平山です。山のすそ野を縁取るように集落が点在していますが、数百年前にも似たような風景が広がっていたのでしょうね。