
高尾山 〜行楽の山・喧噪と静寂と〜
 |
【東京都 八王子市 平成29年5月3日(水)】
ゴールデンウィークまっただ中です。どこにも行く予定はないので高尾山に行ってみることにしました。セッコクとかいくつかお目当ての植物はあるのですが、まだちょっと時期が早いかも。でも緑のシャワーを浴びて気分転換にはなるでしょう。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
高尾山は東京都の西部に位置しています。我が家からだと車で行くのが最も早いですが、現地での駐車場確保が難しいので(特に連休中は)、電車で行くことにしました。ルートは2つあって、移動距離は短いが乗り換えが3回ある橋本経由コースと、乗り換えは1回しかないが所要時間の長い調布経由コースです。やっぱり乗り換えは面倒くさいということに意見が一致したので、調布経由コースにすることにしました。地図を見るとかなりの大回りではありましたが。
調布で高尾山口行きの電車に乗り換えると、程度には差はあれ車内はほとんど全ての人が山行きの格好をしていて、その時点で終点まで座れないことが確定。どうせ立ちっぱなのなら所要時間の短い方にしておけば良かったと軽く後悔したしだいです。
| ケーブルカー駅 |
京王線の高尾山口駅に着くと人、人、人…。普段でも人出の多いところですが、さすがはゴールデンということで「アメ横か?」というくらいの喧噪でした。そこから登山口のあるケーブルカー駅までも、まるでコンサート会場に向かう人の流れのような感じ。これだけの人が高尾山に登ると重みで標高が下がるのではないかと心配になるくらいでした。
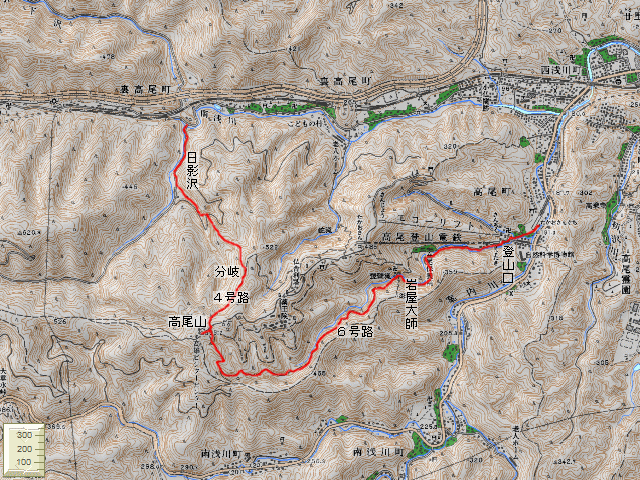 |
Kashmir 3D |
今日のルートは、登山口から沢沿いを進む6号路で登り、山頂で休んだ後、4号路で下り始め、途中から日影沢に分岐して高尾山の北側に下るというもの。下山後はバスでJR高尾駅に帰ってきます。
| 6号路入口 |
10時15分、スタート。ほとんどの人はケーブルカーやリフトで上るか、ないしは1号路から登りますが、それでも6号路にもたくさんの人が流れてきます。立ち止まって植物の写真を撮るのにもちょっと気を遣うほどの人の多さです。
| シャガ |
この時期沢沿いの6号路の彩る花としてはこのシャガが主役。登山道脇にずっと続いていました。シャガは斜面に根を張り、土留めの役割を果たすので、もしかしたら意図して増やしているのかもしれません。
| ツルカノコソウ |
ツルカノコソウの白い花。1個の花はごく小さく7、8mmくらいですが、寄り集まることによって虫へのアピール度を高めています。
| ヤマルリソウ |
涼しそうな色合いのヤマルリソウ。薄桃色のものも見かけます。花冠の中央にもう一つ花があるみたいですね。
| ミミガタテンナンショウ |
マムシグサの仲間のミミガタテンナンショウ。何が「耳型」かというと、仏炎苞が左右に広がった形をしていて、それが耳たぶみたいということのようです。
| イワボタン |
高尾山周辺でよく見かけるイワボタン。ネコノメソウの仲間です。花は早春に咲き、この時期もう果実ができています。
こんな感じで、前にも後にも人が続いています。
| 岩屋大師 |
岩窟の中に仏像が収められていました。岩屋大師というのだそうです。
見上げると、日を透かした葉が自ら発光しているかのようでした。
| ニリンソウ |
ニリンソウ。山菜好きの間では人気の植物です。ただ、この葉と間違えてトリカブトの葉を誤食してしまう事故が多いとのこと。確かに似てはいますが、トリカブトといえば全草猛毒。そんな危険を冒してまで食べようとするとは、ニリンソウの若葉ってそんなに美味しいんでしょうか。
| ハナネコノメ |
湿っぽいところを好むハナネコノメ。雄しべの先の葯が深紅色をしていて、それが目立つ花ですが、開花期は3月末です。今は花弁状の萼裂片が残るのみです。
| ウスバスミレ? |
スマートなスミレ。自信はないけど…、ウスバスミレでしょうか。ちょっと違うか。高尾山はスミレの山と言われるほどスミレの種類の多い山です。
| 硯岩 |
「硯岩」との標識。その昔、海底で生成された黒色粘板岩が隆起の過程で直立し、地上に顔を出したものとのことです。黒色粘板岩はその名のとおり硯に加工されるのだそうです。
| クサイチゴ |
「草」と名が付き、加えて丈も小さいものの、クサイチゴは立派な樹木の仲間。
登山道はこの辺りから沢筋を離れ、山肌を上っていきます。だいぶん山頂に近づいて来ました。
| タチツボスミレ |
日本を代表するスミレだそうです。ということは似たようなスミレを見たら「タチツボスミレ」と行っておけばだいたい大丈夫ということですね。
| チゴユリ |
チゴユリは葉陰でうつむいて咲く花。清楚な花です。
| ミヤマシキミ |
ミヤマシキミの花ですが、花弁がみんなヨレヨレですね。まさに開こうとするタイミングなのでしょうか。
この階段が現れると山頂も近いです。それにしても人が多いですね。
| ツクバキンモンソウ |
シソ科のツクバキンモンソウ。よく似た花を付けるニシキゴロモがタワー状に直立するのに対して、こちらはべたっと地面に伏せるような姿です。
| 山頂直下 |
頭上が開けてきました。山頂はすぐそこです。
| ニガイチゴ |
ニガイチゴは花弁が細いので見分けは比較的簡単です。名前に反して果実は甘いです。
| サルトリイバラ |
サルトリイバラの花が咲いていました。葉はよく目立ちますが、花は葉と同じような色をしているのでなかなか目に留まりません。
| 山頂 |
12時ちょうど、山頂に到着です。この向こうが山頂広場。メインルートから上がってきた人と合流してすごいことになっています。
| 展望台 |
人混みをかき分けて山頂部西端の展望台にやって来ました。ここからは富士山が望めるはずですが…。
| 富士山 |
おお、薄雲を背景にして確かに富士山の姿を確認することができます。50km以上離れているにもかかわらずこの大きさ。存在感ありまくりです。ちなみに左の山は丹沢山塊の北端にある大室山(1588m)です。
| 4号路へ |
人混みの中で昼食の弁当を食べ、30分後に出発。山頂直下から左手の4号路に入ります。4号路は稜線の北側の山腹を通る道で、数km先でまた稜線の道(1号路)に合流します。
| ヒトリシズカ |
多摩丘陵ではもう終わってしまったヒトリシズカの花。ここは北側斜面だからか、まだ残っていました。
| 広葉樹林 |
高尾山の森は、東西に走る稜線を境に南側は針葉樹林、北側は広葉樹林になっています。なので北側の方が森の中が明るく感じます。
| ヤマウツボ |
この奇妙なものは…、ヤマウツボ。ブナの根などに寄生する葉緑素を持たない植物です。
| 日影沢へ |
4号路で徐々に高度を下げていった後、途中で左手に折れ、更に急角度で下っていきます。この道を行くと日影沢に至ります。
| ハナイカダ |
4号路を離れると急に静寂が訪れました。これまでわんさかといた人がまったくいなくなったのです。ここからはのんびり山歩きが楽しめそうです。
これはハナイカダ。葉の付け根から花のところまでの主脈が太いのは、本来直立すべき花茎が葉脈と合着した構造になっているからでしょうね。
| ホウチャクソウ |
ホウチャクソウ。この時期、関東地方ではおそらくどこに行ってもお目にかかれる花です。
| ツクバネウツギ |
たまたま小休止した場所でふと見上げるとツクバネウツギの花が揺れていました。ちょっと盛りが過ぎた感じではあります。ここで休憩していなかったらそのまま気づかずにいたのでは。この花に呼び止められたのかもしれませんね。
| 日影沢林道 |
1時40分、日影沢林道に出ました。急な下りはここで終わり。ここから少し行ったところの渓流が日影沢です。
| ハコベ |
日影沢の水辺を散策。ハコベです。小さな花ですが、自然の造形とは思えないポップな姿をしていますね。
| ミツバツチグリ |
こちらはミツバツチグリ。整った造形をしていますね。どっかの家紋みたい。
| ウワバミソウ |
「蟒蛇草」とはおどろおどろしい名前ですね。ヘビでも出そうな陰湿な環境に生える植物ということのようです。写真のものは花序に柄があるので雄株。雌株の花序は無柄です。
| ジロボエンゴサク |
見れば見るほど変わった形の花。ジロボウエンゴサクです。いったいどんな虫が訪れるのでしょうか。
| 日影沢キャンプ場 |
唐突にキャンプ場が現れました。日影沢キャンプ場です。我が家も子どもが小中学校の頃までは家族で頻繁にキャンプに出かけたものですが、もう何年も行っていません。最後に行ったのは10年以上前です。もうテントもタープも寝袋も処分してしまいました。
朽ちようとしている木の洞にスミレやキランソウが咲いていました。誰かが植木鉢代わりにしたのでしょうか。それとも自然の作品?
| |
林道を歩いて行きます。少しずつ谷が広がり、里が近いことを教えてくれます。
| ラショウモンカズラ |
ラショウモンカズラ。名前は、渡辺綱(源頼光四天王の一人)が羅生門に棲む鬼女の腕を切り落とした言い伝えによるもので、この花の花冠がその腕に似ているとの由来だそうです。命名した人には「見たのか」と言いたいですが。ちなみに、本来の言い伝えでは鬼女は羅生門ではなく一条戻橋に現れたとされています。この橋は陰陽師の安倍晴明の話に良く出てくる橋ですね。物の怪の出やすいところだったのかもしれません。
| シロヤマブキ |
シロヤマブキは自生地が限られている(中国地方など)そうなので、ここにあるものは植栽なのかも。公園樹としても使われるそうです。
2時15分、道路が見えました。この先にバス停があるはずです。
20分ほど待ってバスが3台連なって現れました。さすがはゴールデンウィークです。この奥の終点に小仏峠から下りてきた人たちや我々のように日影沢から下りてきた人たちを運ぶために同じ便として3台運行しているのです。そうしないと積み残しが出るからでしょうね。京王バス、なかなかやってくれます。
さて、ゴールデンウィーク中の高尾山。前半は人、人、人でしたが、後半は静かな山歩きを楽しむことができました。身近にこんな場所がある幸せ。有難いことです。