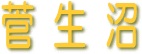
菅生沼 ~野辺にもようやく秋の風情~
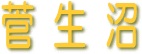 |
【茨城県 坂東市 令和6年10月20日(日)】
秋を三分して、初秋、仲秋、晩秋と言い表すことがあります。某書では、初秋を「秋めくころ」、仲秋を「秋色づくころ」、晩秋を「秋深しころ」と表したりしていました。趣がありますね。
ところが、今年は(去年もだったか?)初秋を感じられませんでした。いつまでも夏日が続き、やや暑さが和らいだかと思うと急に薄ら寒くなり、もう晩秋も近いいった風情に。なんか変ですね。
そんなどさくさのような今年の秋ですが、野山もちゃんと季節に応じて移ろっているか確かめに行くとこにしました。場所は茨城県の平野部、利根川の支流にある菅生沼(すがおぬま)です。何か珍しいものがあるというわけではなく、ごく普通の野辺の様子を見に行くだけです。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午前8時、ドリーム号Ⅲで出発。高尾山ICから圏央道に上がり外回り方面へ。中央道、関越道、東北道とのジャンクションを通過して、坂東ICで一般道へ下りました。朝の坂東市街を南下して、今日の野山歩きのベースとなる茨城県自然博物館に到着したのは10時過ぎになっていました。
| 茨城県自然博物館 |
博物館の駐車場は概ね半分くらい埋まっていました。県外ナンバーもけっこう停まっています。休日ということもあって多くの親子連れが館内に向かって歩いていました。
この博物館には過去に2、3回来たことがあります。その当時は新宿に住んでいたので、今日のように延々100km以上走ってくるということはなく、もっと気軽に来られる場所でした。
| 花木の広場 |
とりあえず博物館の展示をひと通り見学。その後館内のレストランで早めの昼食を取り、食後博物館の裏手にある広場に出てきました。この先に菅生沼が広がっています。つまり博物館は菅生沼を背にして建っているのです。
広場の縁に立って東側を眺めると、一段下がったところに広い葦原が広がっていました。左手が上流側、右手が下流側です。対岸は常総市で、あすなろの里という自然体験施設があります。こことの間には木橋の遊歩道が架けられていて、両施設間を行き来することができるようになっています。
早速、坂道を下って水辺に下りてみることに。
| セイタカアワダチソウ |
秋の野といえばこのセイタカアワダチソウが欠かせません。往々にして邪険に扱われたりしますが、元々は観賞用に移入されたものだそうです。大きな群落を作ることが多いのは、セイタカアワダチソウが他の植物の成長を抑えるような物質を放出しているから。ただそれにも限界はあるようで、やがて自ら衰退していくそうです。
シダレヤナギの根本に美味しそうなキノコが生えていました。一応図鑑で調べてみましたが、案の定分かりませんでした。ヌメリスギタケ?
| カナムグラ |
藪を覆い尽くすかのように勢いよく茂っていたのはカナムグラ。これは雌花序です。草本でありながら雌雄異株なんです。見た目は刺々しいですが、実際、茎や葉柄には下向きの棘が密生していて、触るとザラザラしています。この棘を他の植物に引っ掛けその上にのし上がって、被さるように茂るというスタイルです。
ほどなく水辺に到着しました。ここから沼を横断するように架けられた木橋を歩いていきます。
| 下沼 |
秋の空ですね。水面にも写っています。菅生沼は、南北約5km、幅約200m~500mの細長い沼。水をたたえているのは主に下沼と上沼という池で、それ以外は広い湿地帯になっています。地図を見ると、沼には江川、飯沼川、東仁連川という小河川が注いでいて、菅生沼から下流は飯沼川として利根川に合流しています。
| タチヤナギ |
これはタチヤナギの葉です。柳というと細長く垂れ下がるシダレヤナギの葉をイメージしますが、こんなしっかりした葉を持つ柳もあるのです。というか、むしろこっちのほうが主流です。
タチヤナギの全身ショット。名前のとおり立っていますね。(どのヤナギも立っていますが。)
| カワヤナギ |
こちらはカワヤナギの葉。タチヤナギよりも細身です。
カワヤナギは秋が深まると濃い黄色に紅葉するので、よく目立ちます。
それにしても誰もいません。博物館の中はごった返すくらい人がいたのに。おかげでこの気持ちの良い空間を独り占めできました。
| アシ |
水辺にはアシが広がっていました。これは花序。ちょうど目の高さにあったものですが、一般にアシは1.5mから3mくらいに成長するので、多くは橋の上に立っているyamanekoの更に頭上で花序を揺らしていました。ちなみに、この植物をヨシと呼ぶこともありますが、これはアシが「悪し」に通じることから呼び替えたもの。現に万葉集より前にはヨシの呼び名は見当たらないそうです。よく似たものにススキやオギがありますが、それぞれ別の種で、生息域が水辺に近い順にアシ、オギ、ススキとなります。なお、茅葺きとかのカヤは、特定の種の名前ではなく、アシ、オギ、ススキをまとめて呼ぶ俗称だそうです。
| アメリカネナシカズラ |
なんだか赤い塊が。これはアメリカネナシカズラが別の植物に覆いかぶさるようにして茂っているもの。ツル性の寄生植物で、一旦寄生の状態に入ると、名前のとおり根までなくしてしまうそうです。そんなことをすると相手が枯れたら自分も死んでしまいそうなものですが、そうなる前に他の植物に取り付くのでしょうね。
| イシミカワ |
カラフルな実を付けているのはイシミカワ。正確には花被が肉厚になって丸く実を包みこんだものだそうです。熟すにつれて白色から紅紫色、青藍色に変化していきます。葉が三角形なのも特徴的。
下沼の上流側。静かです。聞こえるのはどこかでモズが鳴いているくらい。
こちらは下流側。広々としています。足を止めしばらく眺めていたら、一瞬「あれ? ここどこだっけ」と意識がワープしてしまいました。縁もゆかりも無い、しかも無音の場所に一人いたら、そんな感じにもなろうというものです。
対岸に渡ると土手下を川筋に沿って歩きます。こちら側は常総市になります。一昔前は水海道市と言っていました。
| コセンダングサ |
草花は水辺のものから野のものに変わりました。これはコセンダングサ。
| クサギ |
土手の斜面にはクサギが。落葉小高木で、大きいものでは8mくらいになります。濃い赤紫色の萼とその中心に青紫色の実。かなり派手な色合いですが、誰に向けたアピールでしょうか。
| カラスウリ |
カラスウリが朱い実をたくさんぶら下げていました。花は繊細なレースの飾り物のようですが、実はなんというか素朴な感じです。♪静かな静かな里の秋…。どこからか聞こえてきそう。
| シラカシ |
シラカシにどんぐり(堅果)ができています。まだ緑色ですね。ブナ科の植物の実は受粉後その年の秋に成熟するものと、翌年の秋に成熟するものがあり、このシラカシはその年派。
|
茶色は落葉樹 緑色は常緑樹 |
表にまとめるとこんな感じに。翌年派には常緑樹が多いですが、何か因果関係があるのかも。
| オオブタクサ |
おお、これは秋の花粉症の原因となる植物の一つ、オオブタクサですね。既に花粉は飛ばし終えています。一年草で、毎年種子から成長しますが、成長スピードが半端なく、春の発芽後あっという間に数mにまで達します。ただ、株自体の寿命は半年ほど。極めて慌ただしいライフサイクルです。
| カラスウリ |
手の届くところにカラスウリの実があったので中を見てみました。ぎっしりと身が詰まっているわけではなく、結構スカスカ。半ゼリー状の果肉に包まれて種子が何個かありました。種子は両端を切り落としたクロワッサンみたいな形です。(現物を見ればああなるほどと思うはず。)
| アキノノゲシ |
アキノノゲシの花は淡い黄色。優しい色合いです。草丈は人の背ほどにもなり、周りの草から抜きん出ているのですが、その色合いからあまり自己主張していないように思えます。なのでつい見逃すことも。
坂道を上って土手の上へ。この先にあすなろの里があるはず。
| あすなろの里 |
歩いた先に入り口が。正門は別のところにあり、ここは言ってみれば裏口に当たるところ。つまりあすなろの里から菅生沼にアプローチするためのゲートということです。yamanekoはここでUターン。
| メリケンムグラ |
再び土手を下ります。これはメリケンムグラ。1cmほどの小さな花で、地面を這うように茂っていました。花弁に細かい毛があるのが分かります。
| ノコンギク |
これはノコンギク。漢字では「野紺菊」です。野山の菊ではポピュラーなものの一つ。花弁の色には濃淡があります。
時刻は12時30分。さて、橋を渡って博物館に戻りましょう。
坂東市側の土手下まで戻ってきました。ここを上ると博物館が建っています。
| 川土手 |
午後1時、博物館を後にして、車で上沼の方に移動してみることにしました。
飯沼川の土手。子供の頃、近所の川土手の砂利道を歩いた記憶が蘇ってきました。当時はずいぶん長い道のように感じていましたが、今思うとそうでもない距離です。
| 天神山公園 |
上沼の近くに天神山公園という史跡っぽいところがあり、そこに駐車場がありました。土手から河原に突き出すようにこんもりとした丘がありましたが、ここがどういう由緒をもった場所なのかよく分かりませんでした。名前からすると昔は天満宮があったのかもしれません。丘に上がってみてもそれらしい痕跡はありませんでしたが。さすがにこんな河原に古墳ってことはないですよね。
| 展望デッキ |
丘の麓、川側には高床式の展望デッキがありました。おそらく鳥を観察するためのものだと思います。冬季、ここにはオオハクチョウが飛来するとのことで、鳥好きには有名な場所とのことです。
| 上沼 |
上沼。ここでオオハクチョウが長旅の疲れを癒やすんですね。この日は鳥の影はまったくありませんでした。せめて留鳥くらいは姿を見せてくれても良いようなものでしたが。
天神山公園でしばらくボーッとしてから、帰途につきました。今日はごくごく普通の秋の野辺を楽しむことができました。おかげでずいぶんとリフレッシュできたような気もします。ロングドライブをしてきた甲斐もあったというものです。そして、幸いなことに帰りの圏央道もまったく渋滞していませんでした。
ところで、茨城県自然博物館に興味深い展示がありました。1本のブナの木に葉や実がどのくらい付いているのか調べてみたというものです。それによると、幹の直径14.4cmのブナで、葉が2万6千枚(重さ5~6kg)、実が500個だったそう。葉はそんなもんかと納得感がありましたが、実は案外少ないんだなと思いました。また、実際に数えたものか計算上のものかは分かりませんが、幹の直径40cmで実が1万5千個、直径75cmで6万個とのことでした。そんなにたくさんの実を付けるためには相当なエネルギーを要するでしょうね。1本でそれだけなのだから、ブナの純林がある白神山地などでは全体でいかほどのエネルギーが費やされどのくらいの葉や実が作られるのか。想像もできません。(余談)