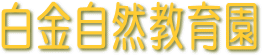
白金自然教育園 〜時間がゆっくり流れた空間で〜
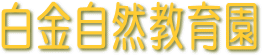 |
【東京都 港区 令和4年10月29日(土)】
「10月」というと運動会や遠足を連想しなんとなく秋晴れのイメージがあるのですが、東京ではここ数年、「10月ってこんなに雨が多い月だったっけ?」と首をひねるほどぐずついた天気の日が多い気がします。週末ごとに天気が崩れることが多かったのでそう感じるのでしょうか。
さて、今週末は晴天の予報だったので、懐かしい白金自然教育園に行ってみることにしました。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
白金自然教育園は、正式には「国立科学博物館附属自然教育園」といい、港区という大都会の中に奇跡的に残されているほぼ手つかずの自然エリアです。高度経済成長期やバブル期の開発の波に飲み込まれることなくよく生き残ってこれたものです。
この場所は、室町時代には「白金長者」が館を構え、江戸時代には松平讃岐守の武家屋敷に。明治になると軍の火薬庫となって、大正時代には宮内省の御料地となったのだそうです。そして戦後になって文部省の所管となり自然教育園として今に至っているとのこと。なかなか数奇な運命をたどったようですが、そのいずれの時代にもお上の土地だったことで切り売りされることがなかったというのが、豊かな自然が残った理由の一つなのかもしれません。こちら(公式HP)参照。
| 自然教育園入口 |
目黒駅からトコトコ歩いて、お昼12時、自然教育園に到着しました。平成の初め頃にこの近所に住んでいて、目黒駅の辺りまでは生活圏だったので懐かしいです。入口から見える木々もずいぶん大きくなりました。
園内に入ったところ。奥に向かってまっすぐに道が続いています。
以前は、オーバーユースを避けるため同時に400人以上入れないよう管理されていて、入園の際にリボンを渡されてそれを胸とかに付けて散策し、帰るときに受付に返すというシステムだったのですが、コロナ禍の影響でリボンのやりとりは休止になっていました。
| シロヨメナ |
道の両側には様々な植物が。ここは路傍植物園というエリアで、草本は基本的に植栽だと思います。これはシロヨメナ。花の少ないこの季節に綺麗に咲いていました。
| カラムシ |
カラムシです。葉の付け根から毛の密生した球のような物がたくさんぶら下がっていますが、これは雌花序。つまり雌花が球形に集まったものがぶら下がっているということです。カラムシの茎からは丈夫な繊維が採れ、人間の生活と密接な関係があったことから、今でも人里近くで見かけることが多いです。
| タマサンゴ |
タマサンゴ。初めて見る植物だなと思ったら、南米原産の外来植物だそうです。花はナス科の特徴をよく示していますね。(南米だけに、ナスカ…)
| ムクロジ |
ムクロジの実が落ちていたので、拾って杭の上に置いてみました。右下のは完熟する前に落ちた物のようです。完熟したものは蝋質に固くなり、表面にはメロンのような網目模様が現れます。中には黒く硬い種子が1つ入っていて、振るとカラカラと音がします。昔この種子を羽子板の羽根の錘に使ったのだそうです。
| スダジイ |
見上げるほどの大きなスダジイ。園内の樹木は元からここにあったもので、伐採をまぬがれて巨大なものが多いです。
| モミジガサ |
モミジガサ。花は少し盛りを過ぎたあたりか。
| キチジョウソウ |
晩秋にかけて咲くキチジョウソウ。漢字では「吉祥草」と書きます。縁起が良さそう。
ここから左手に向かい、谷戸の底に向かって下って行きます。
| 物語の松 |
その下り坂の途中にある「物語の松」。江戸時代、ここが松平讃岐守の下屋敷だった頃、回遊式の庭園にあったものとのこと。樹齢300年以上ということですね。
| ひょうたん池 |
坂を下りきると池や湿地のあるエリアに。ここはひょうたん池。以前、ここにはオシドリがやって来ていました。
| ハンター |
しばらく見ていると、カワセミのハンティングを見ることができました。水面に突き出た枝から飛び立ち、一瞬で狩りをしてまた枝に戻ってきました。
| 東屋 |
池の畔には東屋もあります。
| 水生植物園 |
東屋の先は開けた空間が。ここは水生植物園です。
| コバノカモメヅル |
園路のロープに蔓を絡ませていたコバノカモメヅル。紡錘形のものは果実(袋果)。熟すと裂けて、中から白い綿毛を持った種子が出てきます。風に飛ばされて広がるためです。
| ハンノキ |
湿地を好むハンノキ。楕円形のものは今年の果実。長細いものは来春咲く雄花序です。
| ヒメガマ |
これはヒメガマですね。褐色の「ちくわ」みたいな物は種子がぎゅっと寄り集まったもの。成熟するとちょっとした刺激で一部分がほぐれ、そうなると一気にバラバラになって風に乗って飛んでいきます。
| ナガボノシロワレモコウ |
馴染みのあるワレモコウは暗紅色をしていますが、こちらは白色。しかも穂が長いです。だから「長穂の」、「白」、「吾亦紅」。
ここ、東京都港区です。
| ミツガシワ |
ミツガシワの群落。秋の陽が水面に反射しています。長閑です。
| 森の小径 |
水生植物園を離れ、「森の小径」という本当に森の小径を歩いて行きます。
| メハジキ |
これはシソ科のメハジキ、花はとうに終わり、黒い種子がたくさんできている状態です。
| 武蔵野植物園 |
丘の上に上がるとそこは武蔵野植物園。そういえば以前ここでシロモジを見たことがありますが、シロモジって武蔵野にもあるのだろうか。
ベンチで小休止。ここからだとビルが見えません。でも首都高の音は聞こえてきます。
| おろちの松 |
まったりとした後、再び歩き始めました。
しばらく行くと倒木が。なんと、「おろちの松」が倒れているではないですか。この松は、さっきの「物語の松」といい勝負の巨木だったのですが。こちらも推定樹齢350年。令和元年の台風19号が通過した数日後、突然倒れたとのことです。立派な根の様子などを見られるよう、あえてそのままにしてあるのだそうです。もう3年間もこの状態だったんですね。ちなみに、倒れた当時の松ぼっくりから種子を採取し発芽させているそうで、いずれ園内に植栽する予定だそうです。350年後には立派になっているでしょうか。
| コクサギ |
コクサギの実。まだちょっと若いです。
| サネカズラ |
ツル性のサネカズラです。大仏の頭のようなのは集合果。その中心に球形の花托があり、その表面に小さな丸い粒が密集して付いているという構造です。茎から採れる粘液を昔は整髪料として利用していたそう。だから別名を「美男葛(びなんかずら)」。
| カラスウリ |
カラスウリ。別にカラスが好んで食べるということではないでしょうが、人間様の役に立たない植物の名前のパターンとして、「動物の名前+類似のもので役に立つものの名前」があり、カラスにでも食べさせるのにちょうどいい瓜といった意味合いで名前が付けられているのだと思います。カラスとしてもいい迷惑ですね。
| 水鳥の沼 |
園の西端にある水鳥の沼までやって来ました。このすぐ裏手は首都高が通っています。ちょっと信じられませんね。
沼ではカルガモがのんびりと。まさに都会のオアシスです。
さあ、ここからは坂を上って入口に向かいます。
| ヤツデ |
ヤツデの若い花序。この植物も民家の周囲によく植えられたもの。山を歩いていて唐突にヤツデに出会うと、昔そこに人家があったんだなと分かることがあります。
| カリガネソウ |
園を反時計回りに一周して、再び路傍植物園に戻ってきました。
これはカリガネソウの果実。1個のものもあれば2個、3個、4個と寄り集まっているものもあります。
| ムサシアブミ |
これから赤く熟していくムサシアブミの集合果。葉はもううち枯れてしまっていますね。
時刻は1時35分。入口まで戻ってきました。木立越しに通りの向こうにあるマンションが見えていて、現実世界に戻っていく感じがします。
| 目黒通り |
園を出るとこの風景。おお、ここは港区白金台だった。
もしもVRで「白金長者」の時代のこの場所を見ることができたとすると、ゴーグルの内側には海を臨む丘の上に照葉樹林と原野、その間に農耕地が点在するといった風景が映っているのではないでしょうか。
yamanekoがここを離れて約25年。以前しょっちゅう来ていた頃見ていた園内の樹木もその年月分生長しているということになります。ここが何年先まで自然教育園で在り続けるのかは分かりませんが、園内だけはゆっくりと照葉樹林に遷移していくのでしょうね。