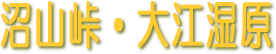
沼山峠・大江湿原 ~湿原の秋、その始まり~
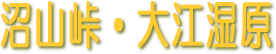 |
【福島県 檜枝岐村 平成24年9月14日(金)】
9月になりましたが、連日の真夏日。ようやくとれた夏休みも違和感を感じないくらいのギラギラとした夏の日射しです。とはいえ、いまさら夏の雰囲気を満喫するのもどうかと思い、ここはひとつ残暑の巷を抜け出して、一足早い秋を楽しみに行くことにしました。場所は尾瀬。そう、あの遙かな尾瀬です。今回は尾瀬ヶ原を見下ろす燧ヶ岳に登るのが目的です。
東京からの尾瀬へのアプローチは南側の群馬県片品村を基点とするのが一般的ですが、燧ヶ岳は広大な尾瀬エリアの北東端に位置していることから、このルートだと尾瀬エリアに入ってからの徒歩移動の距離が長くなり結構な労力を要します。今回はエネルギーを登山に集中させたいので、ちょっと遠回りにはなりますが、尾瀬の北側の福島県檜枝岐村にぐるっと回り込み、燧ヶ岳の麓の御池というところまで車で行くことにしました。ここまでは一般車が入ることができるのです。
燧ヶ岳登山には(yamanekoの足では)丸一日を要するので、初日は御池から尾瀬沼東岸まで移動して一泊し、2日目の早朝から登りはじめます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午前6時45分、ドリーム号に荷物を積み込んで出発です。いつもより若干遅めの出発ですが、夕方に宿に到着するためには昼頃までに御池に到着できればいいので、これでOKです。
西池袋の高松ランプから首都高中央環状線に入り、川口線を経由して東北道へ。平日の朝の下り線ということもあり、渋滞はまったくありませんでした。栃木県の西那須野塩原ICで一般道に下りて、そこから会津の山の中に分け入っていきます。車窓から見えるのは初秋の風景。長閑な山里の中を走っていきます。
| 御池ターミナル |
檜枝岐村の中心部を過ぎ、民家も途切れた山道を走ること30分。突然、広い駐車場が現れました。午前11時15分、ここが御池です。東京からは4時間半かかりました。
ここは燧ヶ岳の北麓に位置していて、ここから直接登ることもできますが、yamanekoはここからシャトルバスに乗り換えて、沼山峠入り口まで行き、そこから徒歩で尾瀬沼湖畔を目指します。御池から登った場合、山頂までの標高差は830m余りですが、尾瀬沼湖畔からだと670m余りとなり、170mほど楽ができるのです(これが本当に楽だったのかは後で分かることになるのですが。)。今回は尾瀬に来ておきながら登山がメインなので、これから歩く沼山峠を越えたところに広がる大江湿原も楽しみの一つなのです。
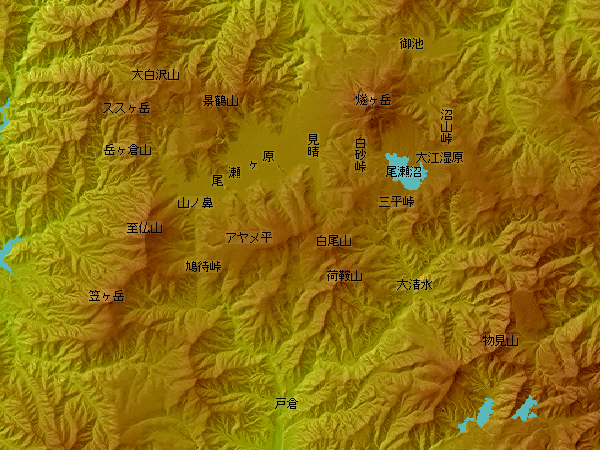 |
尾瀬エリア Kashmir 3D |
|
| 〔今回のルートを大きな地図で〕 |
御池の駐車場(440台収容!)にドリーム号を残して、11時30分発のシャトルバスに乗車。乗客はわずか6人でした。沼山峠入口までは約10㎞。所要時間は15分程度です。
| ブナ平 |
窓を開けていると寒いくらいの風が入ってきます。さすがは標高1500mです。
発車してほどなく、運転手さんがバスを停めて車窓の解説をしてくれました。上の写真は眼下に広がるブナ平。その名のとおりブナの純林です。写真奥の谷深く、檜枝岐村の中心部から谷のどん詰まりまでさかのぼり、そこからくねくね道で標高差100mを登るとこのブナ平に上がってきます。秋の紅葉は見事でしょうね。
| 沼山峠入口 |
11時45分、沼山峠入口に到着。車道はここで途切れていて、バスはここで折り返していきます(シーズン中は30分間隔で運行しています。)。
さて、移動がようやく一段落したので、休憩所のデッキに腰掛けとりあえず持参の弁当で昼食です。観光客もまばらで静かです。
| 出発 |
昼食後、休憩所で尾瀬の情報を仕入れて、入念に準備運動。そして午後1時にスタートです。今回は一泊分の荷物を背負っているのでザックはなかなかの重量になっています。あと明日の登山用の水分(4リットル)も入っていますし。
| ゲンノショウコ |
登山口にはゲンノショウコが咲いていました。そういえばじっくり見るのは久しぶりです。西日本ではピンクのものが一般的なのに対し、東日本では白いものが多いとのことです。それにしても雄しべや雌しべってこんなに色鮮やかでしたっけ?
| |
「オオシラビソ」とプレートが掛かっている樹木の下に落ちていました。明らかにモミやトウヒの雌花ですが、オオシラビソのものとしては疑問点がいくつか。まず、全体的に色が赤っぽく、種鱗と種鱗の間に隙間があるのが気になります。あと雌花の根元にちょっと残っている葉の形も先端が尖っているところが違うような。全体の印象からはアカエゾマツがぴったりなんですが、これは本州では早池峰山にしかないとのこと。ふーむ?
| ゴゼンタチバナ |
ゴゼンタチバナです。花の季節から2箇月あまり。たわわに実をつけています。隣の株は実が着いていませんが、ゴゼンタチバナは葉が4個のものはまだ若く実をつけず、成熟して6枚になると実を付けるのだそうです。木本がほとんどのミズキ科では珍しい草本です。
| |
沼山峠に向かって木道を上っていきます。森の中で風はありませんが暑くはありません。やはり標高のおかげでしょう。スタート地点の標高が1700m。峠の最高点が1781mなので、標高差は約80m。そうたいした上りではありません。峠を越えてからは標高166mのの大江湿原まで120mほど下ることになります。
| ヒロハゴマキ |
果実の柄まで赤いヒロハゴマキ。葉や枝を折るとゴマに似た匂いがするのが名の由来だそうです。「広葉(ひろは)」と名が付くとおり、ゴマキの葉と比較すると、大きさは5倍くらいになります。
| 沼山峠 |
1時25分、あっという間に峠に到着しました。木立の向こうに見えるのはまだ夏の空です。
| ハクサンシャジン |
ハクサンシャジンはツリガネニンジンの高山適応タイプ。ツリガネニンジンの花冠がやや細身の鐘型で縁が軽く反り返るのに対し、ハクサンシャジンはやや広がった鐘型で縁はそれほど反り返らず、花序の取り付け部分の柄が短いので花が密生した感じに付くのだそうです。いずれにしても微妙な差なので、生育地や標高が重要な判断材料になるのかもしれません。あと、至仏山に多く咲くヒメシャジンにも似ていますが、こちらは花柱が花冠から長く突き出ているか否かで識別できます。
| ミヤマアキノキリンソウ |
別名コガネギクとも呼ばれるミヤマアキノキリンソウ。低山や野原で見かけるアキノキリンソウより頭花が大きいのが特徴です。林内でも湿原でも見ることができます。
| シラタマノキ |
おっ、シラタマノキの果実ですね。白い部分は萼が肥大化したもので、本当の果実はその中に包み込まれています。美味そうにも見えますが、実を潰すとサロメチールの匂いがします。味は推して知るべし、ですね。
| ジョウシュウオニアザミ |
尾瀬で下向きに咲くアザミはジョウシュウオニアザミだけだとか。そう言われると自信を持って紹介できます(笑)。
| タケシマラン |
ランと言いつつユリ科のタケシマラン。初夏、葉の下に柄を伸ばして花を付けるのでその時期には控えめなイメージですが(花弁も黄緑色で目立たない。)、むしろ晴れ舞台は秋で、赤い実がよく目立っています。瑞々しく輝き、宝石のようです。
| オヤマリンドウ |
大江湿原に向かってどんどん下っていきます。路傍にはなんか上品な感じのリンドウが。オヤマリンドウです。これが満開の状態です。湿原で見かけるエゾリンドウとは異なり茎頂にのみ花を付けるのが特徴。エゾリンドウは茎頂のみならず、茎の上部の葉腋にも何段か花を付けます。色が淡いのはこの個体の特徴なのか、どうなのか。
| マイヅルソウ |
このマーブル模様の果実はマイヅルソウのもの。この状態でも十分に綺麗ですが、これから季節が進むと真っ赤に変わっていき、最終的には透明感のある石榴色になります。アクリルとかで固化したら指輪にでもできそうなんですよね(本当にあったら案外売れるかも。)。
| 湿原入口 |
2時5分、大江湿原が見えてきました。まだ9月中旬ですが、早くも草紅葉が始まっているような色合い。湿原は輝いています。
| アブラガヤ |
さあ、湿原の植物を見ていきましょう。これはアブラガヤですね。派手ではありませんが秋の湿原を彩る重要な役どころを負っています。群生しているところではまるで稲穂のようにも見えます。でも花序には油臭があるとのこと。だから「油萱」なんですね。この花は湿原の中程というより縁に近いところに多く生育しているように思います。
| オゼミズギク |
短冊状の舌状花をやや疎に付けているのはオゼミズギクです。ミズギクの変種で、尾瀬だけでなく東北地方にも生育しているそうです。ゼンテイカの花の時期が終わると、入れ替わりで湿原を黄色く彩る花です。
| ワレモコウ |
普通のワレモコウですが、尾瀬で見ると特別なものに見えてしまうのが不思議なところ。それにしても深く味わいのある色をしていますね。
| |
静かです。ほぼ無音。こんなに広くて、かつ静かな空間に身を置くことが日常に存在するだろうか。いや、しない。 と、反語を用いてしまうほど、やっぱり尾瀬は特別なところです。
| |
|||
| イワショウブ |
おお、まだイワショウブが咲いていました。この時期にはもうすっかり果実になっているかと思いましたが、辺りには白く可憐な花を付けているものも散見されます。これが写真のように赤い実になっていくのです。岩場にではなく湿原に咲くのですが、にもかかわらず名前に「岩」が付いているのは何故。ちなみに「菖蒲」は葉が似ているからだそうです。
| 燧ヶ岳 |
いよいよ燧ヶ岳が見えるところまでやって来ました。文字で表現しがたいほどの圧倒的な存在感。歩みを停め、正面に向き直ってしっかりと見据えます。明日あの山に登るのかと思うとなんかワクワク身震いするようです。体力的にはきつそうですがゆっくりと登っていこうと思います。
右端のピークが俎嵓(2346m)。その左の台形のピークは御池岳。左端はアカナグレ岳です。最高峰の柴安嵓(2356m)は奥にあり、御池岳の右肩にちょんと頭を出しています。あの山頂から眺める尾瀬ヶ原はどんなだろうか。楽しみです。おーい、待っててくれよ-。
| オクトリカブト |
有毒植物の代表格、トリカブト。その中でも世界で2番目に毒性が強いといわれているのがこのオクトリカブトだそうです。怖いですね~。2番とか言われるとリアルに怖いです。じゃあ1番は何なのかというと、北海道に分布するエゾトリカブトだそうです。昔、ヒクマを狩るのに用いた毒だそうで、よっぽど強力なんだと思います。恐ろしいです。
| 尾瀬沼 |
尾瀬沼が見えてきました。銀色の湖面、広い空。趣のある風景ですね。見渡す限り誰一人いないのもこの景色を独り占めしているみたいで気持ちいいです。湖畔に立っているのは三本カラマツ。沼尻方面からの木道がこの木の元を通って、100m先でこちらの木道と直角に交わっています。
| ウメバチソウ |
午後の日射しを受けて浮き立つように輝くウメバチソウ。もう本当に秋なんですね。
| 尾瀬沼ヒュッテ |
午後3時、尾瀬沼湖畔に到着しました。今日の宿泊場所の尾瀬沼ヒュッテがある場所です。ここには他に長蔵小屋という山小屋もあります。尾瀬沼ヒュッテも山小屋ですが、基本的には相部屋なしの個室で、ゆったりと宿泊できます。この日は8割方部屋が埋まっていたみたいです。チェックインの際に、御池の駐車場が無料になるコインと檜枝岐エリアで使える1000円分のクーポン券をもらいました。宿泊料も平日割引(一人△2千円)。いきなり大サービスの出迎えで、ほんとにいいんですかといった感じです。
山小屋での生活時間帯は俗世間のそれとは数時間の時差があります。風呂は3時半から。チェックインしたらすぐに入浴です(尾瀬ルールにより石鹸やシャンプーは不可。)。夕食は5時から。なんと入院中の病院よりも早いです。消灯は9時、そして朝食は6時からです。
夕方4時半、風呂上がりにヒュッテの周りを散策しました。涼しい風が吹いてきて、林の木々をざわざわと揺らしています。予報では明日の天気も晴れ。今日は早めに就寝して、明日に備えようと思います。