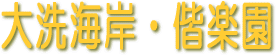
大洗海岸・偕楽園 〜春の兆しを探しに〜
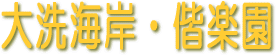 |
【茨城県 大洗町・水戸市 平成19年1月28日(日)】
地球温暖化が言われて久しいですが、この冬は特に暖冬のようです。少なくともこれまで東京では雪は降っていませんし、ひょっとしたら一度も降ることなく春を迎えるかもしれないそうです。ニュースでも気の早い梅の開花を各地から伝えています。
梅といえば水戸。天気予報も晴天を伝えているので、水戸周辺を散策してみることにしました。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午前9時半、首都高に乗って、中央環状から6号三郷線、さらにそのまま常磐道へ。渋滞もなく快調に走っていきます。
友部JCTで北関東自動車道に入り東へ、水戸大洗ICを下りたのは11時すぎでした。まずは那珂川の河口近くの大洗海岸に向かいます。
 |
大洗海岸 |
どーん! 太平洋です。けっこうな大波が次から次へと押し寄せてきています。
利根川の河口がある銚子から北に弧を描く砂浜の鹿島浦。それが那珂川の河口のある大洗で終わるのですが、この長い海岸線の砂を供給したのが利根川と那珂川でしょう。そしてその砂を強い波が押し戻し長くなめらかな海岸線を造ったのです。
| 那珂川河口 |
その波の力の強さを物語っているのが上の写真。中央に写っている青いガードレールのある車道。その護岸がガードレールごとはぎ取られようとしています。もちろん通行止めになっていましたが、それにしても凄まじい力です。まだ新しい護岸なのに。ちなみに遠くに見えているのは那珂湊漁港。その間が那珂川の河口になります。
どうやらここはサーフィンのスポットのようです。もうじき立春とはいえ、今が一番寒い時期のはず。心底好きでなければできないでしょうね。
| コウボウムギ |
この辺りで何か植物はと探すと、浜に下りる途中の砂の斜面にコウボウムギのドライフラワーを見つけました。あちこちにありますので、夏にはこの斜面を覆い尽くすのではないでしょうか。ちなみにムギと名が付いていますが、カヤツリグサの仲間です。別名をフデクサといい、これは地中部の繊維を筆に使ったとされることからだそうです。コウボウは弘法大師のこと。いくら「筆を選ばず」といったって、これは書きにくいでしょう。
| ハマハタザオ? |
うーん…、ハマハタザオの根生葉でしょうか。身をかがめて冬を乗り切ろうとしています。左にあるのはハマヒルガオの枯れ葉です。
| 大洗磯前神社 | 大判焼 |
冷たい風で体が冷え切ったので、風のないところに移動です。
海岸からほどないところの松林の中にある「大洗磯前神社」。太平洋を望む丘の上に位置していて、その参道は海に向かって延びています。縁起によると平安中期の創建で、その後中世には荒廃したものの江戸時代に水戸藩主によって再建されたのだそうです。門の奥に立派な拝殿がありました。でも、yamanekoの興味はもっぱら門の左の屋台。さっそく購入です。ところで、この大判焼。全国的に見るといろいろな呼び名があるようで、九州、関西では回転焼、中国地方では二重焼、関東、東海では今川焼というのが主流のようです。ちなみにyamanekoの故郷、島根県では大判焼と言っていました。
| 松林の道 |
大判焼をたいらげたところで神社の裏手をぐるっと回る道を歩いてみました。
松林の中の道で、アオキやツツジ(何ツツジかは分からなかった。)が林床を覆っていました。
| ツツジの仲間 | 前年の果実 |
さて、まったりとしたところで、水戸市内にある偕楽園へと向かいます。偕楽園といえば、岡山の後楽園、金沢の兼六園とともに日本三名園のうちの一つに数えられていることは有名ですね。
| 水戸といえば |
偕楽園の東門前にあるお土産屋です。「ねばり丼」、かなりフィーチャーしてます。素材ではなく粘っていることを全面に押し出す戦法。確かに「具のラインナップはなんだろう。」などと興味がわいてくる一品です。(?)
| 梅林 |
園内に入ってみました。全体にうっすらと紅くなっていますが、開花しているものはほとんどないようです。
偕楽園は、江戸時代後期、水戸を流れる桜川の段丘を利用して造られた広大な庭園で、その名は「民と偕(とも)に楽しむ」という意味。その名のとおり開園当初から毎月「三」と「八」の付く日には領民にも開放されていたのだそうです。その流れか、現在も入園無料です。
| 左近桜 |
存在感満点の桜。京都御所の紫宸殿の左近桜から根分けしたものなのだとか。満開時にはド迫力でしょうね。奥にある建物は「好文亭」。散策時の休憩所といった役割で、「好文」とは中国の故事に由来する梅を指す言葉なのだそうです。
| せっかちなやつ |
園内に約3千本あるとされる梅のなかで満開状態のものが1本だけありました。どこの世界にも変わり者はいるものです。
梅の枝の下で弁当を広げる親子連れ。ほのぼのとしてますね。「梅一輪 一輪ほどの暖かさ」 今日はそんな気候です。
ところで、梅は万葉の時代に中国から渡来したもので、一部九州に野生化したものがあることは知られていますが、日本にはもともと野生種はないといわれています。渡来当時、宮廷を中心として栽培された梅がその後これだけ万民に親しまれるようになったのは、中国文化とともに全国に広まったからでしょう。菅原道真を慕って一夜にして太宰府まで飛んだ梅があったくらいですから、日本中への伝播も速かったのでは。(?)
その道真の故事から梅といえば「学問」というイメージがありますが、現在ではちょうど受験シーズンと重なって開花することもあるのかもしれませんね。
| ナズナ |
梅林の中には着実に春が近づいていました。春の七草のひとつのナズナが咲き始めています。でも、これは例年どおりのペースでしょう。
今年の冬は確かにおかしい。いや冬だけでなく四季が少しずつ崩れていっているようです。
咲かないはずの時期に咲く、生まれないはずの時期に生まれる、いないはずの地域に繁殖する。海岸の激しい浸食もそうですが、これまで何千年の単位で変化してきたことが、10年とか20年とかそのくらいのタームで変化してきているようにも思えます。このぶんだと近い将来、後戻りできない「分水嶺」を越えてしまうのではないでしょうか。