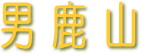
男鹿山 〜世羅台地の展望台から〜
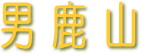 |
【広島県甲山町 平成16年6月1日(火)】
例年より早く5月中に梅雨入りとなった今年。昨日は早朝からバケツをひっくり返したような雨で一日中降り続きましたが、日付が変わって6月に入ったとたんに見事な「五月晴れ」になりました。
代休シリーズ第2弾。今日は自生南限のスズランを見に、甲山町の男鹿山に向かいました。
甲山町は広島県の内陸部、世羅台地の東部に位置する町です。
| 登山口脇 |
世羅台地には「玄武岩ドーム」と呼ばれる形状の山がいくつもあります。この男鹿山の他にもとなりの女鹿山、少し南にある高山、新山などです。いずれも新生代更新世に玄武岩の噴出によってできた山だそうです。その姿は世羅台地の平坦面から突出していて、遠くからでも目立っています。ということはその山頂からの眺めも天然の展望台として期待できるということですよね。
そして、この男鹿山の山頂には自生の南限といわれるスズランが咲くことで有名で、ちょうどこの時期が見頃なのです。
| ハナニガナ |
登山口脇の待避スペースにドリーム号を停めて、山頂を目指します。といってもせいぜい3、40分もあれば山頂に立つことができます。
昨日までの激しい雨で登山道の表面の落ち葉がきれいに流されていて、硬く締まったきめの細かい火山灰質の地面がツルツル滑ります。
| ミヤマナルコユリ |
平日なので行き交う人はほとんどいません。今日も妻と二人連れです。
静かな山。風が梢を揺らす音が大きく聞こえるような気がします。
| 登山道 |
路傍には実を付けたチゴユリが並んでいます。ショウジョウバカマは茎をぐーんと伸ばしていました。
| ハナイカダ | フタリシズカ |
広島県の地形の特徴は、大雑把に言って、中国山地から瀬戸内海に向かって上段、中段、下段の三段の階段状になっている点です。
地表が長ーい間にわたって浸食作用を受けると、起伏がほとんどなくなり、高さも低下した平原状の地形になります。これは浸食作用の到達する終末的な姿で、「準平原」と呼ばれています。ところが日本のような地殻変動の激しいところでは完全な準平原になる前に土地の上昇が起こり、次の浸食作用が始まります。こうやって何段かの平坦面ができあがるわけです。
広島県では上段を高位面(脊梁面)、中段を中位面(吉備高原面)、下段を低位面(瀬戸内面)と呼び、それぞれ1000m〜1300m、400m〜600m、100m〜200mの高さを占めています。ここ世羅台地は中位面のど真ん中にあり、同じような高さの山並みが延々と続いています。
山頂から北方向を眺めると、よく分かります。手前の濃い色の山並みが中位面を構成する山々で標高600m前後です。(平坦面といってもそれは大きく俯瞰した場合の表現であり、実際には隆起後の浸食により谷が刻まれていています。念のため。) 奥の方の薄い色の山並みが高位面を構成する山々。左から、大万木山、猿政山、吾妻山、比婆山、道後山と県境の山々が並んでいます。
| スズラン |
山頂直下にスズランの保護区域がありました。動物園のライオンの檻のような柵で盗掘から守られています。ちょと興醒めですが、こうまでしなければならない現実があるのでしょう。この写真は柵の隙間からズームで撮ったものです。
広島に戻る途中、東広島市にある広島大学に寄ってみました。お目当てはササユリです。
ここに勤務するTさんから「そろそろ見頃だよ」というメールをもらっていたので、楽しみにしていたのです。
工学部と総合科学部の間にある通称「ササユリ谷」に降りてみると、あたり一面に甘い香りが漂っていました。
咲いてる咲いてる、ちょうど今が盛りのようです。あっちにも、こっちにも。狭い谷ですがざっと50株は咲いているようです。
去年の暮れ、仲間と下草刈りをした成果が出たようです。