
西沢渓谷 ~百々と流れ下る水の畔~
 |
【山梨県 山梨市 平成18年7月30日(日)】
いやぁ、しばらく野山から遠のいていたらいつのまにか7月も終わろうとしているじゃないですか。
いかん! こんな生活をしていては。やっぱり週末には(できれば平日にも)野山に出かけて、本来のスタイルをとりもどさなければ。
ということで、今回訪れたのは山梨県北部にある西沢渓谷です。ここには10数年前、ちょうど紅葉の時期に来て感動したことがありますが、盛夏のこの時期もきっといい感じなのではないでしょうか。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
東京から中央道を西へ。車は多いですが、道はスムースに流れています。渋滞ポイントの小仏トンネル、笹子トンネルも順調に抜けて、山梨県の勝沼ICで高速を下ります。
勝沼一帯はブドウの一大産地。道の左右に観光農園がずらりと並んでいました。旧塩山市(現甲州市)の街並みをかすめて北上し、武田信玄の菩提寺である恵林寺脇を過ぎた辺りから左右に山が迫ってきました。ここから奥に向かう道は「秩父往還」と呼ばれ、最奥まで行き当たると標高2000mの雁坂峠を越えて秩父(埼玉県)へと続いています。その昔から人馬でなければ越えられない小径でしたが、平成10年に念願だった雁坂トンネル(全長6.6㎞)が開通したことにより、それまで県境に道路のなかった山梨・埼玉間がつながりました。ちなみに雁坂峠は「日本三大峠」のうちの一つだそうですが、その選定基準と残り二つがどこなのか、興味があります。
| 広瀬ダム |
笛吹川をせき止めて造られた広瀬ダム。そこから県境の山並みを望むことができました。正面に見えているのは木賊山(2468m)。そのすぐ奥に有名な甲武信ヶ岳(2475m)がありますが、残念ながらここからは見ることができません。ご存じのとおり甲州、武州、信州の三国が接する嶺だから「甲武信ヶ岳」です。
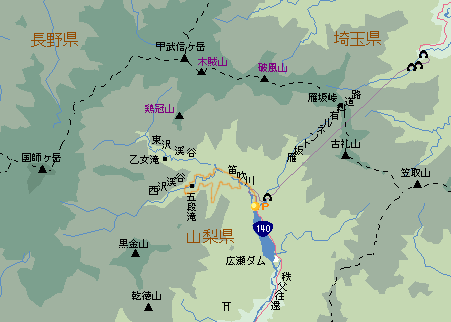 |
このダム湖の先端に道の駅があり、その隣にある「蒟蒻館」という土産物屋の駐車場にドリーム号を停めました。ここは西沢渓谷を歩く人のために駐車場を開放してくれているのです。道はここからループ橋で大きく右手に回り込んで雁坂トンネルに入り込んでいきます。
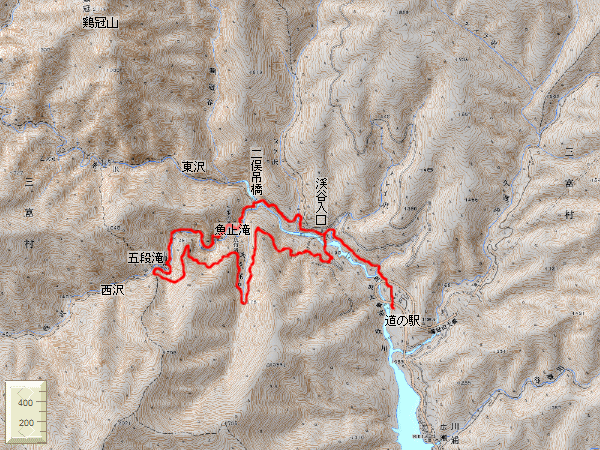 Kashmir 3D |
さて、リュックや装備を整えて、9時15分、出発です。スタート地点の標高は1100mくらいはあります。日差しは強いですが暑くはありません。
| ホソエカエデ |
渓谷の入り口までは1㎞ちょっとあります。それでも既にいい雰囲気。先月クマが出たとの掲示がしてあり、ここももう渓谷の一部といってもおかしくありません。キセキレイやウグイスの声。沢の水音。今日も楽しい一日になりそうな予感がしてきます。
葉の形はウリカエデっぽいのにサイズはウリハダカエデ。なんだろうと調べてみるとホソエカエデでした。西日本では見かけることの少ないカエデです。
| 渓谷入り口 |
休憩所とトイレ施設のあるポイントを過ぎしばらく行くと渓谷の入り口です。ここまででもあれこれ観察しながら歩いてきたので、もう9時50分になっていました。でもここからもペースを上げるつもりはありませんが。
| イワタバコ | ヤマアジサイ |
笛吹川を左に見ながら細い小径を歩いていきます。右手の岩肌に小さな紫色のイワタバコが咲いていました。切り立った岩場に咲き、その葉がタバコの葉ににていることから名が付いたといいます。
ヤマアジサイは変異の多い植物。西日本では青紫色のものが主流ですが、東日本は白いものが多いようです。写真のものは装飾花の萼片の先端が尖っています。
| 二俣吊り橋 |
川筋が二つに分かれる場所にやってきました。ここで東沢と西沢とが合流しているのです。この橋で東沢の川を渡って、写真奥に見える谷の西沢に入っていきます。河床までは15mくらいはあるでしょうか。けっこう高いです。
| 鶏冠山(とさかやま) |
橋の中程から東沢の奥の方を望むと、正面に鶏冠山(2115m)のギザギザの稜線が見えました。本当に山深いところです。
| 沢筋の道へ |
サワグルミやナツツバキなどの林を抜け、水際に下りていきます。
| 魚止滝 |
滝の後退の跡(下流方向) |
この渓谷は花崗岩を削ってできたもので、その白っぽい河床のせいで淵の色がエメラルドグリーンに輝いています。
魚止滝の下流側は細長い水路のようになっています。幅は約2m。まるでパワーショベルで掘削したかのようにきれいに掘られています。これは滝が岩盤を削りながら上流側にどんどん後退していった跡です。どんどんといっても気の遠くなるような時間がかかっているとは思いますが。
| タマガワホトトギス |
しみ出した水が岩肌を濡らしているような場所でタマガワホトトギスを多く見かけました。初めて見る花なのでじっくりと観察します。この花は本州から九州までに広く分布しているそうですが、なぜか中国地方では見たことがありませんでした。花被片が漏斗のように上向きです。ヤマホトトギスの花被片は逆に下向きに反り返り、ヤマジノホトトギスの花被片は水平に開きます。それぞれに理由があってのことだとは思いますが、不思議ですね。
| 渓畔林 |
長かった梅雨のせいか渓谷の水量は豊富です。百々(どうどう)と流れ下る様子を見ると、水が巨大な岩をころがしたり、果ては岩盤を削り谷を浸食していくのもうなずけるような気がします。後で知りましたが、ちょうど今日、梅雨明けしたそうです。
| キンレイカ | サワギク |
キンレイカは経7㎜ほどの小さな花ですが、スミレのように距を持っているのが特徴。秋の七草でおなじみのオミナエシの仲間です。サワギクは別名「ボロギク」。あんまりな名前ですが、歯が抜けたようにまばらに付いた舌状花や薄く切れ切れになっている葉の様子からそう呼ばれたのかもしれません。同じキク科にはハキダメギクというキクもありますから、いずれもかわいそうなものです。
キンレイカもサワギクも流れの畔に多く咲いていました。
| 昼食 |
いくつかの滝を見ながら渓谷に沿って歩き、流れの内側にわずかに河原っぽくなっているところでリュックをおろしました。時計を見ると12時20分。ここで昼食です。川面を渡る風が汗を冷やし、しばらくじっとしていると涼しいというか肌寒いくらいです。
| シモツケソウ | キツリフネ |
シモツケソウの淡いピンク、キツリフネの蛍光イエロー。いずれも涼やかな色合いです。ご飯を食べて、一休みして、またのんびりと歩き始めました。
| 七ツ釜五段の滝 |
13時20分、西沢渓谷の遊歩道の最奥部にある「七ツ釜五段の滝」に到着しました。濃緑の木立の中に大きなプールが何段にも連なっています。碧い淵に飛沫の白があざやか。いくつもの滝から発せられる音がそれぞれ共鳴し合って、超ド級の迫力を演出していました。こんな風景が、初めて人間がここに足を踏み入れる遙か昔から後営々と繰り広げられていたのかと思うと、その悠久のほどに日常の小さな憂いなど消し飛んでしまいそうです。(ちなみに「超ド級」の「ド」とは第1次世界大戦時のイギリスの戦艦ドレッドノート号のことだそう。「ドレッドノート」、なんか強そうです。)
| ヤマグルマ |
七ツ釜五段の滝から方丈橋を渡って対岸にとりつき、そこからいっきに山肌を上っていきます。標高差にして7、80m、やがて昔の森林軌道の跡に出ました。ここには休憩用の木製デッキやベンチがあります。この場所で標高1400mくらい。付近はアズマシャクナゲが大群落を形成していました。
| 森林軌道の跡 |
この軌道跡は、「西沢軌道」といって、約36㎞先の塩山駅まで、西沢や東沢一帯の県有林の木材搬出のために使われていたものだそうです。昭和初期から40年代までのこと。当初は、下りは自然勾配を利用するのみ。上りは馬でトロッコを2台ずつ引き上げていたそうです。戦後ディーゼル機関車が広瀬ダム付近まで運行するようになったそうですが、そこから奥はどうしても馬に頼らなければならなかったとのことです。
| 三国国境の嶺々 |
軌道跡をたどりながら等高線をなぞるように少しずつ下っていきます。途中、展望がひらけたところがあり、そこから対岸の嶺々を一望にすることができました。左が鶏冠山、中央が木賊山、右が破風山で、いずれも2000mを超える山々です。そしてその向こうは信濃の国、武蔵の国になるのです。
この場所と向こうの山々との間に横たわる深い谷が西沢渓谷になります。
| ホタルブクロ | ギンバイソウ |
この軌道沿いにもさまざまな花が出迎えてくれていました。
時計をみると、もう15時を回っています。いかにのんびり歩いたとはいえ、もう6時間になります。ふくらはぎもパンパンに張ってきました。こんなときに思わぬケガをしていますので気を抜かないようにしなければ。
| そろそろ終わりに |
15時30分、「ねとり橋」を渡って、往きに通った休憩所とトイレ施設のあるポイントに合流しました。ここまで来たら駐車場まではあとわずか。30分ほどでしょうか。少し西に傾いた日差しが心地よく感じられます。
16時、無事、駐車場に到着しました。蒟蒻館のご主人が「ずいぶんとゆっくりだったですね。」と声をかけてくれたので、「いつものことなんです。」と言って、お礼の言葉とともに借りていたボールペンを返しました(今日は筆記用具を忘れたのでここのご主人にボールペンを借りていたのです。)。
今日は長かった梅雨のうっとうしさを一気に忘れさせるような、すばらしい山歩きができました。また季節を変えて訪れたいと思います。
(余談)
帰りの中央道の渋滞、特に激しかったです。覚悟の上でしたが。