
長池公園 〜お隣さんを歩いてみたら〜
 |
【東京都 八王子市 令和6年8月20日(火)】
8月に入ってギラギラの猛暑が続いていましたが、お盆が明けてからというもの天気が不安定になってきた感じです。週間天気予報を見ても大体が曇りマークと小さな傘マーク。それでもその日になってみると急に晴れたり、また夕方になって雷雨になったり。つまり安心して遠出ができる状況ではないわけです。ということで、晴天のタイミングを見計らって近場で野山歩きを楽しむことにしました。場所は八王子市南部にある長池公園です。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
長池公園は、多摩丘陵の支稜線の北面にある南北に長い公園で、yamanekoがいつも散策している小山内裏公園のお隣さんと言っていい位置にあります。園内は、北側にある築池から南奥に向かって伸びる2つの谷戸とそれを囲む森とで構成されています。簡単に言うと「人」の文字の形に谷戸が伸びていて、1画目と2画目の接するところに築池があるイメージです。
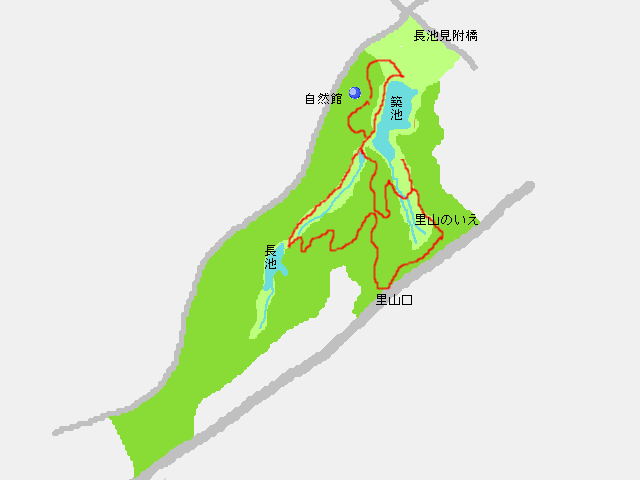 |
yamaneko手作りMap |
今日は、丘の上にある自然館からスタート。まず築池の畔に出て、そこから西側の谷戸を遡ります。この公園の名前にもなった長池まで来たら反対側の丘の上へ。この丘は2つの谷戸を隔てる丘で、やがて十字路が現れるのでそこは右折。しばらく行くと尾根幹線道路に接する里山口に至ります。そこから今度は東側の谷戸を下り、築池の手前にある田んぼ周りを観察。その後丘の上の十字路まで戻り、今度は自然館に向けて下っていきます。
| 自然館 |
午前11時50分、自然館前を出発しました。なんでわざわざこんな暑い時間からスタートするかというと、午前中のルーティン(洗濯など)を終えてやって来たのがこの時刻だったということ。夕方には一雨来るかもしれませんからね。ちなみに自然館は手前の平屋建ての建物。奥のビルは近隣のマンションです。
| 長池見附橋 |
丘を下っていくと長池見附橋が現れました。四谷にあった見附橋を架け替える際に古い橋をここに移築したものだそうです。なぜにここだったのでしょうか。今やっているNHKの朝ドラのロケ地になっていましたね。背景は明治期の四谷界隈にCG加工して。
| 築池 |
見附橋の上流側に堤防があり、築池という大きな池が満々と水をたたえています。元々灌漑用に造られたもので、大正時代には既にあったそうです。ここの谷戸は大栗川まで続く大きな谷戸なので、灌漑する範囲も広かったでしょうね。
| ミソハギ |
その堤防の縁に生えていたミソハギ。お盆のお供え花として用いられてきたもので、「盆花」と呼ぶ地域もあるそうです。といいつつ案外早くから開花していて、6月下旬から見かけたりします。
| アカメガシワ |
池の畔に延びる園路を谷戸の奥に向かって歩いていきます。これはアカメガシワの果序。雌雄異株の植物なので、これは雌の木(雌花を付ける木)ということになりますね。この時期、果実が熟して割れ、中の黒い種子が顔を出しています。光沢があって鳥たちにもよく目立つのではないでしょうか。
時刻はお昼すぎ。真上から日差しが降り注いでいます。
| メハジキ |
これはメハジキですね。高さは1.5mほどもありました。別名を「益母草」(やくもそう)といい、これは妊産婦の保健薬として利用されていたからだそうです。シソの仲間です。
| キツネノカミソリ |
キツネノカミソリ。葉がヒガンバナの葉に似て細くシュッとしているところから、それをカミソリに見立てた名前だそうです。カミソリの前に「キツネノ」が付いているのは、狐が使っていそうなカミソリという意味。夕暮れ時などに見るとそんな怪しげな雰囲気があったのかもしれません。
園路のところどころに水辺に降りる枝道が設けられていて、そういった場所には湿った環境を好む植物が茂っています。足元が滑りやすいので注意して入ってみると…。
| キツリフネ |
ありました。これはキツリフネですね。ツリフネソウの黄色バージョンどいう意味合いですが、れっきとした別の種です。色のほか外見的にもツリフネソウに比べると距(花冠の後ろに延びる尻尾みたいな部分)の巻が緩いです。ツリフネソウの場合、テナガザルの尻尾みたく、くるっと巻いています。
| ミズタマソウ |
こちらはミズタマソウ。花冠の大きさは6mmほどとごく小さいです。写真の下の方には果実があります。細かい毛に覆われていて、ここに露を留めることから「水玉草」の名が付けられたのだそうです。
| 長池 |
12時25分、園路の突き当り、長池の畔にやって来ました。ここから奥は立入禁止です。地形図を見るとこの池のさらに奥にも谷戸が伸びているので、昔はその辺りまで耕作地として利用されていたのではないでしょうか。
| タヌキマメ |
フェンスの際にタヌキマメがありました。水辺を好む植物で、花は昼に咲いて夕方にはしぼみます。紫色の花弁の背後に長い毛が密生している萼があって、この後豆果を包むようになり、花の下に写っている丸っこい果実の姿になります。タヌキマメを初めてみたのは、広島県にある八千代湖の畔で行われた観察会でのことでした。ちょうど20年前のことでした。
ところで、この植物もタヌキという動物の名を冠していますが、こちらの方は毛深いところが狸に似ているということのようです。
長池の奥の方を見上げると、鬱蒼とした木々の森になって…いるように見えますが、案外近くまで開発の波は押し寄せているのです。
| 丘の上へ |
長池からは折り返すような形で丘を上がっていきます。
| ガンクビソウ |
ガンクビソウです。まだ蕾のように見えますが、これで開花状態。ガンクビとは「雁首」と書き、煙管(きせる)の先端部分のことですね。
子供の頃、祖父が煙管を使っていたことを思い出します。半透明のプラスチックのタバコケースから新生だか若葉だかの巻きタバコを出して、その先の部分をちぎって雁首に詰め、火を付けていました。残った部分のタバコはまたケースに戻していました。今考えると、節約して吸っていたのでしょうかね。
| ヤマノイモ |
これはヤマノイモの雄花序です。ヤマノイモとは自然薯のことですが、スーパーで見る自然薯は栽培して立派に育てたもので、この株の根元を掘ってみたところで、必ずしも立派な自然薯が出てくるわけではないです。
| ベニバナボロギク |
ベニバナボロギクはアフリカ原産。遠いところまでやって来たものです。頭花は長い筒状花が束ねられるように集まっている状態で、上を向いているものはまだ未熟。成熟すると下を向きます。
| 十字路 |
丘の上に上がると十字路が現れました。ここは右折です。
園路のところどころにベンチがあります。木陰にはなっていますが、今日は暑くてちょっと腰を下ろそうとは思いません。
| ヒヨドリバナ |
丘の道沿いにはキク科の花がいくつか見られました。このヒヨドリバナもそうですが、さっきのベニバナボロギクもガンクビソウも。そういえばキク科の植物の多くは丘陵地や山地で出会うことが多く、水辺で見かけることはあまりありません。
| 里山口 |
しばらく行くと公園の南側にある里山口に至りました。ここは尾根幹線道路に接する出入り口ですが、ここから入園する人はほとんどいないのではないでしょうか。
| カラスウリ |
フェンスにぶら下がるカラスウリの果実。これから秋に向けて朱色に色づいていくでしょう。
最初に歩いた谷戸とは別の谷戸を今度は奥から下っていく形で歩きます。
| 田んぼ |
木立が切れると田んぼが現れました。しばらくこの田んぼの周りで観察してみましょう。
ここは地域活動グループが手掛けている田んぼだと思います。この手前に「里山のいえ」という施設があって、そこが活動の拠点となっているようです。
| サワギキョウ |
田んぼのそばにサワギキョウが咲いていました。こそういえば小山内裏公園では見ないです。もっとも、小山内裏公園では何本かある谷戸の大部分はサンクチュアリになっているので、その中に入れば出会えるのかもしれませんが。
| ハコネウツギ |
この時期にハコネウツギが咲いていました。本来は5月に咲く花です。
| イネの出穂 |
田んぼのイネを見てみると、ちょうど出穂の時期でした。イネの下から上に向けて5日間くらいかけて開花していくのだそうです。モミの部分から雄しべと雌しべが出ていて、風が媒介して自家受粉をします。開花は午前中の2時間位で、受粉を終えるとさっさとモミを閉じてしまうので、他の株の花粉を受粉することはほぼないようです。
| ジョウシュウカモメヅル |
ジョウシュウカモメヅル。小山内裏公園でよく見るコバノカモメヅルの変種で、上州に限らず関東から近畿にかけて分布しているそうです。母種のコバノカモメヅルよりも花も葉も大型です。
| ガマ |
ご存知、ガマです。雌花穂(いわゆる蒲の穂)の部分がコガマ、ヒメガマに比べて最も大型です。
| 里山のいえ |
里山のいえの周囲では、暑い中、ボランティアの方が草取りをしていました。
田んぼを離れて再び丘に上がります。
木陰に入って少しホッとしました。
| 十字路 |
丘を上がり切るとさっきの十字路に至りました。さっきは奥から来て左へ行きましたが、今度はここを右に行きます。
道はすぐに谷戸の底に向かって下っていきます。
| ガビチョウ |
賑やかに鳴いているのはガビチョウ。元々声量の大きい鳥ですが、無駄に騒いでいるわけではなく、おそらくyamanekoが近づいてきたから仲間に危険を知らせているのでしょう。、
| ヤブラン |
一旦谷戸の底に下りてきて、出だしに歩いた園路を横切り、今度はスタート地点の自然館に向けて上っていきます。
その道すがら、まさに藪の中からヤブランの花序が伸びだしていました。この花を見ると夏も終わりに近づいてきているなと感じます。
午後1時30分、自然館が見えてきました。今日の野山歩きはここで終了です。
今日は、水辺の植物、丘陵地の植物、様々出会いました。その中で、メハジキ、タヌキマメ、サワギキョウ、ジョウシュウカモメヅルなどyamanekoがフィールドとしている小山内裏公園では見かけない植物にも出会いました。両者はわずか1kmほどしか離れていないのですが。面白いものです。