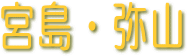
宮島・弥山 〜瀬戸内海PV交流会〜
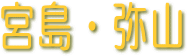 |
【広島県宮島町 平成15年9月27日(土)〜28日(日)】
現在、日本の国立公園はいくつあるか知っていますか。
北は「利尻礼文サロベツ国立公園」から南は「西表国立公園」まで、合計28地域あります。
子どもの頃、切手の収集が流行っていて「国立公園シリーズ」も好きな切手のひとつでした。
その写実的なデザインと未知の地名とが、子ども心にも遠い憧憬を抱かせたことを覚えています。
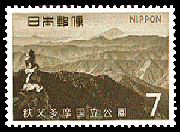 |
画像 http://kitte.com |
その国立公園には昭和60年以降、パークボランティア(以下、PVとします。)が設けられ、自然解説や普及啓発、環境整備などの活動を中心として、国立公園の保護と適正な利用をサポートする活動が続けられています。
28の国立公園の中にはまだPVが設立されていない地域(秩父多摩、小笠原、大山隠岐、西海)もありますが、霧島屋久国立公園のように4つものPVを設けている地域もあります。ちなみに瀬戸内海国立公園には、香川県の五色台地区と岡山県の鷲羽山地区、そしてこの宮島地区にPVがあります。
今回、瀬戸内海の3つのPVの交流研修会を、国立公園であり世界遺産の島でもある宮島で行うこととなりました。
| 「杜の宿」 |
開会は午後1時。午前中は太田川の河原で定点観察をしていたので、大急ぎで宮島に駆けつけたのですが、会場となった「杜の宿」に着いたのは3時を回っていました。忍び足で席に着きます。
既に各地区PVの活動状況の報告は終了していて、環境省の自然保護事務所から環境行政をめぐる情勢についての話が進められていました。
| 研修会の様子 |
研修会の最後のプログラムは、地元宮島町の専門員の岡崎さんから「宮島の動植物と自然環境について」と題しておもしろい話を聞かせてもらいました。宮島の自然とそこに住む人間の自然観との相互干渉など、自然科学というよりも人文科学的な切り口で宮島を解説するところに新鮮みがあり、そのへんはさすがに「歴史の島・宮島」といったところです。
| 懇親会 |
夜にはお楽しみの懇親会がまっています。
昼間の堅い話は置いといて、楽しいエピソードなどの紹介におおいに盛り上がりました。
料理もなかなかのもので、町営の国民宿舎とはいえちょっとした観光旅館のようです。
宮島のシンボル「大鳥居」がライトアップされているというので、懇親会の後、みんなで見物に行きました。
| 闇に浮かぶ大鳥居 |
暗闇の海に屹立する朱の大鳥居を眺めていると、あたかも対岸の光の帯びとの間に千年の時が横たわり、今立っているこの地が遠い平安の波打ち際であるかのように思えてもきます。
2日目(9月28日(日))も素晴らしい晴天。
朝8時にチェックアウトして、弥山に登ります。
| 大聖院コースの登山口 |
いくつもある登山コースの中から、今回は「大聖院コース」を往路に選びました。
木立に遮られて朝陽は差し込んできませんが、頭上には高く澄み渡った空が望めます。
なんだかみんなペースが早いようですが、大丈夫でしょうか…。
| 途中の展望台から |
尾根筋に出ると明るい景色が広がっていました。
眼下には大野瀬戸。今日もたくさんの観光客がこの瀬戸を渡って宮島にやって来ることでしょう。
| ミヤジマママコナ |
ミヤジマママコナはミヤマママコナの亜種(変種?)だそうです。ママコナとは「飯子菜」。花冠の中にある黄色の斑紋をご飯粒に見立てたネーミングです。 はい、「ミヤマママコナ」を早口で3回!
9時50分、山頂に到着です。
時間が早いせいか我々以外にはほとんど人影がありませんでした。
弥山にはロープウェイで登ってくることもできます。ただし、終点からでもけっこう歩かないと山頂にはたどり着かないので、たまにハイヒールで苦労している女性を見かけることもあります。
| 広島市街 |
山頂からは360度の展望。
北東方向には広島湾を隔てて広島の街並みを見ることができます。こうやってみると、海あり山あり川あり島ありで、ほんと広島って飽きない街だとつくづく思います。
少し慌ただしいですが、10時半には下山開始。復路は「紅葉谷コース」をたどることにしました。滑りやすい山道を注意して下ります。寡黙になりがちな上りとは異なり、楽しい雑談や情報交換などをしながら下っていきました。
| 閉会 |
紅葉谷に下りてくるとたくさんの観光客で賑わっていました。時計を見るともう12時前です。
ふくらはぎに若干の張りはあるものの、みんな怪我もなく下りてこられたことが何よりでした。
また来年の交流会で再開することを約束して、笑顔で解散。それぞれ港に向かいました。