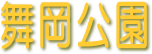
舞岡公園 ~谷戸に下りると昭和の風景が~
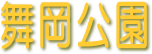 |
【横浜市 戸塚区 令和7年1月17日(金)】
年も改まり令和7年になりました。西暦では2025年。今年で21世紀も4分の1が過ぎることになります。子供の頃、21世紀なんてほぼSFの世界と思っていましたが、21世紀に入って随分経った今の世相を見渡してみても、実際そんなに未来感はありませんね。目に見える明らかな変化はコンピュータが手のひらサイズになって万人に行き渡ったことくらいでしょうか(いやもっとあるか。)。とはいえ昭和生まれとしてはそのくらい緩やかな変化の方がありがたいです。
さて、世の中の大きな流れは別として、yamanekoとしては今年も野山での活動に勤しんでいきたいと思います。家長としての責任を概ね果たした今(この辺の考え方が決定的に昭和)、これからの行動基準は「残された時間と引き換えるに値するか(と思えるか)」です。というとなんだかかっこよさげですが、平たく言うと「なるべく好きなことだけをして生きていく」ということで、まあお気楽とのそしりは免れ得ません。
そんなこんなで、今回の野山歩きは横浜の郊外にある舞岡公園で。里山の環境がよく保全されていると聞いたので以前からちょっと気になっていた場所です。実は去年、鳥を観に電車を乗り継いで行ったのですが、みぞれ混じりの冷たい雨が降りだしたので最寄の舞岡駅で引き返したことがあったのです。そういう意味ではリベンジですね。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
今回は電車ではなくドリーム号Ⅲでのアクセスです。渋滞の国道16号線を南下し、保土ヶ谷バイパスに入って新桜ケ丘ICで県道へ。この辺りは多摩丘陵の南東端に当たる場所で、緩やかな起伏を、あるところでは削り、またあるところでは埋めて作られた広大な住宅地が広がっています。そんな中をナビを頼りに走っていきました。
| 舞岡公園駐車場 |
10時40分、舞岡公園の駐車場に入りました。平日ということもあり3割くらい区画が埋まっている状況でした。
| 管理詰所 |
管理事務所に併設されているトイレを借りてから軽くストレッチを。長時間の運転で体が硬くなっていますからね。
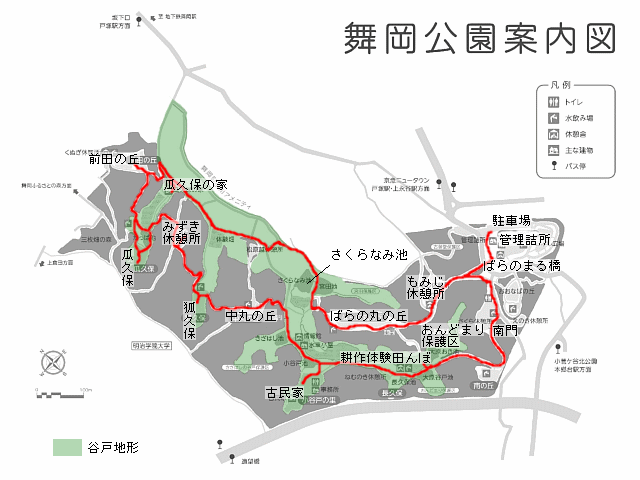 |
横浜市HPから (一部加工しています) |
舞岡公園は南北に長い大きな谷戸(北が谷戸口、南が谷戸奥)を取り囲むような形をしていて、今日はその南端からスタートし、北端までを往復するルートになります。
| ばらのまる橋 |
スタートしてすぐ、車道を跨ぐ「ばらのまる橋」を渡ります。変な名前だなと思いましたが、どうやらこの橋の先に「ばらの丸の丘」というエリアがあるからのようです。yamanekoはこの橋を渡ってすぐ車道に下り、道沿いにしばらく歩きました。
| 南門 |
すぐに右手に延びる園路が現れ、その先に進んで行くと南門に至りました。ここからが里山環境が保全されているエリアになります。舞岡公園は谷戸を中心とした里山環境が保全されているエリアといわゆる都市公園のようなエリアがあり、里山エリアのうちの中核的な部分は夜間は閉鎖されるようです。そのための門なんですね。地図を見ると、ここ南門のほか東門と北門があるようでした。
| キヅタ |
門から延びる道は非舗装ですが管理車輌が通られるくらいの幅があります。そこを谷戸の方に下って行くとキヅタが盛大に垂れ下がっていました。本来キヅタは気根を出して樹木の幹に張り付き登っていくものですが、こんなに垂れ下がるということは 、これ以上登れないところまで行き着いてもなお成長を止めず、やむなく垂れ下がっているということでしょうか。先端まで水と栄養を届けるのは相当大変でしょうね。
| シロダモ |
シロダモの冬芽です。なんだかミサイルみたいですね。それともロボットの指か?
坂道を下ると視界が開けました。右手には大きな谷戸が延びています。
| 耕作体験田んぼ |
谷戸に下りてみるとこの風景。この谷戸が舞岡公園を南北に貫く最も大きな谷戸で、写真奥が谷戸口の方向になります。この谷戸の名前がどこを調べても分からなかったので単に主谷戸と呼びますが、この主谷戸からさらに魚の骨のように小規模な支谷戸がいくつも伸びています。
この農地は耕作体験田んぼだそう。谷戸は両側の丘から水が供給されるので水利がよく、一定の広ささえあれば耕作には適しています。ここもこれだけ開けた場所になっているので昔から水田として利用されていたと思います。また、見通しの利く空間はワシタカなど猛禽も狩りがしやすい場所で、ここでは彼らを生態系のトップとして多様な生物が生息できていたでしょう。今はどうなのか。
| おんどまり保護区 |
振り返って背中側はこんな感じ。「おんどまり保護区」と呼ばれていて、その名のとおりもうすぐそこが主谷戸の最奥部になっています。一般的に谷戸では奥に行くにしたがって水の供給量が少なくなることから、奥の方は田んぼではなく畑として利用されていたケースが多いようです(大きな谷戸では谷戸内に灌漑用の溜池がいくつか作られていることもあります。)。畑地の更に奥はもう斜面の林となり、そのような場所は柴刈りや狩猟などの場として利用されていました。まさに谷戸全体が生産の場だったということです。
| トウネズミモチ |
これはトウネズミモチの果実です。黒色ですが粉がふいたようなマットな色合いになっています。トウネズミモチは「唐鼠糯」の名前のとおり明治期に中国から渡来したもの。中国ではこの木から蝋を採集したり漢方薬を作ったりしているそうですが、日本ではもっぱら庭木とのことです。
| ガマズミ |
ガマズミの果実はこの時期固く乾燥しています。鳥にとってあまり美味しくないものなのか、いつまでも枝に残っているのをよく見かけます。
| 東屋 |
耕作体験田んぼの脇には東屋が。ちょっとした作業や休憩のための施設のようです。手前が広くなっているのは田植えや稲刈り、脱穀などの作業で必要となるスペースなんでしょうね。
| タイワンリス |
グァッ、グァッ。田んぼの向こう側から変な鳴き声が聞こえてきました。何だろう? ガマガエルかな…、とキョロキョロしていたら、いました。樹木と同化するようにじっとしている大型のリスが。タイワンリスです。大きさはネコくらいはありました。特定外来生物で、神奈川県では三浦半島を中心に生息していて、横浜市では南部で急速に数を増やしているのだそうです。この個体の周囲だけでも数匹いたので、近隣の住宅地などでも結構な頻度で出没し、ケーブルをかじったり被害も出ているのではないでしょうか。
| 小谷戸の里 |
道にもどってしばらく歩くと、支谷戸の奥に古民家が見えました。課外学習でしょうか、小学生の賑やかな声が聞こえてきます。ここは「小谷戸の里」といい、この公園の環境維持をしているNPOの活動拠点。建物自体は公園開設に合わせて移築されてきた古民家だそうです。
| コブシ |
コブシの冬芽が少し膨らんでいます。これからが冬の本番ですが、春を迎える準備はちゃんと進めているようです。
| ミツマタ |
ミツマタの花序も少しほぐれ始めている様子。昔はミツマタを栽培している民家も普通にあり、その後住人がいなくなってミツマタだけが残っているといった状況を、野山歩きをしているとたまに見かけることがあります。
| タシギ |
田んぼの中で動くものが。双眼鏡で覗いてみると、タシギでした。まっすぐな長い嘴が特徴的です。泥の中の餌を採るのに適した形で、逆に木の実とかは採りにくいでしょうね。シベリアから冬鳥として渡ってくるのだそうですが、この田んぼのような環境がなくなってしまうと必然的にタシギもいなくなるいうこと。長旅をしてやってくる鳥たちのためにも里山環境を保全していってもらいたいものです。
| 中丸の丘へ |
田んぼエリアを過ぎた辺りから、いくつかの支谷戸を串刺しに横断する形で丘を上ったり下りたしていきます。まずは中丸の丘という展望広場へ。坂道はなかなかの傾斜で、太ももの筋肉がミシミシいっていました。
| 狐久保 |
中丸の丘では何人かが日向ぼっこをしていました。そこはスルーしてその先の狐久保という支谷戸に下りていきました。この谷戸は奥に長い谷戸になっていて、いかにも昔はキツネが出没していた風のところでした。狐に化かされたなんて話も伝わっているかもしれませんね。
| アオキ |
アオキの実が赤くなっています。アーモンドより一回りくらい大きいサイズなので、この実を食べる鳥はそれなりの大きさがあって、大きく開くことができる嘴を持っていなければなりません。例えばヒヨドリとか。
| |
狐久保からは再び左手の丘に上がります。
なだらかな坂道をゆっくりと。冬晴れの空が気持ちいいです。
| みずき休憩所 |
上った先には広場が。「みずき休憩所」という広場でした。
| 東方向 |
広場からは東方向の眺望が広がっていました。正面には谷戸を挟んで向こう側の丘が見えました。こことほぼ同じ高さであることから、もともと一つの台地に谷戸が切れ込んできていることが分かります。あの丘の向こう側は大規模な住宅団地。木立越しに見えている四角い屋根は南舞岡小学校のものでした。
みずき休憩所からまた丘を下ります。うっかりすると転げ落ちそうな斜度です。
| 瓜久保 |
坂の先は瓜久保という谷戸。さっきは狐久保でしたが、こんどは狐ではなく瓜なんですね。ここも結構大きな支谷戸のようです。
| ソシンロウバイ |
瓜久保の谷戸の中ほどではソシンロウバイが満開になっていました。春を待つ頃に見ることが多いからか、明るい気持ちになれる花です。
| 瓜久保 |
瓜久保の最奥部。きれいに草刈りがされています。かなり広いので通年の手入れもなかなか大変そう。
| かっぱ池 |
かっぱ池。もともとは溜池だったのかも。見る限り水量が少なく灌漑用としては不向きな感じもしますが、この谷戸の谷戸口の方には耕作地もあるので、ひょっとしたら現役の灌漑用溜池なのかもしれません。かっぱ池ということで池のほとりにカッパが相撲を取っている銅像がありました。なんとも唐突感があり、薄暗いときに来たらドキッとするかもしれません。
瓜久保からは三たび丘を上っていきます。
| 前田の丘 |
上った先は「前田の丘」という広場でした。誰もいません。さて、ここが舞岡公園の北端になるので、ここで折り返し。まず主谷戸まで下ります。
| 氷河? |
前田の丘を下りると、公園の敷地の先に広がる広大な住宅地の一部が見えました。住宅がこちらに向かって迫ってきているように見えます。まるで氷河の先端のよう。(飛躍しすぎ)
| 瓜久保の家 |
左手に「瓜久保の家」という休憩施設が現れました。入口に門があり、夜間は閉鎖されるようです。ということは毎日誰かがここまで来て門を開け閉めしているということですよね。寒いこの時期は特に大変でしょう。ご苦労様です。ここはさっきかっぱ池のあった谷戸の谷戸口に当たるところ。ここから写真奥に向かって谷戸が延びているという形です。
| 火の見櫓 |
門の脇に火の見櫓がありました。もちろんどこかから移築されたものだと思います。
| 体験畑 |
瓜久保の家を後にしてしばらく行くと、また左手に支谷戸が延びていました。ここは狐久保の谷戸口で、耕作体験ができる畑となっていました。
| さくらなみ池 |
主谷戸を更に遡っていくと、やがて池の畔へ。ちょっと大きめの溜池で、「さくらなみ池」とのことでした。
| ハンノキ |
水辺に立つハンノキ。枝先から花序が垂れています。今はまだ固く締まっていますが、もうじきびろーんと伸びて、表面にできた隙間から花粉を風に飛ばします。
| アオジ |
ハンノキの足元にアオジが。写真を撮ろうと構えていてもどういうわけか日陰から出ようとしません。それどころか半径1mくらいの範囲をちょこちょこ歩くのみでその場を離れようとしないのです。これはどういうことか。守らなければならない大切なものが近くにあるのだろうか。
| ばらの丸の丘 |
さくらなみ池から坂道を上ると「ばらの丸の丘」です。日当たりのよい芝生広場でした。休日には家族連れで賑わうのでしょうが、この日は人っ子一人いませんでした。ただカラスが鳴いているのみ。谷戸を離れてここからは丘の上を行きます。
| もみじ休憩所 |
ばらの丸の丘を過ぎるとその先には「もみじ休憩所」という広場。若者が声を張り上げてギターの練習をしていました。路上デビューのリハーサルかな。
分岐が現れました。今日のスタート直後、写真左奥にあるばらのまる橋を渡ってやってきて、ここでUターンするように右奥に向かったところです。ここまで戻ってきたら今日の野山歩きもあとちょっとで終了です。
ばらのまる橋を渡ると管理詰所などの施設が見下ろせました。その奥が駐車場です。
時刻は12時40分。ちょうど2時間の野山歩きでした。昼を過ぎたので、帰りがけにロードサイドの牛丼屋さんにでも寄って帰ることにしました。
今日歩いた舞岡公園、谷戸を歩いていると近代的な構造物が視界に入らないので、まるで昭和にタイムスリップしたような感じでした。実際どうだったんだろうと昔の航空写真を調べてみたら、1976年の時点では既に周囲に大規模住宅団地ができていましたが、1965年まで遡ると一面に農地が広がっていて、丘はことごとく畑に、谷戸は隅々まで水田になっていました。これはこれで一般的な谷戸の姿とは異なると思いますが、大都市近郊という立地と戦後の食糧増産がそういう状況を作ったのでしょうね。むしろ適度に森や雑木林が残っている今の風景は更に遡った時代の谷戸の姿に近いのかもしれません。