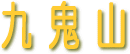
九鬼山 ~輝く陽射、滴る緑の中を行く~
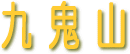 |
【山梨県 都留市 平成28年5月5日(木)】
ゴールデンウィーク後半。昨日までの強い風も収まり、朝から輝くような晴天です。今日は山梨県都留市と大月市の境に位置する九鬼山に登ってみることにしました。標高は970m。yamanekoにはちょうど良いクラスの山です。
ところでこの九鬼山、何やら曰くありげな名前ですが、この辺りに昔からある桃太郎伝説に由来するもののようです。大月盆地の北にある百蔵山(ももくらさん)の周辺には犬目、猿橋、鳥沢という土地があり、盆地を挟んで南に九鬼山があることから、桃太郎が犬と猿と雉を引き連れて鬼を退治しに行ったという言い伝えとなっている由。また、富士山に棲んでいた10匹の鬼が桃太郎に追われ、1匹が大月の岩殿山に逃れ、残りの9匹が九鬼山に逃れたという話もあり、いろいろな話で語り継がれているようです。でも、前者は九鬼山ありきの話なので、この話から九鬼山という名になったのかは?です。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午前7時半過ぎの電車に乗り、橋本、八王子を経由して、大月で富士急行に乗り継ぎました。時間が早いせいか、連休中にしてはそれほど乗客は多くなく、車内では外国人観光客の一団が目に付く程度。今日は終日富士山の眺望も素晴らしいでしょうから、帰国後のよい土産話ができたでしょうね。
| 禾生駅 |
9時13分、目的地の禾生(かせい)駅に到着。大月駅から3つ目の駅ですが、かなり長閑な雰囲気でした。線路がなけれは駅舎だか何だか分からないくらいです。でもちゃんと有人駅でした。
改札を出てから駅前でストレッチをして、9時35分、スタートです。
| 国道139号線 |
まずは国道139号線沿いに歩いて登山口を目指します。富士山に向かう車のほとんどは並走する高速道路を利用するからか、車はスカスカでした。
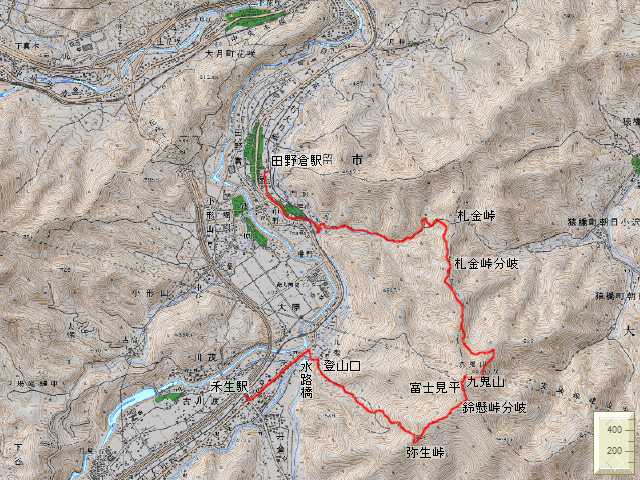 Kashmir 3D |
今日のコースは、この国道をしばらく歩き、落合橋という橋を渡ったところで右手に折れます。集落の中をしばらく歩くと登山口。そこから山腹を直登し、山頂南側の稜線に出ます。その後は稜線沿いにわずかで山頂です。下山は反対方向に向かい、田野倉駅(禾生駅の1つ大月側)まで歩きます。標準コースタイムは4時間10分。
| 九鬼山 |
途中、九鬼山を望める場所が。写真中央のピークが山頂。その右手の稜線から手前に伸びる支尾根を登ることになります。登山口から稜線までの標高差は400mほどです。
| 水路橋 |
やがて右手にレンガ造りの水道橋が現れました。これから行く手の落合橋を渡った先にある脇道に入り、あの水路橋の下をくぐります。
ところでこの橋は、名前のとおり水を通す橋。ここより1.5km上流で取水した水をトンネルと水路で5km下流の駒橋発電所の頭上まで引いて、そこで高低差を利用して一気に落として発電するのですが、地形上ここで川を跨ぐ必要があったということでしょうね。建造されて100年以上経っているそうです。
ちなみに駒橋発電所で発電に使った水は再び取水し、今度はさらに13km下流にある八ツ沢発電所に供給しているとのこと。つまり発電用水の使い回しですね。この橋を流れている水も上流の川茂発電所で使い終わった後のものです。
| 馬頭観音 |
水路橋の下をくぐり、その先の集落の中を歩いて行くと、やがて分岐が現れました。左右どちらに行っても九鬼山への登山道に至りますが、ここは右手の杉山新道へと続く道へ。 分岐の脇に馬頭観音が祀られていたので、今日一日の安全を祈願しました。
| 三ツ峠山 |
右手に三ツ峠山が望めました。手前の道路は中央道の富士河口湖線です。
| 杉山新道登山口 |
ほどなく登山口に到着しました。時刻は9時50分です。標識がなけれは踏み込むのを躊躇するような入り口ですね。
山道の歩き始めは鬱蒼としたスギ(ヒノキだったか)林。今日は朝から日差しが強いので日陰は気持ちいいです。
ガイド本ではこの先登山道はY字に分かれ、左手が1号路、右手が2号路となっていて、yamanekoは1号路を登る予定でいましたが、いつまで行っても分岐らしきものが現れません。すると左に直角に折れる分岐が現れ、そこに1号路、2号路の文字が見える案内板はありました。ただ、ほとんど朽ちていて、しかもグラグラしていたので、指し示す方向がよくわかりませんでした。もしここがY字分岐だとするとここを左折ということになりますが、その方を見るとやや鬱蒼としています。朽ちた案内板の下にある新しい案内板は直進を示しているので、ここはまっすぐ行くことにしました。仮にこれが2号路であっても最終的には同じ尾根に出るのですから。
ほどなく道は支尾根を直登し始めました。小さなジグザグを繰り返しつつ尾根筋を登って行っています。やはりこの道が1号路なのか。
| イカリソウ |
ちょっとくたびれかけているイカリソウ。静かに咲く花に癒されます。
道は引き続き尾根筋を辿っているのでGPSのログで確認してみると、やはり1号路を登っているようでした。ということは、きっとどこかにあったY字分岐を見逃したのだと思います。それが直角分岐の前だったのか後だったのか分かりませんが。
| ヤマルリソウ |
ヤマルリソウ。天然の花の色とは思えない鮮やかな青色です。
| ダンコウバイ |
ダンコウバイの葉は先割れスプーンみたいで可愛いですね。先割れスプーン自体知らない人が多いかもしれませんが。
| シャガ |
木漏れ日のスポットライトを浴びるシャガ。ちょっと場違いな華麗さです。
| エンコウカエデ |
光を透かし、まるで自らが発光しているかのようなエンコウカエデの葉。
いったい何度ジグザグを繰り返したか。やがて道は尾根筋から山腹に沿うようになりました。地図によると稜線に出る直前のようです。
| 弥生峠 |
おっ、何やら標識が見えます。稜線のようですね。
10時50分、稜線に出ました。古ぼけた標識に「弥生峠」とあります。右手から合流してきているのが2号路だと思いますが、よく見ると通行を止めるようにして木が2本横たえられていました。どうやら2号路に入らないようにしているみたいです。
ここからは主稜線を登っていきます。地図によると傾斜はたいしたことない模様。
明るい山道で気持ちがいい。山を歩く歓びを感じますね。
| ミツバアケビ |
ちょっとピントが甘いですが、これはミツバアケビの花。短い棒のような部分がアケビの実になります。
| 鈴懸峠分岐 |
ほどなく分岐が現れました。右に折れると鈴懸峠方面。ここは左斜めに延びる道を行きます。 山頂まではあとわずか。
富士見平というポイントで今日初めて富士山の姿を拝むことができました。雲ひとつなく本当に美しいですね。
| 富士見平 |
池ノ山コース(麓の集落の分岐を左に向かって辿るコース)から登ってきたという男性が休憩していました。聞くと途中に天狗岩という眺望の素晴らしいポイントがあったとのこと。yamanekoは寄らずに山頂に向かいましたが、あとで考えたらちょっと寄ってみればよかったと軽く後悔。写真は天狗岩に向かう分岐を振り返ったところです。
11時25分、山頂に到着です。禾生駅を出てからの所要時間は1時間50分でした。
| 九鬼山山頂 |
山頂は東西に細長く、そんなに広くはありませんでした。男性の先客が数人。いずれも単独行らしく、みな黙々と食事をしていたりして静かでしたね。その代わりウグイスの声がよく響いていました。
| 北方向 |
山頂からは北側の眺望が開けていました。横一列の山並みに見えますが、左の滝子山が最も近く直線距離で10km。右に行くにしたがって奥に位置していて、雁腹摺山で13km、雲取山に至っては30km先にあります。
| 南方向 |
ガイドブックには眺望は北側のみで富士山側は木立で視界が遮られているとありましたが、実際には富士山が望めるように木が刈られていました。切り口がまだ新しく、倒された木もそのままにしてあったので、この大型連休に向けて登山客のために作業したんだろうかと思っていました。でも、帰宅後ネットで見た写真によると既に数年前には切られていたようです。ということは追加で伐採し、視界を広げたということでしょうか。
| 北東方向 |
北東方向には扇山や百蔵山、その奥に権現山、更に奥に三頭山が見えました。
| マルバアオダモ |
昼食後、山頂付近で植物観察を。これはマルバアオダモの花。斜面に生えていたので目線より低い位置に花を見ることができました。普段は見上げるような形になり、なかなか上手く観察できないんですよね。
| ニガイチゴ |
これはニガイチゴですね。名前に反して甘く食べられます。ただ口に中に若干苦味が残るのでこの名が付いているようです。
| 下山開始 |
11時50分、下山開始です。地理院地図では北側に延びる尾根を辿るように登山道が記されていますが、探してもその方向には下山口がありません。どうやら一旦北東側に延びる尾根に沿って下っていき、途中で山腹をトラバースする形で横移動して北尾根に合流するみたいです。
| チゴユリ |
これはチゴユリ。下界では花の時期はあらかた終わっています。
| 分岐 |
数分下ったところで道は尾根を左に折れていました。ここからは山腹を辿る道です。ちなみにここでは間違って直進しないように正面に丸太が横たえてありました。
| トラバース |
ズルズルと滑りそうな斜面を下りながら横切って行きます。こうやってみると結構な傾斜ですね。渡してあるロープを掴みながら下っていきましたた。
| ユキザサ |
またこんなところに限って可愛い花が咲いていたりするもの。これはユキザサの若い花です。滑り落ちないよう足場を確保して写真を撮りました。
ほどなく北側の尾根に出て、そこからは普通の登山道を下っていきます。そして踊り場のような平坦な場所が現れました。花見などにはもってこいの場所です。
| 三ツ峠山と本社ヶ丸 |
ここからは三ツ峠山が望めました。上りの富士見平にいた男性がここにもいたので、ちょっと休憩して雑談などを(山頂にもいましたが。)。
更に下ると富士山が望める場所も。遮るものなくどーんと見える富士山もいいですが、このように山並みの向こうに覗く富士山も趣があります。
| ミツバツツジ | ヤマツツジ |
道はまだまだ下っていきます。森に中で見かけたツツジ二種。ミツバツツジとヤマツツジですね。
傾斜も緩くなり、のんびりと山歩きを楽しめました。
| 札金峠分岐 |
12時40分、分岐が現れました。ここで稜線を離れ、左手に下っていきます。直進すると札金峠に至ります。
| 林道 |
山腹を下ること10分、林道に出ました。陽射しが強く、夏のよう。ここからしばらく林道歩きです。
| フジ |
フジの花。房として見たときの印象が強いですが、一つ一つの花も個性的です。
| ミツバウツギ |
これはミツバウツギですね。可愛い花です。実は扁平な蒴果で形に特徴があり、初心者マークの先端を尖らせたような形をしています。ミツバアケビ、ミツバツツジに続き今日3つ目の「ミツバ」です。
何かの作業小屋が現れました。ここから先は舗装路です。いよいよ下界も近くなってきました。
集落に出てきたところでこの風景が迎えてくれました。ちょうど富士山に鉄塔が被っていますが、そこは心眼で見えないことにして、うむ、やっぱり絶景です。手前の高架はリニアの実験線です。
| 富士急行 |
ゴールの田野倉駅まではあとちょっと。田園風景の中をのんびりと歩いていきます。やあ、富士急の電車が。鮮やかなブルーが緑の景色に映えて…、ってちょっと待て! ここで追い越されたら次の電車は40分待ちだー。
| 九鬼山 |
2、3歩走りましたがすぐに無理と悟り(あたりまえ)、諦めて更にのんびり歩くことにしました。振り返ると今日登った九鬼山が。堂々としていますね。今日はありがとう!
| 田野倉駅 |
1時25分、ゴールの田野倉駅に到着しました。休憩時間を入れても3時間50分。yamanekoにしてはハイペースでした。次の電車までには十分に時間があるので、入念にストレッチをすることに。更に木陰に腰掛けて撮った写真のチェックなどを。
そうこうするうちに電車の時間に。帰りの電車は満員でした。大月からの中央本線も通勤電車並み。そういえば今日はまだゴールデンウィークの最中だったですね。
今日は滴るような緑の中を歩くことができ、心身ともにリフレッシュすることができました。4月の異動で新しい仕事に就きストレスも溜まり気味でしたが、それもどっかに飛んでいったようです。やっぱり野山歩きはいいですね。