
交野山 〜迷いそう?低山侮ることなかれ〜
 |
【大阪府 交野市 平成30年12月2日(日)】
12月になりました。早いものです。一年の長さの感じ方は生きてきた期間の長さに反比例するという、なんとかの法則というのがあるそうですが、それが真実だとすると、もう百年くらい生きてきたんじゃないかと思うほど近年は一年が早く過ぎていきます。特に今年は大阪に引っ越してきていろんなことがあったのでなおさらです。
さて、そんな一年を締めくくる野山歩きはどこにしようかと考えていたところ、職場でお手軽で眺めが素晴らしい山があると聞き、素直にそこに決めました。北河内の交野市(かたのし)にある交野山です。「かたの」という市名も難読ですが、山の名前は「こうのさん」と読むというややこしさ。ここも含めて大阪周辺には難読地名が多いような気がします。歴史のある土地柄だからでしょうか。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
JR環状線京橋駅で学研都市線に乗り換えて30分。津田駅で下車しました。休日の朝とはいえ乗降客は数えるほどでした。
| 津田駅 |
今日の野山歩きはこの津田駅からのスタートです(ちなみにここは交野市ではなく枚方市)。時刻は10時30分です。
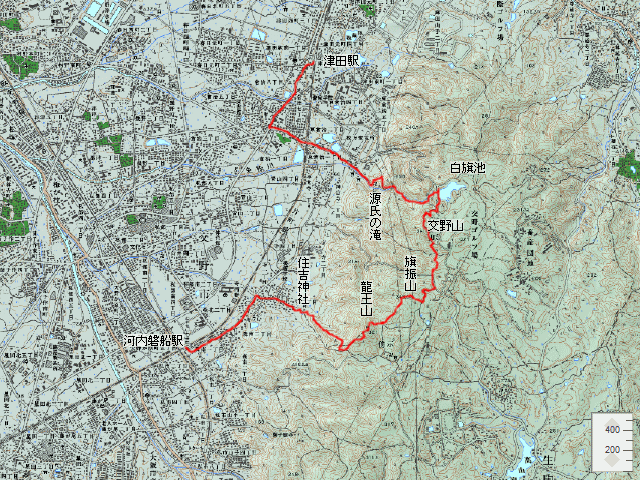 |
Kashmir 3D |
今日のコースは、津田駅から県道を800mほど南下し、倉治交差点で左手に向かいます。山の懐に突き当たると源氏の滝が現れ、そこから山道に。交野山の山頂を踏んだ後は南側に並ぶ旗振山、龍王山と歩いて、最終的に河内磐船駅に戻ってくるというものです。ちなみにこの3つのピークを交野三山というのだそうです。
倉治交差点左折後、しばらく行くとJR学研都市線と第二京阪道路とをくぐり、住宅地の縁を歩きます。正面に見えている山の右隣が交野山だと思います(たぶん)。
住宅地が切れると細い川沿いに庭のようなエリアが。どうやら近くにある糸吉神社の参道入口のようでした。この辺り、まだ紅葉が残っていました。
そのまま歩いて行くとやがて行き止まりに。なにやらいい雰囲気の場所です。
| 源氏の滝 |
突き当たりの壁面に風情のある滝が現れました。これが源氏の滝です。高さは20m弱。水量は…この時期なので少なめですね。
| 宜春禅院 |
滝を正面に見て左手の壁面に急な階段が穿ってあり、そこを登ると仏閣が現れました。宜春禅院というのだそうです。
宜春禅院の境内を抜けて右手に坂を登るとちょっとした広場が現れました。作業小屋のようなものが建っています。看板には「都市近郊の森を育てる会」とありましたが、ボランティア団体か何かでしょうか。道は正面の山腹に沿って右手に延びているようです。
いい感じの山道です。早速体が温まってきました。
もう朝とは言えない時刻ですが、角度の浅い日差しが梢越しに届いて気持ちの良い山歩きです。
| アキノタムラソウ |
この時期には珍しく花に出会いました。アキノタムラソウです。残り花ですね。
途中から傾斜がきつくなってきました。ある程度登ったところで振り返ると、こんな感じ。「道なき道」感がすごいですが、ちゃんとした登山道がありました。
進行方向はこんな感じ。しっかりした水の流れがあります。これが源氏の滝の元になる流れでしょう。
山道を抜けると整備された場所に出ました。これは白旗池という農業用ため池の堰堤です。さっきの流れはここからの放流水だったということですね。
| 白旗池 |
堰堤の上に登ってみると広々とした景色が待っていました。池のほとりには公園も整備されていて、そこで弁当を広げているグループもありました。
| 交野山 |
ここから堰堤の上の道を進みます。奥に見えるピークが交野山の山頂になります。なんかすぐそこのように見えますね。
堰堤を過ぎしばらく小径を行くと、やがて車道を横切ります。そに先は山頂に向けて傾斜が急になるはずです。
| ヤマコウバシ |
常緑樹の森の中に枯れ葉をまとった変わり者が。これはヤマコウバシ。落葉樹でありながら葉は春まで枝から落ちません。常緑樹が冬にも葉を落とさないのは次のシーズンも使い回すためですが、既に枯れていてもう使えないのにヤマコウバシがが葉を落とさないのはなんでなんだろう。
| ナナミノキ? |
うーむ、これはナナミノキかな? これぞ常緑樹といった葉です。葉が長持ちするよう、厚手にし、さらに表面をクチクラ化させて強度を持たせています。使い回すため耐久性を重視しているのでしょう。植物って凄いです。
| エノキの落ち葉 |
登山道に敷き詰められたエノキの落ち葉。落葉樹が葉を落とすのは寒さと乾燥から身を守るためで、冬場の環境が厳しい地域で生き延びる知恵です。使い捨てでもったいないようですが、逆に春から秋口まで使えれば良いと割り切って、耐久性は劣るとしても、少ない労力で作れる薄い葉を付けていると考えることもできます。
山頂が近いのか傾斜が一段ときつくなってきました。
| 交野山山頂 |
11時40分、山頂部に出ました。あれが交野山のシンボル、観音岩ですね。標高341m、交野山の山頂です。
| 空 永遠 |
手前の岩に梵字が彫ってありました。これは「ア」と発音し、これ一文字で「阿字本不生」(あじほんぷしょう)という密教の根本教義の一つを表すのだそうです。
「阿字本不生」の意味するところは「(梵字の)アという文字はすべての文字の始まりであり、これは宇宙の根源を表すもの。それは本来不生不滅。すなわち永遠に存在するということ、また、すなわち空であるということ」なのだそうです。確かに宇宙の根源、ビッグバンの前の状態は「無」(空)であり、時間のない状態で、すなわち永遠の状態なのかもしれません(永遠とは時間がとどまることなく流れる状態ではなく、時間のある世界の外側のことなのだとすると。)。
| 観音岩 |
観音岩の登り口です。ここから岩のてっぺんへ。
| 北西方向 |
平坦な部分がなく不安定。でも、評判に違わぬ素晴らしい眺望に、足下のことを忘れ魅入られてしまいました。これは北西方向(岩の向いている方向)。枚方、高槻、茨木などの街並みになります。
眼下に横たわっているのは第二京阪自動車道。これに並行して、遠方の山並みとの間に淀川が流れています。この低地の幅は約10km。淀川が削り蛇行して作ったものです。
| 北方向 |
視線を右手に移すと、遠くに京都盆地。肉眼でも京都タワーを確認することができました。
| 永田町? |
んん? あれは何だ? 国会議事堂か? いや、京都府境近くにある大阪工業大学だそうです。攻めてますね。
| 人類の進歩と調和 |
いろんなものを見渡せます。目を西に転じると、おお、太陽の塔! かなり霞んで見えますがここからの距離は15kmほどです。48年前からずっとあそこに立っているんですね。そういえば2025年の万博も大阪に決まりました。場所は千里丘陵ではなく、湾岸エリアの夢洲(ゆめしま)だそうです。
| 急降下 |
一通り眺望を楽しんだ後、次の旗振山に向かいます。急な山道を下っていきます。
旗振山という名前はなにやら曰くありげですが、これは旗振り通信の中継地だったことによるものだそうです。江戸時代半ば、全国の米相場の基準だった大阪堂島での相場を素早く伝えるために、数キロ間隔で設置された中継地で旗を振って伝えたのだそうです。その通信スピードはなんと京都まで4分、広島まで27分、江戸まででも数時間(箱根の峠は飛脚で伝えていたにもかかわらず)で伝わったそうです。すごいですね。旗振りに関わる人々の間で統制がとれていないとこれほどの早さは実現できなかったでしょうね。この旗振り通信、電話が普及する大正時代まで続けられていたそうです。
鞍部まで下って振り返る交野山。晩秋の佇まいです。
落ち着いた山道をゆっくりと登っていきます。 こういった雰囲気のところを歩くのも野山歩きの楽しみなんです。
| タカノツメ |
渋い黄葉を見せているのはタカノツメ。黄葉の後は落葉し、地面で朽ちていく過程で甘い綿あめのような香りを放つのもタカノツメの特徴です。歩いているとその香りでタカノツメの存在が分かるんですよね。
途中、駐車場がありました。看板には「いきものふれあいの里駐車場」とありましたが、そのいきものふれあいの里はさっきの白旗池の畔りにあるので、ここから相当歩かなければならないです。むしろ交野山ハイキングの駐車場なのではないでしょうか。
車道から道を折れ林道に入りました。yamanekoは山歩きには「ヤマップ」という便利なアプリを使っています。登山道のルート表示のほか自分の現在位置とこれまでの移動履歴も表示されるので、迷うことなく歩くことができます。GPSなので電波が届く届かないは関係ないし、あとは電池切れだけに注意しておけば(予備バッテリーがあると安心)。でもアプリに頼り切らず紙の地図は必携です。いざというときはアナログに助けられることも多いですから。
コナラが見事に色づいています。モミジほどの鮮やかさはありませんが、里山の秋を心地よく感じます。
| 旗振山入り口 |
更に細い山道に入っていきます。この分岐でもヤマップが頼りになりました。
少なくとも観光気分で訪れる人はいないと思われる旗振山。ほとんど藪の中の道を行きます。
| 旗振山山頂 |
12時25分、旗振山の山頂に到着しました。なんと先客が一人。アマチュア無線を楽しんでいるとのこと。この旗振山は交野市の最高峰なんだそうです。とはいえ標高345m。交野山よりわずか4mほど高いだけですが。旗振り通信を行っていた頃にはここ山頂一帯の樹木はきれいに伐採されていたのでしょうね。
山頂で先客の人としばし雑談をしてから次の龍王山へ向かいました。
| 悪路 |
…向かいましたが、相当に荒れた山道に若干の後悔が。木の幹や竹に付けられた赤いマークとヤマップがなければかなり高い確率で迷っていたと思います。
写真はずいぶん歩きやすいところで、ひどいところでは道らしいものは完全に見えなくなり、写真を撮る余裕もありませんでした。
旗振山から龍王山までのルートはずっとこんな感じでした。この夏の台風の影響もあるんでしょうね。ここはまだ先が見えていますが、荒れた竹藪の中などはまるで鳥かごに入れられたみたいで方向感覚を失いそうになるほどでした。
山頂直下に至ってようやく登山道らしくなってきました。
| 龍王山山頂 |
12時45分、旗振山から時間にしてわずか20分弱で龍王山山頂に到着。肌感覚では1時間くらいは歩いたように思われましたが。
山頂には大きな磐座がいくつかあって信仰の名残を感じました。もちろん無人でした。ここでは休憩する気にもなれず素通りです。
山頂を通り過ぎてすぐ、小広い場所が現れ、そこには朽ち果てた祠がありました。なんだかかわいそうな気持ちがしたので、汗を拭って手を合わせ、無事の下山をお祈りしておきました。
そこからも道なき道を赤いマークとアプリを頼りにたどっていき、ようやく山道らしい山道に下りてきました。ここに鳥居があるということは、今下りてきたルートが龍王山山頂の祠への参道だったということです。そりゃあ訪れる人もいないわと納得。
ようやく道迷いの心配から解放されました。とはいえここも寂しい山道であることには変わりありません。この山道は「峡崖越(かいがけの道)」といい、古くから大和と河内を結ぶ重要な交通路だったそうで、奈良に大仏が造営された頃には多くの仏師が行き交ったりしたのだそうです。
ようやく里が見えてきました。時刻は13時5分。そういえば昼食をとっていなかったので、ここで休憩。あんパンと水でパワー充填です。
と、ここで少し不思議な体験をしました。パンを頬張りながらふと下りて来た道の方を見ると、若い男性が道の奥に向かって足早に去って行く後ろ姿が見えました。男性までの距離は20mほど。すぐにカーブの先に隠れて見えなくなったので見ていた時間は1、2秒くらいだったでしょうが、鮮明に残像が残るほど確かにはっきりと見えたのです。ただ、ここは一本道。奥に向かって行くには当然yamanekoの前を通っていかなければならないわけで、一瞬キツネにつままれたような感じでした。ただ、不思議と怪しいとか怖いとかいった感情は湧いてきませんでした。そのときふっと思い出したのが龍王山頂直下で手を合わせた祠。もしかしたらあの祠の神様が式神を使わせて、yamanekoが道に迷わないように案内してくれていたのかもしれません。里の見えるところまで来て役目を終え、引き返していったのかもしれません。そうだとしたら感謝です。ありがとうございました。
| 住吉神社 |
休憩を終え歩き出してすぐ、住吉神社が現れました。小さな集落の小さな神社です。
| ザ・里山 |
神社の前から里山を望む。モズの高鳴きが聞こえてきそうです。
遠くに町の賑わいが見えてきました。
| 龍王山 |
この辺りは交野市「寺」という集落になります。振り返ると、道に迷いそうになった龍王山が。「今日はありがとー!」
寺集落からJR線沿いに南下して河内磐船駅に到着したところで今日の野山歩きは終了。時刻は13時30分でした。
| 交野三山 |
数日後、淀川を挟んで反対側(天王山の麓)から見た交野三山。遮るものもなくよく見えます。それなりに目立つ山容ではありました。
今年の野山歩きは今回が最後です。1月には千葉の鹿野山、2月には箱根の旧街道を歩いたりしましたが、まさかその春からは関西の山を歩けるようになるとは。会社勤めの定めとはいえ、転勤も悪くはないものですね。
さあ、来年も楽しく自然に遊んでもらえるよう、体に気をつけて過ごしたいと思います。